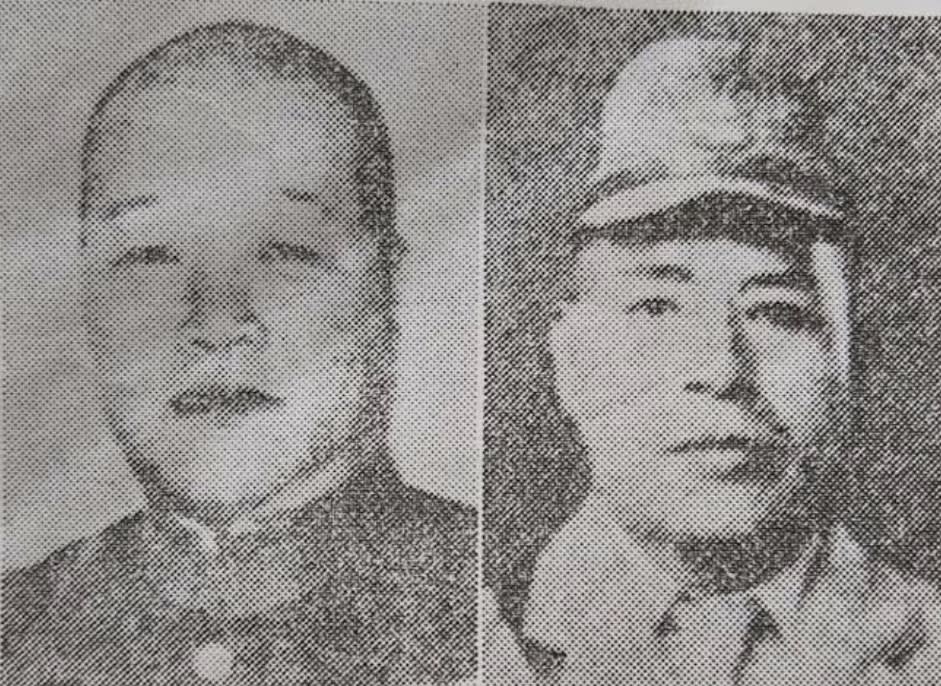前回、邪馬台国と卑弥呼を特定しましたが、これが正解であるかどうかは誰も否定出来ないし、肯定もできません。
同じ考えの方も居られるでしょうが、確定するまでの過程が千差万別で考える時期もばらばらだからです。
古事記、日本書紀に纏めた当時、もしくはそれ以前の卑弥呼が亡くなった242年〜248年とされる時に、その場に存在しなかった者達にとっては約1700年以上も何処の誰だかを思い巡らせたことでしょう。


祇園山古墳


久留米の権現塚古墳

みやま市の権現塚古墳

みやま市の近くにある蜘蛛塚

蜘蛛塚

記紀の中にはこの邪馬台国と卑弥呼の名が一度も登場せず、それはわからないのか、それとも隠されているのかすらも知ることが出来ないからです。
今回はこれらが意図的に隠されていると仮定して、またその行為の効果、目的についても考えていきたいと思います。

wikiより
『日本書紀』では神武天皇が即位以前の己未の年、大和国で恭順に及ばなかった波哆丘岬の新城戸畔(にいきとべ)和珥坂下の居勢祝(こせはふり)臍見長柄丘岬の猪祝(いはふり)という三箇所の土蜘蛛をそれぞれ討ち取らせた。
景行天皇12年(82年)冬10月景行天皇が 碩田国(おおきたのくに、現大分県)の速見村に到着し、 この地の女王の速津媛(はやつひめ)から聞いたことは、山に大きな石窟があり、それを鼠の石窟と呼び、土蜘蛛が2人住む。名は白と青という。また、直入郡禰疑野(ねぎの)には土蜘蛛が3人おり、名をそれぞれの打猿(うちざる)、八田(やた)、国摩侶(くにまろ・国麻呂)といい、彼ら5人は強く仲間の衆も多く、天皇の命令に従わないとしている。
仲哀9年3月丙申(200年3月25日)筑後国山門郡(やまとぐん、現柳川市・みやま市)に田油津媛(たぶらつひめ)という女王があり、神功皇后により誅殺されたとある。
『肥前国風土記』には、景行天皇が志式島(ししきしま 現在の平戸南部地域)に行幸した際(72年)、海の中に島があり、そこから煙が昇っているのを見て探らせてみると、小近島の方には大耳、大近島の方には垂耳という土蜘蛛が棲んでいるのがわかった。そこで両者を捕らえて殺そうとしたとき、大耳達は地面に額を下げて平伏し、「これからは天皇へ御贄を造り奉ります」と海産物を差し出して許しを請うたという記事がある。
『豊後国風土記』にも、五馬山の五馬姫(いつまひめ)、禰宜野の打猴(うちさる)・頸猴(うなさる)・八田(やた)・國摩侶、網磯野(あみしの)の小竹鹿奥(しのかおさ)・小竹鹿臣(しのかおみ)、鼠の磐窟(いわや)の青・白などの多数の土蜘蛛が登場する。この他、土蜘蛛八十女(つちぐもやそめ)の話もあり、山に居構えて大和朝廷に抵抗したが、全滅させられたとある。八十(やそ)は大勢の意であり、多くの女性首長層が大和朝廷に反抗して壮絶な最期を遂げたと解釈されている。この土蜘蛛八十女の所在を大和側に伝えたのも、地元の女性首長であり、手柄をあげたとして生き残ることに成功している。
このようにヤマト王権と敵対した勢力は土蜘蛛の名として登場しています。
景行天皇12年(82年)冬10月景行天皇が 碩田国(おおきたのくに、現大分県)の速見村に到着し、 この地の女王の速津媛(はやつひめ)から聞いたことは、山に大きな石窟があり、それを鼠の石窟と呼び、土蜘蛛が2人住む。名は白と青という。また、直入郡禰疑野(ねぎの)には土蜘蛛が3人おり、名をそれぞれの打猿(うちざる)、八田(やた)、国摩侶(くにまろ・国麻呂)といい、彼ら5人は強く仲間の衆も多く、天皇の命令に従わないとしている。
仲哀9年3月丙申(200年3月25日)筑後国山門郡(やまとぐん、現柳川市・みやま市)に田油津媛(たぶらつひめ)という女王があり、神功皇后により誅殺されたとある。
『肥前国風土記』には、景行天皇が志式島(ししきしま 現在の平戸南部地域)に行幸した際(72年)、海の中に島があり、そこから煙が昇っているのを見て探らせてみると、小近島の方には大耳、大近島の方には垂耳という土蜘蛛が棲んでいるのがわかった。そこで両者を捕らえて殺そうとしたとき、大耳達は地面に額を下げて平伏し、「これからは天皇へ御贄を造り奉ります」と海産物を差し出して許しを請うたという記事がある。
『豊後国風土記』にも、五馬山の五馬姫(いつまひめ)、禰宜野の打猴(うちさる)・頸猴(うなさる)・八田(やた)・國摩侶、網磯野(あみしの)の小竹鹿奥(しのかおさ)・小竹鹿臣(しのかおみ)、鼠の磐窟(いわや)の青・白などの多数の土蜘蛛が登場する。この他、土蜘蛛八十女(つちぐもやそめ)の話もあり、山に居構えて大和朝廷に抵抗したが、全滅させられたとある。八十(やそ)は大勢の意であり、多くの女性首長層が大和朝廷に反抗して壮絶な最期を遂げたと解釈されている。この土蜘蛛八十女の所在を大和側に伝えたのも、地元の女性首長であり、手柄をあげたとして生き残ることに成功している。
このようにヤマト王権と敵対した勢力は土蜘蛛の名として登場しています。
前回特定した邪馬台国の場所筑紫平野の旧山門郡、現在の久留米市やみやま市が登場する上記アンダーライン部分、第14代仲哀天皇の妃である神功皇后が田油津媛という土蜘蛛を誅殺したとあります。
邪馬台国の南に位置する熊襲を竹内宿禰と撃った直後久留米で田油津媛を撃ったようです。
それを証明するかのように久留米には祇園山古墳に寄り添うように高良大社が併設されています。

祇園山古墳

久留米の権現塚古墳とみやま市の権現塚古墳
赤星が祇園山古墳の位置
赤星が祇園山古墳の位置

久留米の権現塚古墳

みやま市の権現塚古墳

みやま市の近くにある蜘蛛塚

蜘蛛塚
普通に考えれば田油津媛の墓が蜘蛛塚とは考えにくく、みやま市の権現塚古墳の可能性が高いのです。従ってそれよりも大規模な久留米市の権現塚古墳が田油津媛の先々代である卑弥呼の墓であると仮定できます。

ご覧のようにこの塚は前方後円墳であったものが無惨にも国道によって前方部分が破壊されています。
いかにも土蜘蛛に対する杜撰な対応とその先々代の墓を見守るような場所から神功皇后と竹内宿禰が見下ろしているかのようです。
ですが、これも想像に過ぎません。権現塚古墳と神功皇后の次期が卑弥呼の死から100年ずれているからです。二つの権現塚古墳も同じく4世紀頃の古墳と考えられています。
ここで考古学的観点から第7代孝霊天皇の皇女である倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)の墓とされる箸墓古墳が240〜260年に作られていることが放射性炭素年代測定で分かったことと、巫女的な女性であったことで、卑弥呼に比定され近畿説の有力な候補となっています。
このように決定的な資料と史料が欠けている為に九州説と畿内説は現在でも決着が付かず、近年は四国説や陰謀論の類いまで登場して益々混迷しているのです。
決着しないからこそ記紀から意図的に隠されたと考えると、邪馬台国とヤマト王権が同時に存在していた事、邪馬台国が朝貢してしまった事実を歴史から抹消する目的があったのかも知れません。
武内宿禰の73世であった子孫故竹内睦泰氏は古事記には系図と空間と時間の嘘があると明言しています。
竹内氏はまた、5代考昭、6代孝安、7代孝霊、8代孝元と考の付く天皇の都は九州にあったということも発言されてもいました。
では一体何の為に邪馬台国と卑弥呼を隠したのでしょうか。
それはきっと皇統の正当性と国防の観点から日本の平和と国民の安寧を願ってのことだったに違いありません。
統治と祭祀を分けたことも天皇の地位を争っての殺し合いも隠す事なく残したことも全てがここにあったのでしょう。
稚拙な文章を最後まで読んで頂きいつも有難う御座います。