
我々日本人にとって、江戸時代後期には写真のような妖怪チックである人魚が一般的と言える。
したがって未確認生物UMA観は拭い去れない。

ネット上では人魚と日本軍を融合させた都市伝説がまことしやかに語られているが、これも半分オカルトとして懐疑的に捉えてはいる。
インドネシアではオランウータンは森の人
というマレー語が語源のようだ。
この話もオランイカン、魚の人、つまり人魚の話である。
男性は山口歩兵第42連隊第一大隊第三中隊所属、堀駒太郎軍曹とキャプションがあり、インドネシアカイ諸島の原住民の報せで捕らえた人魚の容姿を克明に記録し、数百人で食したというものだ。
だが冒頭の人魚と明らかに違う点は尾鰭でなく手足があることだ。
「塩漬けにして焼き魚として食べ、鯨よりも美味しい」との記述からも"魚"としているが、オランウータンよりも人間に近いものを食べているのだ。
これらのことからもUMA、都市伝説の域を出ない日本軍のネガキャンとも考えられるのである。
更に人肉のキーワードで広げていくと、父島事件、又は小笠原事件というストレートな人肉事件が史実としてwikiには存在する。
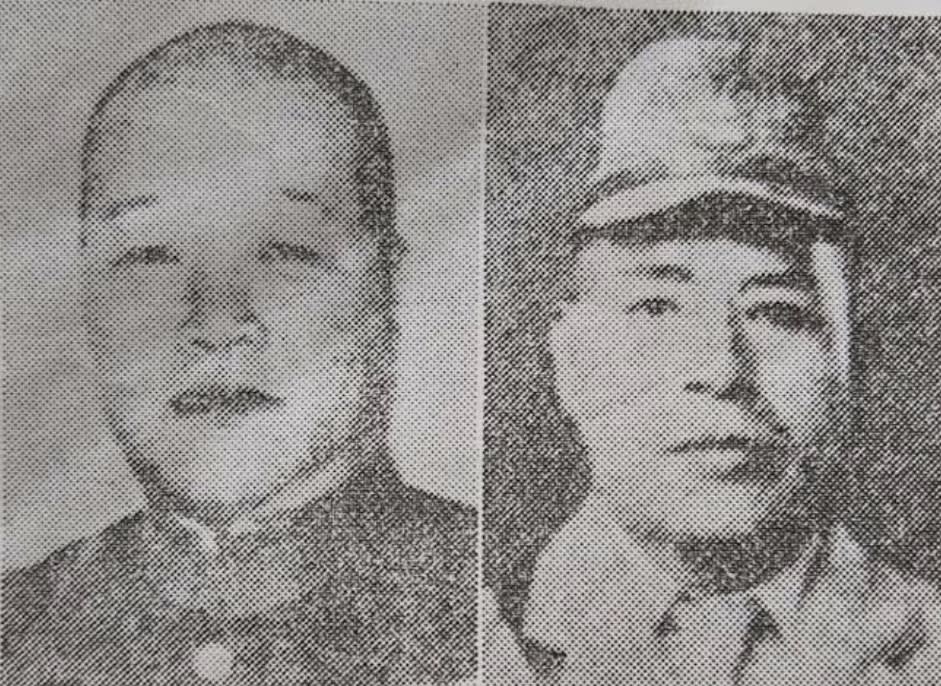
『昭和20年に小笠原諸島父島において日本の陸海軍高級幹部が、アメリカ軍航空部隊の搭乗員である捕虜8名を処刑し、そのうち5名の人肉を嗜食した事件。父島事件とも』
と事件概要としてはあまりにも杜撰である。
裁判では捕虜殺害と死体損壊のBC級戦犯として裁かれたが、父島に派遣され、後に日弁連の会長にもなる土屋公献は米兵と会話も交わし事件を否定している。
このように、人肉食という濡れ衣は日本軍人の残虐性を高める恰好の材料、真実味のあるネガキャンとして人魚伝説とリンクするのである。
時を経るということは真実も虚構もおしなべて記憶は薄れていくものであるが、こと日本軍に関しては鵜呑みにせず懐疑的に慎重になったほうが良いだろう。









