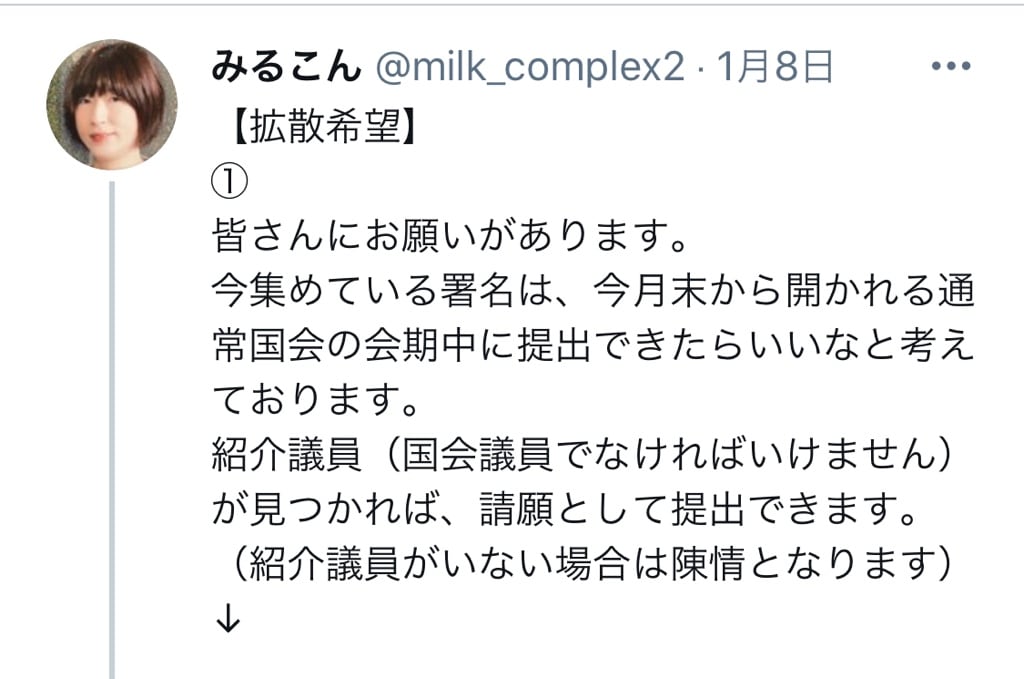クラウゼヴィッツは戦争論の中で「戦争とは他の手段をもってする政治の継続」であると書いている。
政治の延長上にあり、なんら政治と変わらないものが戦争だと言える。つまり、戦争と政治は同義であるのだ。
いや、同義であったといったほうが良いだろう。現代日本は国権の発動たる戦争は放棄しており、同義ではないのだ。
この戦争論日本へは幕末頃入って来ていたようだが、森鴎外が留学先から持ち込み軍人達に認知され軍人勅諭に影響を与えたと言われる。
一方世界最終戦論を書いた石原莞爾がこの戦争論から影響を受けたかは定かではないが、読んでいたことは確実である。
自身の最終戦争論を元に満蒙領有計画を立案し(1928)満州事変に突入(1931)、226事件を鎮圧し(1936)、 北支事変が勃発(1937)するも石原は不拡大方針であくまで対ソ戦のために満州での軍拡を主張し反対した。
参謀本部から関東軍へ左遷、東條との確執もあり、参謀副長を罷免され、また左遷。
世界最終戦論が刊行され(1940)翌年予備役となる。
クラウゼヴィッツが戦争と政治を結び付けたことが、後々それぞれの過程で戦争を招いたとしても、結果シビリアンコントロールが確立される要因となったことは非常に意義深いと言えよう。
戦争を肯定はしないが、世界が近代化していく過程で世界大戦へと膨張したことは逃れようのない過程であったとも考えられる。
天才石原莞爾が世界最終戦後の平和を待望して満州事変を実行したが、対ソ戦を経てから米国との最終戦を想定してのことである。
それに反発するように、中国との戦いが深みにはまって長期化して行ったことは、石原が時の流れからも裏切られ孤立していった状況に見ることが出来る。
対米戦が不可避であったことや、その戦い方は石原の予言通りに、加速して実現してゆく。
戦争が政治の継続と言ったクラウゼヴィッツや世界戦後に平和が訪れると言った石原が好戦的であったかとの問いには両者とも否定的に捉えたほうが良い。
つまり平和とは勝ち負けではなく戦争の多大なる犠牲の上にしか築けないという非常に観念的なものであると言えるのである。
戦争を経験したものが、現在の戦争の無い時代を平和と捉えて実感することは当然だ。
私を含めた経験していないもの達は単に戦争の無い時代が平和というように、観念的なものとして捉えていることは、両者のように戦時中にあった者との平和の概念と合致するのではないだろうか。
つまり、石原が戦時中に最終戦を想起している時点で平和を希求して逆算的に今何をどうするという戦術を立案していたように思えるのだ。
秀才東條が天才石原を左遷したことは綿密な計画で突拍子もないことを秘密裏に且つ的確に成し遂げた暴走性を警戒してのことだったのかもしれない。
226事件で顕著となったように陸軍には派閥が存在してた。
統制派と皇道派である。自らを満州派と語った石原がこの事件を鎮圧したのも派閥に属さない立ち位置からだからだろう。
そんな石原の印象を昭和天皇は
「一体石原という人間はどんな人間なのか、よく分からない、満洲事件の張本人であり乍らこの時の態度は正当なものであった」と語っている。
永田鉄山と荒木貞夫
昭和8年6月の陸軍全幕僚会議
大勢は「攻勢はとらぬが、軍を挙げて対ソ準備にあたる」
「将来の陸軍大臣」「陸軍に永田あり」「永田の前に永田なく、永田の後に永田なし」
と形容された参謀本部第二部長の永田一人が反対
「ソ連に当たるには支那と協同しなくてはならぬ。それには一度支那を叩いて日本のいうことを何でもきくようにしなければならない。また対ソ準備は戦争はしない建前のもとに兵を訓練しろ」
これに対し荒木貞夫陸軍大臣
「支那を叩くといってもこれは決して武力で片づくものではない。しかも支那と戦争すれば英米は黙っていないし必ず世界を敵とする大変な戦争になる」と反駁。
対支戦争を考えていた永田は、対ソ戦準備論の小畑敏四郎と激しく対立し、これが皇道派と統制派の争いになる。
226事件により皇道派が粛清されると統制派で纏まっていく。つまりこの事件をきっかけに対支那へと舵を切ることとなる。
支那事変の拡大を否定的に捉えていた石原であるが、支那事変の原動力、お手本となったものが自身の起こした満州事変であり、その流は天才石原でも止めることはできなかった。
暴力的な武力を使って相手を屈服させるのが戦争であって、両者は何も好き好んで戦争に挑んだ訳ではない。
したがって石原の戦争論は現実的で仮に支那事変を早々に切り上げてソ連に向かっていれば、少なくとも東條が戦犯として裁かれることはなかったかも知れない。
下の者には優しく、上司、例えば東條に厳しく馬鹿にしていた石原は戦後東條が戦犯指名された時でさえ東條には何の思想もないとこき下ろした。東條暗殺まで画策した石原は自分が戦犯指名を逃れ、憎き東條が戦犯となったことで寧ろGHQを嘲笑したかったようにも思える。
東京裁判酒田法廷で、「トルーマンが戦争犯罪人だ」と主張した。
また、判事に歴史をどこまでさかのぼって戦争責任を問うかを尋ね、およそ日清・日露戦争までさかのぼるとの回答に対し、「それなら、ペリーをあの世から連れてきて、この法廷で裁けばよい。もともと日本は鎖国していて、朝鮮も満州も不要であった。日本に略奪的な帝国主義を教えたのはアメリカ等の国だ」と返した。
統帥権の独立の欠陥を利用して起こした満州事変がそれを手本に統制派が支那事変へと深みにはまって行き、東條が首相と陸相、軍需相更に参謀総長を兼任し、統帥権の独立の欠陥を解消した時には奇しくも対米開戦に突入という時既に遅しという数奇なタイミングとなった。
これを東條幕府や独裁と呼ぶ者、その東條が戦犯として処刑されスケープゴートにされたことを未だにA級戦犯とするような日本人は戦後体制から抜け出せない忘恩の徒なのである。