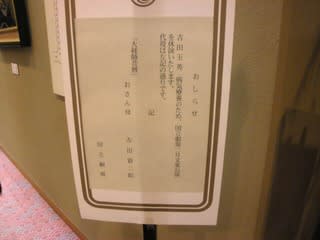
溝口健二監督の映画『近松物語』の原作として知られる、「大経師昔暦(おさん茂兵衛)」。歌舞伎でもあまりやらないし、文楽でも・・・。ということを考えると、なぜ、溝口が近松の数ある作品のうちでコレを選んだのか、なかなかの謎だって気もしますが、まずは舞台の感想を書きましょう。さて・・・。
話は、今でいうカレンダー屋さんの奥さんと手代の不倫モノ。ただ注意が必要なのは、カレンダー(暦)作りって商売がかつては許認可事業みたいになっていて、大変儲かる商売だったということと、妻の不倫は犯罪だったという二点でしょう。
で、映画との違いでいうと、映画の大経師夫婦は若い妻と老いた夫の「年の差カップル」という設定だったのにたいして、原作では特にそういう夫婦事情は強調されていない。
これは、映画の場合、若い香川京子を主演にしたための辻褄で、三十以上年の離れた夫婦ということにしたというなんですかね?(ただし、実説に近い、西鶴の「好色五人女」に出てくる「おさん」は歳の離れた妻という設定にはなっている。)
また、手代茂兵衛も、戦後にこの浄瑠璃を復活させた先代の竹本綱大夫(今の咲大夫のお父さん)の芸談によると、「茂兵衛は童貞だと思って語っている」そうだから、初心(うぶ)な若者という設定が本来のものなんでしょうね~。
しかし、ここでも、映画で演じているのが世紀の二枚目スター・長谷川一夫なので、いくらなんでも初心な設定になりようがなく、おさんよりかなり年上の艶っぽい手代ということで、作り手も観客も納得しているんだと思います。
で、なんで改めて登場人物の設定を確認しているのかというと、この原作、かなり性的な暗示、隠喩に満ちているからなんですよね。
冒頭の詞章の猫に関するくだりから、夫がちょっかいを出している女中お玉とおさんが寝所を交換する理由にいたるまで、なかなか相当に艶っぽいことになっているんですよ。
そもそも、同じ近松作品にも「堀川波の鼓」や「鑓の権三」みたいな人妻不倫物が存在しますが、どちらにもいえるのは女性の方がわりあい積極的で、奔放ですらあるということ。
なので、映画と芝居の違いは近世と現代の女性観の違いが背景にあるといえるんじゃないですかね?
さて、このあたりで舞台にひきつけた感想。
最初の場面、大経師内の段では夫・大経師以春が後ろ髪の長い、ちょっとホストっぽい若々しい男として描かれているのが面白い。映画の進藤英太郎みたいな太った初老のオジサンではないんですよね~。
また、人形で描かれる大店の人妻というのは、人形遣いがベテランの吉田文雀だからということもあるけれど、落ちついた風で香川京子よりはしっとりとしている。
ここの切場語りは綱大夫だったんだけど、CDになっている「曽根崎心中」の頃に比べると、枯れ切った語り口で、最後のおさん茂兵衛が暗闇で交わり、それぞれが思っていた相手(おさんは夫、茂兵衛はおたま)とは違う相手だったことに気づくくだり。
文楽でも珍しい、大夫の静かな語り「おさんさまか・・・」「茂兵衛か・・・」で幕になるところが、今の綱大夫だからこその深い味わい。ここは思わず息を呑みましたね~。
で、次がお玉の後見人・梅龍の家の前。岡崎村梅龍内の段。
ここは梅龍とおさんの父母が登場する親子情愛ネタの場面で、おさん茂兵衛の逃亡を助けるくだり。映画では省略された場面である一方、西鶴の「好色五人女」にも出てこないので、近松の浄瑠璃特有の場面だといえると思うのですが、ここは住大夫の語りが絶品。
やはり、このひとは老人の語りに情があっていいですね~。ただ、住大夫だから感動したのであって、他の大夫だったらどう思ったかどうか・・・。というのも、ありきたりといえばありきたりな場面ではありますからね~。(物干しのそばに立つ二人の影が、徒刑台を連想させたりして。)
ただ、悪役の手代・助右衛門(映画では小沢栄がやってた役ね。)がお玉を縄で縛って駕篭で梅龍のところに連れてくる冒頭は、お玉の人形が妙に可愛らしくて印象的(人形は豊松清十郎)。因みに、近松作品の女中の名は皆「お玉」だということだそうですね・・・。何か意味があるのかな?
そして、次が二人が逃げ隠れる奥丹波隠れ家の段。
前の段から、文雀のおさんの人形がしっとりと艶っぽくていいんですよね。たぶん、落ち延びてからの方がいいんじゃないでしょうか、雰囲気があって。
ただ、この場面、最終的に二人はお縄になるんですが、梅龍が二人のためにお玉を殺して首を切り、駆けつけるという設定。それで、二人を許してくれとお上に頼むわけですが、「お玉を殺さずに証人として出せば、二人は助けられたかもしれなかった」と役人が言い出すくだりはいかがなものか・・・。
要するに、梅龍の行動は勇み足だったということになるのですが、前の段の住大夫の語りによるこの役の説得力が、ココで急に地に落ちてしまう印象。
梅龍は映画でもチラッとしか出てきませんが、ココを省略した溝口は慧眼だったという気がするなあ~。
一方、西鶴になく、近松にあったのが、以春の浮気心や軽薄な助右衛門みたいな悪役キャラで、近松になくて溝口にあったのが、以山のような、以春の同業他社で人間臭くてズルイ人物だというあたり。それぞれの作家の特異性がわかるのではないでしょうか?(この映画に限らず、溝口は脇役に醜い世間そのものみたいなキャラを使いますよね~。)
なお、近松の原作では、市中引き回しの最中にお坊さんが二人の命を助けるという場面が出てきますが、そのくせ、二人の命日が同じ日であるという微妙な内容で話は終わります。
芝居では、命が助かるという締まらなさが問題なのか、市中引き回しまでは演じられないのが普通のよう。
しかし、この演目は歌舞伎では片岡仁左衛門家が大当たりを取っていたということらしいので、今の仁左衛門で、引き回し中に命が助からない改作でもして上演したら面白そうだと思うんですけど、どうですかね~。玉三郎と共演で!
以上、比較も交えた感想でした。
PS:そういえば、以前、歌舞伎座で梅玉&時蔵コンビでやっていましたね。悪くはなかった記憶があるけれど・・・。
話は、今でいうカレンダー屋さんの奥さんと手代の不倫モノ。ただ注意が必要なのは、カレンダー(暦)作りって商売がかつては許認可事業みたいになっていて、大変儲かる商売だったということと、妻の不倫は犯罪だったという二点でしょう。
で、映画との違いでいうと、映画の大経師夫婦は若い妻と老いた夫の「年の差カップル」という設定だったのにたいして、原作では特にそういう夫婦事情は強調されていない。
これは、映画の場合、若い香川京子を主演にしたための辻褄で、三十以上年の離れた夫婦ということにしたというなんですかね?(ただし、実説に近い、西鶴の「好色五人女」に出てくる「おさん」は歳の離れた妻という設定にはなっている。)
また、手代茂兵衛も、戦後にこの浄瑠璃を復活させた先代の竹本綱大夫(今の咲大夫のお父さん)の芸談によると、「茂兵衛は童貞だと思って語っている」そうだから、初心(うぶ)な若者という設定が本来のものなんでしょうね~。
しかし、ここでも、映画で演じているのが世紀の二枚目スター・長谷川一夫なので、いくらなんでも初心な設定になりようがなく、おさんよりかなり年上の艶っぽい手代ということで、作り手も観客も納得しているんだと思います。
で、なんで改めて登場人物の設定を確認しているのかというと、この原作、かなり性的な暗示、隠喩に満ちているからなんですよね。
冒頭の詞章の猫に関するくだりから、夫がちょっかいを出している女中お玉とおさんが寝所を交換する理由にいたるまで、なかなか相当に艶っぽいことになっているんですよ。
そもそも、同じ近松作品にも「堀川波の鼓」や「鑓の権三」みたいな人妻不倫物が存在しますが、どちらにもいえるのは女性の方がわりあい積極的で、奔放ですらあるということ。
なので、映画と芝居の違いは近世と現代の女性観の違いが背景にあるといえるんじゃないですかね?
さて、このあたりで舞台にひきつけた感想。
最初の場面、大経師内の段では夫・大経師以春が後ろ髪の長い、ちょっとホストっぽい若々しい男として描かれているのが面白い。映画の進藤英太郎みたいな太った初老のオジサンではないんですよね~。
また、人形で描かれる大店の人妻というのは、人形遣いがベテランの吉田文雀だからということもあるけれど、落ちついた風で香川京子よりはしっとりとしている。
ここの切場語りは綱大夫だったんだけど、CDになっている「曽根崎心中」の頃に比べると、枯れ切った語り口で、最後のおさん茂兵衛が暗闇で交わり、それぞれが思っていた相手(おさんは夫、茂兵衛はおたま)とは違う相手だったことに気づくくだり。
文楽でも珍しい、大夫の静かな語り「おさんさまか・・・」「茂兵衛か・・・」で幕になるところが、今の綱大夫だからこその深い味わい。ここは思わず息を呑みましたね~。
で、次がお玉の後見人・梅龍の家の前。岡崎村梅龍内の段。
ここは梅龍とおさんの父母が登場する親子情愛ネタの場面で、おさん茂兵衛の逃亡を助けるくだり。映画では省略された場面である一方、西鶴の「好色五人女」にも出てこないので、近松の浄瑠璃特有の場面だといえると思うのですが、ここは住大夫の語りが絶品。
やはり、このひとは老人の語りに情があっていいですね~。ただ、住大夫だから感動したのであって、他の大夫だったらどう思ったかどうか・・・。というのも、ありきたりといえばありきたりな場面ではありますからね~。(物干しのそばに立つ二人の影が、徒刑台を連想させたりして。)
ただ、悪役の手代・助右衛門(映画では小沢栄がやってた役ね。)がお玉を縄で縛って駕篭で梅龍のところに連れてくる冒頭は、お玉の人形が妙に可愛らしくて印象的(人形は豊松清十郎)。因みに、近松作品の女中の名は皆「お玉」だということだそうですね・・・。何か意味があるのかな?
そして、次が二人が逃げ隠れる奥丹波隠れ家の段。
前の段から、文雀のおさんの人形がしっとりと艶っぽくていいんですよね。たぶん、落ち延びてからの方がいいんじゃないでしょうか、雰囲気があって。
ただ、この場面、最終的に二人はお縄になるんですが、梅龍が二人のためにお玉を殺して首を切り、駆けつけるという設定。それで、二人を許してくれとお上に頼むわけですが、「お玉を殺さずに証人として出せば、二人は助けられたかもしれなかった」と役人が言い出すくだりはいかがなものか・・・。
要するに、梅龍の行動は勇み足だったということになるのですが、前の段の住大夫の語りによるこの役の説得力が、ココで急に地に落ちてしまう印象。
梅龍は映画でもチラッとしか出てきませんが、ココを省略した溝口は慧眼だったという気がするなあ~。
一方、西鶴になく、近松にあったのが、以春の浮気心や軽薄な助右衛門みたいな悪役キャラで、近松になくて溝口にあったのが、以山のような、以春の同業他社で人間臭くてズルイ人物だというあたり。それぞれの作家の特異性がわかるのではないでしょうか?(この映画に限らず、溝口は脇役に醜い世間そのものみたいなキャラを使いますよね~。)
なお、近松の原作では、市中引き回しの最中にお坊さんが二人の命を助けるという場面が出てきますが、そのくせ、二人の命日が同じ日であるという微妙な内容で話は終わります。
芝居では、命が助かるという締まらなさが問題なのか、市中引き回しまでは演じられないのが普通のよう。
しかし、この演目は歌舞伎では片岡仁左衛門家が大当たりを取っていたということらしいので、今の仁左衛門で、引き回し中に命が助からない改作でもして上演したら面白そうだと思うんですけど、どうですかね~。玉三郎と共演で!
以上、比較も交えた感想でした。
PS:そういえば、以前、歌舞伎座で梅玉&時蔵コンビでやっていましたね。悪くはなかった記憶があるけれど・・・。
 | 田中澄江の心中天の網島 (集英社文庫―わたしの古典)田中 澄江集英社このアイテムの詳細を見る |
 | 富岡多恵子の好色五人女 (集英社文庫―わたしの古典)富岡 多恵子集英社このアイテムの詳細を見る |
 | 近松物語 [DVD]角川エンタテインメントこのアイテムの詳細を見る |



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます