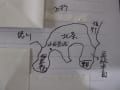平成27年7月20日(海の日)、梅雨が明け、海に行くには絶好な日和、私たち夫婦は、こんな題目の講演会に行った。
会社を経営しているわけではないし、ましてや子どもたちに残す遺産があるわけではないのに、歴史好きな私は、この武田氏の滅亡の真相を知りたくて、申し込んだ。
果たして、期待の裏切らない内容で、私は面白かった。



まずは、相模原と信玄の接点を話された。
それは、相模原にある八景(はけ)の棚には「さいかち」という樹?植物?が群生している。それは信玄が三増合戦の戦勝を祝って、植えたもので、また、中腹一帯の横穴には、敗軍の将士の自刃のところだということが、昭和43年にこの地に建てられた碑に書かれていると話してくれた。
ほー、津久井の方で勝ち名乗りを上げたと聞いていたが、景勝と言われているこの地でもこういうことをしていたんだなと感慨深く思った。

そして、いよいよ、武田家の滅亡の話に入る。
「戦国屈指の大名武田信玄の功績は、言うまでもないが、あまりに自分に自信があり過ぎ、自分亡き後の課題の認識が甘かったと言わざるおえない」と、講師の真崎正剛氏が熱弁を振るっていた。
なるほど、信玄の遺言を見ても、勝頼をないがしろにするようなものになっていて、真崎氏が言うように、あれじゃあモチベーションが上がらないよなと思った。
信玄の遺言というのはこうだ。
①自分が死んだら、三年間は喪を隠せ これは有名なことだ。
②勝頼の子信勝を武田家第 28代当主とするが、16歳になるまでは勝頼を「陣代(信勝の代理)」とする。た だし、兜は使ってもよいが、それ以外のものは使ってはならない。有名な「風林火 山」の旗も自分で作れとも。 なんじゃこれ?
勝頼の妻は、信玄の政略により、昔はまだ友好関係にあった「今は宿敵」織田信長の 養女である。だから信勝は、血のつながりはないが信長を祖父に持つことになる。
③勝頼は武田の諸将を朋輩と思うべきだ。決して家臣などと低く見てはならない。
④弟の信廉は予の影武者を務めよ
どうしてこんな遺言を書いたのか?どうも勝頼のことを嫌っていたのではなく、側室の子だという出生に秘密があるらしい。
勝頼は信玄の4番目の子で、その前の3番目までは、正室三条家の子どもである。
嫡男である義信が家督を継げば、何の問題もなかったのだが、義信は、今川家から嫁をもらっている。桶狭間の戦いで信長が義元を撃ったことで、京に上る近道は東海地方から進みたいと思った信玄は、今川義元の娘である嫁や今川家と親密な関係を持っている義信は、邪魔になると考えたらしい。義信は、30歳にして非業な最期を遂げている。病死か自刃かそれとも殺されたのか分からないということだ。次男は目が見えなくて坊さんになっていて、三男は病死。4番目である勝頼が武田家を継がなければならない状況に追い込まれてしまったということだ。
また勝頼を生んだ側室は、諏訪氏の姫で、諏訪大社の大祝(おおほうり)の一族で、一言で言えば「生き神様の一族」という、えらく由緒あるところから迎えてきた。
また、正式に「武田勝頼」に襲名したのは、信玄が死ぬたった2年前だという。そして、何の官位ももらっていない状態であったという。普通、大名が家督を相続するには、まして、源氏の流れを汲む大大名であるのだから、官位をいただくのは当たり前なのに、信玄はそういう手はずもせずに亡くなっている。可哀相といえば可哀相である。
そんな勝頼だから、自分の存在を示すためには、勝って勝って勝ちまくって、自分を誇示したかったのであろう。1574年には、難攻不落な遠江の高天神城を攻略し、領土を拡大している。
長篠の合戦では、老臣は戦わないことを勧めたが、無理強いしてこういう結果を招いてしまった。信玄が死んで(1573年、信州伊那駒場にて病死)、10年足らずで、武田家が滅亡(1582年3月、甲斐天目山にて勝頼自刃)という悲劇も起きなかったと思う。
ここに、真崎氏がいう「継がせるための教訓・継ぐがわのための教訓」を載せておく。


会社を経営しているわけではないし、ましてや子どもたちに残す遺産があるわけではないのに、歴史好きな私は、この武田氏の滅亡の真相を知りたくて、申し込んだ。
果たして、期待の裏切らない内容で、私は面白かった。



まずは、相模原と信玄の接点を話された。
それは、相模原にある八景(はけ)の棚には「さいかち」という樹?植物?が群生している。それは信玄が三増合戦の戦勝を祝って、植えたもので、また、中腹一帯の横穴には、敗軍の将士の自刃のところだということが、昭和43年にこの地に建てられた碑に書かれていると話してくれた。
ほー、津久井の方で勝ち名乗りを上げたと聞いていたが、景勝と言われているこの地でもこういうことをしていたんだなと感慨深く思った。

そして、いよいよ、武田家の滅亡の話に入る。
「戦国屈指の大名武田信玄の功績は、言うまでもないが、あまりに自分に自信があり過ぎ、自分亡き後の課題の認識が甘かったと言わざるおえない」と、講師の真崎正剛氏が熱弁を振るっていた。
なるほど、信玄の遺言を見ても、勝頼をないがしろにするようなものになっていて、真崎氏が言うように、あれじゃあモチベーションが上がらないよなと思った。
信玄の遺言というのはこうだ。
①自分が死んだら、三年間は喪を隠せ これは有名なことだ。
②勝頼の子信勝を武田家第 28代当主とするが、16歳になるまでは勝頼を「陣代(信勝の代理)」とする。た だし、兜は使ってもよいが、それ以外のものは使ってはならない。有名な「風林火 山」の旗も自分で作れとも。 なんじゃこれ?
勝頼の妻は、信玄の政略により、昔はまだ友好関係にあった「今は宿敵」織田信長の 養女である。だから信勝は、血のつながりはないが信長を祖父に持つことになる。
③勝頼は武田の諸将を朋輩と思うべきだ。決して家臣などと低く見てはならない。
④弟の信廉は予の影武者を務めよ
どうしてこんな遺言を書いたのか?どうも勝頼のことを嫌っていたのではなく、側室の子だという出生に秘密があるらしい。
勝頼は信玄の4番目の子で、その前の3番目までは、正室三条家の子どもである。
嫡男である義信が家督を継げば、何の問題もなかったのだが、義信は、今川家から嫁をもらっている。桶狭間の戦いで信長が義元を撃ったことで、京に上る近道は東海地方から進みたいと思った信玄は、今川義元の娘である嫁や今川家と親密な関係を持っている義信は、邪魔になると考えたらしい。義信は、30歳にして非業な最期を遂げている。病死か自刃かそれとも殺されたのか分からないということだ。次男は目が見えなくて坊さんになっていて、三男は病死。4番目である勝頼が武田家を継がなければならない状況に追い込まれてしまったということだ。
また勝頼を生んだ側室は、諏訪氏の姫で、諏訪大社の大祝(おおほうり)の一族で、一言で言えば「生き神様の一族」という、えらく由緒あるところから迎えてきた。
また、正式に「武田勝頼」に襲名したのは、信玄が死ぬたった2年前だという。そして、何の官位ももらっていない状態であったという。普通、大名が家督を相続するには、まして、源氏の流れを汲む大大名であるのだから、官位をいただくのは当たり前なのに、信玄はそういう手はずもせずに亡くなっている。可哀相といえば可哀相である。
そんな勝頼だから、自分の存在を示すためには、勝って勝って勝ちまくって、自分を誇示したかったのであろう。1574年には、難攻不落な遠江の高天神城を攻略し、領土を拡大している。
長篠の合戦では、老臣は戦わないことを勧めたが、無理強いしてこういう結果を招いてしまった。信玄が死んで(1573年、信州伊那駒場にて病死)、10年足らずで、武田家が滅亡(1582年3月、甲斐天目山にて勝頼自刃)という悲劇も起きなかったと思う。
ここに、真崎氏がいう「継がせるための教訓・継ぐがわのための教訓」を載せておく。