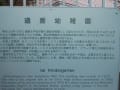令和6年12月28日(土)~30日(月)、「名湯・有馬温泉と京都伏見稲荷大社と平等院、神戸港ディナークルーズを愉しむ年末3日間」のツアーに行ってきた。子どもたちは独立し、年末は時間があるので、ゆったり温泉でもということで、まだ行ったことのない有名な有馬温泉というチラシにひかれて申し込んだ。秀吉が千利休を引き連れて、たびたび茶会を開いた場所である。
また、今回の旅行で一番印象に残ったのは、外国人の多さである。京都の駐車場では、バスを一つの場所に置いておけなくて、どんどん下ろしては違う場所に行って、時間になったら迎えに来るというようなピストン輸送をしていた。そこで少し早めに見学を終えてその駐車場に行ってバスを待っていると、私たちの周りはほぼ外国の方々で埋まってしまった。ここは日本なのかと目を丸くした。いくら円安で日本の物価は安いからって、日本の人気がわかる。
では、順に書いていこう。
新横浜駅から新幹線のひかりに乗って、新神戸駅へ。3時間くらいである。富士山に雪がなかった。



1日目は神戸港のクルーズである。
コンチェルトという船に乗って生演奏を聴きながらフレンチの夕食を食べた。










2日目は先ずは六甲山に行く。神戸の街並みや大阪湾を一望できるはずだったが、霧がかかっていてあまりはっきりとはいかなかった。
それに大輪田の泊りの方向を見たけどあまりよく分からなかった。平清盛が宋との貿易をしたところで、今までは物々交換だったけれど、初めて貨幣で取引をしたんだそうだ。清盛は貨幣経済の礎を築いたといっても過言ではないかもしれない。




いよいよ有馬温泉へ。太閤の湯という温泉施設で、館内着に着替えてお風呂に入る。足の角質を食べてくれるという「ドクターフィッシュ」もやってきた。最初はゾゾッとしたけど、慣れてきたら気持ちよくなった。
駅前の太閤橋や寧々の像も写真に収めてきた。















生田神社にも行ってきた。生田の森は、源平合戦の古戦場とはいうものの、全く面影はなかった。周りは開発され、神社の裏に少しだけの林が残っているだけである。梶原景時親子の奮戦を物語っている梅の木があった。

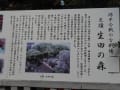








南京町では、龍の置物とヒスイの石を買った。



この日の夕食、目の前で神戸牛を鉄板焼きをしてくれるステーキはとても美味しかった。レアにして正解。

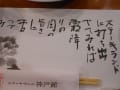





3日目は京都である。
先ずは伏見稲荷神社。千本鳥居が有名である。山の上の方まで鳥居が続いている。途中で抜けて入口まで戻る。







最後は宇治・平等院である。紫式部ゆかりの世界遺産、極楽浄土、開運出世のご利益があるといわれている。
藤原道長の別荘をその子頼道によって寺院に改めて建てられた。阿弥陀如来像を設置するための鳳凰堂が建てられた。それが左右対称で極楽浄土の宮殿をモデルにされた。25年位前に家族で行ったときは「はっ」と息をのむ荘厳な感じの印象があったが、今回はそんな感じはなく、10円玉に彫られているのと同じだなあくらいの印象である。












京都駅から新幹線ひかりに乗って帰ってくる。添乗員さんが551の豚マンがおいしいといっていて、それもその場で食べるのがやっぱり1番だとも。すごく並んでいたのでやめようと思ったが、時間があるのでやっぱり並んで買った。そしてベンチがあったのでその場で食べた。私の体は最近は植物油に慣れているので、動物油は少し抵抗があるみたいだ。これからは並んでまでは買わないかなあ

とはいえ、また新たな発見や知識が増えた3日間であった。こうやって旅行をしてみると、世の中は様々な歴史の上に成り立っているとつくづく感じる。感謝である。
また、今回の旅行で一番印象に残ったのは、外国人の多さである。京都の駐車場では、バスを一つの場所に置いておけなくて、どんどん下ろしては違う場所に行って、時間になったら迎えに来るというようなピストン輸送をしていた。そこで少し早めに見学を終えてその駐車場に行ってバスを待っていると、私たちの周りはほぼ外国の方々で埋まってしまった。ここは日本なのかと目を丸くした。いくら円安で日本の物価は安いからって、日本の人気がわかる。
では、順に書いていこう。
新横浜駅から新幹線のひかりに乗って、新神戸駅へ。3時間くらいである。富士山に雪がなかった。



1日目は神戸港のクルーズである。
コンチェルトという船に乗って生演奏を聴きながらフレンチの夕食を食べた。










2日目は先ずは六甲山に行く。神戸の街並みや大阪湾を一望できるはずだったが、霧がかかっていてあまりはっきりとはいかなかった。
それに大輪田の泊りの方向を見たけどあまりよく分からなかった。平清盛が宋との貿易をしたところで、今までは物々交換だったけれど、初めて貨幣で取引をしたんだそうだ。清盛は貨幣経済の礎を築いたといっても過言ではないかもしれない。




いよいよ有馬温泉へ。太閤の湯という温泉施設で、館内着に着替えてお風呂に入る。足の角質を食べてくれるという「ドクターフィッシュ」もやってきた。最初はゾゾッとしたけど、慣れてきたら気持ちよくなった。
駅前の太閤橋や寧々の像も写真に収めてきた。















生田神社にも行ってきた。生田の森は、源平合戦の古戦場とはいうものの、全く面影はなかった。周りは開発され、神社の裏に少しだけの林が残っているだけである。梶原景時親子の奮戦を物語っている梅の木があった。

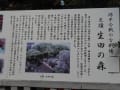








南京町では、龍の置物とヒスイの石を買った。



この日の夕食、目の前で神戸牛を鉄板焼きをしてくれるステーキはとても美味しかった。レアにして正解。

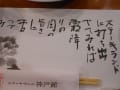





3日目は京都である。
先ずは伏見稲荷神社。千本鳥居が有名である。山の上の方まで鳥居が続いている。途中で抜けて入口まで戻る。







最後は宇治・平等院である。紫式部ゆかりの世界遺産、極楽浄土、開運出世のご利益があるといわれている。
藤原道長の別荘をその子頼道によって寺院に改めて建てられた。阿弥陀如来像を設置するための鳳凰堂が建てられた。それが左右対称で極楽浄土の宮殿をモデルにされた。25年位前に家族で行ったときは「はっ」と息をのむ荘厳な感じの印象があったが、今回はそんな感じはなく、10円玉に彫られているのと同じだなあくらいの印象である。












京都駅から新幹線ひかりに乗って帰ってくる。添乗員さんが551の豚マンがおいしいといっていて、それもその場で食べるのがやっぱり1番だとも。すごく並んでいたのでやめようと思ったが、時間があるのでやっぱり並んで買った。そしてベンチがあったのでその場で食べた。私の体は最近は植物油に慣れているので、動物油は少し抵抗があるみたいだ。これからは並んでまでは買わないかなあ

とはいえ、また新たな発見や知識が増えた3日間であった。こうやって旅行をしてみると、世の中は様々な歴史の上に成り立っているとつくづく感じる。感謝である。