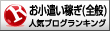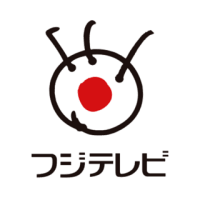3)中野百合子
九月の二学期が始まって一週間ほど経ったある日、行雄は授業に出た後、甘泉園の方へ散歩してみることになった。 大学の裏門を通り抜けて商店街に出たが、夏の蒸し暑さが残っていて、歩いていると汗がにじみ出てくる。
商店街から路地に入ると人通りもほとんどなくなり、日影になったので行雄はほっとした。 いつまでこの蒸し暑さが続くのだろうかと思いながら、彼は狭い路地から甘泉園前の広い通りに出た。
その通りを横切ろうと、行き交う車や自転車に注意しながら前方を見ると、小柄な男がうつむきながら右の方向へとぼとぼと歩いていた。 学生でもないようだし、さりとて社会人という風体でもない。
青白い顔をしたその男は元気のない様子で、歩き方も弱々しく一見して浮浪者のような印象を与える。 彼の横顔を見ているうちに、行雄は背筋がすう~っと寒くなるのを覚えた。 その男は大川勇だった。
大川が三池闘争で鼻硬骨を砕かれ、全学連の過激な闘争に疲れ果てたのか自殺を図って倒れていた時に、行雄は大久保の彼の家に見舞いに行ったが、会えなかったことがある。 あれ以来、行雄は自分のことでも大変だったので、大川のことをほとんど忘れていた。
その彼がいま、力ない足取りで歩いている。 行雄は通りを横切ると、甘泉園のことはすっかり忘れて本能的に大川の後をついていった。 暫く彼の後をつけながら、行雄は声をかけようかと思ったが、なぜか言葉が出なかった。なお暫く、行雄は大川の後をつけていく。
そのうちに、もし大川と話しを交わしても、語ることは何もないという気持になった。 今さら自分は元気にやっていると言っても、心身ともに傷ついた彼にとって、どれほどの意味があるのだろうか。 仮に二人が互いの“傷をなめ合った”としても、それが何になるというのだろうか。 行雄は空しさを感じて、大川の後をつけていくのを止め、遠ざかっていく彼の後ろ姿を見送った。大川はやがて行雄の視界から消えていった。
秋もたけなわの季節になり、行雄は平凡だが落ち着いた学生生活を送っていた。 自分の将来について少しは考えるようになったが、取り立てて進路を固めようという気持にもならなかった。「なるようになれ」が信条みたいなものだから、将来の進路について真剣に考えようとはしなかったのである。
ただ、このまま仏文科にいるのが良いのか、それとも好きな歴史の勉強をするため、第三学年の専門過程で史学科に移った方が良いのか考えることはあった。 しかし、行雄にとって、フランス文学はそれなりに楽しく思え、一部の作家、文学者に興味を惹かれるものがあった。
自分は文学の研究者には向いていないと思うが、場合によっては大学院に進んで少しは専門的に勉強したいという気にもなる。 当面は、いま置かれている仏文科で学んでいくうちに、いずれ自分の進路が見えてくるだろうと考えていた。 そうした在り来たりの学生生活を送っているうちに、行雄にとって生涯忘れることのできない、衝撃的な事態がやってくる。
その日は十一月七日だった。別にその日は特別の日ではない。 ただ、彼にとって終生忘れることのできない日になったから、覚えているだけである。 その日は、朝から暖かく穏やかな日和だった。“小春日和”というのがあるが、春のように暖かく晴れ渡った一日だった。
行雄はいつものように、北浦和駅から国電で赤羽経由、池袋で乗り継いで高田馬場駅で下車した。普段よりやや遅めに着いたので、彼は駅前からバスに乗った。 時間に余裕がある時は、二十分ほどかけて文学部の校舎まで歩くのだが、遅刻しそうな時などはバスを利用して通学していた。
この日は、バスの中はけっこう込み合っていたので、行雄は吊り革につかまりながら窓の外をぼんやりと眺めていた。 国電に乗っていた時から、十一月七日の今日は「ロシア革命」の記念日なんだと思っていた。
行雄のように、つい最近まで左翼の学生であった者には、ロシア革命記念日は十一月七日ということが、頭の中にこびりついているのである。 左翼の者には、ロシア革命記念日は“聖なる日”だから、脳裏に染み込んでいるのだ。従って、そう言えば今日は「ロシア革命記念日」だと、行雄は思い出したに過ぎない。 しかし、今の彼にとっては、そんな記念日はどうでもよいことだった。
大学へ向うバスは、交通渋滞でいつもよりのろのろと走っていた。 腕時計を見ると授業開始の十分ほど前だったので、行雄は少し時間が気になってきた。 今日の一時間目は、K教授がマルセル・プルーストの「失われた時を求めて」を講義することになっている。
K教授はいつも定刻に講義に出てくるので、行雄は自分が遅刻するのではと心配になってきた。 しかし、バスは相変らずのろのろと走っている。少し進んだかと思うと止まり、また動き出すという具合だ。
西早稲田のバス停で二十人余りの学生が降りると、前の座席が空いたので行雄はそこに腰かけた。 もう一度腕時計を見ると、授業開始時刻まで二、三分ほどしかなかった。これでは完全に遅刻だ、仕方がないと彼は諦めた。バスは相変らず、進んだり止まったりしている。
行雄はぼんやりと前方を見ていたが、後ろ向きの長身の男子学生の黒いズボンが、バスの動きに合わせて左右に小刻みに揺れている。 すらりと伸びたズボンの向う側に、女子学生の白いふくよかな両脚が垣間見えた。行雄はなんとなくその両脚に目をやっていた。
車内に強い日差しが射し込んでいて、少し暑苦しい感じがする。 馬場下の交差点に近づいた時、バスが急停車し、長身の学生の背中がぐらりと右に揺れ、黒いズボンの両脚も一、二歩右に動いた。
その瞬間、行雄の眼前にクラスメートの中野百合子の姿態が現われた。息を呑む一時であった。彼の視線は彼女の姿態に釘付けになっていた。 右に一、二歩動いた男子学生の背中は、元の位置に戻らなかったので、行雄の眼前には百合子の姿態が“あからさまに”現われたままである。
ふっくらとした頬、伏せた視線、水色のカーディガン、緑色のタイトスカート姿の百合子が目の前に座っている。 彼女は膝の上にベージュ色のカバンを置き、その上に淡いピンク色のハンカチを出していたが、多少いらいらした感じでそれを畳んだり広げたりしていた。
百合子はうつむいたままだったが、その様子は、他人に見られていることをはっきりと意識しているようだった。 相手がクラスメートなのに、行雄は声を掛けることも忘れていた。心の中でただ「ああ、中野さんだ、中野さんだ、中野さんだ!」と叫んでいるだけである。
彼は目のやり場がなくなった。 彼女の白く長い両脚が妙に視線にこびりついてくる。ふくよかな白い両脚はぴっちりと閉じられている。 行雄は無理やり視線をバスの前方へと移した。彼は一刻も早く大学前に着けばいいのにと、そればかりを念じていた。
馬場下の交差点を過ぎると、バスは勢いよく走り出した。 交差点を左折した時に、前にいる長身の男子学生が少し左に動いたため、百合子の姿態はほとんど見えなくなり行雄はほっとした。 バスの進行方向に大隈講堂が見えてきた。腕時計を見ると、授業開始時刻を五分ほど過ぎている。
バスが終点に着くと、学生達がぞろぞろと下車していく。 行雄は中野百合子を避けるため、一番最後に降りようと思って暫く座席に腰かけていた。遅刻などは、もうどうでもいいことだ。 彼は学生達の最後から降りようとして乗降口に近づいた。
そして、何気なくバスの外に目をやると、大柄な百合子が肢体を伸ばすようにして、先程まで行雄が座っていた座席の方に向って、さも“わざとらしく”微笑んでいる。 行雄は動転し暫く足が止まった。運転手が、何をしているのだと言わんばかりの表情で彼をにらみ付けた。
一瞬の後に、百合子は身を翻すと軽快な足取りで大学構内へと去っていく。 行雄の脳裏に、今度は百合子のわざとらしい微笑が焼き付き、彼はある種の衝撃を覚えながら、ゆっくりした歩調でキャンパスに入っていった。
百合子と同じ教室に居合わせるぐらいなら、いっそのことK教授の講義をサボってしまおうかとも考えたが、行雄は“機械仕掛け”のように足を動かして文学部の校舎に着いた。
今日の講義は地下一階の小教室で行なわれるため、正面階段を少し上って、右横の昇降口から地下へ下りなければならなかった。 行雄は重い気持で階段を二、三歩上った所で、ふと顔を上げると愕然として立ちすくんだ。 百合子が階段を下りてくるではないか!
彼女はとっくに教室に入っているはずだったのに、行雄を待ち構えていたのだ・・・そして、何食わぬ顔をして一歩、また一歩と非常にゆっくりと階段を下りてくる。 百合子のタイトスカートが太股で盛り上がって見え、彼女が一歩下りるたびに、その長くて太い大腿部の動きがはっきりと見て取れるのだ。
行雄は息を呑んだ。視線が合うと彼は思わず会釈した。 すると、今まで素知らぬ顔をしていた百合子の表情がパッと輝き、彼女は満面に笑みを浮かべて勢いよく階段を駆け下りてきた。
「村上さん、同じバスに乗っていたでしょ!」百合子の声が弾む。「うん、知ってた!」 行雄は悲鳴に近い声をあげると、彼女から逃れるようにして昇降口を駆け下りた。 百合子はその後を追うように足早に付いてくる。行雄の心臓は早鐘のように鼓動を打っていた。
二人が相次いで教室に入ると、K教授の講義はすでに始まっていた。「すいません」行雄はK教授に一言謝ると、前方の椅子に腰かけた。百合子は後方の座席についた。「失われた時を求めて」の教材を取り出して目をやったが、頭に血が上っているので、行雄は暫くの間、何がなんだか分からなかった。
プルーストの文章は、ただでさえ長たらしくて難解である。 気持が動転しているのですぐに分かるわけがない。彼は講義に沿って教材を読んでいくのを諦め、授業を聴いている風を装い心を静めようとした。
百合子との今日の出会いはなんと鮮烈だったことか。 いつも教室で顔を合わせている彼女なのに、今日はどうしてこんなに衝撃的な印象を受けたのだろうか・・・そんなことを考えているうちに、行雄の動揺はようやく治まってきた。 後方に座っている百合子の方をそっと見ると、彼女は何事もなかったかのように、平然とした様子で教材に目を落としていた。
その日から、行雄の脳裏に中野百合子の面影がこびりついて離れなくなった。 朝起きた時から夜寝るまで、百合子の幻影が絶えず行雄の脳裏にまとわりついた。彼女を想わない時間などは、一時もなかった。 食事をしていても、電車に乗っていても、講義を聴いている時も、百合子の幻影が迫ってくるのである。行雄は彼女の“呪縛”にかかり心の自由を失った。
十一月七日の出来事が、あの日の百合子の姿態が、走馬灯のように絶えず繰り返されて彼の脳裏を駆け巡る。 行雄は強いて他の事を考えようと努めたが、その努力はほとんど無駄であった。来る日も来る日も彼は百合子の幻影にまとわりつかれ、どうしようもない精神状態に追い詰められていった。
緑色のタイトスカートを盛り上げていた彼女の太くて長い大腿部、バスの中へ送ってきた“わざとらしい”微笑、パッと輝いて満面に笑みを浮かべたあの表情・・・それらが渾然一体となって、巨大な中野百合子の幻影を生み出してくるのである。
十一月中旬のある日、行雄は文学部の大教室で一般教養課目の文科人類学の講義を聴いていた。 文科人類学は嫌いな科目ではなかったが、彼は百合子のことで頭が一杯だったので、この日の受講はあまり身が入っていなかった。
行雄はN教授の講義をほとんど聞き流していたが、右の最前列に近い席で、“立ったまま”男子学生と何やら話しをしている女子学生の姿が目に留まると愕然とした。 百合子が男子学生からノートを返してもらっているようである。
講義中だというのに、大教室に大勢の学生がいるせいか、N教授はそうした事をほとんど気にしていないようだ。 百合子は男子学生とにこやかに言葉を交わした後、右端の通路を足早に後方へ去っていった。
行雄は彼女を目で追うことはなかったが、心の中で「ああ、中野さんだ、中野さんだ、中野さんだ!」と叫んでいた。 それまでのぼんやりした気分が一変して、怪しげな甘酸っぱい不安に駆られてきた。
一時して、左やや前方の五、六メートル離れた席に、人影が着席するのが視界に入った。 行雄がぎょっとして見ると、それは正しく百合子だった。彼女は明らかに行雄の存在を意識しているようだ。 彼はにわかに緊張して百合子の姿態を凝視した。
息が詰まるような状況になったが、行雄は気を取り直して講義を聴くことにした。 眼鏡をかけてがっしりした体格のN教授は、今や文科人類学の講義に熱弁をふるっている。 彼の赤ら顔が一層紅潮しているように見えた。行雄はN教授がとても熱心な人だという印象を受けていたので、これまでその講義に引き込まれることが多かった。
しかし、今は違う。百合子がすぐ側にいるのだ。 甘酸っぱい不安と胸騒ぎが彼の心を締めつける。行雄は怖いものでも窺うように、恐る恐る左前方に目をやった。 次の瞬間、百合子の潤んだ右の瞳が彼の視線をしっかりと捕らえた。彼女の目元と口元に艶やかな微笑が浮かび、その秋波は彼の視線を決して離すまいとしているようだった。
行雄は動転して息がつけなくなった。百合子の嫣(えん)然とした微笑は彼の心に“毒”を注ぎ込み、その精神を麻痺させた。行雄は完全に金縛りにあい、両眼は彼女の姿態に釘付けになった。
クリーム色のタイトスカートの中で、百合子の大腿部が上の方へうごめく。 その大腿部の暖かい血潮の流れが目に迫ってくるように感じられ、行雄の心臓は早鐘のように鼓動を打ち始めた。 ドキン、ドキンという鼓動が耳の奥に達してくる。彼はもうどうしてよいのか分からなくなった。
この異常な様子に気がついたのか、隣に座っていた男子学生がけげんな面持で行雄の方を見たので、彼はようやく我に返った。 行雄は急に恥ずかしくなり、百合子から目を離すとうつむいた。
その日から彼は、なんとしても百合子と親しく付き合いたいと考えるようになった。 同じクラスメートだから、仏文科専修の授業の際にはいつでも声を掛けることができるのに、行雄は気後れがして彼女に近づくことができなかった。
全学連で活躍していた頃、彼は自分の考えや主張を誰はばかることなく披瀝していたのに、いま百合子に対しては何も言えない状態なのだ。 どうしてこんなに意気地がなく尻込みしてしまうのかと、自分が歯がゆく思えてならない。
異性との交際は悪いことではないし、かつて雨宮和子や森戸敦子と付き合った時には、怖じ気づくようなことはほとんどなかったはずである。 しかし、中野百合子と交際しようと思うと、なぜか怖じ気づいてしまうのだ。 どうしてそうなるのか。そこには、何か得体の知れない恐るべきものが潜んでいるようだ。
和子や敦子にほとんど感じなかったものを、行雄は百合子に感じていたのだろう。それは“女性の肉体”というものだろう。 後日、その決定的な違いを彼は知るのだが、その当時は、自分がどうしてこんなに臆病になるのか理解できなかった。