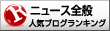11)艶・・・妄想
11月も半ばに差しかかると、歌舞伎研究会は早稲田祭の準備に追われていた。百合子は長唄の発表会があるのでその練習に余念がなかったようだが、行雄はまだ“新入り”なので大したことをやるわけでもなく、展示会場の手伝いをする程度だった。
そんなある日、徳田誠一郎が久しぶりに行雄に声をかけてきたので、二人は仏文科の講義が終ったあとS喫茶店に入った。「家庭教師の方は順調にいっている?」と徳田が聞いてきたので、行雄は「問題ないよ」と答えた。「君に代ってもらって助かったよ、僕の方もどうにか上手くいっている」 徳田はそう言うと、某商社のフランス製品販売促進キャンペーンのアルバイトについて、おおむね順調に取り組んでいることを説明するのだった。
初めのうちはそのアルバイトも大変だったようだが、慣れてくるとスムーズに“こなす”ようになり、今では他のアルバイターより自分の方がずっと上手に処理していると、徳田は自慢げに語った。 あれこれ雑談を交わしているうちに、彼は「早稲田祭で、中野さんは長唄の発表会に出るんだってね」と言ってきた。
日頃、百合子には面倒見の良い徳田だけあって、さすがによく知っているなと行雄は思った。歌舞伎研究会の話しに移ると行雄も黙っているわけにはいかず、最近のサークル活動について幾つか説明すると、徳田は百合子から話しを聞いているせいか「君もだいぶ頑張っているようじゃないか」と言って、行雄を激励するのだった。
彼は今でも、俺と百合子の関係を気にかけていてくれるのかと思うと、行雄は有り難いと素直に受け止めたが、彼女との関係が進展しているわけではないので、それ以上は話したくない気持だった。 すると、徳田は「君も歌舞研のメンバーだから、中野さんの発表会を見に行くのだろう?」と聞いてくる。
「ああ、行くつもりだ」と行雄が答えた。「それじゃ、一緒に見に行こう。実は小野も誘っているんだ。彼女はフランスのことばかりに興味があって、歌舞伎といった日本の伝統的な文化のことにはまったく関心がない。あれでは駄目だ。 だから、小野にも一緒に行こうと誘っているんだ。せっかく、中野さんも出るというのだから」徳田がやけに熱心に言ってくる。
彼はその後、自分は能が好きで、水道橋の能楽堂にも時おり見に行っていると言う。徳田がそういう趣味を持っていることに行雄は驚くと同時に感心した。 普段はフランス流の“きざっぽさ”が目につく彼に、日本の伝統的な芸能を嗜む風情は見られなかったからだ。 結局、行雄は徳田とその彼女と一緒に、百合子の長唄発表会を見に行くことを約束した。
早稲田祭が始まって2日目、三人は大隈侯の銅像前で落ち合うと、歌舞研の長唄発表会が行なわれる本校舎の小講堂に向った。中に入ると、観客は“まばら”であった。長唄などは一般の学生には興味がないのだろう。 幾つかの演目があった後、百合子らの一団が登場してきた。三味線の音色に合わせて長唄が始まる。
もともと行雄は、長唄や浄瑠璃と言った三味線音楽には興味がないが、今日は唄方の百合子を見ようと思って来ただけである。徳田と小野はけっこう熱心に聴いているようだったが、行雄はやや退屈な感じになって、唄声がもれる百合子のおちょぼ口に目をやっていた。
そのうちに何気なく右の方を見たとたん、彼はギョッとして目を凝らした。数メートル先にいる中年の婦人の横顔が、いかにも百合子の顔付きに似ているのだ。 もしかすると、この婦人は百合子の母親ではないかと思うと、行雄は急に緊張してきた。
和服姿の彼女は恰幅が良く、背筋を真直ぐに伸ばして舞台に注目している。姿勢が良いのも百合子そっくりで、その視線は“娘”の方へ向いているようだ。少なくとも行雄にはそう思えた。この婦人は百合子の母に間違いない! そう確信すると退屈な感じは消え失せて、彼は緊張が一気に高まるのを覚えた。
行雄は居た堪れない気持になり、長唄が終了する直前になって徳田と小野に小声で話しかけた。「ごめん、急用を思い出したんだ。失礼するよ」 二人は唖然とした面持ちで行雄を見たが、彼は委細構わず席を立つと逃げるようにしてその場を離れた。
徳田と小野には申し訳ないと思ったが、百合子の母だと確信する女性がすぐ側にいるのでは、行雄はのんびりと演目を鑑賞する気持にはとてもなれなかった。自分の確信は誤りだったかもしれないが、人を見る目は誰にも引けを取らないという自負があるから、彼は己れの“直感”を信じたのである。
数日後、徳田と会った時に行雄は先日の非礼を詫びた。「急用だったんだって? それにしても中野さんが出ているというのに、先に帰ってしまうなんて白けたよ」 徳田が非難めいた口調で言ってきたのに対し、行雄は「ごめん。実は彼女のお母さんがすぐ横にいたようなんだよ」と弁解するしかなかった。
表面的にはこれと言った変化もなく、その年が師走を迎えた頃になると、行雄は翌年のことをあれこれ考えざるを得なくなった。百合子との関係がどうなろうとも、新しい年は自分の進路を決めなければならない。 大学院に進んでフランス文学の研究をするのか、あるいは出版社や新聞などマスコミへの就職を選ぶのか、どちらかに決めなければならない。
幾人かの友人の中では、高村宗男だけが新聞記者になるという明確な目標を持っていたが、その他はまだ進路が定まっていなかった。 アルバイトに熱心な徳田誠一郎にしても、社会に出て働くのか大学院へ進んで暫く様子を見るのか決めかねていた。橋本敏夫などは留年必至ということで、進路そのものを考えていない状況である。
そうした中で、行雄は次第に大学院への道を諦めようという気持になった。一つにはフランス文学への関心が薄らいできたことと、それに付随するような形で学問研究の道に自信が持てなくなったからである。学者・研究者として立派な業績を挙げるというのは、自分にはとても望めないことだと思われた。従って、残るはマスコミ関係へ進んで働くだけである。
マスコミも多種多様だが、できれば活字文化を担う出版社への就職が良いのではと考えるようになった。そう考えると、すでに大手出版のI社への就職が内定しているO氏(敦子の婚約者)のことを思い出し、複雑な気持になった。 自分はO氏よりも優秀だろうか・・・どうも、そうとは思えない。O氏に負けないぐらいの仕事が出来るだろうか・・・どうも、自信がないようだ。 行雄はそんな取留めのないことを考えていたが、自分の適性から言って出版関係しか進む道はないだろうと思った。
冬休みに入ったある日、行雄は古い名画を専門に上映している池袋のM映画館に行った。グレゴリー・ペック主演のアメリカ映画「白鯨」を見たかったからだ。 彼はハーマン・メルヴィルの原作は読んでいなかったが、以前からグレゴリー・ペックが好きだったのでこの映画を見ようという気になったのだ。
エイハブという捕鯨船の船長が、モービー・ディックと呼ばれる巨大な白鯨を追いかけて大海原を駆け巡る物語だが、そこには、白鯨の悪魔的な魅力の虜(とりこ)になったエイハブの凄まじい執念が描かれていた。
モービー・ディックは捕鯨船の追跡を嘲笑うかのように、悠々と逃げ回る。エイハブがいくら追いかけても捕まらない。人間の力などはまったく問題にしていないようだ。 この白い怪物は逃げ回ると言うよりも、むしろ隙を見て捕鯨船に襲いかかってこようとしている。
そして、モービー・ディックと捕鯨船は運命の決戦を迎えることになった。巨大な宿敵を目がけて、エイハブは渾身の力を振り絞ってモリを打ち込む。 モリは白い巨体に突き刺さるが、エイハブの体はロープもろとも白鯨にからめ捕られる。彼は必死になってモリを再三射し込むが、やがてその姿はモービー・ディックと共に海の中に消えていく。
行雄はこの映画を見ているうちに、自分がエイハブだと思うと、巨大な白鯨は百合子そのもののように思われてきた。自分は白い体の“魔力”に捕らえられ、海底深く引きずり込まれていくような感じがした。いくら抵抗しても魔力には勝てない。自分も百合子の肉体の中に燃え尽きていくような妄想を抱くのだった。
映画を見たその夜、行雄は彼女の肉体を想像し目眩くようなオナニーに陶酔した。彼には同様の経験がある。 あれは1年ほど前だったろうか、バスの中で百合子から衝撃を受けた後、フランスの映画「カミカゼ」を何度も見たことがある。
この「カミカゼ」は、第二次世界大戦の末期、日本の「神風特別攻撃隊」がアメリカ海軍と死闘を繰り広げた戦いの記録映画である。 爆弾を抱えた神風特攻機が、戦力の圧倒的に優勢なアメリカ海軍の艦船を目がけて突入していくシーンは、極めて英雄的であり、同時に悲劇的であった。
自分と同年齢の若者が、死を決してアメリカ艦隊に体当たりしていく。玉と砕け散華する、死して護国の鬼となり神となるのだ。彼らの悲壮な心情を思う時、行雄は胸が締めつけられ涙なしには映画を見ることができなかった。 百合子だったら、この映画を見てどういう風に思うだろうか。きっと同じように涙にむせぶに違いない。
行雄はそんな思いを巡らせていたが、「カミカゼ」を何度も見ているうちに、海に浮かぶアメリカの巨大な航空母艦が、百合子の白く大きな肢体を連想させるのだった。 いつしか、日の丸の鉢巻を締めて特攻機に乗った自分は、大海原に人魚のように浮かぶ白い巨体を目がけて、決死の覚悟で突入していく。
海上からは砲弾が雨あられと激しく飛んでくるが、行雄の特攻機はそれを物ともせず巨大な空母に突っ込んでいく。そして、行雄は“白い巨体”に見事に体当たりし玉と砕け散ったのだ! 百合子の巨体に特攻機が突き刺さり、爆弾が破裂して彼女は火だるまになった。その妄想は行雄を陶然とさせ、彼は映画館の暗い空間の中で感動に打ち震えた。
あれから1年経っても、同様の妄想はしばしば訪れる。ボードレールの詩を読んでいても、『女の巨人』の膝から大腿部、そして腰から腹を伝って乳房へと、行雄は詩人と同じように這い上がっていく。見上げれば白い巨人は百合子だった。 彼女はまるで“子猫”をあやすように彼をもてあそぶのだ。巨人の手が“子猫”を握り締め豊満な乳房に押しつける。むせ返るような女の体臭に覆われて彼は窒息しそうになる。そういう妄想に耽る時、行雄は形容しがたい欲情と感動にしびれるのだった。