この悪法は多くの国民の反対をおしきって、数の力で成立してしまいました。新聞は新聞協会を通して、意思表示したほか、特に朝日新聞、毎日新聞、東京新聞は連日問題提起し、国会で決めないように訴えていました。国民の知る権利や言論の自由を圧迫する法律が目の前で決められようとしている事への警鐘には説得力がありました。
地方紙も早くから慎重審議や反対を求めていたことがネット上でもわかります。
残念なことに私たち一般国民の気づく遅さやマスコミ等の取り組みの遅さに比べて、自公政権は、はるかに強大な数の力を振り回したと思います。
東京新聞、毎日新聞、神奈川新聞、福島民報の論調を資料として確認しておきたいと思います。尚、朝日新聞の論陣も立派なものでしたが、ネット上では保存できなかったので省略しました。
また,政党では日本共産党や社民党、民主党、生活の党などが反対しましたが、修正に応じ自公を補完することになった維新やみんなの党などの行動は記憶しておきたいと思います。(詳しくは各党のホームページを参照。見出しは私がカラーにしました)
①東京新聞 2013年12月8日 第一面
秘密保護法 法廃止へ揺るがず 監視国家 広がる「反対」
2013年12月8日
国民の「知る権利」を侵す恐れのある特定秘密保護法は六日深夜の参院本会議で、与党の賛成多数で可決、成立した。野党は慎重審議を求めたが、与党が採決を強行した。だが「秘密保護法案反対」を訴えていた人たちの声は、消えることはない。「法律廃止」へと変わるだけだ。国民の権利を守ろうという全国の幅広い層による活動は続く。 (城島建治、関口克己)
法成立に強く反対してきた「特定秘密保護法案に反対する学者の会」は七日、名称を「特定秘密保護法に反対する学者の会」に変え、活動継続を宣言。学者の中には、法律は違憲立法だとして法廷闘争に持ち込む準備を始める動きもある。
女性関係の三十六団体でつくる「国際婦人年連絡会」は、法成立を受けて近く集会を開催する。戦争体験を持つ女性が多く所属しており、秘密保護法が脅かしかねない平和の尊さを広く訴えることの重要性を確認する。
連絡会の世話人で、女性の地位向上に尽くした政治家の故市川房枝氏の秘書を務めた山口みつ子さんは、秘密保護法が成立したのは「昨年末の衆院選と今年の参院選の低投票率の弊害だ」と分析。「有権者が政治への関心を高めないと、権力的な政治がさらにまかり通る」と訴える。
アイヌの有志でつくる「アイヌウタリの会」は、法律廃止への賛同を広く募っていくことを決めた。
弁護士有志による「自由法曹団」も法律の廃止を求めた。自民党の石破茂幹事長がデモとテロを同一視した問題を挙げ「政府に反対する声がテロとして排斥され、密告・監視が横行する。こんな国と社会は許されない」と訴えた。
日本ジャーナリスト会議も、衆参両院での採決強行を「憲政史上、前例のない最悪の暴挙」と非難。安倍政権を「国民の目と耳と口をふさぎ、民主主義を否定する」と批判し、衆院を解散して国民に信を問うべきだと主張した。(東京新聞)
②毎日新聞 12月6、7日 社説
社説:秘密保護法案参院審議を問う 反対の声を無視
2013年12月06日
◇民主主義と人権の危機
特定秘密保護法案の姿があらわになるにつれ、反対や疑問の声が全国にうねりのように広がった。
市民団体やNGOなどのほか、各界の人たちが声を上げ始めた。反対の声は国際社会からも届く。
共通するのは、この国の民主主義と、主権者である国民の人権が、危機に直面しているとの思いだ。
3日、法案に反対する「学者の会」の代表者が東京都内で記者会見した。廃案を求める声明の賛同者が、呼びかけからわずか1週間で2000人を超えたというのは驚きだ。学者の会は、ノーベル賞受賞者の益川敏英名古屋大特別教授や、白川英樹筑波大名誉教授らが結成したものだ。
声明は、指定される特定秘密の範囲が政府の裁量で際限なく広がる危険性を指摘。特定秘密を提供した者、取得した者双方に過度の重罰を科すと批判する。
また、民主政治は市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は、民主的な意思決定の前提だと説く。法案は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、「秘密国家」への道をひらくと指摘する。
批判の矛先は、与党の政治姿勢にも及ぶ。広く市民の間に批判が広がっているのに、何が何でも成立させようとする姿への違和感だ。
法案の抱える欠陥と、議会制民主主義の下で最低限必要な議論さえ放棄した国会の惨状に対する学者たちの憤りが強くにじむ。
山田洋次監督らが呼びかけ人となり、映画界も反対声明を出した。
「知る権利を奪い、表現の自由を脅かす法案は容認できない」というアピールは明瞭だ。
宮崎駿監督や、女優の吉永小百合さんも賛同した。
海外からも批判が出ている。
国連の人権保護機関のトップであるピレイ人権高等弁務官は法案について「政府が不都合な情報を秘密として認定できる。何が秘密かも明確になっていない。表現の自由や、情報入手の権利への適切な保護措置が必要だ」と述べた。
外国にも秘密保護法制は存在するが、情報公開や厳密な秘密指定のチェックと両輪を成すのが通例だ。バランスを欠いた法案の構成が、基本的人権の観点からも看過できない。そういうメッセージと受け取れる。
市民のデモ活動をテロになぞらえた自民党の石破茂幹事長のブログでの発言は、法律が成立した場合の政府・与党の運営に大きな不安を残した。だが、その懸念に正面から応えることはなかった
社説:特定秘密保護法成立 民主主義を後退させぬ
毎日新聞 2013年12月07日 02時30分
「情報公開は民主主義の通貨である」とは米国の著名な消費者運動家、ラルフ・ネーダー氏の言葉である。国の情報公開が市民に政治参加への材料を提供し、民主的な社会をつくっていくことに貢献するとの意味が込められているという。
日本でも戦後、国民の知る権利や政府の説明責任という概念が人々の間に徐々に広がり、国の情報は国民全体の財産であるとの考え方が浸透した。欧米から大きく後れをとったとはいえ、2001年の情報公開法、11年の公文書管理法の施行で、行政情報に誰もが自由にアプローチできる仕組みが整った。
◇息苦しい監視社会に ところが、そうした民主主義の土台を壊しかねないのが、参院本会議で成立した特定秘密保護法である。
国の安全保障にかかわる情報を秘密にし、近づこうとする人を厳しく取り締まるのがこの法律の根幹だ。民主主義を否定し、言論統制や人権侵害につながる法律を私たちは容認するわけにはいかない。制度導入を主導してきた安倍晋三首相と政権与党に、誤った政策だと強く指摘する。
それにしても、目を覆うばかりの政府・与党の乱暴な国会運営だった。今国会の成立に固執して拙速に審議の幕を下ろし、採決を強行した。野党の一部を取り込むために採決直前になって次々と新しい組織の設置を口約束するドタバタぶりだった。その手法は、与野党が時間をかけ熟議を重ねて妥協を図り、多数決は最後の手段とすべき議会制民主主義とは大きくかけ離れたものだ。
強行成立したこの日を、法律の中身と成立手続きの両面で、民主主義が損なわれた日として記憶にとどめたい。
私たちはこれまで、この法律が抱えるさまざまな問題を懸念し、廃案を求めて訴えてきた。
なによりも、国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるとの理由をつければ、行政機関は大量の情報を特定秘密に指定することができ、国民は接することが不可能になる。情報を公開するという原則をゆがめるものだ。「何が秘密かも秘密」にされ、個々の指定が妥当かどうかのチェックは国会も司法も基本的に及ばない。そのため、行政は恣意(しい)的な指定が可能になり、不都合な情報も隠すことができてしまう。
不正アクセスなどの違法行為で特定秘密を取得した人だけでなく、漏えいや取得をめぐる共謀、そそのかし、あおり行為も実際に情報が漏れなくても罪に問われる。取り締まり対象は報道機関に限らず、情報を得ようとする市民全体に向けられる。
③神奈川新聞 社説 2013年12月7日
任務放棄の国会は不要
特定秘密保護法の成立は、国民の「知る権利」を脅かすことにとどまらない。国会の任務放棄をも意味する。権威は失墜した。
このような法を通す国会は信頼できないし、存在の必要も感じない。総辞職し、あらためて国民の審判を仰ぐべきだろう。そこまで指摘されてもおかしくない重大事であることを議員も国民も認識してほしい。
中学校や高校の社会科レベルに立ち返り、説明しておく。
国会の役割は憲法第41条に規定されている。「国権の最高機関」であり「唯一の立法機関」だ。立法府と呼ばれる。担い手たる各議員は、特定の地域や団体に拘束されない「全国民の代表」である。
つまり、国民の生活や自由や安全を守るため、社会の規範である法をつくるのが仕事だ。例えば犯罪をめぐり、何が「してはいけない事」であり、それを逸脱した場合に「どのような処罰を受けるか」といった内容を決める。日本において法制定の権限を有するのは国会だけだ。
ところが、特定秘密保護法では「これを漏らせば犯罪」という「特定秘密」を行政府(内閣)が決める。その漏えいを理由として国民へ刑罰が科せられてしまう。 しかも国民には何が「特定秘密」であるのかが分からない。メールなどでの日常の情報のやりとりが刑事処分の対象となりかねない。
国会は本来、法の制定を通し、内閣をチェックする立場だ。しかし、秘密法では法体系上の裁量を事実上、行政府(内閣)へ丸投げしている。その暴走を助長しかねない。衆院だけでなく参院までもが、立法府としての役割を放棄したも同然だ。
「特定秘密」指定のチェックをめぐり、与党が示した「内閣府への第三者機関設置」などの対案も法に明記してこそ意味があろう。現状では実効性の担保がない。自民、公明両党はもとより法案修正に合意したみんなの党、日本維新の会は国民に対し、どう責任を取るつもりか。
国会議員に憲法上の身分保障を定めたのは「全国民の代表」として役割を果たしてもらうためだ。だが、国民は裏切られてしまった。
これからは政府にとって都合の悪い事実は「特定秘密」に指定して抹殺できる。いさめるべき国会が後押しをしたのだ。2013年の臨時国会は憲政史上に汚点を残した国会として記憶されるだろう。
④福島民報 2013年12月7日 論説
【秘密保護法成立】原発の情報隠し許さない(12月7日)
特定秘密保護法が6日深夜に成立した。与党が衆院に続き、参院でも「採決強行」した末だ。参院での審議は10日足らずだった。「反対」の声が高まる中、なぜ、それほど急ぐ必要があったのか。国民の「知る権利」に大きく関わる法律にしては、拙速の感を拭い切れない。
国会審議では、担当閣僚のあいまいな答弁や修正・訂正が続き、与党議員の欠席が目立った。国会での与野党ねじれによる「決められない政治」を解消した結果が、数を頼んでの「強行政治」だとすれば、何とも情けない。国会の権威を自らおとしめ、国民からの信頼を減じよう。
国家である以上、外交や防衛などで直ちには明かせない情報が存在するのは分かる。問題は指定する秘密の対象や期間が行政機関の長に委ねられ、運用の可否を判断する「外部の目」や、遠い将来に公開を義務付けるなど、乱用への歯止めがないことだ。
安倍晋三首相は4日に、指定の統一基準を策定する「情報保全諮問会議」と、運用の妥当性を判定する「保全監視委員会」などの設置方針を表明した。唐突で、採決の直前では中身を論議する時間があまりにも少ない。しかも、いずれも政府内の組織や機関だ。「自らの行為を自らが審査する」形では、政府の「思惑次第」と変わるまい。
8年前の個人情報保護法施行後に、「判断の難しい情報は非公開」との過剰反応が起きた。学校や団体で名簿を作らない傾向が強まり、緊急連絡時などに支障が出ている。特定秘密保護法でも同様の事態が起きはしないか。
特に本県では、原発の安全や事故に関する情報隠しが懸念される。本来明らかにすべき内容が「特定秘密」に名を借りて閉ざされかねない。指定されれば、何が秘密かも分からない。許してはならない。
福島市で先月25日に開かれた衆院の地方公聴会では、与党推薦を含めた陳述人7人全員が反対や慎重審議を求めた。その後も、疑問の多くが解明されず、法案修正にも反映されなかった。平出孝朗県議会議長は「あらためて慎重な審議を求める」とする談話を5日に発表した。
法成立で原発の取材はこれまで以上に難しくなろう。実態や事故原因を探ろうとすれば、罪に問われる恐れさえ出る。罰則は報道機関に限らず、一般国民にも及ぶ。万一、裁判になっても罪状などが明らかにされない可能性もある。しかし、「見えない影」に萎縮してはいられない。県民の立場に立った報道をさらに強めたい。(鈴木 久)
「見識」から「厳罰」へ(12月8日)
特定秘密保護法が成立してしまった。衆参両院とも強引な形で採決された。先月25日に福島市で開かれた公聴会と称する集会では、発言者全員が反対表明や慎重な審議を求めたにもかかわらず、である。通常、こういう拙速なやり方をされると、いったいどういう魂胆なのかと、それだけで真意を疑ってしまう。法案が国にとって、どうしても必要であり、きちんと話せば分かってもらえると思うなら、腰を据えて議論をすべきではないか。
今月3日には、参議院でこの法案を審議する特別委員会が開かれ、そこで与党側からの参考人として全国地方銀行協会元会長の瀬谷俊雄氏(元東邦銀行頭取)が次のような意見を述べた。
「国際問題や通商問題に携わる人は高いレベルの機密を保つ必要がある。しかし、民間人が処罰の対象になるのは疑問だ。銀行員は取引上、知り得た情報を退職後も守るべきだが、法律ではなく企業倫理で律している。あえて懲役刑を設ける必要はない。法案に該当する国益の範囲を極力絞って、集中的に適用されたらいいのではないか」(4日付「福島民報」)
実に尤[もっと]もな、大人のご意見だと思う。思えば銀行員ばかりでなく、教員も医師も宗教者も職業上知ることになる秘密を抱えている。しかも大抵それは文書によって「特定」されたりしないから、どれが秘密か、なぜ話してはいけないのかは、経験のなかで学んでいくしかない。いや、それこそが職業人としての成長というものだろう。つまり、秘密を特定するのは、殆[ほと]んどの社会人にとってはその職業に従事することで身につく「見識」なのである。
昔、中国では始皇帝の秦[しん]が細かい規則を無数に作り、厳罰主義に陥って15年で滅んだ。続く漢の高祖劉邦は「法は三章のみ」と宣言し、むしろ徳による統治を目指した。漢が400年続いたのは、その「徳治」のおかげと思えるが、日本も、基本的にはその路線で進んできたはずである。しかし、今回の法律の懲役10年という罰則の厳しさは、むしろ疑い深かった始皇帝の厳罰主義を彷彿[ほうふつ]させる。
今後は「行政機関の長」が特定秘密を指定し、「適正評価により、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた職員等」だけがそれを取り扱うらしいが、実際には官僚の情報占有が懸念される。
瀬谷氏が心配するように、話は公務員だけには収まらない。特定秘密の範囲は防衛、外交、特定有害活動(スパイ行為)、テロ活動防止に関することだというが、石破茂氏のようなテロ解釈だと、どこまで広げられるか分からない。
本当の狙いが分からないほど拡大解釈が可能なだけでも悪法である。原発事故以後、「秘密」がどれほど不安を増幅させたか、首相はもうお忘れなのだろうか。「徳治」や「見識」を諦めた国の行く末は、考えるだに末恐ろしい。
(玄侑宗久、僧侶・作家、三春町在住)
⑤共同通信ニュースから
秘密法「修正・廃止を」が82% 内閣支持率急落47%
共同通信社が8、9両日に実施した全国緊急電話世論調査によると、6日成立の特定秘密保護法を今後どうすればよいかについて、次期通常国会以降に「修正する」との回答は54・1%、「廃止する」が28・2%で合わせて82・3%に上った。「このまま施行する」は9・4%にとどまった。法律に「不安を感じる」との回答も70・8%を占め、「知る権利」侵害への懸念が根強い現状が浮き彫りになった。
内閣支持率は47・6%と11月から10・3ポイント急落。50%を割ったのは、昨年12月の第2次安倍内閣発足以来、初めて。
*東京新聞ではこの法律に反対する団体一覧がのっていましたが、残念ながらコピーでは成功しなかったので、関心のある方は東京新聞のホームページで確認してください。
地方紙も早くから慎重審議や反対を求めていたことがネット上でもわかります。
残念なことに私たち一般国民の気づく遅さやマスコミ等の取り組みの遅さに比べて、自公政権は、はるかに強大な数の力を振り回したと思います。
東京新聞、毎日新聞、神奈川新聞、福島民報の論調を資料として確認しておきたいと思います。尚、朝日新聞の論陣も立派なものでしたが、ネット上では保存できなかったので省略しました。
また,政党では日本共産党や社民党、民主党、生活の党などが反対しましたが、修正に応じ自公を補完することになった維新やみんなの党などの行動は記憶しておきたいと思います。(詳しくは各党のホームページを参照。見出しは私がカラーにしました)
①東京新聞 2013年12月8日 第一面
秘密保護法 法廃止へ揺るがず 監視国家 広がる「反対」
2013年12月8日
国民の「知る権利」を侵す恐れのある特定秘密保護法は六日深夜の参院本会議で、与党の賛成多数で可決、成立した。野党は慎重審議を求めたが、与党が採決を強行した。だが「秘密保護法案反対」を訴えていた人たちの声は、消えることはない。「法律廃止」へと変わるだけだ。国民の権利を守ろうという全国の幅広い層による活動は続く。 (城島建治、関口克己)
法成立に強く反対してきた「特定秘密保護法案に反対する学者の会」は七日、名称を「特定秘密保護法に反対する学者の会」に変え、活動継続を宣言。学者の中には、法律は違憲立法だとして法廷闘争に持ち込む準備を始める動きもある。
女性関係の三十六団体でつくる「国際婦人年連絡会」は、法成立を受けて近く集会を開催する。戦争体験を持つ女性が多く所属しており、秘密保護法が脅かしかねない平和の尊さを広く訴えることの重要性を確認する。
連絡会の世話人で、女性の地位向上に尽くした政治家の故市川房枝氏の秘書を務めた山口みつ子さんは、秘密保護法が成立したのは「昨年末の衆院選と今年の参院選の低投票率の弊害だ」と分析。「有権者が政治への関心を高めないと、権力的な政治がさらにまかり通る」と訴える。
アイヌの有志でつくる「アイヌウタリの会」は、法律廃止への賛同を広く募っていくことを決めた。
弁護士有志による「自由法曹団」も法律の廃止を求めた。自民党の石破茂幹事長がデモとテロを同一視した問題を挙げ「政府に反対する声がテロとして排斥され、密告・監視が横行する。こんな国と社会は許されない」と訴えた。
日本ジャーナリスト会議も、衆参両院での採決強行を「憲政史上、前例のない最悪の暴挙」と非難。安倍政権を「国民の目と耳と口をふさぎ、民主主義を否定する」と批判し、衆院を解散して国民に信を問うべきだと主張した。(東京新聞)
②毎日新聞 12月6、7日 社説
社説:秘密保護法案参院審議を問う 反対の声を無視
2013年12月06日
◇民主主義と人権の危機
特定秘密保護法案の姿があらわになるにつれ、反対や疑問の声が全国にうねりのように広がった。
市民団体やNGOなどのほか、各界の人たちが声を上げ始めた。反対の声は国際社会からも届く。
共通するのは、この国の民主主義と、主権者である国民の人権が、危機に直面しているとの思いだ。
3日、法案に反対する「学者の会」の代表者が東京都内で記者会見した。廃案を求める声明の賛同者が、呼びかけからわずか1週間で2000人を超えたというのは驚きだ。学者の会は、ノーベル賞受賞者の益川敏英名古屋大特別教授や、白川英樹筑波大名誉教授らが結成したものだ。
声明は、指定される特定秘密の範囲が政府の裁量で際限なく広がる危険性を指摘。特定秘密を提供した者、取得した者双方に過度の重罰を科すと批判する。
また、民主政治は市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は、民主的な意思決定の前提だと説く。法案は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、「秘密国家」への道をひらくと指摘する。
批判の矛先は、与党の政治姿勢にも及ぶ。広く市民の間に批判が広がっているのに、何が何でも成立させようとする姿への違和感だ。
法案の抱える欠陥と、議会制民主主義の下で最低限必要な議論さえ放棄した国会の惨状に対する学者たちの憤りが強くにじむ。
山田洋次監督らが呼びかけ人となり、映画界も反対声明を出した。
「知る権利を奪い、表現の自由を脅かす法案は容認できない」というアピールは明瞭だ。
宮崎駿監督や、女優の吉永小百合さんも賛同した。
海外からも批判が出ている。
国連の人権保護機関のトップであるピレイ人権高等弁務官は法案について「政府が不都合な情報を秘密として認定できる。何が秘密かも明確になっていない。表現の自由や、情報入手の権利への適切な保護措置が必要だ」と述べた。
外国にも秘密保護法制は存在するが、情報公開や厳密な秘密指定のチェックと両輪を成すのが通例だ。バランスを欠いた法案の構成が、基本的人権の観点からも看過できない。そういうメッセージと受け取れる。
市民のデモ活動をテロになぞらえた自民党の石破茂幹事長のブログでの発言は、法律が成立した場合の政府・与党の運営に大きな不安を残した。だが、その懸念に正面から応えることはなかった
社説:特定秘密保護法成立 民主主義を後退させぬ
毎日新聞 2013年12月07日 02時30分
「情報公開は民主主義の通貨である」とは米国の著名な消費者運動家、ラルフ・ネーダー氏の言葉である。国の情報公開が市民に政治参加への材料を提供し、民主的な社会をつくっていくことに貢献するとの意味が込められているという。
日本でも戦後、国民の知る権利や政府の説明責任という概念が人々の間に徐々に広がり、国の情報は国民全体の財産であるとの考え方が浸透した。欧米から大きく後れをとったとはいえ、2001年の情報公開法、11年の公文書管理法の施行で、行政情報に誰もが自由にアプローチできる仕組みが整った。
◇息苦しい監視社会に ところが、そうした民主主義の土台を壊しかねないのが、参院本会議で成立した特定秘密保護法である。
国の安全保障にかかわる情報を秘密にし、近づこうとする人を厳しく取り締まるのがこの法律の根幹だ。民主主義を否定し、言論統制や人権侵害につながる法律を私たちは容認するわけにはいかない。制度導入を主導してきた安倍晋三首相と政権与党に、誤った政策だと強く指摘する。
それにしても、目を覆うばかりの政府・与党の乱暴な国会運営だった。今国会の成立に固執して拙速に審議の幕を下ろし、採決を強行した。野党の一部を取り込むために採決直前になって次々と新しい組織の設置を口約束するドタバタぶりだった。その手法は、与野党が時間をかけ熟議を重ねて妥協を図り、多数決は最後の手段とすべき議会制民主主義とは大きくかけ離れたものだ。
強行成立したこの日を、法律の中身と成立手続きの両面で、民主主義が損なわれた日として記憶にとどめたい。
私たちはこれまで、この法律が抱えるさまざまな問題を懸念し、廃案を求めて訴えてきた。
なによりも、国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるとの理由をつければ、行政機関は大量の情報を特定秘密に指定することができ、国民は接することが不可能になる。情報を公開するという原則をゆがめるものだ。「何が秘密かも秘密」にされ、個々の指定が妥当かどうかのチェックは国会も司法も基本的に及ばない。そのため、行政は恣意(しい)的な指定が可能になり、不都合な情報も隠すことができてしまう。
不正アクセスなどの違法行為で特定秘密を取得した人だけでなく、漏えいや取得をめぐる共謀、そそのかし、あおり行為も実際に情報が漏れなくても罪に問われる。取り締まり対象は報道機関に限らず、情報を得ようとする市民全体に向けられる。
③神奈川新聞 社説 2013年12月7日
任務放棄の国会は不要
特定秘密保護法の成立は、国民の「知る権利」を脅かすことにとどまらない。国会の任務放棄をも意味する。権威は失墜した。
このような法を通す国会は信頼できないし、存在の必要も感じない。総辞職し、あらためて国民の審判を仰ぐべきだろう。そこまで指摘されてもおかしくない重大事であることを議員も国民も認識してほしい。
中学校や高校の社会科レベルに立ち返り、説明しておく。
国会の役割は憲法第41条に規定されている。「国権の最高機関」であり「唯一の立法機関」だ。立法府と呼ばれる。担い手たる各議員は、特定の地域や団体に拘束されない「全国民の代表」である。
つまり、国民の生活や自由や安全を守るため、社会の規範である法をつくるのが仕事だ。例えば犯罪をめぐり、何が「してはいけない事」であり、それを逸脱した場合に「どのような処罰を受けるか」といった内容を決める。日本において法制定の権限を有するのは国会だけだ。
ところが、特定秘密保護法では「これを漏らせば犯罪」という「特定秘密」を行政府(内閣)が決める。その漏えいを理由として国民へ刑罰が科せられてしまう。 しかも国民には何が「特定秘密」であるのかが分からない。メールなどでの日常の情報のやりとりが刑事処分の対象となりかねない。
国会は本来、法の制定を通し、内閣をチェックする立場だ。しかし、秘密法では法体系上の裁量を事実上、行政府(内閣)へ丸投げしている。その暴走を助長しかねない。衆院だけでなく参院までもが、立法府としての役割を放棄したも同然だ。
「特定秘密」指定のチェックをめぐり、与党が示した「内閣府への第三者機関設置」などの対案も法に明記してこそ意味があろう。現状では実効性の担保がない。自民、公明両党はもとより法案修正に合意したみんなの党、日本維新の会は国民に対し、どう責任を取るつもりか。
国会議員に憲法上の身分保障を定めたのは「全国民の代表」として役割を果たしてもらうためだ。だが、国民は裏切られてしまった。
これからは政府にとって都合の悪い事実は「特定秘密」に指定して抹殺できる。いさめるべき国会が後押しをしたのだ。2013年の臨時国会は憲政史上に汚点を残した国会として記憶されるだろう。
④福島民報 2013年12月7日 論説
【秘密保護法成立】原発の情報隠し許さない(12月7日)
特定秘密保護法が6日深夜に成立した。与党が衆院に続き、参院でも「採決強行」した末だ。参院での審議は10日足らずだった。「反対」の声が高まる中、なぜ、それほど急ぐ必要があったのか。国民の「知る権利」に大きく関わる法律にしては、拙速の感を拭い切れない。
国会審議では、担当閣僚のあいまいな答弁や修正・訂正が続き、与党議員の欠席が目立った。国会での与野党ねじれによる「決められない政治」を解消した結果が、数を頼んでの「強行政治」だとすれば、何とも情けない。国会の権威を自らおとしめ、国民からの信頼を減じよう。
国家である以上、外交や防衛などで直ちには明かせない情報が存在するのは分かる。問題は指定する秘密の対象や期間が行政機関の長に委ねられ、運用の可否を判断する「外部の目」や、遠い将来に公開を義務付けるなど、乱用への歯止めがないことだ。
安倍晋三首相は4日に、指定の統一基準を策定する「情報保全諮問会議」と、運用の妥当性を判定する「保全監視委員会」などの設置方針を表明した。唐突で、採決の直前では中身を論議する時間があまりにも少ない。しかも、いずれも政府内の組織や機関だ。「自らの行為を自らが審査する」形では、政府の「思惑次第」と変わるまい。
8年前の個人情報保護法施行後に、「判断の難しい情報は非公開」との過剰反応が起きた。学校や団体で名簿を作らない傾向が強まり、緊急連絡時などに支障が出ている。特定秘密保護法でも同様の事態が起きはしないか。
特に本県では、原発の安全や事故に関する情報隠しが懸念される。本来明らかにすべき内容が「特定秘密」に名を借りて閉ざされかねない。指定されれば、何が秘密かも分からない。許してはならない。
福島市で先月25日に開かれた衆院の地方公聴会では、与党推薦を含めた陳述人7人全員が反対や慎重審議を求めた。その後も、疑問の多くが解明されず、法案修正にも反映されなかった。平出孝朗県議会議長は「あらためて慎重な審議を求める」とする談話を5日に発表した。
法成立で原発の取材はこれまで以上に難しくなろう。実態や事故原因を探ろうとすれば、罪に問われる恐れさえ出る。罰則は報道機関に限らず、一般国民にも及ぶ。万一、裁判になっても罪状などが明らかにされない可能性もある。しかし、「見えない影」に萎縮してはいられない。県民の立場に立った報道をさらに強めたい。(鈴木 久)
「見識」から「厳罰」へ(12月8日)
特定秘密保護法が成立してしまった。衆参両院とも強引な形で採決された。先月25日に福島市で開かれた公聴会と称する集会では、発言者全員が反対表明や慎重な審議を求めたにもかかわらず、である。通常、こういう拙速なやり方をされると、いったいどういう魂胆なのかと、それだけで真意を疑ってしまう。法案が国にとって、どうしても必要であり、きちんと話せば分かってもらえると思うなら、腰を据えて議論をすべきではないか。
今月3日には、参議院でこの法案を審議する特別委員会が開かれ、そこで与党側からの参考人として全国地方銀行協会元会長の瀬谷俊雄氏(元東邦銀行頭取)が次のような意見を述べた。
「国際問題や通商問題に携わる人は高いレベルの機密を保つ必要がある。しかし、民間人が処罰の対象になるのは疑問だ。銀行員は取引上、知り得た情報を退職後も守るべきだが、法律ではなく企業倫理で律している。あえて懲役刑を設ける必要はない。法案に該当する国益の範囲を極力絞って、集中的に適用されたらいいのではないか」(4日付「福島民報」)
実に尤[もっと]もな、大人のご意見だと思う。思えば銀行員ばかりでなく、教員も医師も宗教者も職業上知ることになる秘密を抱えている。しかも大抵それは文書によって「特定」されたりしないから、どれが秘密か、なぜ話してはいけないのかは、経験のなかで学んでいくしかない。いや、それこそが職業人としての成長というものだろう。つまり、秘密を特定するのは、殆[ほと]んどの社会人にとってはその職業に従事することで身につく「見識」なのである。
昔、中国では始皇帝の秦[しん]が細かい規則を無数に作り、厳罰主義に陥って15年で滅んだ。続く漢の高祖劉邦は「法は三章のみ」と宣言し、むしろ徳による統治を目指した。漢が400年続いたのは、その「徳治」のおかげと思えるが、日本も、基本的にはその路線で進んできたはずである。しかし、今回の法律の懲役10年という罰則の厳しさは、むしろ疑い深かった始皇帝の厳罰主義を彷彿[ほうふつ]させる。
今後は「行政機関の長」が特定秘密を指定し、「適正評価により、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた職員等」だけがそれを取り扱うらしいが、実際には官僚の情報占有が懸念される。
瀬谷氏が心配するように、話は公務員だけには収まらない。特定秘密の範囲は防衛、外交、特定有害活動(スパイ行為)、テロ活動防止に関することだというが、石破茂氏のようなテロ解釈だと、どこまで広げられるか分からない。
本当の狙いが分からないほど拡大解釈が可能なだけでも悪法である。原発事故以後、「秘密」がどれほど不安を増幅させたか、首相はもうお忘れなのだろうか。「徳治」や「見識」を諦めた国の行く末は、考えるだに末恐ろしい。
(玄侑宗久、僧侶・作家、三春町在住)
⑤共同通信ニュースから
秘密法「修正・廃止を」が82% 内閣支持率急落47%
共同通信社が8、9両日に実施した全国緊急電話世論調査によると、6日成立の特定秘密保護法を今後どうすればよいかについて、次期通常国会以降に「修正する」との回答は54・1%、「廃止する」が28・2%で合わせて82・3%に上った。「このまま施行する」は9・4%にとどまった。法律に「不安を感じる」との回答も70・8%を占め、「知る権利」侵害への懸念が根強い現状が浮き彫りになった。
内閣支持率は47・6%と11月から10・3ポイント急落。50%を割ったのは、昨年12月の第2次安倍内閣発足以来、初めて。
*東京新聞ではこの法律に反対する団体一覧がのっていましたが、残念ながらコピーでは成功しなかったので、関心のある方は東京新聞のホームページで確認してください。










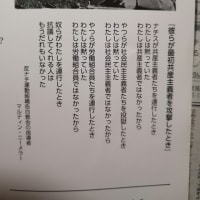










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます