国葬については漠然と、政府が主催して、学校や公共施設などには弔意・半旗を指示して、国中が喪に服すようにさせることは知っていました。それは、昭和天皇の大喪の礼を覚えていたからでした。天皇の時とは違うが税金を使い、上記のようなことを国民に強いることは同じようです。
国葬の位置づけについて調べると、個人と国家の関係が鮮明に見えてきました。戦前は「国葬令」があり、天皇の勅令(天皇の命令・法令)に基づくものでした。大久保利通が最初とされていました。この時期は、西南戦争が前年にあり、士族などの不満や反政府的な動きを天皇の命令による国葬を行うことによって鎮めていくことに大きな狙いがあったとされています。
以後、皇室関係者などを除いて、総理としては伊藤博文、山形有朋、松方正義、西園寺公望の4人でした。戦前は、勅令なので一切異議など言えないのは当然でした。政権にとっては、国論をまとめて一定方向へ導くのに都合の良いものでした。
戦後は民主主義社会としてふさわしくないとして、憲法の改正とともに「国葬令」も廃止(1947年)されました。戦後の総理大臣の国葬は吉田首相のみでした。戦後のGHQの占領終了直後の力関係の中で、法律もない中なのに実施されたものでした。その後は、「国葬令」がないうえ、それをする根拠がないので行われていません。国民葬などと言う名で内閣や自民党、国民有志などが中心になって行われてきました。
以上から言えることは、国家が何かしらの目的をもって多額の税金を使って、故人の生前の業績を政府の立場ですべて是として、個人の宗教や信条などを顧みることなく、強制するものといえます。
今度の岸田首相の発言は?










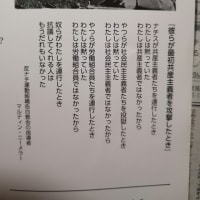










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます