大山へ吟行に行きました。大山は標高1252メートルで伊勢原市にあり、神奈川県民にとっては、雨降山として知られている山です。同じ字の大山でも鳥取県のは「だいせん」といいますが、神奈川県のは「おおやま」です。昔から、海上の守り神として信仰があり、特に漁業関係の方には篤く信仰されていたようです。
江戸時代には「大山詣り」が盛んになり、今でいう観光としても江戸っ子の恰好な旅先になっていました。大山寺、阿夫利神社のある大山に行くために、江戸や横浜には街や職能別に「大山講」つくられていました。今でもたくさん講の名が刻まれた石柱が建てられています。旅人のために、御師の宿と呼ばれる宿坊がたくさんあり、名物の豆腐や独楽の店が並んでいます。そのために落語にまで『大山詣り』として演目があるほどです
さて、その大山に行った日はあいにくの雨でしたが、独楽の絵のある階段をのんびり登りケーブルまで行きました。かなり横殴りの風雨が吹いてきていましたが、みんなケーブルに乗りました。私はケーブルを途中で降りて大山寺へ行きました。
大山寺へ行く途中には羅漢様や東京大空襲の石碑があり、思わず手を合わせました。大きなシャクナゲの木もあり、真っ赤な花が春雨の中咲き乱れていました。
寺はちょうど八の日だったので御開帳でした。雨の日でしたから、その時にはわたし一人だけの参観者で、関東三大不動様の一つといわれる大山の不動様を拝んできました。目玉が光りなかな迫力のあるお不動さまでした。帰りは雨の中でしたが階段を下りました。坂道にはたくさんのマムシ草がさいていました。また大きな石の爪彫地蔵様もなどがありました。地蔵さまは写真のようにとても癒されるお顔でした。20分ほどで入り口につきましたが、階段ばかりでしたので早くも膝が笑うほどでした。この日の俳句はさておいて、昔の人は次のように詠んでいます。
*「夏祓御師の宿札たずねけり」(其角)
*四五間の小太刀をかつぐ袷かな」(一茶)


江戸時代には「大山詣り」が盛んになり、今でいう観光としても江戸っ子の恰好な旅先になっていました。大山寺、阿夫利神社のある大山に行くために、江戸や横浜には街や職能別に「大山講」つくられていました。今でもたくさん講の名が刻まれた石柱が建てられています。旅人のために、御師の宿と呼ばれる宿坊がたくさんあり、名物の豆腐や独楽の店が並んでいます。そのために落語にまで『大山詣り』として演目があるほどです
さて、その大山に行った日はあいにくの雨でしたが、独楽の絵のある階段をのんびり登りケーブルまで行きました。かなり横殴りの風雨が吹いてきていましたが、みんなケーブルに乗りました。私はケーブルを途中で降りて大山寺へ行きました。
大山寺へ行く途中には羅漢様や東京大空襲の石碑があり、思わず手を合わせました。大きなシャクナゲの木もあり、真っ赤な花が春雨の中咲き乱れていました。
寺はちょうど八の日だったので御開帳でした。雨の日でしたから、その時にはわたし一人だけの参観者で、関東三大不動様の一つといわれる大山の不動様を拝んできました。目玉が光りなかな迫力のあるお不動さまでした。帰りは雨の中でしたが階段を下りました。坂道にはたくさんのマムシ草がさいていました。また大きな石の爪彫地蔵様もなどがありました。地蔵さまは写真のようにとても癒されるお顔でした。20分ほどで入り口につきましたが、階段ばかりでしたので早くも膝が笑うほどでした。この日の俳句はさておいて、昔の人は次のように詠んでいます。
*「夏祓御師の宿札たずねけり」(其角)
*四五間の小太刀をかつぐ袷かな」(一茶)












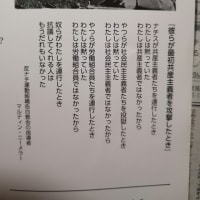










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます