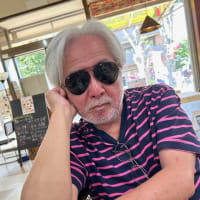【連載】藤原雄介のちょっと寄り道(86)
日台を俳句で結んだ藤原若菜②

▲黄霊芝先生の『台湾俳句歳時記』

▲台北俳句会創立40周年記念の集合写真(2010年12月12日)
前回の「台湾俳句事情(その一)黄霊芝と日本語」では、台北俳句会の始祖である黄霊芝先生について紹介した。今回は、台北俳句会の創設した加藤山椒魚について述べた若菜のエッセイを紹介する。
俳句は不調法な私だが、俳句を通して日台文化交流を垣間見るのも面白いと思い、加藤山椒魚について少しばかり調べてみた。すると、磯田一雄という研究者に行き当たった。彼は、「植民地期東アジアの近代化と教育の展開」「戦前・戦時期における日本語教育史に関する調査研究」などを行ったのだが、台湾の俳句の発展過程、台湾俳句確立に不可欠な台湾歳時記とりまとめに際しての日台間の葛藤などが綴られている。
台北俳句会、燕巣、春燈の微妙な関係性についても時に辛辣に批評している。このようなことは、春燈の先輩方は先刻ご承知であろうし、門外漢の私ごときにこのような繊細なことについて語る資格などあろう筈がない。しかし、これまでほとんど興味のなかった世界に若菜が導き入れてくれたのだと自分を納得させ、少しだけ書いてみることにしたのである。
俳人としての若菜は私の手の届かない高みに立っていたが、私の両親が「燕巣」という俳句結社で活動していたせいで、私は彼女よりほんの少し俳句に接し始めたのは早かった筈だ。「黄霊芝と日本語」に書かれていたように、ひょんなことから彼女と私は「燕巣」と「台北俳句会」の交流句会に紛れ込むことになった。場所は確か、中山北路の日本料理屋の二階だったように思う。
句会の詳しいことは、覚えていない。しかし、句会を終えたその夜、日台双方の何人かの方々と呑みに行き、現代の日本人が話す日本語よりはるかに美しい日本語を話す教養ある「元日本人たち」に圧倒された。
若菜は、その句会を機に俳句にのめり込んでいったが、24時間勤務態勢に近い駐在員生活を送っていた私に定期的に投句する余力はなく、二、三度度句会に顔を出しただけで、自然に台北俳句会から脚が遠のいていった。今になって思えばあの時、もう少し俳句の世界に足を踏み入れておけば良かったと悔やまれる。
台湾俳句事情(その2)
―台湾との懸橋・加藤山椒魚
藤原若菜
一九七〇年に二〇名足らずで発足した台北俳句会は一時八〇名を越えたが、現在は高齢化が進み半減している。しかし日本の俳句会との交流は今も盛んである。俳誌名だけをひとまず五十音順に挙げてみると「伊豆」「岩戸」「燕巣」「海程」「かつらぎ」「耕」「笹」「軸」「春光」「なると」「鵙」そして「春燈」
春燈誌に台湾からの投句が始まったのは一九七五年のことだ。仕事で台湾に駐在されていた加藤山椒魚さんである。インテリアデザイナーだったと聞く。途中、日本との往き来をはさみながら一九八四年まで台湾からの投句を続けられた。台湾独特の風物を積極的に詠まれた次のような句がある。
焚香開門春聯の紅陽に映ゆる
百花繚乱いつそくとびの春なりけり
桃花満村淡江長堤斜陽かな
「春聯」とは新春を迎えるために門や玄関などに貼るお札のようなものだが、その真紅はいかにも異国的である。更に面白いのは、上下逆さまに貼られている場合が少なくないことだ。これは「やって来る(到)」と「ひっくり返る(倒)」の漢語の発音が同じ「タオ」であるからとのこと。そして、日本の注連縄とは違い、春節が過ぎても一年中貼ってある。
それにしても、貼り替えたばかりの春聯の紅は鮮やかだ。次に、彼の地の春はとても短い。春節の頃すでに空気は艶めいており、ほどなく台北近郊の山や川辺では、梅、桃、桜、杏、躑躅、石楠花などがあれよあれよと同時に咲き乱れ、人々は短い花季を楽しむのである。その後を追いかけるようにやって来る夏はほぼ半年続く。
火焔樹炎え猛暑の日々は続くなり
驟雨一過大王椰子は天にさやぎ
火焔樹は鳳凰木とも言われ、花は緋紅色。夏の雨は亜熱帯らしいスコールで、躯に当たると痛いほどの勢いで降るが短時間で思いきりよく上がる。
煎薬を滾らせてゐる残暑かな
とんぼ切るだけの子役や秋風裡 (辻京劇)
朱樂の香曵き朱樂売すれちがふ
巷の匂いと市井の人々へ向けられた加藤山椒魚さんの眼差。これらの句に、奥様への想いと望郷の句が混じる。
実梅漬く老妻苦労いまだ絶えず
藤椅子にうたた寝の妻あはれむも
鳥渡りゆくさびしさを妻に言はず
湯豆腐や異郷に風の荒き夜の
そんな時期、敬虔なクリスチャンでもあった加藤山椒魚さんは、教会で数人の「元日本人」と知り合う。その人達が、現在も春燈誌でご活躍の、陳姝蓉さん、林雪江さん、呂秀文さん達である。生真面目なお人柄の加藤山椒魚さんは熱心にこの方達の俳句指導をされたそうだ。又それによく応えられた方々の縁が縁を招き、一九八三年には、台湾の春燈会員は一七名にもなった。廖運藩さんや現在体調を崩されて休会中の陳錫恭さん、范友佳女さんのお名前もその中にある。呉文宗さん、呉佳君さんのご入会は更に後年になる。
その頃、充実の中の一抹の思いが次の句となり、それを安住敦先生が「余言」(一九八一年十一月号)でとりあげられた。(筆者注:「余言」とは。春燈の巻末に主宰が気に留めた俳句について評論するコラムのこと)
母ひとりふるさとにあり盆の月

▲呂秀文さん(右)

▲呉文宋さん(右)
「この句もけれんもはったりもない句である。けれんもはったりもないけれど、そこには作者の深い感懐がある。作者は現在台湾に住んでいる。旅行でも出張でもない。そこに生活の本拠をかまえているのである。家族も日本から呼び寄せたのであろう。但し老いた母だけは故郷において、異国にある作者の心情が思いきり訴えるように詠われている。それは母親に告げるでもない、人に知らせるでもない、ひたすら作者自身に呼びかけているようである。 「盆の月」は即き過ぎと言われるかも知れない。 しかし作者にとって「盆の月」という季語は、こうした感懐をするためにこそあるような季語であろう。」
台湾の方達と「春燈」との佳き縁を紡がれた加藤山椒魚さんであったが、一九八四年、突然強制送還となってしまう。戒厳令解除まであと三年、中華民國政府は複数の台湾人と日本人との接触をまだ問題視していたのであった。台北俳句会では「あと僅かで世情が変わったのに、本当に残念だった」と惜しむ声が今もある。
かの地なるかのひとびとよ走馬燈 山椒魚
〈本ブログ編集人から〉文中の写真は、本ブログ用に藤原雄介さんから提供されたものです。
その頃の若菜は、俳句を学ぶと同時に日本語教師の資格を取り、日本人が多く住む天母地区の語学学校で日本語を教えるようになっていた。会社から駐妻(駐在員の妻)の副業は禁じられていたが、人事部と交渉の結果、無報酬のボランティアなら可であるとの返事を引き出すことができたのだった。
同じ台北に住みながら若菜は、高齢の「元日本人」俳句仲間、日本語学校の生徒たち、日僑(日本人)学校の母親たち(日本人、台湾人)などとの交流を通じ、仕事漬けだった私とは違った台湾の素顔や景色を見ていたに違いない。台北の街を歩いていて、若い台湾人のグループに「ワカナセンセイ!」と声をかけられてはにかむ表情は私の知らないものだった。
つい先日、若菜の俳句関係の書類が収められたハードディスクに眠っていた彼女が黄霊芝先生のご逝去に際してしたためた一文と幾つかの句を見つけた。
黄霊芝先生に教えて頂いた俳句の基礎は常に心の芯にあります。一、意 見や理屈を述べてもつまらない。一、証拠が必要。その為には絵を描くように、映画を撮るように詠む。一、そこに詩はあるか。・・・不肖の弟子です。
便りせず仕舞も甘え春の雷
仙桃を賜りし日の木洩れ日や
照れ笑ひ残し仙人靄の中
来世また教へを乞はむ含笑花
昭和草仙人草と言ひもして
(つづく)
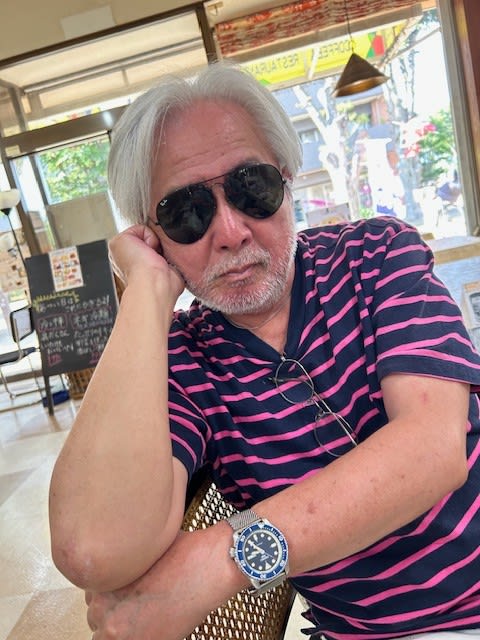
【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】
昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。