
【連載】藤原雄介のちょっと寄り道㉙
200円の星空 モロッコの旅③
マラケシュ(モロッコ)
以前NHKの「世界ふれあい街歩き」という番組でフェズが紹介されていた。偶然を装った「ヤラセ」で構成されている番組だが、私はこの番組のファンだ。ヤラセだの、現地の人との会話が総て日本語に置き換えられていることの不自然さなどは脇に置き、気楽に外国の風情を楽しんでいる。しかし、フェズの特集回については、落胆した。画面に映っていたのは、私が知るフェズではなく、奥行きのない、のっぺりとしたどこにでもありそうな単なる観光地であり、ワクワクもドキドキもなかった。
番組のクルーは、GPSで迷路内の自分の位置を把握しつつ、総て予定調和的に行動していた。50年前の私は、GPSはおろか地図もなく、地元の男の子だけを頼りに、路地の奥の未知への期待に動かされていた。50年の時を経て、私の中で無意識に美化されていたに違いないフェズの記憶が傷つけられたようで、心がチクッと傷んだ。

▲マラケシュのシンボルであるクトゥビアの塔は、12世紀に建立された高さ77mのミナレットだ。マラケシュ・レッドと言われる赤土が使われている
フェズを後にして、メケネス、ラバト、カサブランカを巡った。不思議なことにメケネスとラバトについては、あまり覚えていない。カサブランカには、イングリッド・バーグマンとハンフリー・ボガート主演の名画「カサブランカ」のイメージを重ねていたのだが、当然のことながらそんなものはどこにもない。フェズの後では、フランス統治時代の面影を強く残した、北大西洋に面した開放的な大都市に心惹かれるものはあまりなかった。
カサブランカから、また年代物のボンネットバスに揺られて238km南下し、マラケシュにたどり着いた。砂漠に近くなり、空気が一層乾燥しているのが感じられる。ここまで来ると、気候は地中海性気候からステップ気候(熱い半乾燥気候)に変わる。マラケシュに着くと、街行く人の人種構成が北部と変わっているのに、気づく。青い服を着てターバンを巻いた砂漠の民、ベルベル人が目立つようになった。黒人の姿も少なくない。
マラケシュとは、ベルベル人の言葉で「神の国」という意味らしい。これまでに巡った街には、固有の色があった。テトゥアンとカサブランカは白、フェズは蜂蜜色、そしてマラケシュは赤土の赤だ。現在のマラケシュは、女性がおしゃれな雑貨を買いに行くようなポピュラーな観光地になった。ちょっとネットサーフィンすれば、レストラン、雑貨店、ホテル、観光、どこで何を買えばいいか、何でも分かる。
しかし、1973年当時、マラケシュまで足を伸ばすのは、物好きなフランス人、ドイツ人、アメリカ人、そして世界各国から集まったバックパッカーかヒッピーぐらいのものだった。私は、胸まで届くほどの長髪で、傍目にはヒッピーに見えたことだろう。
マラケシュには、2週間近く滞在しただろうか、ほぼ毎日マラケシュの中心部にあるジャマ・エル・フナ(Jemaa el-Fnaa)広場に足が向いた。ジャマ・エル・フナ(以下フナと略す)とは、アラビア語で「死者の集う場所」を意味し、かつては公開処刑場であったという。フナ広場は昼と夜とで違う顔を見せる。昼間は、少数の工芸品や雑貨を売る露天が軒を並べ、独特の赤い衣装にカラフルな帽子を被った水売り、蛇使い、猿使い、金属製のカスタネットのような楽器を打ち鳴らしながら踊る男達などの大道芸人で賑わう。
そして、日暮れが近づくと、広場全体が無数の裸電球に照らし出され、幻想的な雰囲気に変貌する。大道芸人の数は更に増え、沢山の食べ物の屋台が出現し、タジン鍋やケバブの香ばしい匂いが漂い出す。夜が更けるにつれ、広場は、エスニックな空気が益々色濃くなり、混沌の度合を深めて行く。広場の屋台で、ビールは飲めない。しかし、広場の雰囲気に魅了され、酔ったような気分になってしまうので、酒好きの私でも困る事はなかった。
フナ広場では、同じ屋台やカフェに通うようにして、店の人たちと顔見知りになった。挨拶をし、ちょっとした軽口を叩ける相手がいると言うだけで、それまで強烈に感じていた自分が「異邦人」であるという感覚が薄れていくのが分かった。2009年、フナ広場は、マグレブ、サブサハラ、フランス、ユダヤ等の文化が混ざり合った独特の「文化空間」がUNESCOの世界無形文化遺産に登録された。

▲昼間のジャマ・エル・フナ広場には大道芸人が

▲水売りが革袋から真鍮のカップに水を注ぐ。私はお腹を壊すのが怖くて飲むことはなかった

▲蛇使い

▲夕闇が迫るジャマ・エル・フナ
フナ広場を歩けば、数分おきに怪しげな男が後ろから近づいてきて肩越しに小声で囁きかけてくる。
「ハシシ、ハシシ…いいのがあるよ」
ハシシとは、大麻の成分を抽出した黒っぽい色の濃縮物のことで、乾燥大麻(マリファナ)より、強烈な効果があると言われている。モロッコでもハシシや大麻は、違法なのだが、それらを吸引して捕まったと言う話は聞いたことがない。路地の奥にあるカフェ、安宿の部屋や屋上から独特の匂いが漂ってくることも珍しくはなかった。
マラケシュの朝の空気はフレッシュペパーミントティーの香りに満ちている。行きつけのカフェでは、小さなガラスコップにたっぷりの砂糖を入れ、ミントの葉をギュウギュウに詰めて、熱湯を注いでくれる。ミントの葉は、鮮やかな緑からほんの少し茶色に変色し、爽やかな香りが立ち上る。朝市でミントの葉を買い求めるのは、子供か男の役目らしい。大量のミントの葉っぱをひもで束ねて家に持ち帰る様子は、生活感に溢れ、見ていて心が癒やされた。
マラケシュの夏、昼間は40度近くまで気温が上昇するが、空気が乾燥しているので日陰にいれば、さほど暑さは苦にならない。夜になると20度くらいまで下がり、日によっては肌寒いこともある。安ホテルでは、通常の部屋代の半額(多分200円ほどだった)を払えば、屋上で寝ることができた。共同のトイレとシャワーがあるので、別に困ることはない。多様な国籍の私と同じような貧乏旅行のバックパッカー達と満点の星を眺めながら、とりとめのない話をするのは楽しかった。
社会復帰することを前提に学校を休んで旅行している者もいれば、いわゆる自分探しの旅をしている者もいる。そして、将来のことを考えるでもなく、半ば人生を放棄したかの如く気儘に放浪の旅を続けている者もいた。マラケシュのことを思い出していたら、将来どうしたいのかまだ分からず、不安だった若かりし日の焦燥感が蘇ってきた。
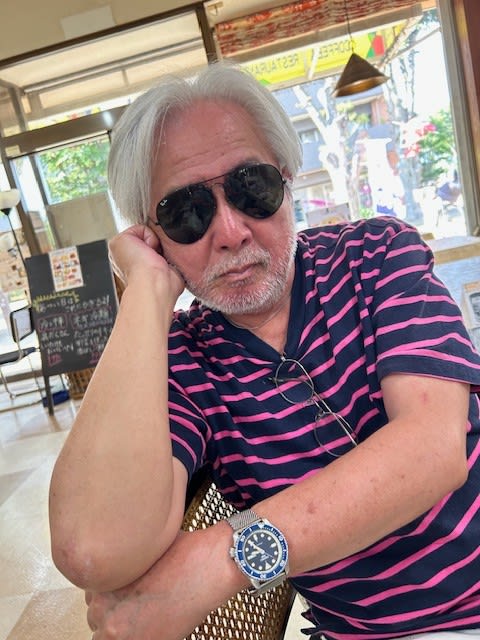
【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】
昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。

























