6/1(月)に放送されたNHKBS1スペシャル「穂高を愛した男 宮田八郎 命の映像記録」の録画を見た。調べてみると、もとは2019年11月2日に放送されたものだった。
なんととりあげられた宮田八郎氏はすでに故人。2018年4月に知床遠征への準備として静岡でシーカヤックの練習中、行方不明となり、遺体で発見された。享年52歳。人生100年時代には若すぎる死だった。宮田八郎氏は穂高岳山荘の小屋番として、例年GW前の4月から冬が訪れる11月まで穂高の山中にこもっていた。
番組の前半では、彼が小屋番をしながら撮りためた映像をもとに穂高の四季を紹介していく(以下ほとんどネタばれになるので、これから見ようという人は注意)。
4月は小屋番の仕事初め。荷揚げのためにヘリポートにスタッフが終結し、しばらくお別れとなる家族も見送りにやってくる。切ない仕事初めだ。ヘリで小屋に到着すれば、雪おろしと雪かきと小屋明け作業で大忙しとなる。やがてGWがやってくれば、小屋は登山者でいっぱいになる。5月毎年小屋に引き込む水の確保のため、雪に埋もれた沢までスコップで掘り進み、雪のトンネルの先にパイプを通す。
6月は雪解けの季節だ。大量の水が穂高を源として流れ出す。その水に促されるように咲き誇るニリンソウの群生地の映像はすばらしい。宮田氏が生前内緒にしていた場所と紹介される。涸沢カールでは、シナノキンバイ、ハクサンイチゲが咲き誇っている。
宮田氏は穂高の大量の映像記録を残していて、貴重なものも多い。番組では惜しげもなくその貴重映像を流していく。つかの間のモルゲンロート(朝焼け)、霧に浮かぶブロッケン現象、白い虹、太陽の上方に光が伸びて見える太陽柱、エリック・ロメールの映画を思い出すけれども、日没時に瞬間現れるグリーンフラッシュ、夏の積乱雲、雷雨、そして直後の見事なアーチを描く虹、見渡す限りの雲海、そして次々に稜線を駆け上がり下っていく滝雲。
秋ともなれば、紅葉はもちろん、北海道の大雪でもなかなか見ることのできない「三段染め」がすごい。三段染めといってもピンとこないかもしれないが、ハイマツなどの常緑樹の緑、紅葉の赤や黄色、そして新雪の白がいっぺんに見られる景色だ。
そして小屋閉めの11月。別れの季節だ。まず学生バイトが下山していく(なぜ11月なのかは突っ込まずにおこう)。そして窓に板を打ち付け、シーズンは終了する。ザックを背負って皆下山だ。
しかし、人を寄せ付けない冬が到来しても、宮田氏は奥さんの握ったおにぎりをザックにしのばせ、穂高を目指し撮影を続けた。そこには、「原始の穂高」があったと宮田氏はいう。厳冬期に撮られた傑作映像は、月、満天の星、雪煙を上げる穂高の岩峰が織りなす自然の造形だ。
後半は、宮田八郎氏の山岳レスキュー活動に焦点を当てる。まったく知らなかったが、コミック『岳』の主人公、島崎三歩のモデルということだ。わが家に最初の1巻目だけがあって、思わずページを繰ってしまった。
生々しい遭難現場、そして救出の映像が流れる。宮田氏は100件以上の遭難救助に携わり、その死も目の当たりにしたことから、「人はなぜ山に登るのか」という哲学的問いにさいなまれるようになる。串田孫一の『山のパンセ』をひもとくのも、この時期だ。
とくに親しくしていた仲間の死がさらに思索を深めることになった。そのうちの一人今井健司氏は、2015年ネパール、チャムラン北壁で遭難。享年33歳。大きく報道され私もよく覚えているが、ピオレドール賞受賞の谷口けい氏も2015年大雪山系黒岳で滑落死した。享年43歳。
そうした思索の結果、宮田氏のなかでは「なぜ人は山に登るのか」の問いに対する答えが出ていたようだ。それは「生きるために登る」。これから生きていく自分への励ましの言葉のように思える。奥さんの和子さんのインタビューからも宮田八郎氏のそんな一生懸命な生き方が伝わってきた。














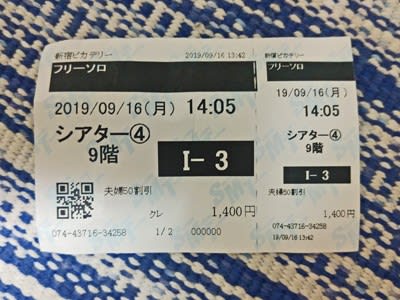
 6月6日放送の秘密のケンミンSHOWを遅ればせながら視聴した。「ワインは一升瓶でガブ飲みしまくるずら? 山梨県民の真実」として、一升瓶のワインが登場した。
6月6日放送の秘密のケンミンSHOWを遅ればせながら視聴した。「ワインは一升瓶でガブ飲みしまくるずら? 山梨県民の真実」として、一升瓶のワインが登場した。


![盛田甲州ワイナリー シャンモリ 山梨県産100% [ 2008 白ワイン 中辛口 日本 1800ml ]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/31deKuNkCaL._SL160_.jpg)






