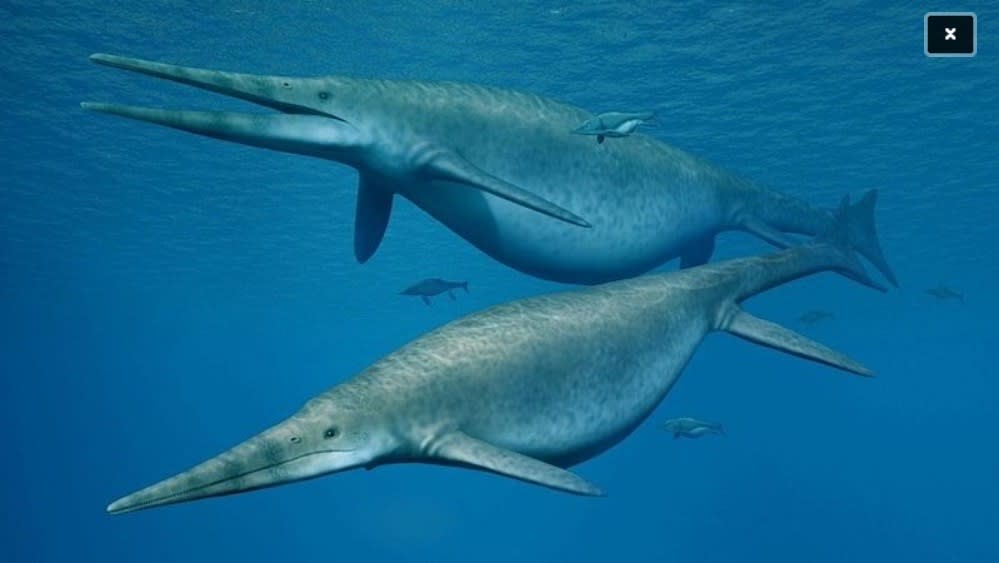一人の男が、空ろな眼をして柵の間からその奥を見詰めている。
午前三時過ぎ、ひっそりと鎮まり返った新興住宅地の一軒家の前で、男は何かを想い詰めた様な顔をして囁く。
「育花(いくか)…育花……育花……」
鼻息を荒くして苦しそうに喘ぎ、男は一階の窓の向こうに映る人影を柵の隙間から覗きながら下半身を頻りに摩る。
男は「育…花…っ」と力なく叫ぶと男の器から、白濁の種が落ち、その下にあったプランターの土の上に蒔かれた。
それから、四年の月日が流れた。
中秋の名月の晩、一人の男が、帰る道すがらふと、ある一角に目を留めた。
今までは何にも生えていなかった枯れた葉ばかりがそのままになっている長方形のプランターの中央部に、小さな芽が、ひょこっと顔を出していたからである。
男は反射的に朗らかに微笑み、プランターの前に腰を下ろすとその小さな弱々しい芽を見つめ、そっと右の人差し指でその芽の先に触れ、愛しげに微笑んだ。
そして満月を見上げて胸に下がった十字架を右手に取り、目を瞑ると囁いた。
「天におられますわたしたちの父よ。今夜は美しい月に人々はみな夜空を見上げあなたの御業に感謝しております。しかし誰も目に留めない涸れた地にもあなたは新しい生命を宿らせ、それを御覧になられて喜ばれていることをわたしたちに知らせ、そしてどれほどの喜びがそこにあるのかをわたしたちは知ることができます。あなたの祝福が、いつまでも絶えることなくわたしたちのうえに降り注がれますように。アーメン。」
男はその後も毎日、自分の家と教会のあいだの道筋にある家の前のこのプランターの芽に朝と晩、必ず目を留め、時に土が渇いている日には持参のペットボトルの水を上から注いでやるのだった。
そうして、一月もの月日が流れた。
或る夜遅く、一人の男が遣って来て、こう小さく呟いた。
「ちきしょう。」
そして男はがすっと気づくと蹴っていたものを見下ろした。
そこには長方形のプランターの中央部に、薄ピンク色の花が咲いていた。
男は力なく「はっ」と卑屈に笑って右手に持っていたカップ酒を飲んで大きくゲップした。
そして腰をこごめ便所坐りをするとカップ酒を左手に持ち替え、右の人差し指と親指でその小さな花弁を摘まんで、指先についた夜露を舐めて言った。
「或る、愚かな夜に愚かな女がいて、愚かな股を愚かに広げ、愚かな男を愚かに誘惑し、愚かな男は愚かな金を払って愚かな女を愚かに買った。愚かな女に愚かな男は愚かな恋をし、愚かな金の尽きた愚かな男から愚かな女は愚かに逃げた。或る、愚かな夜に愚かな家の中で愚かな女は愚かな入浴を済ませ愚かな裸体を愚かな椅子の上で愚かに曝し愚かな仮眠をとっていた。愚かな男は愚かなそれを愚かな情欲を抱いて愚かに見つめ愚かな妄想に耽り愚かな種を愚かな土の上に愚かに蒔いた。愚かな種は、愚かな土から、愚かな芽を出し、愚かに成長を続け、やがて愚かな花を咲かせた。愚かな薄ピンク色の花は、まるであの愚かな女の、愚かな花弁のようであった。愚かな男を誘惑した愚かな女の愚かな花弁にそっくりな愚かな花、愚かな御前の名を、愚かな男が愚かに付けてやろう。御前の名は、今日から、愚かな花と書いて愚花(ぐか)だ。精々、愚かな男を愚かに誘惑し続けて、愚かに枯れて逝け。」
言い終わると男は立ち上がり、人の居なくなった蛻の殻のその家を一瞥して夜のしじまの向こうに去って行った。
男が立ち去った後、花はそっと自分の名を囁いてみた。
「愚花…ぐか…あたしの…名前は…愚花……」
花弁から、夜露が垂れ落ち、その水玉に月光が反射していた。
翌朝、愚花は頬を優しく撫でられる感触を覚え、目を覚ました。
すると目の前に、大きく優しいあの手があり、あたたかい体温を感じた。
神父の男は愚花に向って微笑み、こう言った。
「なんて愛らしい花でしょう。花をあなたが咲かせるとは想いませんでした。」
愚花は嬉しくて瞬きを何度とし、朝露は神父の指先を濡らした。
神父は持っている黒い鞄の中からペットボトルの水を出し、その水を愚花に与えながら言った。
「さあお水ですよ。今日も良いお天気で、神が可愛らしい花を咲かせたあなたのことを祝福しておられます。」
青空から真っ直ぐに陽射しが神父と愚花を照らし、眩しく、世界は耀くようであった。
「あなたはなんという花なのでしょう。」
そう囁くと神父は身を起こしていつものように教会に向って歩いて行った。
神父が立ち去った後、愚花はそっと自分の名をまた繰り返した。
「あたしの名は、愚花…愚かな花と書いて、愚花…」
花弁から、朝露が垂れ落ち、その水玉に朝日がきらめいた。
それから、一週間後のことである。
教会の門塀に、「今日の聖句」と題した紙が貼られているのをちょうどそこを通りかかった男が目に留めた。
そこにはこう書かれてあった。
『あなたは姦淫を犯してはならない』と言われたのをあなた方は聞きました。
しかし,わたしはあなた方に言いますが,女を見つづけてこれに情欲を抱く者はみな,すでに心の中でその[女]と姦淫を犯したのです。
マタイ五章二十七-二十八節
男は空ろな目でその言葉をじっと眺めていた。
一本の煙草を吹かした後、吸殻を地面に棄てて足で火を消す。
男は教会の門を抜けてそっと教会の戸を開けると中を覗き込んだ。
そこには一人の若い神父が講壇に立ち、老若男女の前で聖書の説教を聴かせていた。
男は一番後ろの席に静かに腰を下ろすと神父の説教に耳を傾けた。
神父はゆっくりと、穏かに話し始めた。
「神はどのような理由からも、姦淫の罪を赦してはおられません。
モーセがエジプトから逃れシナイ山で授かった十戒の一つに、『姦淫してはならない。』という言葉を神は最初に、明確に示されました。
神は『殺人』の罪と『盗み』の罪とのあいだに、『姦淫』の罪を置かれました。
では姦淫の罪を犯すことは、わたしたちにどのような報いがあることを示されているでしょうか。
コリント第一の六章九節と十節にはこうあります。
『淫行の者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、大酒に酔う者、罵り誹る者、略奪する者は、いずれも神の王国を受け継ぐことはないのです。』
さらに、ヨハネの黙示録の二十一章八節にはこうあります。
『しかし、臆病な者、信仰のない者、忌むべき者、殺人をする者、姦淫を行う者、呪(まじな)いをする者、偶像を拝む者、またすべて偽りを言う者には、火と硫黄の燃えている湖の中が、彼らの受くべき報いである。これが第二の死である。』
第二の死とは、肉体の死の後、永遠に神の光の届かない地で生きてゆくことを意味しています。
また、テサロニケ第一の四章では神がわたしたちを召されたその御心は、わたしたちをこのような不品行と情欲のままに汚れたことをさせる為ではなく、清くなる為であると示されています。
そして神を知らない異邦人のように、貪欲な性欲のままに歩み、兄弟の権利を害して侵すならば、神はそのすべてについて処罰を科すことを示されています。
ヘブライ十三章四節では『結婚はすべての人の間で誉れあるものとされるべきであり、夫婦の関係は汚してはならない。神は、みだらな者や姦淫する者を裁かれるからです。』と示されました。
マルコ七章二十節から二十三節では主イエスは人を汚すものとは、外側から人に入ってくるものではなく、内側から出る悪が人を汚すことを言われました。
『また言われた。「人から出るもの、これが、人を汚すのです。
内側から、すなわち、人の心から出て来るものは、悪い考え、不品行、盗み、殺人、姦淫、貪欲、よこしま、欺き、好色、ねたみ、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪はみな、内側から出て、人を汚すのです。』
人は多くの時間、何か悪いものが外から遣ってこないかと脅えることがあるかもしれません。しかし最も恐ろしいものは、実は自分の内に在り、それが自らを最も脅かすものであることを主イエスは言われています。
ですから自分の外に、つまり他者の内にどれほどの悪があるかを数えるのではなく、自分の内にどれほどの悪があるかを知り続ける必要があります。」
その時、静かにそれまで話を聴いていた男が右手を挙げて後ろの席から低い声で呼ばわった。
「神父さん。」
そしてすたすたと神父の立つ講壇の前に歩み寄り、神父の目の前に立ってこう言った。
「あのさ、言いたいことは解る。誰だって好き好んで、そんな悪業を積んでみずから地獄にくだってゆこうとしているように見えないよ。俺だって好きで、情欲をいだいて女の、淫らな妄想をして、女から誘惑され、金払わねえと、駄目だっつんで、あいつに、俺は何百万と、俺は払ってあの女と姦淫を繰り返してきたんだ。これはさ、罠だよ。狡猾で、あまりに汚い、最悪な罠じゃねえか。あの女が俺を誘惑さえしなければ、俺だって童貞のまま、可愛い処女の愛する女と結婚して幸せになりたかったさ。俺は好きで、こんな風になったわけじゃないんだ。誰だってさ、綺麗な道を歩むほうが、本当に幸福になれるってわかってる。たった一度の過ちで、もう二度と、その道を歩むことはできずに虚しく死んで逝くこともわかってる。なあ神父さん。俺は気休めの言葉なんて聴きたくねえんだ。人は神から罪を赦されても、もう二度と、死ぬ迄、神の喜びの道を生きることは赦されねえんだろ。俺はわかってるよ。俺はそれを、あんたに言いたかったんだ。俺はさ、あの糞売女(ばいた)女に誘惑され、罠にはまらなかったら、今頃、大学も落第せず、植物細胞生物学の大学院生になって、今頃、食虫植物の遺伝子研究遣って、世界中のアホで屑な人間どもを全員喰ってくれる巨大な食虫花の開発に勤しんでたろうよ。俺はこの世界の救世主になりたかったんだ。まあでもさ、今は落魄れて、大酒飲みだが、最近、店をこの近辺で始めたんだ。死んだ花を売り捌く店だよ。枯れない生きてるみたいな花だって評判なんだ。教会で花を飾るときなんかがあれば、どうぞよろしくお願いします。それじゃ。」
そう言い棄てて男は一枚の名詞を灰色のジャケットの胸元から取り出すと講壇の上に置いてまたすたすたと歩いて教会の外へ出て行ってしまった。
神父は胸の痛みを感じ、人からこのように率直に情熱的な反論を受けたことがなかった為、とても悲しい気持ちに心が塞いだ。
しんと鎮まり返ったままの教会内で、神父は神に問い掛けた。
「人は、もう二度と、戻れない道があるのでしょうか。」
神父はこの日の帰り道、まだ悄然としていた。
なんとなく、今日のあの男の言った言葉が、かつての自分の訴えと同じものであるように想ったからだ。
神父は児童養護施設で育ち、5歳の時に養子に貰われた神父である義理の父親の家で育ったが、義理の母親が神父の十歳の時に三十八歳で心筋梗塞で他界し、その後、義父は独りで神父が中学を卒業するまで育ててきた。だが高校に入学した年に、義父は仕事が忙しくなり家事手伝いの女性を雇った。義理の母と同じ生まれ年の、四十四歳の女性だった。
その女性と、義父の関係がどういうものであったかは、今でもわからない。
妾のような関係にあったのかもしれないし、何もなかったのかもしれない。
義父は四年前の夏の夜、道路の真ん中でこけて腰を痛めている見ず知らずの老婆を助ける為にその場に駆け寄った瞬間、余所見運転しながら速度を落とさず走ってきたトラックに跳ねられ即死した。
六十九歳だった。
二十九歳で、神父は義父の跡を継いで神父になった。
今は三十三歳。あの女性が行方を晦ましてから十四年が経つ。
ただ側で眺め、情欲をいだき、彼女を心のなかで犯し続ける時間が三年続いて、彼女は跡形もなくどこかへ消えた。
道端で、今夜も儚げにその花は月夜を見上げるようにひっそり咲いていた。
神父は歩き寄り、屈んでその花の弁に指先を触れ、まるでその冷たく清らかな夜露を吸い取ろうとした。
神父はいつもと違って憂いのある表情でじっと花を見つめた。
そしていつも声を最低でもひとつ掛けたり、微笑んだりしていたのが今夜は黙って立ち去ってしまった。
ひとり残された愚花は、こころに不安の露を湧きあがらせ、その水滴は花の真ん中から垂れ流れ、湿った土のうえに音もなく落ちた。
それから、また一週間が過ぎた。
神父はすぐに笑顔を取り戻し、愚花に微笑みかけたが、その顔はまだ、憂鬱な影が帯びていた。
愚花は一分一分、自分の身体から水分が抜け出て、枯れていることを感じ取るようになった。
強い陽射しは、もう前のように快いものではなくなり、苦しく時に焼かれるような熱さも感じるようになり、夜には夜で骨の髄まで染み入るような寒さに身をふるふると震わせ神父のあたたかい体温を前以上に求むようになった。
愚花はどれほど寒くてもいつも、神父に微笑み返した。
会う度に、神父への愛おしさが大きく膨らみ、愚花は神父の雄蕊によって受粉する夢を見た。
神父の雄蕊はあの優しく白く細いが同時に隆々としている右の人差し指であった。
その雄蕊によって愚花の雌蘂は愛撫され、その時、神父の雄蕊の先から金色の粉が湧き出て愚花の雌蘂の先に着き、受粉する。
愚花が恍惚な感覚に満たされたその時、花糸(かし)が一つ、下に落ちた。
今まで自分の元でそっと息づいていたそれが死ぬように土のうえに落ちたままであるのを見て愚花は自分の身体は日に日に、壊れゆくのだということを知った。
愚花はこころの中で静かに叫ぶように祈った。
このまま壊れゆくのならば、いっそのことあのかたに摘まれ、押花にされ、ずっと側に置かれたい。
その時である。
一筋の月光が、愚花の柱頭を光らせ、そこから声が聴こえた。
ではおまえは行ってその通り、あの男に伝えるが良い。
ふと気づくと、愚花はひとつの長細いプランターの中央部に生えた一輪の薄ピンク色の花を見下ろしていた。
まったく同じ色をした、薄ピンク色のワンピースを着た自分が、自分を見下ろしていたのである。
愚花はすこしのま、忙然として突っ立っていたが、はっと我に返り、いっ、急がねばならんがな。と声に出して言うと、裸足のままでとにかく道の向こうを駆けてった。
たぶんこの道を、真っ直ぐに行くとあの神父に会えるであろう。
そう信じてとにかく全速力で愚花は走った。
すると目の前に、眩しき灯りが見えて、そこに向って走った。
どうやらそこは24時間営業のスーパーマーケットであるようだった。
長い黒髪が、汗ばんだ額や首筋にへばりついたまま、愚花はちょっとスーパーマーケットへ寄って行くことにした。
籠にとにかく、甘そうな果実を詰め込んだ。
それでレジカウンターで待っていると店員が愚花に向って言った。
「合計753円。」
「為口かっ。」
愚花は想わず声が出た。
金髪の若い男はもう一度ぶっきら棒に言った。
「合計で753円です。」
愚花はワンピースのポケットのなかを弄(まさぐ)った。
すると不思議なことに、そこにはちょっきし、753円のお金が入っていたのであった。
愚花はそれを払い、籠を持って台の上に移動し、そこで袋に買った果実を放り込もうと袋を開こうとした。
だがこれが、どうしたことか、開かない。開け口の部分を人差し指と親指で擦り合わせるのであるが、一向に、開こうとしないのである。
愚花は想わず、叫んだ。
「くわあっ。枯れる。涸れる。早くしないと。水分がぜんぶ抜けて、愚花は枯れてしまう。」
だがふと台の上に、水を沁み込ませたスポンジ状のものを見つけ、ときめいて愚花はそこへ指をつけた。
そしてその指で袋を擦るとすぐに、袋は開いたのであった。
果実をすべて放り込み、愚花はまた、郊外へ出て走った。
そして走って走って、とうとう神父の家を見つけたのである。
何故かはわからぬが、この家に絶対にあのかたが住んでいると、愚花にはわかった。
愚花はその戸を、想い切り叩いた。
時間は午前の三時過ぎであったが、愚花にはそれがわからず、焦眉の急を要する為、そんなことは言ってられなかった。
するとすぐに、戸は開かれた。
中から、神父が、驚いた顔で顔を覗かせ、そして何かを言おうとしたその時、
愚花は叫んだ。
「神父さま。愚花を、摘んで、それで押してください!」
「今すぐに!今すぐに!」
神父は目を大きく開いて丸め、開いた口が塞がらなかった。
愚花は地団駄をその場で踏み、神父を押し倒して、神父と愚花は玄関に倒れ込み、ドアは閉まった。
可笑しなことに、神父の家のなかへ入った途端、愚花は大人しくなって、何も話せなくなった。
神父は押し倒されたまま、困りに困り果て、この四十歳前後に見える女と、黙って見つめ合っていた。
そうやって見つめていると、神父はこの女がどことなく、自分が想いを寄せ続け、その情欲に身を焦がし続けたあの女性に見えて来るものがあり、生唾をごくりと飲み込み、股間に鈍痛を覚えた。
神父は心臓が高鳴るなか女を起こして玄関に座らせた。
女はこのもうすぐ十一月に入ろうとしている気温のなかに薄いワンピース一枚でしかも裸足で足が膝辺りまで泥だらけであった。
神父は落ち着いて、困った顔で見つめるばかりの女に向って落ち着いて訊ねてみた。
「貴女は、どこから来たのですか?」
愚花は落ち着かない様子でまごまごとして何を言えばいいのかわからなくなった。
「貴女は、どこのだれでしょう?わたしと、会ったことがありますか?」
愚花はうんうんうんうんうんっと首を縦にぶんぶん振った。
神父はどこで会ったかを中空に目を遣って首を傾げて目をきょろきょろさせながら想いだそうとしている。
だが想いだすことができず、その代わり想いを馳せていた女の顔が浮かんでしょうがないのであった。
愚花の顔を眺め渡し、観れば見るほど似ているように想えて胸が苦しくなるのだった。
神父は大きく息を吐いて、「ちょっと待っててくださいね。」と優しく言うと洗面所に言ってタオルをお湯に濡らして持って来て、愚花の足の泥を丁寧に拭いてやった。
愚花はどきどきする余り、足が震えて止まらない。
神父が「大丈夫ですか。」と訊ねるも、愚花は黙って神父を見つめ、それでまた苦しそうに言った。
「愚花を、摘んで、どうか押してください。」
神父はちんぷんかんぷんで一体この女が何を訴えているのかがてんでわからないのだった。
「”ぐか”とは、一体なんでしょう?」
神父がそう問うと愚花は自分を指差した。
「ああ、貴女のお名前が、”ぐか”というのですか。それはとても変わったお名前ですね。」
愚花は素直に自分の名前の意味を神父に告げた。
「愚かな花、と書いて、愚花なのです。」
神父は言葉に詰まり、一瞬、からかわれているのであろうかと訝った。
だが女の切実な潤んだ目を見つめると、嘘をついているようには見えなかった。
神父は小さく嘆息し、もう一度訊ねた。
「貴女の住んでいるおうちは、どこですか?」
愚花は考え込んだ。自分の家とは、一体どこなのかがわからなかったからである。
あの長方形のプランターが自分の家なのであろうか?
しかし家とは、屋根や壁があるものなのではないのか?
ということは、あれは家ではない。そうか、愚花には家というものがないのだ。そう想って愚花は素直に答えた。
「愚花は、家がない。」
神父はこの返事に、またまた困惑した。
家がなくて、一体この女はどこでどう生活をしてきたのであろうか?
それとも、もしかして、夫のもとを出てきたのではあるまいか。
もしそうであるなら、大変である。
この女は夫を騙して姦淫をしているなどと噂され、このわたしも姦淫神父野郎などと陰口を叩かれるかも知れぬ。
そうすると、どうしたら良いのであろう。
わたしもこの女も、この町を出て行かねばならないことになるだろう。
あの教会を棄て…また新しい町で、この女と遣り直すしかない。
神父は不安と胸のときめきが胸中で混濁となる感覚に、先のことを考え過ぎだ、主イエスは「明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。」と言われたではないか。とみずからを叱咤した。
神父は毎夜の聖書の勉強で寝不足となった目でまた女の目を見つめ、「一先ず上がってください。あたたかい飲み物を淹れましょう。」と言って女の肩を支え女を家のなかへ上げた。
女を和室の客間へ案内し、淹れた豆乳チャイティーの入ったマグカップを二つ持って来て座った。
女は差し出されたそれに口をつけ、また焦燥のなかに壊れたA.I.ロボットのように同じことを言った。
「愚花をどうか摘んで押してもらえませんか。」
神父は落ち着いて、ひとつひとつ訊ねることにした。
「その、摘む、とは、一体なにを摘むのでしょう?」
愚花は目を瞬かせて、「摘むとは、根元から、くきっと折って、千切ることです。」
「どこを…?」
「だから、愚花の、根元らへんです。」
神父は俯いて、頭を悩ませた。
顔を上げると、次の質問をしてみた。
「では、押すとは、一体なにを押すのでしょう?」
「愚花を押すのです。愚花の全身を。重いものを載せて。」
「どこへ…?」
「手帖などがよろしいかと…。」
神父は空笑いをすると続けて言った。
「はは、愚花さんを押すにはとても大きな手帖を発注しなくてはなりませんね・・・。」
愚花はこのとき、初めて信じられない衝撃に満たされた。
果たしてあのプランターのなかに咲く愚花と今ここにいる愚花は、同じ存在なのであろうか。
愚花は神父に向って言った。
「あの…新しいビニール袋はありませんか?袋の開く口が開いていない…」
神父は、はて、何に使うのだろうと想ったが「ちょっと待っててくださいね。」と快く返事をするとすぐに新しいぺちゃんこの袋を一枚持って来た。
愚花は「ありがとう。」と御礼を言って、その袋の開き口を人差し指と親指でこすった。
やはり開かなかった。
愚花は絶望した。
あの愚花と、ここにいる愚花は、やはり同時に枯れて行ってるに違いない。
枯れ切る前に、神父さまに摘まれて押されなくては、愚花は、枯れた後も、神父さまのお側にいることができない・・・。
愚花は悲しくて、涙をぽたぽたと落とし、着ている薄ピンク色のワンピースが斑模様となった。
神父は焦って愚花に膝を擦って進み寄り、その右手を両手で握った。
「大丈夫ですよ。神はいつでも貴女のことを見つめて、貴女がどのような時でも変わらず暖かい光を照らし、時に雨を降らし共に泣いてくださる御方なのです。」
愚花はそんな言葉を神父から言われ、想いきり泣きたくなったのだが、此処で泣いては水分が流れ出て、愚花が枯れるまでの時間が早まってしまうと、必死に涙を堪えて我慢した。
だが神父は、「泣きたいときは、存分に泣くのが良いのですよ。さあたくさん泣いてください。たくさん泣けば、すこしすっきりとしますから。」と言った。
愚花は泣きたいのに泣けなくて、本当に泣きたくなった。
そして、「水を貰えませんか。」と愚花は言った。
神父は頷いて急いで2リットルのペットボトルの水とグラスを持って来て水を注いで愚花に飲ませた。
愚花は、ごくごくと、2リットルすべての水を、飲み干したのであった。
神父は、「そんなに喉が渇いていたのですか…気づかなくて申し訳ない…」と謝った。
しかし愚花は、黙って泣くばかりであった。
多分、これで1リットルほどは、泣いても大丈夫やろうと想ったからである。
神父は、懐かしく切ない想いでそんな愚花の泣いている姿を見つめて、愚花の痩せた冷たい手を握り締めていた。
そして愚花が一頻り泣き終わったと見るや、神父は愚花に、こう告げた。
「良かったら…貴女の新しいおうちが見つかるまで、此処で一緒に暮らしましょう。」
愚花は神父の目を見つめてこくんと頷くと、神父の右の人差し指を自分の右の目の下に当て、一粒の涙を神父の指先に落とした。
神父はそのとき、デジャヴュを感じた。
翌朝、ソファーの上で眠っている神父を朝早く、愚花は起こして昨夜買った果実を食べさせた。
皿の上には柿と蜜柑と梨が細かく刻まれて載せられてあった。
ふと、神父が愚花の左手の指を見ると、その指がまるで躊躇い傷がいくつも付いたようにずたずたな状態となっており、ショックの余りに神父は失神しかけた。
だが、その傷だらけの指が、どう見ても違和感を拭えないのだった。
何故なら、一滴も、赤い血が出ていないようだったからである。
その代わりに透明な粘液をともなった液体が、愚花の傷口から垂れているのを神父は見た。
神父はひとつひとつの愚花の傷に、手当てをし、もう決して刃物を使ってはならないと愚花に誡めた。
愚花は神父に、水をたくさん買ってきて貰えないだろうかと頼んだ。
神父はそれを疑問も持たず聞き入れ、2リットルのペットボトルを歩いて往復30分近くかけて十本買って来た。
愚花は不安気な顔でその十本のペットボトルの水を眺めていた。
神父は腕時計を見て、あと30分で教会に着かなくてはならない時間であるのに気づき愚花に言った。
「今日は夕方の五時半頃にはきっと帰ってきます。その時にあと十本のペットボトルの水を買ってきますから。それではいってきます。お昼ごはんは昨晩に作ったものを電子レンジで温めて食べてくださいね。電子レンジの使い方は紙に書いて電子レンジの開けるところに貼ってありますから。」
心許無い愚花を残し、神父は心配でならない想いで家を出た。
急いで神父が家から帰ると、時間は夕方の六時を少し過ぎていた。
家のなかを探しても愚花の姿がなかった。
「愚花さん。」と呼ばわりながら神父が裏庭の雨戸を開けて覗くと、狭い庭先に愚花が目を瞑ってうつ伏せに倒れ込んでいた。
神父は愚花の頬に触れると、その肌はとても乾いていた。
急いで水をグラスに入れて愚花に飲ませ、愚花は飲むというより、口許から吸い取るように水を飲み、2リットルの水を二本飲んだところでやっと目を覚ました。
安心して涙を流しながら神父は愚花を起き上がらせて縁側で抱き締めて言った。
「貴女を愚かな花と名づけたのは誰なのでしょう…わたしがどれほど貴女の元気な姿を見かける度に嬉しかったことも知らずに…」
愚花は一命を取り留めたが、その枯れ具合が、元の瑞々しい状態へと戻ることはなかった。
それでも神父は、愚花の枯れる前の美しさを愛するのだった。
その枯れ行く美しさは、四十七歳で自分の前から姿を消し去った愛する女性の面影があった。
その夜、愚花は縁側に置かれた、プランターと、自分の姿を見つけた。
神父がこの日の教会の帰りに、5本の2リットルのペットボトルの水の入った袋を左手に持ち、残りの5本のペットボトルの水をバックパックに詰めて背負い、そして右手に、愚花の咲いたプランターを抱えて家に連れて帰ってきたからである。
愚花は枯れかけている自分の姿を見るのが痛々しくてならず、そのことを、神父に話すことすらできなかった。
愚花はもう、ただ枯れる前に摘んで押花として神父の側に居られるなら、それで良いと諦めていた。
でも神父は、この日から毎日、どうすれば愚花を生き永らえさせることができるのか、そればかり考えていた。
次の日愚花は、神父が自分を摘んでくれない悲しみのなかにこんなことを言い放った。
「愚花は、ただ生きているだけです。毎日、神父さまは愚花のために重たい水を何本と買ってきて、力をなくした枯れかけの愚花は、もう本当に、生きているだけなのです。ただ枯れかけた見苦しい姿で、咲いているばかりなのです。なぜ、愚花を、摘んでは貰えないのですか?愚花は、これ以上枯れるまでに、せめて今の姿で神父さまの御側におりたいのです。」
気づけばまた、大事な水分が愚花の目から、垂れ流れて止まらぬのであった。
神父は神父で悲しみに暮れ、それでも愚花に向き合って話した。
「すべての花が、実を実らせる為に生まれて生きているのではありません。多くの花はただそこに、咲いているだけのものです。田んぼに出て、農作業をしたりもしない。畑へ出て、野菜や果実を捥ぎ取ったりもしない。工場のなかで働くこともなければ食事を運んだりもせず、誰かのクレームを聴いたりもしません。掃除も洗濯もお皿洗いもしません。それでも神は、その小さな誰も目に留めぬ花でさえ、これを綺麗に着飾らせて、その花に雨を降らせ、日を照らさせるのです。いつか枯れてしまうからといって、神は摘み取ることはしません。」
愚花は悲しくて泣いた。
神父は愚花の代りに泣くことを我慢し、ひたすら愚花の命が永らえる方法をネット上や本のなかに探し出そうとした。
「花を長持ちさせる方法」という本のなかに、「ドライフラワー」という言葉を見つけた瞬間、神父はあの男の言葉を想いだした。
確かあの男は「枯れない生きているような花」だと評判の花を売っていると、そのようなことを言っていたはずだ。
神父は廊下を走って椅子に掛けたままであったジャケットの内側から財布を取り出し、その中に仕舞ったままのあの男の名詞を取り出した。
そこには店の名前と住所と電話番号が書いてあった。
ネットで調べると朝の十時から開いているようだ。
神父は愚花のもとへ戻るとしょんぼりと縁側に座って月光に照らされている愚花を優しく抱き締めて言った。
「わたしはいつまでも貴女とこうしていたいのです。」
翌朝早くに、神父は眠っている愚花を残してあの男の店に一人で出掛けた。
開店の三時間前に、その店のガラス戸を叩いた。
すると奥のほうから、あの男がやって来てドアを開け、にやついた顔で笑って神父を見た。
「まだ開店前に申し訳ない。実はあなたに相談したいことがあるのです。」
男は頷き、「待ってたよ。」と言うと神父を店のなかへ迎え入れた。
神父はなかへ入ると、鮮やかな色彩の花々が芸術作品のように様々なオブジェとして飾られ、展示されているのを見て心が躍動するものを感じ、その独特な華やかさは生花に似てはいるのだが生花とは違う何かを感じるのだった。
「これって…みんな生きた花ではないのですか…?」
男は一緒になって部屋のなかを眺め渡して言った。
「さあ…どうなんだろうね。俺は生きていると感じるが、生きた花よりもね。」
神父は何か闇の光を感じているような感覚で言った。
「これはみんな、水を必要としたり、光が必要だったりしないのですか・・・?」
「うん、水も光も土もなんの栄養素も必要ではない。気をつけることは高温多湿と急激な温度変化を避け、適度な湿度管理、直射日光や強い照明光に当て続けないこと、そして一番重要なのは、”生きている花より美しい”と話しかけることくらいだな、ははは。」
「これは何か名称があるのですか?素材というのかな…」
「プリザーブドフラワー(Preserved flowers)ってやつだよ。特殊液に一、二週間漬け続け、そして乾燥させるだけだ。脱色してから着色するという作り方もあるが、うちでは全部生きたままの色を保存させることのできる特別な液体を使っている。だから死んでいるはずなのに、見た目は生きているのと変わりはない。」
「これは…」
神父は言葉が続かず、言うのを躊躇っていた。
「相当、想い詰めた顔しちゃって、深刻な相談なんだろう。金さえ積んでもらえるなら、俺にできることは遣ってやるよ、神父さん。まあ立ち話も疲れるから、ああ、その前に、あっちに水槽があるから、それを見せるよ。」
「水槽…?」
男のあとを追って神父が着いて行くと、一つの部屋に案内された。
部屋のなかには白いカーテンが壁の端から端まで引かれており、男はそのカーテンを一気に引いた。
そこには部屋の半分ほどの大きさの水槽があり、その中にはものすごい数の花々や葉が漬けられていた。
神父が言葉を失っていると男が平然な口調で言った。
「俺の本業は実はこれじゃないんだよ。俺の本業はさ、人間を強引に無理無体に、咲かせたままの状態にすることだよ。」
神父は目を見開いて左を向き、男の目を見た。
「聖書はそういえば、呪術者に近づくことすら禁じているよな。俺の本業は一種の呪術と言ってもいい。植物人間もこの液体に漬けると、目を開け、言葉を発することもあることに気づいたんだ。でも死んでるのか生きてるのかは俺にはわからない。でも生きているように、そいつは喋ることもできるし笑うこともできる、飯食って糞して寝て、性行為だってする。ただ記憶とか、人間の理性とか、愛とか、失くしちまってるように外からは見えるだけだ。」
神父は気が朦朧とし、気を喪うような感覚のなか虚脱状態に陥り、貧血も起こって立っていられなくなり蹲って、二の句が継げず、心臓がとてつもなく早く鼓動を打って死ぬのではないかと感じた。
すると男は呆れたように神父に向って言った。
「あんたさ、よりにもよって、愚かな花に恋をするなんて、どうしようもねえ神父だよな。」
神父は胸を押さえて男を見上げ、かすれた声を発した。
「何故、それを…?」
ははは、と男は渇いた笑いをしたあと深く溜息を吐き答えた。
「当たり前だろ、愚花は俺の蒔いた種から、芽を出し、そして花を咲かせたんだ。俺が知らないはずはない。あいつの名を付けたのも俺さ。あいつにぴったしの名前だろう。あいつの母親が、あの雌犬になるのかどうか、わからねえが、あの雌豚が俺を誘惑して、金を奪い取り、そして俺が情欲をいだいてあいつを求めなければ、愚花も、この世に存在してないんだぜ。神父さん。愚花はとんでもなく醜い女だよ。だって俺の最悪な姦淫の罪の、その種が咲かせた花なんだからなあ。穢ねえにもほどがある女だ。愚花はさ、生きててもしょうがないんじゃないかと俺には想えるが、というか早く死んでもらいたいが、でも俺はあんたに借りがあるから、神に借りがあるから、だから神父さんの願いを俺は引き受けるつもりだよ。枯れかけて死に掛けている愚花を、この液体に漬け込んで、そして生きた状態のままで、何十年、いや何百年、生き続ける術を、この際、無償で、俺が遣ってやるよ。神父さん。」
神父は意識の遠くなるなかに、時間がどれほど過ぎたかもわからないなかに、男に、「お願いします…」と、声を絞り出すように、言って、男の靴に頭を付けて拝むように懇願した。
家に帰ると、まだ午前十時過ぎだった。
愚花は、疲れているのかぐっすりと、まだ眠っていた。
神父は愚花の寝顔を見つめながら、途方もない永い時間を、愚花と過ごしてきたような感覚になるのだった。
「何故なのでしょう…。」
神父は、吐き気を感じるなか、同時に、今までに感じたことのない安心と幸福感のようなものを感じているようだった。
やっと、ずっと一緒にいられるのだと、想って、神父は眠る愚花の渇き切ったその口に、そっと接吻をした。