婦人会創設に関するおさしづ 7
(7)
明治31年10月26日 (4巻3124頁)
『桝井安松身上歯の痛み願』
(411)さあ/\尋ねる事情/\、いかな事情も尋ねにゃ分からん。前々一つ、ようこそ尋ねたなあと諭したる。(412)治まれば身上治まる。(413)古い処の理、(414)一日なりと楽します/\。(415)これ一つ、後は一つ。堪えられんと言うであろう。(416)一時一つ事情、後一つ小人という、だん/\事情、(417)内々の事情であろか、道の事情であろか分からん。尋ねる。(418)分かるように諭す。皆双方の理も分かる。よう聞き分け。(419)長い話に伝え置く。(420)年限の間、それ/\皆んな日々順序の道考え思やんしてみよ。(421)婦人会の理、婦人会を始め掛けた。(422)これはめん/\一つ思えば、一時どうなる。(423)事情の道と言えば楽しみ。(424)身上は楽々と言うて、長らえての道、長らえての苦しみ。(425)未だや/\年限余程身を苦しんで、(426)年限長い間、どうなる知らんと思うた日もある。(427)さしづに基づいて日を送り、(428)楽々と使わして貰うた。(429)日々取次出る中である。(430)又一時掛かる/\、(431)身上に掛かる。(432)さしづに順序、(433)中に何名取次何名中何人(434)この理を取り調べて、(435)心に関心の理を治めにゃならん。(436)この道どういう事から成った。(437)男女隔て無い。(438)一つの台にして始め掛けた。(439)この理がとんと分かり難ない。(440)この道の始めた教祖一代の処は女、後席は男。(441)男女の隔て有るか無いか。(442)この順序の理、(443)日々取り次ぎ、男女の隔て無い。(444)今日入り明日入るような者には、どうせいこうせい言えようまい。(445)道無き理はあろうまい。(446)無理に入ろうと思うても、入れるものでなし、(447)入れようと思うても、入れられるものやない。(448)隔てる理は無きもの。(449)取りよう聞きようの理、(450)又一時の理、又分かり難ない。(451)めん/\さえこうと言えばこう、(452)誰がこうと言う者は無い。(453)よっく聞き分け。(454)心又一つの理が治まらねば、尋ね返やすがよい。(455)ほんにこうとめん/\からこうすれば、皆んな心を寄せてくれる。(456)入って長らくの道と言えば、(457)日々取次の中、(458)こゝらから相談せにゃならん。(459)相談すれば、こう/\言わねばならん。(460)めん/\からこうすれば、(461)それはいかんと言う者はあろまい。(462)上から下を育てにゃならん。(463)一日でも早く入りた者は、(464)育てる理が無くば聞き流し、(465)思い違いなら、(466)育てにゃならん。(467)思い違い/\、(468)これから綺麗な順序聞き取ってくれにゃならん。(469)上の理寄って聞き取ってくれにゃならん。
『押して願、おことの事でありますや』
さあ/\尋ねる処/\、まあ年取れた者/\。そりゃ今一時の処、ならんと言うやない。今替わり/\゛替わり番/\。それはならんとは言わん。休息所々々々、結構々々、当分の一つの当番、当分日々の順序、もう程無う日が移る。どういう役はどういう役。程無う教祖存命順序、楽しみ移って、一つの理、又程無う替わって、一つ楽しんでくれにゃならん。
さあ/\未だ/\順序諭す。書取々々の理、筆に記したる。書取の理清書、こういう理の諭しであった、どういう事やら答が無くばならん。どうも、道理の道が鮮やかならん/\。日々寄り来る中に、取次何人あるか。人数改めてみよ。何人あっても、出て働いて居る者もあろ。順序替わりて働いて居る。そんならすっきり揃うは、年分に何ぼうも無い。大祭と言えば皆揃う。間は用がある中に、よう聞き取ってくれにゃ分からん。日々別席皆んな諭する中に、どういう事諭する者もあれば、こういう事諭する者もある。未だ一時は定めが有って定め無い。日々取次、別席言わにゃならん理言わず、言うわいでもよい事言う。早く取り揃えて一つ順序という。
『教長へ別席の順序願』
さあ/\別席というもの、これ始めた時から理を以て始めた。最初一席三名、だんだん始め掛け。取次三人、書取一人、筆は三人にまで許してある。取次どうもならん。思い/\勝手を言う理がありては、欠けて了う。近い所何程の事がある。遠い所より席と言うて、教一つ楽しんで来る。先々信徒心を揃えて来る。大抵やない。皆んな揃うて来る中に、数えられん。それ/\゛心運んで、連れ戻る理を治めて来る。日々席さして、遠く所を戻りて来る。栄える元という、栄える順序の理、取次から始める。取次、人を改め/\。何人の中に何人ある。席一日遅れる二日遅れる中に一つ思いやらにゃならん。特別何席、十分運ばしてある中に一つの心の理を思いやらにゃならん。区別掛け隔てあってはそも/\という。遠く中を連れ帰りてそもそもでは映し難くい/\。一日に何席するという。成程々々という理が治まる。今日は何する、道の理を諭す。道具に譬えて話す。要るものによって違う。道具を持って居てどうもならしょまい。さしづは台。取りようという、聞きようという。清書して、この理があったと言えば、一々届けにゃならん。めん/\ばかり道理治めるのは、仕難くうてならん。心の理を積み立てゝはどうもならん。年中に席の休む日は、何日あるか。何時でも勤めさしてある。席が無くては満足与えられようまい。余儀無く席が休まにゃならんようになる。
さあ/\こうして話し掛けたら胸に嵌まるで。めん/\合点行くまで尋ね返やし、一時でも、二時でも、神は退かんで/\。
『押して』
さあ/\尋ねる処の理が治まれば諭しよう。取次何人ある。日々楽しんでこそ取次取次。皆そも/\、一日休み、三日になり、鮮やかならん。苦しいからや。何人別席、やしき何人ある。役員の中、やしきの中で今日明日に上ぼって運ばりゃしょうまい。皆々の理ではありゃしょまい。昨日や今日、一つ運ばしょまい。同じ一つの理を以て通れば、同じようにせにゃならん。むさくろしい/\。
一寸話し分かり掛ける/\。取次一条の話、一寸話し分かり掛けた。取次同時同格同様、同格外れて同じ理とは言わさん/\/\。
『押して』
さあ/\分かったか/\。女と言うてならん。女は入れてない。今日から入りて勤まらん者は、同格とは言わん。同格同様の使いである/\。
『押して(女)』
さあ/\道理を以て話し掛けるから道理を諭す。満足という理を知らんか。日々嬉しい満足の理を知らんから、この理分からん。この理が分からねば、何名何人のうち、外れのようなもの。今日は余儀無くどうもならん。余儀無く勤まるか勤まらんか。満足という理分かりたか。分かりたら分かりたと言え。
さあもう一声々々、どういう理を話する。身上から事情尋ねる。こういうさしづあったとて、皆んなそれ/\の中から、何処にどういう理あるまいかも知れん。世界身上から寄せる。楽しみなか/\の理、たゞ一つの何でもなき者なら、尋ねただけの理を諭す。又一つ深き/\の諭する。楽しみ一つの理である、と、順序一つの理をさしづして置く。
「おさしづと婦人会」p43~46(本文1のみ)
明治31年10月26日 (4巻3124頁)
『桝井安松身上歯の痛み願』
(411)さあさあ、尋ねている事がどんなものであれ、尋ねなければ神の理はわからないであろう。前にも、「ようこそ尋ねたなあ」と諭したことがあった。(412)事情が治まれば、身上の方も治まってくる。(413)むかしの事情について理を諭し、(414)たとえ一日でも楽しませよう。(415)これ一つはいいとしても、あと、もう一つの事情がある。それについての悩みは容易ではなく、耐えられないと言うかもしれない。(416)ここでいう一つの事情、つまり、あと一つの事情というのは、子供の事情であって、それが次第に難しくなってきている。
(417)そして、それが内々の事に対する問題なのか、それとも、広く道の上の問題であるのかわからなくなってしまっている。だから、尋ねているのであろう。(418)ここで、それを理解り易いように諭そう。そうすれば、みな、内々のものと、道の上の事と両方にわたる神の理もわかってくるであろう。よく聞きわけるがよい。(419)ちょっと長い話をして伝えておく。(420)これまでの長い年限の間、それぞれがみな、神の理を聞きわけ、手を引かれるようにして、一歩々々と歩いて今日に至った道すがらを考えてみるがよい。
(421)婦人会に対する神の思いを明かし、婦人会をはじめかけたのも、その順序の道の一つである。(422)銘々が、これまでの道すがら一つをとって思案してみれば、一時はどうなるかと思ったこともあったであろう。(423)難渋な事情の中を神の理を見つめて、いさんで通ることは、さきざきの楽しみであり、(424)「身上苦しい中を、道を求めてこそ、楽々のご守護を頂ける」と言って、長い間、苦しみの中を通ってきた。(425)そうして、ずいぶん長い間、「まだよくならない。まだご守護頂けない」などと言って、身上苦しんで通り、(426)「もう、どうなるのか、わからない」と思案に余った日もある。(427)しかし、そうした中も、指図したところに基づいて、日々通ることにより、(428)「あとから思えば、楽々と身上つかわせてもらった」ということになるであろう。
(429)日々取り次ぎに出る中にも、(430)いろいろな事情が出てくる。(431)身上にかかることもある。(432)これまで指図したところに従い、(433)何名か定められている取り次ぎの者がいる中に、(434)こうした身上や事情をもっている者が何人いるかを、(435)きちんと取り調べて、そうすることによって、神の理の取り次ぎという理について、心に銘記することがなくてはならない。
(436)いったい、この道は、どういうことから成ったと思っているのか。(437)そもそも、男女の隔てはないのである。(438)この道は世界一れつ救けたいという神の思いを根本にして始めかけた道なのである。(439)それなのに、お前たちには、そのことが全くわかっていない。(440)この道を始めた教祖一代の間は、当然ながら、女である教祖が連れて通った道であるが、そのあとは、男である本席を通して教え導いた道が続いている。(441)そこに、男とか女とかの隔てがあるかないか、よく考えてみるがよい。(442)このような次第で、道が続いてきているところから思案すれば、(443)日々、取り次ぎをする者についても、決して、男女の隔てなどはない、ということがわかるであろう。
(444)しかし、今日明日に入るような者に対して、直ちに「どうしろ、こうしろ」と言って、させることはできないであろう。(445)自ずから、そのように成ってくるものでなければならないであろう。(446)無理に入ろうと思っても入ることができるものではないし、(447)また、入れようと思っても、入れることができるものではない。(448)しかし、そのことは、決して、隔てるという意味のものではない。(449)ものごとは、受けとり方、聞き方一つで、どのようにもなってしまうもので、(450)今の問題にしても、また、取りよう、聞きようで、わかりにくくなってしまうのである。
(451)こうして、神の指図を尋ねているお前たちが、「こうだ」と言いさえすれば、これで事が決まってしまう。(452)それに対して、他から誰も「こうだ」と言って反対する者はない。(453)だから、神が諭しているところを、しっかり聞きわけてもらいたい。(454)こうして諭している神の理に、まだ得心できないところがあるならば、くり返して尋ねるがよい。(455)「本当にそうだ」と得心し、お前たちが、自ら進んで神の理につくというのならば、みなの者が心を寄せてくれるようになるであろう。(456)入ってから長い年限の道を通ったというのならば、(457)日々、取り次ぎを進める中で、(458)こうしたところから相談していかなければならない。(459)相談すれば、時には、「こうするべきだ」などと言わなければならない。(460)しかし、銘々が進んで事を運ぶようにするならば、(461)それを「いかん」と言う者はないであろう。(462)いずれにしても、上に立つ者から下の立場にある者を育てるのでなければならない。(463)たとえ一日でも早く道に入ったならば、(464)その者は、育てるという心をもつようにならなければならない。そうでなければ、自らも神の理を聞き流し、思いちがいをしてしまうものである。(465)思いちがいをするようなことがあるならば、それを反省して、(466)何よりもまず、他を育てるようにしなければならない。(467)お前たちは、神の思いをまちがって受けとっていることが多い。それではならないのであって、(468)これからは、神が諭すところを、まちがいなく聞きとってくれなければならない。(469)上に立つ者が、寄り合って、しっかり聞きとってくれなければならない。
(以上)










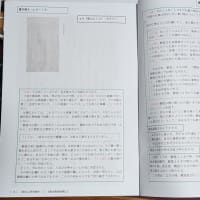















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます