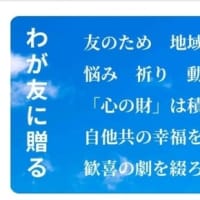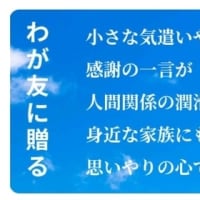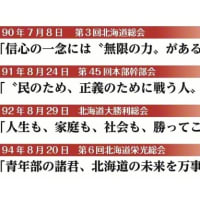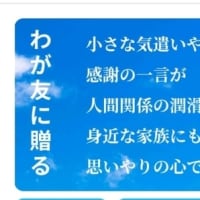[一年後]
「大変残念ですが、血腫が増大し始めています。
これまで良好に経過しておりましたので、このまま安定するかと思われたのですが…。
前回の手術で取り除くことができなかった場所ですので、再手術は難しいと思われます」
「それは、つまり…もう長くは生きられないということですか」
「残念ながらそういうことです。
後三年とお考えください。
もちろん今後も治療は継続していただかなくてはなりません。
われわれとしても最大限の努力をしてまいります」
手術前の記憶が戻っていないミニョンにとって、この宣告は青天の霹靂(へきれき)だった。
「死ぬのか、僕は…」
視力を失うのは時間の問題と自分でも覚悟を決め、その対策をできうる限り講じてきた。
しかし、手術後の回復は順調だったため「死」を考えたことはなかった。
職場復帰への具体的な準備をに取りかかろうとしていた矢先の出来事だった。
「後三年…ユジンさんとももう会えなくなるのか…」
ユジンの顔が浮かんだ。
ミニョンはいつしか真剣にユジンを愛している自分に気が付いていた。
今は、メールをやり取りするだけの間柄だったが、もうミニョンにとってかけがえのない人であった。
〈もし僕が死んだら…
ユジンさんは自分の責任と自分自身を攻めることだろう。
ユジンさんは一生の負い目を負ってしまうことになる。
僕はユジンさんに辛い思い出だけを残して去っていかなければならないのか…。〉
ミニョンは堪らなかった。
自分にできることはないのか?ユジンとの未来はもう望むべくもなかったが、悲しい思い出だけを残して逝きたくはなかった。
翌日、ミニョンは父親のイ氏に会い、主治医の話を伝えた。
イ氏は、予想されたこととはいえ、愛する息子に残された時間が少ないことを知ると、動揺を隠せなかった。
「そうか、ミニョン。そうだったか。…大丈夫か?」
「はい。いえ、正直とてもショックです。
でも…この事実が変えられないのなら、まだ後三年あると思って、…何とか最善を尽くしたいと思います」
イ氏は頷いていた。
「それで、お父さんにまたお願いがあります。
チョン・ユジンさんをぼくの仕事のパートナーとして迎えたいのです。
僕に時間があるのであれば他の人でもいいのです。
ゆっくりと僕の考え方、仕事のやり方を覚えてもらえばいいのですから。
彼女なら、僕のことをすでに分かってくれています。
僕の考え、やりたいことを打てば響くように分かってくれます。
彼女しかおりません。一緒にフランスへ行ってユジンさんを説得していただけますか?」
「そう考えていたのか。一緒にフランスへ行くことは、何とかしよう。
だが、そう決心したなら、お前に話しておかなければならないことがある。
失った記憶のことだ。残念ながら催眠療法は効果がなかった。
体への負担を考えて話すことを先生から止められていたのだが、お前とユジンさんは、取引先の理事と一建築デザイナーという間柄ではなかった。
二人は恋人同士だったんだ。
しかも二人が出会ったのは二年半前ではない。
十二年前の高校二年生の時、韓国の春川高校で出合っているのだ」
それから長い物語りとなった。
「私が知っているのはミヒやマルシアンのキム次長から聞いたことだ。
春川のお友達ならもっと詳しいことも知っているかもしれない。
いや、二人だけしか知らないことももっとたくさんあったのだと思う。
ともかく、ユジンさんはお前だけをもう十三年近くも待ち続けていることを分かってほしい。
その上でもう一度良く考えて…分かったね」
「…はい」
「今日は家に戻ってはどうかね。一緒に帰ろう」
イ氏はミニョンを一人にしておくのが気がかりであった。
「死」の宣告に加えユジンとの過去、いつかは話さなければならないことであったが、ミニョンのショックを考えると心が痛んだ。
ミヒは海外で留守であったが、せめてミニョンの好きな食事でも用意させようと思った。
「大変残念ですが、血腫が増大し始めています。
これまで良好に経過しておりましたので、このまま安定するかと思われたのですが…。
前回の手術で取り除くことができなかった場所ですので、再手術は難しいと思われます」
「それは、つまり…もう長くは生きられないということですか」
「残念ながらそういうことです。
後三年とお考えください。
もちろん今後も治療は継続していただかなくてはなりません。
われわれとしても最大限の努力をしてまいります」
手術前の記憶が戻っていないミニョンにとって、この宣告は青天の霹靂(へきれき)だった。
「死ぬのか、僕は…」
視力を失うのは時間の問題と自分でも覚悟を決め、その対策をできうる限り講じてきた。
しかし、手術後の回復は順調だったため「死」を考えたことはなかった。
職場復帰への具体的な準備をに取りかかろうとしていた矢先の出来事だった。
「後三年…ユジンさんとももう会えなくなるのか…」
ユジンの顔が浮かんだ。
ミニョンはいつしか真剣にユジンを愛している自分に気が付いていた。
今は、メールをやり取りするだけの間柄だったが、もうミニョンにとってかけがえのない人であった。
〈もし僕が死んだら…
ユジンさんは自分の責任と自分自身を攻めることだろう。
ユジンさんは一生の負い目を負ってしまうことになる。
僕はユジンさんに辛い思い出だけを残して去っていかなければならないのか…。〉
ミニョンは堪らなかった。
自分にできることはないのか?ユジンとの未来はもう望むべくもなかったが、悲しい思い出だけを残して逝きたくはなかった。
翌日、ミニョンは父親のイ氏に会い、主治医の話を伝えた。
イ氏は、予想されたこととはいえ、愛する息子に残された時間が少ないことを知ると、動揺を隠せなかった。
「そうか、ミニョン。そうだったか。…大丈夫か?」
「はい。いえ、正直とてもショックです。
でも…この事実が変えられないのなら、まだ後三年あると思って、…何とか最善を尽くしたいと思います」
イ氏は頷いていた。
「それで、お父さんにまたお願いがあります。
チョン・ユジンさんをぼくの仕事のパートナーとして迎えたいのです。
僕に時間があるのであれば他の人でもいいのです。
ゆっくりと僕の考え方、仕事のやり方を覚えてもらえばいいのですから。
彼女なら、僕のことをすでに分かってくれています。
僕の考え、やりたいことを打てば響くように分かってくれます。
彼女しかおりません。一緒にフランスへ行ってユジンさんを説得していただけますか?」
「そう考えていたのか。一緒にフランスへ行くことは、何とかしよう。
だが、そう決心したなら、お前に話しておかなければならないことがある。
失った記憶のことだ。残念ながら催眠療法は効果がなかった。
体への負担を考えて話すことを先生から止められていたのだが、お前とユジンさんは、取引先の理事と一建築デザイナーという間柄ではなかった。
二人は恋人同士だったんだ。
しかも二人が出会ったのは二年半前ではない。
十二年前の高校二年生の時、韓国の春川高校で出合っているのだ」
それから長い物語りとなった。
「私が知っているのはミヒやマルシアンのキム次長から聞いたことだ。
春川のお友達ならもっと詳しいことも知っているかもしれない。
いや、二人だけしか知らないことももっとたくさんあったのだと思う。
ともかく、ユジンさんはお前だけをもう十三年近くも待ち続けていることを分かってほしい。
その上でもう一度良く考えて…分かったね」
「…はい」
「今日は家に戻ってはどうかね。一緒に帰ろう」
イ氏はミニョンを一人にしておくのが気がかりであった。
「死」の宣告に加えユジンとの過去、いつかは話さなければならないことであったが、ミニョンのショックを考えると心が痛んだ。
ミヒは海外で留守であったが、せめてミニョンの好きな食事でも用意させようと思った。