地域よっては、刺激の統制のレベルが高く段ボールのビルディング状態の教室も多く見ます。
様々なセミナーで、自立課題に注目できないと、迷わず「周囲の人に影響を受けているので、パーテーションを入れる」という発言を聞きます。
もちろん刺激の統制は、課題そのものに注目する重要な支援です。
しかし、その自立課題の手立て、つまり視覚的構造化、またはそれを用いた教えるプロセスを検討することをまず考える必要があるのではと考えます。
まずは、本人が気づける状況づくりが重要と私は考えます(繰り返しますが、刺激の統制は重要な支援です。必要な刺激の統制は入れる必要があります)。
将来、様々な刺激や地域移行を目指すのであれば、ある必要以上に、また安易に刺激の統制をすることは問題があると考えます。
先日、佐賀のトレセミで周囲のスタッフより「刺激の統制」の必要性がトレーナーである私に伝わってきました(考えを伝えることは重要で、さすが佐賀と言う感じです)。しかしトレーナーとして佐賀の地で刺激の統制を安易に変えることを受講生に見せたくなかったので、視覚的構造化、ルーティンの工夫をしました。結果、2面の刺激の統制を変える必要がありませんでした。
ジョブコーチとしても、刺激に影響を受けやすい自閉症の方が、刺激の多い現場実習先で、ジョブマッチングと明確な仕事内容、明確な指示があることで、いつも以上に自立的だったことは何回も経験しています。
児童発達支援事業の中で、ある程度フラットな中でも、明確な境界とその他の構造化によって自立的に活動できています。
とにかく安易な刺激の統制は注意が必要というのが私の視点です。
【2012年度 自閉症支援に関する講演・ワークショップ等の予定】
【『フレームワークを活用した自閉症支援』のFacebookページができました】
【『フレームワークを活用した自閉症支援』を10倍活用する!(随時更新)】
【Amazonでの購入はこちら】
【スペース96での購入はこちらから】
いつもランキングにご協力ありがとうございます。1日も1クリックお願いしま す。
 にほんブログ村 にほんブログ村
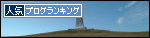 よろしければこちらもクリックお願いします よろしければこちらもクリックお願いします
| Trackback ( 0 )
|
|



