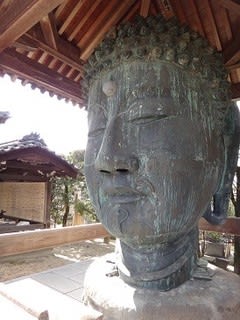事前に読んでいた資料では、
ここには一等三角点がある
と書かれてあったのですが、
どうも間違いのようですねえ。
その山頂付近にあったのは
「三等三角点」でした。
さて吉田神社はこの西側にあるのですが、
哲学の道とは反対側ですから、
今日は遠慮しておきましょう。
その先にある公園で、
トイレをすましたら、
目的の東の方へ下って
いくことにしましょう。
長い坂道を降りて下っていくと、
この下にあったのが
陽成天皇の陵墓です。
この天皇は先ほどの
後二条天皇よりももっと昔の天皇で、
9歳で天皇になりました。
そして8年間天皇だったのですが、
宮中の殺人事件などにより退位し、
その後なんと最多の80歳まで
上皇として過ごしたんだそうです。
65年の上皇生活は
さぞや長かったでしょうねえ。
今はここの陵墓に静かに
眠っているそうです。
その先にあるのが真如堂。
ここは紅葉がきれいだそうですが、
季節が違います。
お金を払って入ることはなく、
スルーしましょう。
こういう昔の道を通って行きますと、
右手に広い場所がありますよ。
ここが京都帝国大学医学部の
納骨墓地でした。
なんか医学部の墓地って
どうなんでしょうかあ。
考えてしまいますねえ。
じっとよく見ると横に立っている
卒塔婆に書かれていましたねえ。
京都大学解剖体、
と書かれています。
ああ、ここは献体の慰霊碑なんですね。
今の医学の根本部分を
支えているんでしょうねえ。
いわばいわゆるパワースポットなわけです。
そしてその先にあるのが
金戒光明寺の入り口です。
ここは閑静なお寺で、
時代劇のロケが行われるそうです。
そしてここは新撰組を支配下に置く
京都守護職の本陣ともなった寺院です。
地元ではくろ谷さん
と呼ばれて親しまれています。
おおきな「くろ谷」の石が
建っていますねえ。
そんな入り口だけ眺めて
コース歩きを進めていきましょう。
ここには親鸞聖人の
草庵跡がありますねえ。
そしてここが岡崎神社です。
まあ子授けの神様として
信仰されています。
境内にはウサギ関連の彫刻が多い、
例えば狛うさぎが置かれていますねえ。
そして手水鉢には多産のウサギの
置物もいます。
さらなる孫誕生のための
安産祈願もしておきましょうかね。
そうしているうちに、
道は白川通りと丸太町道理の交差点
「天王町」に出てきました。
このあたりから道はさらに
東向いて行き、哲学の道へと
続いていきます。
大豊神社への案内とともに
哲学の道への道標もありました。
ここから入っていきましょう。
大豊神社への鳥居をくぐると
案内のボランティアの
おじさんのいる橋のところに
出てきます。
この橋のかかっている水路が
琵琶湖疏水の分流ですね。
以前、琵琶湖のところから
インクラインのところへ
歩いてきましたね。
あの疏水がインクラインの
手前で分岐して南禅寺のあたりを
通りここへと流れてきているのですね。
そしてこの疏水のこの辺りから
下流へつながっている道が、
世間でいう「哲学の道」なのです。
京大教授の西田幾多郎が
哲学の思索に耽った散歩道
ということでこういう
名前がついています。
さらさらと流れる川の水の音、
木々の葉っぱをゆする季節の風、
自分の足音やはく息の音が
彼の脳みそをどんどん
刺激していったのでしょう。
75歳まで生きて最後に
尿毒症で亡くなったそうです。
ではそんな水路の横の道を
doironも思索深い顔をしながら
(わあ、絶対嘘や)
てくてくと歩いて
いくことにしましょう。
この日はさすがに観光客は
少なかったですね。
道を歩いていても50mに
一組ぐらいの感じで
すれ違ったりしていました。
川沿いに並ぶお土産屋さんも
全く静かな状態でしたね。
う~ん、doironの思索も
どんどん深まっていきます。
続く