
そもそも、ビタミンって何だっけ?
主要栄養素はご存知でしょう。そう、脂肪、たん白質、炭水化物です。では、微量栄養素は? 微量栄養素とは、少量で十分ながら、ないと身体が機能しなくなる栄養素です。
たとえばビタミンCがないとコラーゲンを作れず、皮膚の健康を保てなくなったり、歯が抜けたりします。ビタミンの多くにはアルファベットの名前(A、B、C、D、E、Kなど)が付けられていますが、B群にはさらに数字を付けて種類を区別しています。たとえばビタミンB1はチアミン、B9は葉酸です。
ビタミンは体内で作ることができない微量栄養素のため、どこかからとってこなければなりません。通常はそれが食事です。
ビタミンは有機分子であり、炭素とその他の原子がつながってできています。ミネラルも微量栄養素ですが、鉄、カルシウム、ナトリウムなどの周期表元素そのものである点がビタミンとは異なります。
よく売られている「マルチビタミン」には、ビタミンとミネラルが含まれています。
- ビタミンB6(ピリドキシン):米国人の約10%が不足しています。ビタミンB6不足は、全般的に食料を十分に食べられていない人(飢えや食事制限)とアルコール依存症の人に多いようです。ひよこ豆、マグロ、鶏肉、栄養強化シリアル(ほとんどのシリアルがそうです)など、多くの食べ物に含まれます。
- 鉄:鉄を失う主な理由は生理です。つまり、ほとんどの男性は対象外です。12歳から49歳の女性の9.5%が鉄不足です。1歳から5歳の子どもも成長にも十分な鉄が必要ですが、この年齢の子どものうち6.7%が不足しているそうです。
- ビタミンD:ビタミンDの場合、血中濃度が低いことがすなわち不足を意味するのかという議論があります。CDCによると、米国に住む非ヒスパニック系黒人のうち31%、メキシコ系米国人の12%、非ヒスパニック系白人の3%がビタミンD不足だそうです。
- ビタミンC:壊血病は少ないものの、6歳以上の米国人の約6%が、ビタミンC不足です。
これらに次いで一般的なのがビタミンB12、A、E、葉酸の不足ですが、いずれも人口の2%未満です。
問題があると思う人は、医師か栄養士にご相談を。答えがビタミン剤かどうかを問わず、ビタミンは食事からも摂取できることを覚えておいてください。それに、健康な食生活が必要な理由は、ほかにもたくさんあります。

トップ 3
大塚製薬 ネイチャーメイド スーパーマルチビタミン&ミネラル 120粒

ディアナチュラ ストロング39アミノ マルチビタミン&ミネラル 300粒

マルチビタミン ミネラル 酵素 360粒
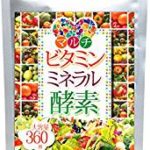
食事と成長
成長期の子供が順調に大きくなって行くために必要な3大要素、 「睡眠」「運動」「食事」
ここでは、「食事」および「栄養」にスポットをあてて考えてみましょう。

成長に必要な食事と栄養素
体がどんどん大きくなっていく成長期。その体づくりの元となる栄養は何よりも大切です。 元気な毎日を過ごすためにも、3度の食事をしっかり食べて、食べ物から栄養素を取り入れましょう。 平成24年度の文部科学省の調査によれば、小学6年生で9人に1人、中学3年生で6人に1人の割合で「朝食を食べないことがある」児童・生徒がいることがわかりました。
大人にも朝食を食べる派・食べない派がいますが、少なくとも成長期の子供にとっては朝の食事は大切です。 規則正しい生活を身につけるためにも、毎朝決まった時間に起きて朝食を取る習慣をつけたいもの。 寝ている間にもエネルギーは消費しますので、たくさんのエネルギーを必要とする成長期には朝食でエネルギーを補給するよう心がけましょう。
例えば、脳を働かせるブドウ糖は食後4時間で消費されてしまいますので、朝起きた時には脳のエネルギーは不足した状態になっています。朝食を食べる児童・生徒の方が食べない生徒より成績が良く、肥満も少ないという統計結果もあります。
成長期の子供にとって大切な3度の食事。食事で摂るべき重要な栄養素について、これから紹介したいと思います。 カルシウムにマグネシウム、たんぱく質、ビタミン、ミネラルとさまざまな栄養素をバランス良く摂取することが重要で、「これさえたくさん食べていれば大丈夫」というものではありません。
例えば、乳製品でカルシウムを、大豆製品でたんぱく質を、野菜や魚でビタミンやミネラルを…という具合に、さまざまな食材をまんべんなく食べることで、栄養素をバランス良く摂取し、すくすく育つ元気な体がつくられるのです。
骨の成長にはカルシウムだけじゃダメ?
成長期に必要な栄養素として、まず最初にあげられるのは骨の材料となるカルシウム。
しかし、カルシウムはあくまで「骨を丈夫にする」栄養素。「背が伸びる=骨を伸ばす」働きとは異なります。 また、カルシウムを吸収し骨に定着させるためにはマグネシウムが必要です。マグネシウムが不足していたり、カルシウムを過剰に摂取した場合、骨に留まらなかったカルシウムが血中に流れ出し、かえって健康を損なうことにもなります。
マグネシウムは、昆布やひじき、海苔などの海藻類や、ゴマやアーモンドなどのナッツ類に多く含まれています。 昔の日本人の食生活では、和食に使われる海藻などでマグネシウムが足りていた反面、乳製品を食べる習慣がなくカルシウムが不足していました。そのため、カルシウムを豊富に含んだ牛乳などが推奨されて来たのですが、食習慣の西洋化が進んだ現在、むしろマグネシウムの方が不足しがちになっています。
カルシウムとマグネシウムの理想的なバランスは2:1。マグネシウムは骨を強くするために必要なだけでなく、緊張をほぐすなど多くの働きがあります。育ちざかりの子供はもちろん、大人にとっても欠かせない大切な栄養素です。 また、乳製品にはカルシウムと共に脂肪分やリン酸が含まれています。
リン酸の過剰摂取により血中のリン濃度が上昇すると、カルシウムとのバランスが崩れ骨からカルシウムが血中に流れ出してしまうということも。 リン酸は乳製品などに含まれるだけなく食品添加物としても使われています。清涼飲料水やインスタント食品、スナック菓子などに含まれていますので、摂り過ぎには注意が必要です。

骨の成長とたんぱく質
「骨を丈夫にする」のがカルシウムだとすれば、「骨を伸ばす」栄養素となるのがたんぱく質です。筋肉や血液などを作るだけでなく、 「身長と成長期」 でも紹介した骨端軟骨で骨芽細胞が新しい骨を作り出すための材料としても、たんぱく質から作り出されるコラーゲンが使われているからです。
たんぱく質が豊富に含まれているのは肉や魚、大豆などの豆類。肉類にはたんぱく質も豊富に含まれていますが、一緒に含まれている飽和脂肪酸は摂り過ぎると肥満につながります。肥満も身長の伸びを阻害する原因のひとつとされていますので、魚や豆類と合わせてバランス良く摂ることが大切です。
また、たんぱく質の過剰な摂取はカルシウム不足の原因にもなります。 特に動物性のたんぱく質を摂り過ぎると血液が酸性に傾きます。体は血液を中性に保つためにカルシウムで中和しようとするため、カルシウムが血中に溶け出してしまうのです。
カルシウムとビタミンD
骨を強くし、伸ばすためにはカルシウムとマグネシウム、たんぱく質が重要ですが、それ以外にも、成長のためにはさまざまな栄養素が必要となります。 カルシウムを骨に定着させるためにマグネシウムは必須ですが、それに加えて、体に吸収しにくいカルシウムの吸収率を高めるのに重要な役割を果たすのが、ビタミンDです。
カルシウムと共に摂取されたビタミンDは、カルシウムの運び屋として血液中に取り込むように働きます。また、カルシウムが体外に排泄されるのを防いだり、骨端軟骨における骨代謝のバランスを整えてくれる働きもあります。 ビタミンDは青魚やきのこ類に多く含まれています。
魚はビタミンDだけでなく、たんぱく質も摂取できます。また、肉類の脂の多くが肥満への影響が心配な不飽和脂肪酸なのに対し、青魚は血中の善玉コレステロールを増やし悪玉コレステロールを減少させると言われる、オメガ3系の脂が中心です。 これらの脂には、脳や目に良いと言われるDHAや、血液の粘度を下げる作用があるとされるEPAなども含まれていますので、子供の食生活に積極的に取り入れたい食材です。
ビタミンDは、太陽の光を浴びることで体内でも作られます。 皮下脂肪にあるプロビタミンDという物質は紫外線にあたるとビタミンD3に変化しますので、日光の下での運動は子供の成長にも大切です。 夏場は過度の紫外線や熱中症などを心配する方も多いと思いますが、直射日光の当たらない日陰でもビタミンDの形成には十分ですので、暑さに気をつけながら外に出る機会をつくりましょう。
ビタミンB群とアミノ酸
ビタミンB群は、体に摂り込んだ栄養素をエネルギーに変えるための重要な役割を持っています。 その中で、たんぱく質がエネルギーとして使われるために需要な役目を果たすのがビタミンB6です。 体に摂り込まれたたんぱく質は、体内でアミノ酸に変わることでエネルギーとして使われます。アミノ酸にはさまざまな種類があり、それぞれに異なる働きを持っています。
ビタミンB6はたんぱく質をアミノ酸に分解したり、アミノ酸を別のアミノ酸へ組み換えたりする働きを助けるので、不足するとたんぱく質をエネルギーとして利用することができなくなります。 また、さまざまな種類のあるアミノ酸の中には、成長を助けると言われているものがあります。
その中でも有名なのがアルギニンです。食品からまとまった量を摂るのは難しい栄養素ですが、大豆や肉・魚などに含まれていますので、たんぱく質と一緒に摂取できます。 アルギニンは様々な作用を持つと言われています。
このアルギニンと強い関わりを持つのが、ウリ科の食品(特にスイカ)に含まれているシトルリンです。代表的なのものが尿素回路です。有害なアンモニアを排出するための回路で、アルギニン・シトルリン・オルニチンは互いに密接に関わっています。 シトルリンもアルギニンと同じく子供の成長にも良い影響を与えることが期待できます。
また、二日酔いに良いと有名になったオルニチンにも、アルギニンと一緒に摂ることで相乗効果があると言われています。 しじみに含まれていることで有名ですが、たんぱく質が豊富な食品にはほぼ含まれています。
日常生活で不足することはあまりありませんが、過剰摂取での害も報告がないため、成長期には積極的に摂りたい栄養素のひとつです。

成長期のための食事と栄養
これまでに上げたもの以外にも、成長期の体をつくるためにはたくさんの栄養素が必要になります。 カルシウムやたんぱく質だけでなく、それらが機能するための他の栄養素も一緒に摂ることが大切です。 そのためには、特定の食物に偏らず、いろいろな種類のものをバランス良く食べることが重要です。
とは言え、食事だけですべての栄養素をカバーするのは大変ですし、不足している栄養素を摂取しようとして、他の栄養素が過剰摂取になってしまっては逆効果。そんな時にはサプリメントなどを利用するのもひとつの方法です。しかし、サプリメントも特定の栄養素だけを抽出したものを使い続けると栄養が偏りがちに。同じ栄養素をうたっていても原材料や製造過程も異なるので、選ぶ際には品質も含めて十分注意してください。
















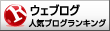












![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15c3bcaa.cb883178.15c3bcab.221dc914/?me_id=1261122&item_id=10674117&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2Fwb770%2F12770.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2Fwb770%2F12770.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


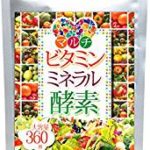

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18372115.61b3cc05.18372116.e546ead1/?me_id=1279984&item_id=10000977&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flavie-cosme%2Fcabinet%2Fmak%2Fmak29_p01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flavie-cosme%2Fcabinet%2Fmak%2Fmak29_p01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)







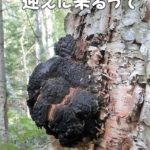
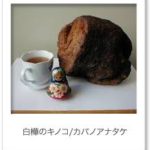 寒い地域で育ち、主な原産国はロシアである。日本では北海道で発見することができたが、
寒い地域で育ち、主な原産国はロシアである。日本では北海道で発見することができたが、





