中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法
親の言うことを聞かない理由
計算ミスが多かったので、お母さんが「やっぱり式を書きなさい。」と言ったとしましょう。
で、次の試験でもあるいは、授業のノートでも見てみると、相変わらず、式は書いていない。ちょこちょこと計算が書かれていて、そして間違っていたりする。
いや、そういうことは多々あるものです。
なぜ、言うことを聞かないのか?
(1)自分のやりたいようにやりたいから。
(2)面倒だから
まあ、そんなところでしょうか。
では、本人は良い点を取りたくないか?
いいえ、そんなことはありません。
じゃあ、言うことを聞いた方が良いのでは? これはお母さんの考えですね。
考えていることが合理的であったとしても、子ども本人がそれを合理的であると考えない限り、多分、実行されないのです。本人は「面倒ではなく、点数が上がる方法」の方を追い求めている。
そんな良い方法はない! とこれもまたお母さんの考えです。
本人は間違えずに、ちょこちょことやれればいいのだと思っているわけですから、これは水掛け論です。
式を書けば、当然、時間が取られる。もしかしたら、間に合わないかもしれない。だったら、ちょこちょこと計算をして間違えないようにすればいいのだ、と考えてもこれはおかしい話ではない。
以前に比べて、子どもが言うことを聞かないのは、親の言い方が高圧的に感じられることと、やはり自分の考えがあるからです。
だったら、どうすればいいか?
実験をしてみたらどうだろうか。
実際に式を書いたら間に合わないのか?
あるいはちょこちょこと計算するときに、間違わないように見直してみるのはどうか?
お互い、目的は「ミスをしないで良い点を取りたい」ということです。
ここは一致している、ということをまず確認しましょう。
「お母さんは僕をいじめてる」と思う子はいないと思うが、しかし、そんな印象を持っている可能性はないとは言えない。まず、目的はこれ、と確認する。
そして、何がいいかを実践してみる。
時間を計ってもいいし、過去問で試してみてもいい。
実際にやることによって、お互いに「これがベストだ」という道がわかればいいのです。
子どもは、もはや親の言うことを鵜呑みにする段階ではありません。
だとすれば、どう納得させればいいか。
実はここに智慧がいるのです。
しかし、多くの方は「不満に思ってストレスを感じる」ようになる。
ストレスを感じれば、子どもに対してイライラした態度が出るでしょうから、それはお互いまったく寄り合わない方向に進むでしょう。
そんな、面倒な、と思わないことです。
結果を出すためには、面倒なこともしなければならない。
これは実は、ごくごく当たり前のことです。
=============================================================
今日の田中貴.com
受験のつわもの
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
9月19日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================


にほんブログ村
で、次の試験でもあるいは、授業のノートでも見てみると、相変わらず、式は書いていない。ちょこちょこと計算が書かれていて、そして間違っていたりする。
いや、そういうことは多々あるものです。
なぜ、言うことを聞かないのか?
(1)自分のやりたいようにやりたいから。
(2)面倒だから
まあ、そんなところでしょうか。
では、本人は良い点を取りたくないか?
いいえ、そんなことはありません。
じゃあ、言うことを聞いた方が良いのでは? これはお母さんの考えですね。
考えていることが合理的であったとしても、子ども本人がそれを合理的であると考えない限り、多分、実行されないのです。本人は「面倒ではなく、点数が上がる方法」の方を追い求めている。
そんな良い方法はない! とこれもまたお母さんの考えです。
本人は間違えずに、ちょこちょことやれればいいのだと思っているわけですから、これは水掛け論です。
式を書けば、当然、時間が取られる。もしかしたら、間に合わないかもしれない。だったら、ちょこちょこと計算をして間違えないようにすればいいのだ、と考えてもこれはおかしい話ではない。
以前に比べて、子どもが言うことを聞かないのは、親の言い方が高圧的に感じられることと、やはり自分の考えがあるからです。
だったら、どうすればいいか?
実験をしてみたらどうだろうか。
実際に式を書いたら間に合わないのか?
あるいはちょこちょこと計算するときに、間違わないように見直してみるのはどうか?
お互い、目的は「ミスをしないで良い点を取りたい」ということです。
ここは一致している、ということをまず確認しましょう。
「お母さんは僕をいじめてる」と思う子はいないと思うが、しかし、そんな印象を持っている可能性はないとは言えない。まず、目的はこれ、と確認する。
そして、何がいいかを実践してみる。
時間を計ってもいいし、過去問で試してみてもいい。
実際にやることによって、お互いに「これがベストだ」という道がわかればいいのです。
子どもは、もはや親の言うことを鵜呑みにする段階ではありません。
だとすれば、どう納得させればいいか。
実はここに智慧がいるのです。
しかし、多くの方は「不満に思ってストレスを感じる」ようになる。
ストレスを感じれば、子どもに対してイライラした態度が出るでしょうから、それはお互いまったく寄り合わない方向に進むでしょう。
そんな、面倒な、と思わないことです。
結果を出すためには、面倒なこともしなければならない。
これは実は、ごくごく当たり前のことです。
=============================================================
今日の田中貴.com
受験のつわもの
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
9月19日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
数字が示すのは今の力
この時期は過去問の点数をつけたり、模擬試験の結果が出て、数字を突きつけられることが多くなります。
得点率が5割を切った、合格可能性は20%以下。
数字はウソはつきません。その通りだと思います。ただ、それは今の力を表しているに過ぎない。
過去問ができないのは、今、できない。
だからこれから練習していけばいい。知識を覚えていなければ、覚えていけばいい。
模擬試験ができないのは、今、できない。
しかし、入試の時はまだ半年も先なのです。ようやく暑さが和らいだが、入試の時は厳冬。この半年でいくらでも力が変わります。
ただ、子どもたちには経験がない。
そういう数字を突きつけられれば、「6か月先もそうだ」と思いがちになるもの。
それは違うのだ、ということを明確に教えてあげる必要はあるでしょう。
今の数字は、今の力を表す。
だから、何を半年で変えるのか。ここに集中しなければなりません。
そのために、個別に戦略が必要になる。一人一人の状況が違うし、目標が違うのだから、やり方もいろいろあるべきだし、またそうでないと効果がない。
そこをしっかり考えて、今の数字を変えていく。
その前向きな気持ちが非常に大事な時期です。
ぜひしっかり応援してあげてください。
==========================================================
今日の田中貴.com
第101回 試験期間中の子どもの力
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
国語に手を抜かない
==============================================================
お知らせ
算数5年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
背伸び
2020年のオリンピックが東京に決まりましたが、その最後のプレゼンテーションにフェンシングの太田選手が登場しました。
オリンピック選手によるプレゼン枠は1人。しかし、ここに太田選手は立候補したのだそうです。
「英語はダメでも、五輪招致プレゼンターは太田に」なった理由
「オリンピック招致にかかわり始めて、アスリートとしてアンバサダーの一人に選ばれたのは13年1月からなんですが、どうしても9月7日の最終プレゼンターをやりたい、と強く思っていたんです。選手としてはたった一人の席です。日本に、東京に、オリンピックを誘致したい、絶対に勝ちたい。で、そのためには俺がプレゼンをしなければ、と。」
なぜ、自分がしなければ、と思ったのかと言えば、やはり彼の競技がメジャーではないフェンシングであったことと無縁ではないようです。
彼は自分のプレゼンを将来を担う子どもたちの親御さんに見てもらいたいと言いました。
「子供にスポーツのチャンスを与えるのは親御さんですから。もし、僕がプレゼンを成功させて、結果として、東京オリンピック・パラリンピックが実現したとき、「うちの子を、あの太田っていうフェンシングの選手みたいに育てたいな」と思ってくれる親御さんが、一人でもいてくれたらいいなあ、と。というか、そう思っていただけるようなスピーチを、したいんです。その結果、スポーツに、フェンシングに興味をもってくださる親御さんがいて、その結果、次のアスリートが日本に誕生したら、こんなにうれしいことは、ないです。特にフェンシングのようなマイナースポーツの場合、一般の方々にアピールする機会はほとんどありません。このチャンス、逃すわけにはいかないです。」
「普通、子供たちが憧れるのは、メジャースポーツのヒーローです。テレビや実際の試合で直接目に触れる機会がいっぱいありますからね。サッカーの本田圭佑選手だったり、野球のイチロー選手だったりすると、世界レベルで注目が集まります。
ただ、大半の親御さんはどう思っているかというと、我が子に対して、世界で活躍して高い年俸を得るスーパーヒーローになってほしい、っていう方は少数派じゃないでしょうか。スポーツを通じて、我が子が健やかに元気に育ってほしい、って親御さんが大半だと思うんですよね。
そんな親御さんの中で、ひとりでもいいから、「あの太田がやってるのがフェンシングか。うちの子も、フェンシング、やらせてみようかな」って思ってくださる方が増えるといいなあというのが本心です。」
しかし、その一人の枠に入るのは並大抵ではない。英語ができる選手はいくらもいるが、実は太田選手は英語はあまり上手ではない。
そこで、必死に覚えた。しかもプレゼンの練習を相当したそうです。
他の選手がどれだけしたのかはわかりませんが、太田選手がこれだけしっかりとした動機を持っていたとしたら、それは相当強い。実際、プレゼンのコンサルも太田選手を選んだわけです。
「あいつが、一番練習してる。」
英語があまり得意でないにも関わらず、自分がオリンピック誘致のプレゼンをする。これはなかなかの背伸びです。
しかし、太田選手は常に自分に対するハードルを上げてきました。だからこそ、オリンピックで並み居る強豪を相手に銀メダルがとれたわけですが、今回の誘致も相当気合が入っていた分、決まった時の涙は自然とあふれてきたのだと思います。
「苦手だから、やらなきゃいけない環境を無理矢理つくっているんです。要するに背伸びしないといけない状況を用意するんですね。」
行きたい学校あるならば、多少背伸びをしないと届かない、これもその通りかもしれません。
=============================================================
今日の田中貴.com
速さとグラフの問題
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
9月17日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================


にほんブログ村
オリンピック選手によるプレゼン枠は1人。しかし、ここに太田選手は立候補したのだそうです。
「英語はダメでも、五輪招致プレゼンターは太田に」なった理由
「オリンピック招致にかかわり始めて、アスリートとしてアンバサダーの一人に選ばれたのは13年1月からなんですが、どうしても9月7日の最終プレゼンターをやりたい、と強く思っていたんです。選手としてはたった一人の席です。日本に、東京に、オリンピックを誘致したい、絶対に勝ちたい。で、そのためには俺がプレゼンをしなければ、と。」
なぜ、自分がしなければ、と思ったのかと言えば、やはり彼の競技がメジャーではないフェンシングであったことと無縁ではないようです。
彼は自分のプレゼンを将来を担う子どもたちの親御さんに見てもらいたいと言いました。
「子供にスポーツのチャンスを与えるのは親御さんですから。もし、僕がプレゼンを成功させて、結果として、東京オリンピック・パラリンピックが実現したとき、「うちの子を、あの太田っていうフェンシングの選手みたいに育てたいな」と思ってくれる親御さんが、一人でもいてくれたらいいなあ、と。というか、そう思っていただけるようなスピーチを、したいんです。その結果、スポーツに、フェンシングに興味をもってくださる親御さんがいて、その結果、次のアスリートが日本に誕生したら、こんなにうれしいことは、ないです。特にフェンシングのようなマイナースポーツの場合、一般の方々にアピールする機会はほとんどありません。このチャンス、逃すわけにはいかないです。」
「普通、子供たちが憧れるのは、メジャースポーツのヒーローです。テレビや実際の試合で直接目に触れる機会がいっぱいありますからね。サッカーの本田圭佑選手だったり、野球のイチロー選手だったりすると、世界レベルで注目が集まります。
ただ、大半の親御さんはどう思っているかというと、我が子に対して、世界で活躍して高い年俸を得るスーパーヒーローになってほしい、っていう方は少数派じゃないでしょうか。スポーツを通じて、我が子が健やかに元気に育ってほしい、って親御さんが大半だと思うんですよね。
そんな親御さんの中で、ひとりでもいいから、「あの太田がやってるのがフェンシングか。うちの子も、フェンシング、やらせてみようかな」って思ってくださる方が増えるといいなあというのが本心です。」
しかし、その一人の枠に入るのは並大抵ではない。英語ができる選手はいくらもいるが、実は太田選手は英語はあまり上手ではない。
そこで、必死に覚えた。しかもプレゼンの練習を相当したそうです。
他の選手がどれだけしたのかはわかりませんが、太田選手がこれだけしっかりとした動機を持っていたとしたら、それは相当強い。実際、プレゼンのコンサルも太田選手を選んだわけです。
「あいつが、一番練習してる。」
英語があまり得意でないにも関わらず、自分がオリンピック誘致のプレゼンをする。これはなかなかの背伸びです。
しかし、太田選手は常に自分に対するハードルを上げてきました。だからこそ、オリンピックで並み居る強豪を相手に銀メダルがとれたわけですが、今回の誘致も相当気合が入っていた分、決まった時の涙は自然とあふれてきたのだと思います。
「苦手だから、やらなきゃいけない環境を無理矢理つくっているんです。要するに背伸びしないといけない状況を用意するんですね。」
行きたい学校あるならば、多少背伸びをしないと届かない、これもその通りかもしれません。
=============================================================
今日の田中貴.com
速さとグラフの問題
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
9月17日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
マイペースな子
6年生は最高学年ですから、学校でのイベントも中心的な役割を負うことになります。
例えば運動会では応援団をやることもあるだろうし、連合運動会ではリレーの選手もやらないといけない。あるいは、学芸会で劇をやったり、音楽会の伴奏の練習をしなきゃいけなかったり。
受験生の親とすれば、当然、なるべく勉強時間を確保してほしいと思うものですが、そうはいかないものです。
その女の子は、ハキハキしているし、明るいし、明らかにクラスでリーダーシップをとるような子でした。
だから、いろいろ引き受ける。生徒会の委員長みたいなこともやっていたし、かと思うと、展覧会のプレゼンテーションの司会をやらないといけないとか、まあ、盛りだくさん。
当然、勉強する時間はなく、塾に時々、遅刻していました。
では、勉強はというと、まあ、そこそこやっている感じ。課題も見事とはいえないが、そこそこにはやっている。
「先生、来週の火曜日は休みます!」
「ほい、なんだっけ?」
「展覧会の作品が終わりません。」
「はい。了解。」
そんなの、早くやっちゃいなさい、とは言いません。この子は自分で何をしなければいけないかは、何となくわかっているのです。深く考えているかどうかは別ですが、それなりに考えて時間を使っている。
自分が受験することも、また行きたい学校もしっかりわかっている。それでも最後の小学校生活。それなりにしっかり過ごしたいと思っているのです。
そういうところはもう、信頼するしかない。
また、無理していろいろやらせても、結局勉強が手に付かなかったり、集中できなかったりするくらいなら、その子の考える通りにやらせる、というのが結果としては良かったように思います。
追い込みの時期に入って、
「やっぱり、ぎりぎりかしらねえ。」
と自分で言っていましたが、最後、帳尻を合わせたのはさすがでした。
6年生ですから、そろそろ自分でもいろいろ考えられる子は多いもの。
いつまでも子どもだと思っていない方が良いように思います。
==========================================================
今日の田中貴.com
オープンキャンパス
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
中等部の体育館
==============================================================
お知らせ
算数5年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

==============================================================


にほんブログ村
例えば運動会では応援団をやることもあるだろうし、連合運動会ではリレーの選手もやらないといけない。あるいは、学芸会で劇をやったり、音楽会の伴奏の練習をしなきゃいけなかったり。
受験生の親とすれば、当然、なるべく勉強時間を確保してほしいと思うものですが、そうはいかないものです。
その女の子は、ハキハキしているし、明るいし、明らかにクラスでリーダーシップをとるような子でした。
だから、いろいろ引き受ける。生徒会の委員長みたいなこともやっていたし、かと思うと、展覧会のプレゼンテーションの司会をやらないといけないとか、まあ、盛りだくさん。
当然、勉強する時間はなく、塾に時々、遅刻していました。
では、勉強はというと、まあ、そこそこやっている感じ。課題も見事とはいえないが、そこそこにはやっている。
「先生、来週の火曜日は休みます!」
「ほい、なんだっけ?」
「展覧会の作品が終わりません。」
「はい。了解。」
そんなの、早くやっちゃいなさい、とは言いません。この子は自分で何をしなければいけないかは、何となくわかっているのです。深く考えているかどうかは別ですが、それなりに考えて時間を使っている。
自分が受験することも、また行きたい学校もしっかりわかっている。それでも最後の小学校生活。それなりにしっかり過ごしたいと思っているのです。
そういうところはもう、信頼するしかない。
また、無理していろいろやらせても、結局勉強が手に付かなかったり、集中できなかったりするくらいなら、その子の考える通りにやらせる、というのが結果としては良かったように思います。
追い込みの時期に入って、
「やっぱり、ぎりぎりかしらねえ。」
と自分で言っていましたが、最後、帳尻を合わせたのはさすがでした。
6年生ですから、そろそろ自分でもいろいろ考えられる子は多いもの。
いつまでも子どもだと思っていない方が良いように思います。
==========================================================
今日の田中貴.com
オープンキャンパス
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
中等部の体育館
==============================================================
お知らせ
算数5年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
社会のシラバス
最後は社会です。
31回になりましたが、まあ、こんなものかなあと思います。
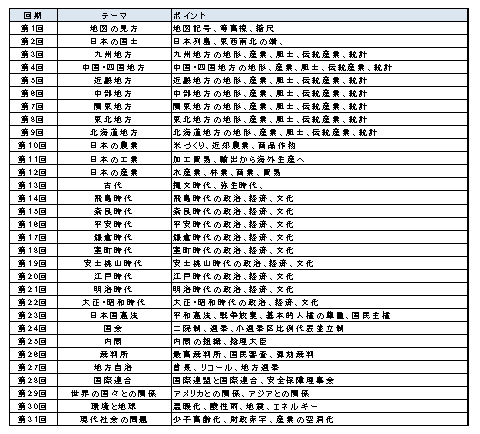
拡大版(PDF)
社会の出題は地理、歴史、公民の3分野になります。地理、歴史とも日本に限ることになっていますが、現代社会の問題ということで、世界の地理や歴史の問題が出ることもたまにあります。
で、これも理科と似ているところがあるのですが、日本という国がわかってから、歴史や公民を学ぶべきだということで、塾で勉強すると地理の時間が長い。
歴史は5年生後半、公民は5年生後半から6年生前半にかけて、というカリキュラムになっているところが多いでしょう。
これはある意味妥当な話であって、自分の国がどんな国か、まず地理的に知ることから始まって、そこを基礎に今度は歴史を勉強する。
例えば鎌倉時代、って鎌倉ってどこ? 奈良時代の奈良ってどこ?ということがわかっていないと勉強にならないところがあるわけです。
その分地理を学ぶ時間は結構長いが、これは理科の生物と地学と同じようなところがあります。つまり、ある程度全体のカリキュラム進行を合わせる。
実は一番多いのは、4回ご覧いただいてわかるように算数です。
算数が勉強することが多いので、その回期に合わせるように他の教科のカリキュラムを作る。結果として理科は生物・地学、社会は地理が長い、ということになるわけです。
じゃあ、歴史を早めればいいじゃないか、という議論もありそうですが、やはり知識分野なので、早く勉強しても忘れてしまう。
まあ、適度に試験間近という感じで考えれば歴史を5年後半、公民をその後、という流れは悪い時期ではないように思います。
4回にわたってお話してきましたが、すべて基本の内容であって、ここから学校別対策や入試問題演習があるので、このカリキュラム+半年の演習、というのが最短でしょうか。
これが最近3年になっているのが、冗長であるように思えるのです。
1年半は大変でも2年で充分行けるのではないだろうか。
以前の子どもたちは2年でやりあげていたし、それは今の子どもたちにも十分できるはずです。
しかし、そうなっていないのは塾がそうしているだけだ、ということなのですが。
=============================================================
今日の田中貴.com
平面図形と比(1)
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
9月15日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
理科のシラバス
さて、今回は理科です。
これはやりすぎかなあ、と思うものの24回になってしまいました。
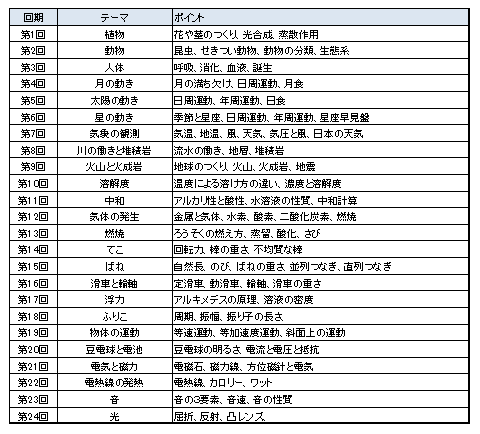
拡大版(PDF)
理科の出題は4分野に分かれます。
生物、地学、化学、物理。
で、化学、物理は計算の問題が含まれるわけで、それは少なくとも割合、比が自在にできるようになってからでないと難しい。したがって、どうしても算数の進み具合に左右されます。
最近は、割合や比を5年生の中盤で勉強するようになったので、その分多少前倒しが可能ではありますが、それでも自在に使える、ということになるとやはり練習は必要になります。したがってどうしてもこの2分野を勉強するのが遅くなる。
となると、前半はどうしても生物、地学になるわけで、それを思いきり膨らますことになります。
だからといって、入試に出るレベルに限るわけですが、4年生から5年生の前半の理科はそういう単元が繰り返されることになる。
それではおもしろくないから、一応化学や物理の範囲も少しやるのだけれど、本質には迫れないので、電気なんかは何となくわかったような気になるが、実はそれが後々、計算問題をやっていて邪魔になることもあるわけです。
で、生物、地学は知識範囲だから、それは最後に覚えたい。しかし、5年生後半からは物理、化学の勉強があるから、この辺がどうもうまくないところです。どうしても算数の範囲との兼ね合いがあるから、この順番は変えられない。
結果として前半の生物、地学偏重カリキュラムができあがるわけで、生物が嫌いな子はここで理科が嫌いになる、ということも起こることになります。
私は、前半は4教科ではなくてもいいのではないかと思います。昨日の国語でもお話しましたが、国語はかなり力をつけるのに時間がかかる。しかし、組み分けテストの前に漢字ぐらいしかやらない。他のことをやった方がテストの点数が取れるからですが、これは入試対策、として考えるとむしろ反対のことをやっている感じがします。
だったら、前半は算数と国語にしぼってみるのもひとつの手です。それで間に合うか。社会は若干苦しいが、理科はいけるかもしれません。
最後に、その理科を非常にコンパクトにまとめているテキストをご紹介しておきます。
これは予習シリーズの改編が行われるので、今年までになるから、手に入れておかれた方が良いと思います。本当に入試に必要なことをコンパクトにまとめています。
四谷大塚 予習シリーズ 6年下
予習シリーズのカリキュラムは、これまで6年上で全部終わるので、6年下はその総復習という意味ですべての範囲の大事なポイントを整理しています。
よくまとまっています。特に知識分野は秀逸と思います。
==========================================================
今日の田中貴.com
中和の問題
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
学則定員
==============================================================
お知らせ
算数5年後期第4回 算数オンライン塾「平面図形と比(2)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

==============================================================


にほんブログ村
これはやりすぎかなあ、と思うものの24回になってしまいました。
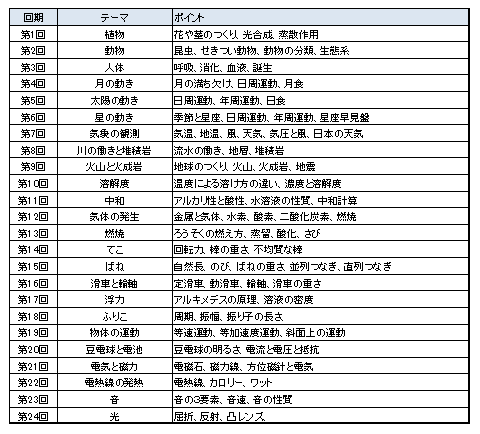
拡大版(PDF)
理科の出題は4分野に分かれます。
生物、地学、化学、物理。
で、化学、物理は計算の問題が含まれるわけで、それは少なくとも割合、比が自在にできるようになってからでないと難しい。したがって、どうしても算数の進み具合に左右されます。
最近は、割合や比を5年生の中盤で勉強するようになったので、その分多少前倒しが可能ではありますが、それでも自在に使える、ということになるとやはり練習は必要になります。したがってどうしてもこの2分野を勉強するのが遅くなる。
となると、前半はどうしても生物、地学になるわけで、それを思いきり膨らますことになります。
だからといって、入試に出るレベルに限るわけですが、4年生から5年生の前半の理科はそういう単元が繰り返されることになる。
それではおもしろくないから、一応化学や物理の範囲も少しやるのだけれど、本質には迫れないので、電気なんかは何となくわかったような気になるが、実はそれが後々、計算問題をやっていて邪魔になることもあるわけです。
で、生物、地学は知識範囲だから、それは最後に覚えたい。しかし、5年生後半からは物理、化学の勉強があるから、この辺がどうもうまくないところです。どうしても算数の範囲との兼ね合いがあるから、この順番は変えられない。
結果として前半の生物、地学偏重カリキュラムができあがるわけで、生物が嫌いな子はここで理科が嫌いになる、ということも起こることになります。
私は、前半は4教科ではなくてもいいのではないかと思います。昨日の国語でもお話しましたが、国語はかなり力をつけるのに時間がかかる。しかし、組み分けテストの前に漢字ぐらいしかやらない。他のことをやった方がテストの点数が取れるからですが、これは入試対策、として考えるとむしろ反対のことをやっている感じがします。
だったら、前半は算数と国語にしぼってみるのもひとつの手です。それで間に合うか。社会は若干苦しいが、理科はいけるかもしれません。
最後に、その理科を非常にコンパクトにまとめているテキストをご紹介しておきます。
これは予習シリーズの改編が行われるので、今年までになるから、手に入れておかれた方が良いと思います。本当に入試に必要なことをコンパクトにまとめています。
四谷大塚 予習シリーズ 6年下
予習シリーズのカリキュラムは、これまで6年上で全部終わるので、6年下はその総復習という意味ですべての範囲の大事なポイントを整理しています。
よくまとまっています。特に知識分野は秀逸と思います。
==========================================================
今日の田中貴.com
中和の問題
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
学則定員
==============================================================
お知らせ
算数5年後期第4回 算数オンライン塾「平面図形と比(2)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
国語のシラバス
国語のシラバスは実は大変難しいと思います。
入試問題を考えてみると、結局のところは物語文の読解と、説明文の読解。漢字、熟語の知識、ことわざ、慣用句。
それにこれは学校によってですが、詩、短歌、俳句、文学史ということになるでしょう。
結局のところで言えば、フィクションとノンフィクションの文章を読み解くことができるか、とういうことが中心になるので、それを最初から練習していく、ということになります。
しかしながら、小学校3年生ぐらいで読める文章はそう多くはない。
中心は小学生用の物語文になるわけで、そういう本を読み続けていく、というところから始まります。
で、それが次第に高度になっていき、ことばや熟語が増えて、少しずつ入試問題の文章に近づいていく。それまでは例えば子ども新聞の記事を読んだり、少し背伸びして大人の新聞を読んでみたり、ということも子どもたちの国語力を作る源になるでしょう。
そして、小学校5年生の後半ぐらいから、入試問題を解き始める、という練習になっていくわけです。
各塾のシラバスを見てみると、心情をつかむ、場面をつかむ、とか要旨をまとめる、などのテーマはあるものの、それぞれの年代に合わせた文章の読解を地道に続けていく、ということになっています。
国語というのは、一朝一夕に力がつくものではありません。
やはり長年日本語に親しみ、読み慣れて、書き慣れて国語力が形成されていくから、どこからスタートする、というスタートラインは明確ではありません。
どこかが最初かと聞かれれば、それは1年生かもしれないわけです。
だとすれば、中学受験の塾に行く行かないにかかわらず、国語の力は日々成長するものと考えられる。子どもが成長するにつれて使える語彙が増え、コミュニケーション能力がついて、いろいろな概念が理解できてくるようになるわけで、これをやったら、大丈夫というものではない部分があります。
逆に言えば、塾に行っていたとしてもそういう国語を鍛錬する場が少なければ、あまり力はついていかない、ということでもあるわけです。
小さいころから本を読み慣れるか、お父さん、お母さんとたくさん話をするか、そういうことがどうしても必要になるでしょう。
だから・・・
慌てて塾にいく必要はない、と思います。
まずは、ちゃんと本を読む習慣をつけるところからスタートするべきです。
夢中になって本を読んでいる、ということであるならば、ある意味何もしなくてもいいかもしれない、とすら思います。
入試問題の練習はその文章が読めなければできないわけだから、そこにたどり着くまでは漢字を覚えたり、本を読んだりすることを積み重ねていった方が早道なのです。
そして、充分に読めるようになったのであれば、それからは毎週2回、ぐらいのペースで問題を解いていく。学校の問題は難易に差があるから、まずはやさしいものからやっていき、やがて少しずつレベルを上げていけばいいでしょう。
塾では組み分けテストが行われますが、国語の対策はあまりしない。まあ、漢字や熟語を覚えるぐらいでしょうか。
つまり何か対策をしたところで、その子の読解力で勝負するしかないわけだから、逆にそれまでに地道に力をつけていけるかどうかに、かかっていると言えます。
だったら、家で低学年からしっかり本を読むことを習慣づけ、漢字を覚える、ということでいいのではないでしょうか。
受験対策は、入試問題の文章が読めるようになったら、しっかり過去問を読み解いていくことで力はついていくと思います。
=============================================================
今日の田中貴.com
私学の魅力
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
9月13日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年後期第4回 算数オンライン塾「平面図形と比(2)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================


にほんブログ村
入試問題を考えてみると、結局のところは物語文の読解と、説明文の読解。漢字、熟語の知識、ことわざ、慣用句。
それにこれは学校によってですが、詩、短歌、俳句、文学史ということになるでしょう。
結局のところで言えば、フィクションとノンフィクションの文章を読み解くことができるか、とういうことが中心になるので、それを最初から練習していく、ということになります。
しかしながら、小学校3年生ぐらいで読める文章はそう多くはない。
中心は小学生用の物語文になるわけで、そういう本を読み続けていく、というところから始まります。
で、それが次第に高度になっていき、ことばや熟語が増えて、少しずつ入試問題の文章に近づいていく。それまでは例えば子ども新聞の記事を読んだり、少し背伸びして大人の新聞を読んでみたり、ということも子どもたちの国語力を作る源になるでしょう。
そして、小学校5年生の後半ぐらいから、入試問題を解き始める、という練習になっていくわけです。
各塾のシラバスを見てみると、心情をつかむ、場面をつかむ、とか要旨をまとめる、などのテーマはあるものの、それぞれの年代に合わせた文章の読解を地道に続けていく、ということになっています。
国語というのは、一朝一夕に力がつくものではありません。
やはり長年日本語に親しみ、読み慣れて、書き慣れて国語力が形成されていくから、どこからスタートする、というスタートラインは明確ではありません。
どこかが最初かと聞かれれば、それは1年生かもしれないわけです。
だとすれば、中学受験の塾に行く行かないにかかわらず、国語の力は日々成長するものと考えられる。子どもが成長するにつれて使える語彙が増え、コミュニケーション能力がついて、いろいろな概念が理解できてくるようになるわけで、これをやったら、大丈夫というものではない部分があります。
逆に言えば、塾に行っていたとしてもそういう国語を鍛錬する場が少なければ、あまり力はついていかない、ということでもあるわけです。
小さいころから本を読み慣れるか、お父さん、お母さんとたくさん話をするか、そういうことがどうしても必要になるでしょう。
だから・・・
慌てて塾にいく必要はない、と思います。
まずは、ちゃんと本を読む習慣をつけるところからスタートするべきです。
夢中になって本を読んでいる、ということであるならば、ある意味何もしなくてもいいかもしれない、とすら思います。
入試問題の練習はその文章が読めなければできないわけだから、そこにたどり着くまでは漢字を覚えたり、本を読んだりすることを積み重ねていった方が早道なのです。
そして、充分に読めるようになったのであれば、それからは毎週2回、ぐらいのペースで問題を解いていく。学校の問題は難易に差があるから、まずはやさしいものからやっていき、やがて少しずつレベルを上げていけばいいでしょう。
塾では組み分けテストが行われますが、国語の対策はあまりしない。まあ、漢字や熟語を覚えるぐらいでしょうか。
つまり何か対策をしたところで、その子の読解力で勝負するしかないわけだから、逆にそれまでに地道に力をつけていけるかどうかに、かかっていると言えます。
だったら、家で低学年からしっかり本を読むことを習慣づけ、漢字を覚える、ということでいいのではないでしょうか。
受験対策は、入試問題の文章が読めるようになったら、しっかり過去問を読み解いていくことで力はついていくと思います。
=============================================================
今日の田中貴.com
私学の魅力
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
9月13日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年後期第4回 算数オンライン塾「平面図形と比(2)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
算数のシラバス
中学受験はいったい何を勉強すればいいのか、全体を俯瞰してみようと思います。
算数、国語、理科、社会にわけて全体を眺めてみましょう。
まず今回は算数です。
多少強引なところはあるが、40回でまとめてみると、こんな感じになるでしょうか。
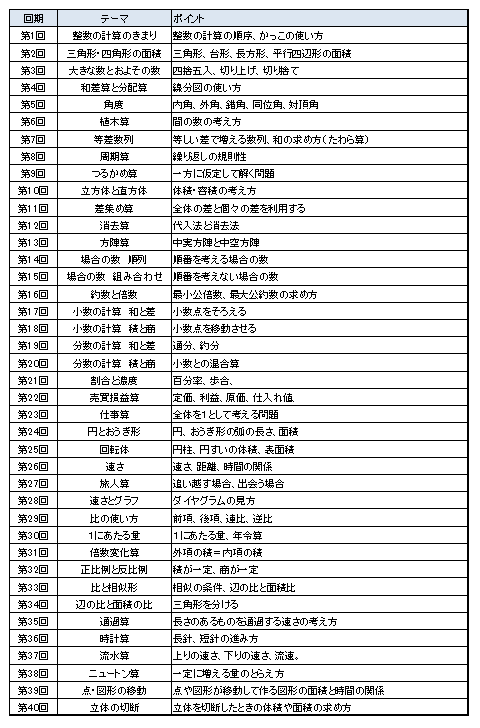
拡大版(PDF)
もちろん、これは基本的な内容の一覧であって、これを組み合わせた問題が入試ではでるわけですから、これに対する演習が当然必要になります。また過去問対策もあるから、当然40回の勉強で終わる、というものではありません。
ただ、全体としてこれだけのことを基礎として学べばいいので、例えば問題演習に6年生の夏休みから入るとすれば、5年生の最初からでも十分に間に合うし、がんばれば5年生の秋からでも十分やれる可能性はあります。
多くの塾はスパイラル式というカリキュラム方式を採用しています。ここでは場合の数は1回しか出てきませんが、そんな塾はまずない。
最低でも3回から4回はカリキュラムに登場するでしょう。これは、一度習っても忘れてしまうし、わかったことを使って応用問題を解くにはステップアップ的な学習が不可欠であるからです。
しかし、短期間に勉強するのであれば、逆に一気に進めばいいという考え方もあるので、ここでは1回しか登場させていません。
第1回~第15回までは、整数の範囲で勉強が進む部分です。
第16回以降は分数、小数が扱えないとできない。ここにひとつの壁ができます。
これが昔小5の壁と言われた部分で、今はいつの壁になったのか判然としませんが、分数や小数がうまく扱えないために、算数ができない、ということになりやすい。
学校のカリキュラムとはかけ離れていますから、当然そういう計算練習をしっかり積み重ねないといけないわけですが、それが充分でないから、壁になるわけです。
ここを乗り越えてくると、今度は比が始まり、多くの入試問題は比で解くことが多くなるので、比がある程度できるようになるとだいぶ楽になってきます。
で、塾のカリキュラムはもっと早くから、もっと細かく分けてあるので、遅くから始められるわけではない。けれども、子どもたちはそれぞれ成長のスピードがあります。
だれもがそんなに早くからできるかといえばそうではない部分もあるのです。
だったら、家庭の事情や子どものペースに合わせて勉強するというスタイルがあってもいいのではないでしょうか。
まずはこれだけはマスターしないといけないわけですが、それをどうマスターすればいいか、いろいろとアイデアがあって良いだろうと思います。
==========================================================
今日の田中貴.com
海外の私立校
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應湘南、生徒の居住地域
==============================================================
お知らせ
算数5年後期第4回 算数オンライン塾「平面図形と比(2)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

==============================================================


にほんブログ村
算数、国語、理科、社会にわけて全体を眺めてみましょう。
まず今回は算数です。
多少強引なところはあるが、40回でまとめてみると、こんな感じになるでしょうか。
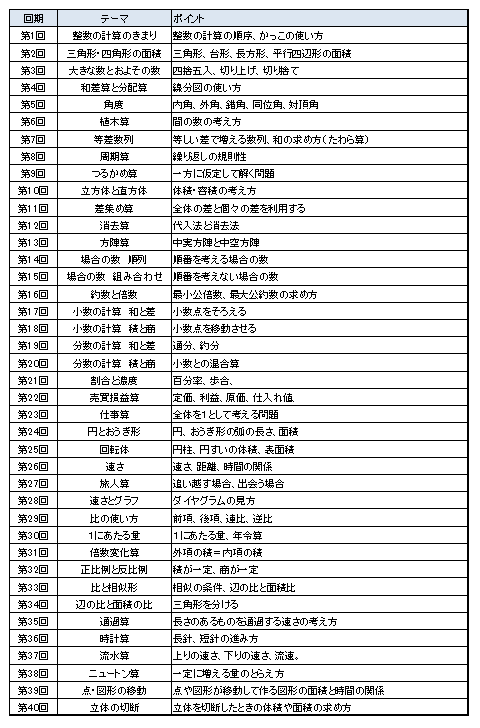
拡大版(PDF)
もちろん、これは基本的な内容の一覧であって、これを組み合わせた問題が入試ではでるわけですから、これに対する演習が当然必要になります。また過去問対策もあるから、当然40回の勉強で終わる、というものではありません。
ただ、全体としてこれだけのことを基礎として学べばいいので、例えば問題演習に6年生の夏休みから入るとすれば、5年生の最初からでも十分に間に合うし、がんばれば5年生の秋からでも十分やれる可能性はあります。
多くの塾はスパイラル式というカリキュラム方式を採用しています。ここでは場合の数は1回しか出てきませんが、そんな塾はまずない。
最低でも3回から4回はカリキュラムに登場するでしょう。これは、一度習っても忘れてしまうし、わかったことを使って応用問題を解くにはステップアップ的な学習が不可欠であるからです。
しかし、短期間に勉強するのであれば、逆に一気に進めばいいという考え方もあるので、ここでは1回しか登場させていません。
第1回~第15回までは、整数の範囲で勉強が進む部分です。
第16回以降は分数、小数が扱えないとできない。ここにひとつの壁ができます。
これが昔小5の壁と言われた部分で、今はいつの壁になったのか判然としませんが、分数や小数がうまく扱えないために、算数ができない、ということになりやすい。
学校のカリキュラムとはかけ離れていますから、当然そういう計算練習をしっかり積み重ねないといけないわけですが、それが充分でないから、壁になるわけです。
ここを乗り越えてくると、今度は比が始まり、多くの入試問題は比で解くことが多くなるので、比がある程度できるようになるとだいぶ楽になってきます。
で、塾のカリキュラムはもっと早くから、もっと細かく分けてあるので、遅くから始められるわけではない。けれども、子どもたちはそれぞれ成長のスピードがあります。
だれもがそんなに早くからできるかといえばそうではない部分もあるのです。
だったら、家庭の事情や子どものペースに合わせて勉強するというスタイルがあってもいいのではないでしょうか。
まずはこれだけはマスターしないといけないわけですが、それをどうマスターすればいいか、いろいろとアイデアがあって良いだろうと思います。
==========================================================
今日の田中貴.com
海外の私立校
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應湘南、生徒の居住地域
==============================================================
お知らせ
算数5年後期第4回 算数オンライン塾「平面図形と比(2)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
塾にたくさん行くと
塾に早くから週3日とか、行くようになると塾で勉強していればいい、とみんなが思い始めるところがあります。
夜遅くまでやっているんだから、家ではしなくてもいい、みたいな感覚がつい出やすい。
逆にあまり勉強していないと、じゃあ、もう少し塾を増やそうかしら、みたいな感覚も同じようなものかもしれません。
つまり外で勉強する機会が増えるごとに、「自分で勉強する機会が減少する」ということになります。
これを低学年からやってしまうのは、あまり良いことではないように思うのです。
塾では、情報を一方的に与えられる。
塾の授業はある意味効率を大事にするところがありますから、たくさんのことを教えてもらえる。
つまり、それは自分で調べる必要もないし、テキストを自分で読み込む必要もない。
聞いていれば、自動的に耳に入ってくる、という受動的なものです。
これに慣れすぎてしまうと、自分から調べたり、自分で考えたりする、ということが少なくなる。
しかし、入試問題はそうではない。
自分で考えたり、数え上げたり、作業をしたりしながら解いていくものだから、能動的な作業が必要なわけで、あまり受動的な機会を低学年のうちからたくさん与えてしまうのはプラスにはならないのです。
つい塾に出してしまえば、と思いがちですが、実はかえって逆効果になる場合もある。特に低学年の場合は、まずはじっくり自分で勉強できるようにすることが大事でしょう。
これは確かに最初は手間がかかるかもしれない。しかし、身について自分のものになってしまえば、自分でとっとと勉強してくれるわけだから、こんなにスムースなことはないのです。
まずはそういう時間を低学年のうちにしっかり作っていくことが、受験負担の軽減につながると思います。
=============================================================
今日の田中貴.com
第100回 6年生の夏休みから塾に行く
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
9月11日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年後期第4回 算数オンライン塾「平面図形と比(2)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================


にほんブログ村
夜遅くまでやっているんだから、家ではしなくてもいい、みたいな感覚がつい出やすい。
逆にあまり勉強していないと、じゃあ、もう少し塾を増やそうかしら、みたいな感覚も同じようなものかもしれません。
つまり外で勉強する機会が増えるごとに、「自分で勉強する機会が減少する」ということになります。
これを低学年からやってしまうのは、あまり良いことではないように思うのです。
塾では、情報を一方的に与えられる。
塾の授業はある意味効率を大事にするところがありますから、たくさんのことを教えてもらえる。
つまり、それは自分で調べる必要もないし、テキストを自分で読み込む必要もない。
聞いていれば、自動的に耳に入ってくる、という受動的なものです。
これに慣れすぎてしまうと、自分から調べたり、自分で考えたりする、ということが少なくなる。
しかし、入試問題はそうではない。
自分で考えたり、数え上げたり、作業をしたりしながら解いていくものだから、能動的な作業が必要なわけで、あまり受動的な機会を低学年のうちからたくさん与えてしまうのはプラスにはならないのです。
つい塾に出してしまえば、と思いがちですが、実はかえって逆効果になる場合もある。特に低学年の場合は、まずはじっくり自分で勉強できるようにすることが大事でしょう。
これは確かに最初は手間がかかるかもしれない。しかし、身について自分のものになってしまえば、自分でとっとと勉強してくれるわけだから、こんなにスムースなことはないのです。
まずはそういう時間を低学年のうちにしっかり作っていくことが、受験負担の軽減につながると思います。
=============================================================
今日の田中貴.com
第100回 6年生の夏休みから塾に行く
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
9月11日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年後期第4回 算数オンライン塾「平面図形と比(2)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
いろいろな選択肢
先日、各進学校の資料を読んでいたら、進学先に海外の大学が出ている学校が結構ありました。
アメリカの大学が多いが、中国の大学などもあり、結構子どもたちの目がいろいろな方向に向き始めています。
また、公立高校がここのところ大学進学実績を伸ばし続けていて、その復権もだんだん明確になってきました。
ここ20年ぐらい、関東の1都3県では中学受験をしなければ上位の大学に行けない、みたいな風説がありましたが、そろそろそれも終わりに近づいています。
子どもたちの将来にはいろいろなチャンスがあります。
受験の機会も中学受験ばかりではなく、高校受験も大学受験もある。
また、その進学先も日本ばかりとは限らない。つまりいろいろな選択肢があり得るのです。
親としては、そういろいろなことを調べられるわけではないが、ただ「こうしなければいけない」とは考えなくても良いのです。
子どもの成長に合わせて、また子どもの志向に合わせて、やってくるチャンスを活かすことが大事。
そのために小学生の間は本来、もっといろいろなことにチャレンジした方が良いように思うのです。
例えば家族で旅行をして、いろいろなところを見るのも大事だし、理科実験や生物の観察、あるいは音楽や、美術に親しんでみるのもいいでしょう。
もちろんすべて経験できるわけではないが、それでも関心があることには時間を使うべきでしょう。その中から子どもたちの道筋はだんだん見えてくる。
これから子どもたちが出ていく世界は、どんどん広がるはずです。活躍の舞台は日本だけではないでしょうし、それこそいろいろな分野に子どもたちの力が発揮されるようになると思うのです。
その可能性を中学受験があるからといって、狭める必要はありません。
中学受験準備はお父さん、お母さんが力を貸してくれれば、もっと負担を軽減することができるはずです。
その分、いろいろな選択肢を考えられるようにしてあげていくべきではないかと思います。
==========================================================
今日の田中貴.com
立体を切断する問題
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
願書
==============================================================
お知らせ
算数5年後期第4回 算数オンライン塾「平面図形と比(2)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

==============================================================


にほんブログ村
アメリカの大学が多いが、中国の大学などもあり、結構子どもたちの目がいろいろな方向に向き始めています。
また、公立高校がここのところ大学進学実績を伸ばし続けていて、その復権もだんだん明確になってきました。
ここ20年ぐらい、関東の1都3県では中学受験をしなければ上位の大学に行けない、みたいな風説がありましたが、そろそろそれも終わりに近づいています。
子どもたちの将来にはいろいろなチャンスがあります。
受験の機会も中学受験ばかりではなく、高校受験も大学受験もある。
また、その進学先も日本ばかりとは限らない。つまりいろいろな選択肢があり得るのです。
親としては、そういろいろなことを調べられるわけではないが、ただ「こうしなければいけない」とは考えなくても良いのです。
子どもの成長に合わせて、また子どもの志向に合わせて、やってくるチャンスを活かすことが大事。
そのために小学生の間は本来、もっといろいろなことにチャレンジした方が良いように思うのです。
例えば家族で旅行をして、いろいろなところを見るのも大事だし、理科実験や生物の観察、あるいは音楽や、美術に親しんでみるのもいいでしょう。
もちろんすべて経験できるわけではないが、それでも関心があることには時間を使うべきでしょう。その中から子どもたちの道筋はだんだん見えてくる。
これから子どもたちが出ていく世界は、どんどん広がるはずです。活躍の舞台は日本だけではないでしょうし、それこそいろいろな分野に子どもたちの力が発揮されるようになると思うのです。
その可能性を中学受験があるからといって、狭める必要はありません。
中学受験準備はお父さん、お母さんが力を貸してくれれば、もっと負担を軽減することができるはずです。
その分、いろいろな選択肢を考えられるようにしてあげていくべきではないかと思います。
==========================================================
今日の田中貴.com
立体を切断する問題
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
願書
==============================================================
お知らせ
算数5年後期第4回 算数オンライン塾「平面図形と比(2)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================

==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




