童話村を出て、こんどは宮沢賢治記念館へと向かう。
雨がまた降り始めていた。駐車場も混んでいる。
駐車場の奥には「山猫軒」がある。いかにもという名前だがご安心を。捕って喰ったりはしません。
時間は午後の2時半。遅いけどすこし食べていきますか。
ここのお店は以前訪れた時にはいっぱいで入れなかった。お昼ピークをすぎていたのが幸いしたかも。20年越しでやっと入れた。
めいめい食事をすまして、賢治記念館へと向かう。けっこう遅い時間になりつつあった。
ここで僕はわがまま言って別行動取らせてもらうことにした。
近くに「花巻新渡戸記念館」がある。
僕は新渡戸稲造博士を「武士道」の著者としてしか知らない。
博士のご先祖・新渡戸一族の功績を紹介している記念館があるというので見てみたいと思った。
丘を下り、少しちいさな路地を抜けると、林に囲まれた静かなところに記念館はあった。もともと新渡戸氏の居館があったという。林の奥には氏神様もそのまま残っていた。
新渡戸氏は、鎌倉期からの武功もある一方で、時代の権力者とも上手く渡り合い続いてきた名家である。
本貫地は「下総国新渡戸駅」と言われているが、現在ではどこなのか判らなくなってしまった。次の本貫地として判っているのがここ、花巻の高松ということなんだろう。
新渡戸氏はこのあと十和田の方へ移り、幕末にかけて開拓事業に貢献する。
記念館では、歴代の新渡戸氏の書や武具を多く展示。ジオラマを使い、土木・治水事業へも造形の深かった一族の技量を紹介していた。
ひとつ知りかったことは、新渡戸氏の武技がどのようなものであったか、ということ。
古くから東北に伝わる古流や南部藩の御留流「諸賞(掌)流」について知りたかった。
残念ながら、「新陰流の目録」などの全国的なものしか書かれているものはなかった。あれこれ見るうちに時間切れ。残念。
しかし、風のきもちいい、いい場所だったな。
再び丘の上の宮沢賢治記念館を目指す。
もう4時。また雨が強くなってきた。閉館間際でエントランスにすべり込む。
エントランスには賢治の描いた絵(「日輪と山」拡大版)がお出迎え。この絵、好きです。
館内では賢治のセロが展示されている。これも20年ぶりのご対面だ。
館内からは胡四王山(なんか高麗人が入植したような地名)の豊かな自然が堪能できる。途中、デッキがあって、そこから沢のほうへ降りられる。降りてゆけば「イーハトーブ館」の方へ続いているのではないだろうか。しかし雨がすごい。ちょっとデッキに出る勇気はなかった。
一旦展示室を出て、ロビーでみんなと合流。さあ、今日のお宿へ行こうか。
なんか、雨ばっかりで残念だけど、これはこれで思い出深い旅かもね。暑さもやわらいでありがたいし。
雨がまた降り始めていた。駐車場も混んでいる。
駐車場の奥には「山猫軒」がある。いかにもという名前だがご安心を。捕って喰ったりはしません。
時間は午後の2時半。遅いけどすこし食べていきますか。
ここのお店は以前訪れた時にはいっぱいで入れなかった。お昼ピークをすぎていたのが幸いしたかも。20年越しでやっと入れた。
めいめい食事をすまして、賢治記念館へと向かう。けっこう遅い時間になりつつあった。
ここで僕はわがまま言って別行動取らせてもらうことにした。
近くに「花巻新渡戸記念館」がある。
僕は新渡戸稲造博士を「武士道」の著者としてしか知らない。
博士のご先祖・新渡戸一族の功績を紹介している記念館があるというので見てみたいと思った。
丘を下り、少しちいさな路地を抜けると、林に囲まれた静かなところに記念館はあった。もともと新渡戸氏の居館があったという。林の奥には氏神様もそのまま残っていた。
新渡戸氏は、鎌倉期からの武功もある一方で、時代の権力者とも上手く渡り合い続いてきた名家である。
本貫地は「下総国新渡戸駅」と言われているが、現在ではどこなのか判らなくなってしまった。次の本貫地として判っているのがここ、花巻の高松ということなんだろう。
新渡戸氏はこのあと十和田の方へ移り、幕末にかけて開拓事業に貢献する。
記念館では、歴代の新渡戸氏の書や武具を多く展示。ジオラマを使い、土木・治水事業へも造形の深かった一族の技量を紹介していた。
ひとつ知りかったことは、新渡戸氏の武技がどのようなものであったか、ということ。
古くから東北に伝わる古流や南部藩の御留流「諸賞(掌)流」について知りたかった。
残念ながら、「新陰流の目録」などの全国的なものしか書かれているものはなかった。あれこれ見るうちに時間切れ。残念。
しかし、風のきもちいい、いい場所だったな。
再び丘の上の宮沢賢治記念館を目指す。
もう4時。また雨が強くなってきた。閉館間際でエントランスにすべり込む。
エントランスには賢治の描いた絵(「日輪と山」拡大版)がお出迎え。この絵、好きです。
館内では賢治のセロが展示されている。これも20年ぶりのご対面だ。
館内からは胡四王山(なんか高麗人が入植したような地名)の豊かな自然が堪能できる。途中、デッキがあって、そこから沢のほうへ降りられる。降りてゆけば「イーハトーブ館」の方へ続いているのではないだろうか。しかし雨がすごい。ちょっとデッキに出る勇気はなかった。
一旦展示室を出て、ロビーでみんなと合流。さあ、今日のお宿へ行こうか。
なんか、雨ばっかりで残念だけど、これはこれで思い出深い旅かもね。暑さもやわらいでありがたいし。










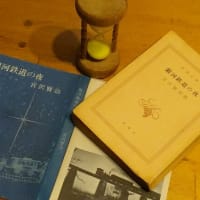














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます