今週は、この3冊。
ハリネズミの願い/東京湾岸畸人伝/ホテルローヤル/
■ハリネズミの願い/トーン・テレヘン/
『ハリネズミの願い』を読んでいて、英会話「チャロ2」の孤独な王、ラークを思い出してしまった。
ラーク (Lahk)
迷いの森の手前にある巨大な城の主。緑色の奇妙な外見をしており、赤いアーガイル柄のマントを羽織っている。
彼の城には現世に生きる人々の魂が夢を見に一時的にやってくるが、すぐに去ってしまうため、何千年もの間、友人もなくたったひとりで生きてきた。
人恋しさから、夢みる魂がずっととどまることができるスイートルームをつくり、チャロのかつての友人キャンディの魂を引き止めていた。
(リトル・チャロ2 - Wikipediより)
童話と言っても、その内容は難しく、読む人がなにを掴み、何を感じるかは、様々だと思います。
ぼくが、この童話を読み解く時、ヒントとしたのは次の部分です。
手紙を読んだハリネズミはフクロウの質問について考えるだろう。<存在>は大きいか小さいか・・・・・・。
おそらく小さいはずだ、とハリネズミは思った。あまりに小さくて、目に見えないかもしれない。それだ!だからそういうものを見ることがないんだ----<人生>も<幸福>も・・・・・・それはみんな、見るには小さすぎるんだ。だれもそれらを見ないのだから!
カメがためいきをついて聞いた。「よかったらぼくの甲羅の上に乗る?」
「キミの甲羅の上に?!」カタツムリはさけび、大きく目を見開いた。
「そうしたら先に進めるから」とカメは言った。
ハリネズミとリスは紅茶を飲み、ハチミツを舐め、ときどきうなずきあった。
午後が過ぎていくにつれ、リスもハリネズミも時間が止まればいいのに、と思った。あるいはカミキリムシがその日偶然、一秒を一時間に、一日を一年に変えればいいのに・・・・・・そして紅茶とハチミツがいつまでもなくならなければいいのに、と。
挿絵が魅力的で愛らしい。
見ていて飽きません。
ほのぼの心優しくなれます。
また会おうね!
『 ハリネズミの願い/トーン・テレヘン/長山さき訳/新潮社 』
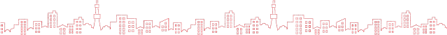
■東京湾岸畸人伝/山田清機
無名だけど凄い男たちの生き様
どんな畸人、変人に会えるのか楽しみです。
【築地のヒールより】
マグロを買うんじゃない、人を買うんだ。
死取(しーとー)になったら損を覚悟でやりを突く。
(『どうしてもそのマグロを落としたいという仲卸が二軒あれば、死取になる。』)
【横浜、最後の沖仲仕より】
明日行く場所が決まっているのは、安心でしたね。体を使って働いている者にとっては、一日の仕事の終わりにみんなでビールを飲むのが最高なんですよ
こうした風景を一変させたのが、1968年、横浜港に起こったコンテナ革命である。
掲載されている写真を見ながら、ぼくは、つぶやいていた。
彼らは、みんな何処へ消えたのか、一人ひとりの人生の行方。
助け合うんじなきゃ、協会なんていらないよ。困ったら助けっこしようってのが協会でしょう。ミナトはねぇ、ひとつの長屋なんです。GNO、義理と人情と恩返しの世界なんですよ
女房子供が困るようなことをしちゃいけないんだ。
そうやって人を切り捨てないと・・・・・・どうだというのか。
「その方がね、人間、生きていて、気持ちがいいんだよ」
酒井の親分は、いつも佐々木小次郎みたいに背中に日本刀を背負っていたもんだから、誰も文句を言えなかったんですね。
昔は、腰をぬかしそうになる人もいたのですね。
もう一つ、忘れられない言葉がありました。
人間が傲慢になるのは、金を使うときだ。
【木更津の「悪人」より】
たくさんの煩悩の中でもっとも厄介なのが自己顕示欲です。人によく思われたい、人に勝った、人に負けた……。いかにもつまらない葛藤だと思いますが、捨て去ることができません。
【久里浜病院のとっぽいひとより】
僕の理論ではね、男はちょっととっぽくないといけない。ただ単にいい人じゃなくて、この一線は譲れないって、意地を張る部分を持っていなくてはならない。それこそ、男っぽいなーって理論なんだ。
「楽しく会話をしながら飲む酒ほど、ステキなものはない」
「やっぱりさ、俺はよぅって、肩で風切る感じが、自分の中を流れいてほしいよね。言ってもわからないやつには、この野郎、テメエ、バカ野郎って、常に心の中で思っていることが大切だよな」
【羽田、夢見る老漁師より】
でもさ、羽田の漁師には残ってほしいじゃん。陸の畑は取っちゃえばお終いだけど、海の畑は湧いてくるんだ。当たるとすごいんだよ。もったいないよなぁ。海の畑にゃ夢があるんだよ
筆者の言われていることで、少々気になった部分がありました。
いかにも昭和という胡散臭い時代を象徴しているような気がする。
人様が、どんな時代認識を持たれようと自由だと思うのですが、ぼくは少なからず違和感を覚えました。
『 東京湾岸畸人伝/山田清機/朝日新聞出版 』
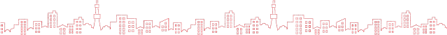
■ホテルローヤル/桜木紫乃
『裸の華』に続いて、桜木紫乃さんの2冊目、『ホテルローヤル』を読みました。
お釈迦様が、人間界の営みに眼を向けられて、ふっともらされるだろう微苦笑を感じました。
「先代にはとてもお世話になりました。こうしてご縁を続けさせていただくことになり、心から感謝しております。」
すっきりと乾ききった胸奥に、心地よい風が吹き始めた。そよそよと明日へ向かって吹く、九月の風だ。
信心も、心と財布に余裕のある人間がやることだ。
「俺さぁ、商売って夢がなくちゃいけないと思うわけよ。世の中男と女しかいないんだからさ、みんなやりたいこと同じだと思うのよ。夢のある場所を提供できる商売なら、俺もなにか夢がみられそうなんだ」
過去には、ラブホテルと岐阜県の人とのこんな話題もありました。
東京のラブホテル誕生 奥飛騨からのダム移転者の功績大きい
『 ホテルローヤル/桜木紫乃/集英社 』
ハリネズミの願い/東京湾岸畸人伝/ホテルローヤル/
■ハリネズミの願い/トーン・テレヘン/
『ハリネズミの願い』を読んでいて、英会話「チャロ2」の孤独な王、ラークを思い出してしまった。
ラーク (Lahk)
迷いの森の手前にある巨大な城の主。緑色の奇妙な外見をしており、赤いアーガイル柄のマントを羽織っている。
彼の城には現世に生きる人々の魂が夢を見に一時的にやってくるが、すぐに去ってしまうため、何千年もの間、友人もなくたったひとりで生きてきた。
人恋しさから、夢みる魂がずっととどまることができるスイートルームをつくり、チャロのかつての友人キャンディの魂を引き止めていた。
(リトル・チャロ2 - Wikipediより)
童話と言っても、その内容は難しく、読む人がなにを掴み、何を感じるかは、様々だと思います。
ぼくが、この童話を読み解く時、ヒントとしたのは次の部分です。
手紙を読んだハリネズミはフクロウの質問について考えるだろう。<存在>は大きいか小さいか・・・・・・。
おそらく小さいはずだ、とハリネズミは思った。あまりに小さくて、目に見えないかもしれない。それだ!だからそういうものを見ることがないんだ----<人生>も<幸福>も・・・・・・それはみんな、見るには小さすぎるんだ。だれもそれらを見ないのだから!
カメがためいきをついて聞いた。「よかったらぼくの甲羅の上に乗る?」
「キミの甲羅の上に?!」カタツムリはさけび、大きく目を見開いた。
「そうしたら先に進めるから」とカメは言った。
ハリネズミとリスは紅茶を飲み、ハチミツを舐め、ときどきうなずきあった。
午後が過ぎていくにつれ、リスもハリネズミも時間が止まればいいのに、と思った。あるいはカミキリムシがその日偶然、一秒を一時間に、一日を一年に変えればいいのに・・・・・・そして紅茶とハチミツがいつまでもなくならなければいいのに、と。
挿絵が魅力的で愛らしい。
見ていて飽きません。
ほのぼの心優しくなれます。
また会おうね!
『 ハリネズミの願い/トーン・テレヘン/長山さき訳/新潮社 』
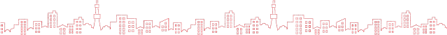
■東京湾岸畸人伝/山田清機
無名だけど凄い男たちの生き様
どんな畸人、変人に会えるのか楽しみです。
【築地のヒールより】
マグロを買うんじゃない、人を買うんだ。
死取(しーとー)になったら損を覚悟でやりを突く。
(『どうしてもそのマグロを落としたいという仲卸が二軒あれば、死取になる。』)
【横浜、最後の沖仲仕より】
明日行く場所が決まっているのは、安心でしたね。体を使って働いている者にとっては、一日の仕事の終わりにみんなでビールを飲むのが最高なんですよ
こうした風景を一変させたのが、1968年、横浜港に起こったコンテナ革命である。
掲載されている写真を見ながら、ぼくは、つぶやいていた。
彼らは、みんな何処へ消えたのか、一人ひとりの人生の行方。
助け合うんじなきゃ、協会なんていらないよ。困ったら助けっこしようってのが協会でしょう。ミナトはねぇ、ひとつの長屋なんです。GNO、義理と人情と恩返しの世界なんですよ
女房子供が困るようなことをしちゃいけないんだ。
そうやって人を切り捨てないと・・・・・・どうだというのか。
「その方がね、人間、生きていて、気持ちがいいんだよ」
酒井の親分は、いつも佐々木小次郎みたいに背中に日本刀を背負っていたもんだから、誰も文句を言えなかったんですね。
昔は、腰をぬかしそうになる人もいたのですね。
もう一つ、忘れられない言葉がありました。
人間が傲慢になるのは、金を使うときだ。
【木更津の「悪人」より】
たくさんの煩悩の中でもっとも厄介なのが自己顕示欲です。人によく思われたい、人に勝った、人に負けた……。いかにもつまらない葛藤だと思いますが、捨て去ることができません。
【久里浜病院のとっぽいひとより】
僕の理論ではね、男はちょっととっぽくないといけない。ただ単にいい人じゃなくて、この一線は譲れないって、意地を張る部分を持っていなくてはならない。それこそ、男っぽいなーって理論なんだ。
「楽しく会話をしながら飲む酒ほど、ステキなものはない」
「やっぱりさ、俺はよぅって、肩で風切る感じが、自分の中を流れいてほしいよね。言ってもわからないやつには、この野郎、テメエ、バカ野郎って、常に心の中で思っていることが大切だよな」
【羽田、夢見る老漁師より】
でもさ、羽田の漁師には残ってほしいじゃん。陸の畑は取っちゃえばお終いだけど、海の畑は湧いてくるんだ。当たるとすごいんだよ。もったいないよなぁ。海の畑にゃ夢があるんだよ
筆者の言われていることで、少々気になった部分がありました。
いかにも昭和という胡散臭い時代を象徴しているような気がする。
人様が、どんな時代認識を持たれようと自由だと思うのですが、ぼくは少なからず違和感を覚えました。
『 東京湾岸畸人伝/山田清機/朝日新聞出版 』
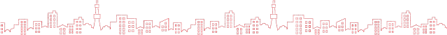
■ホテルローヤル/桜木紫乃
『裸の華』に続いて、桜木紫乃さんの2冊目、『ホテルローヤル』を読みました。
お釈迦様が、人間界の営みに眼を向けられて、ふっともらされるだろう微苦笑を感じました。
「先代にはとてもお世話になりました。こうしてご縁を続けさせていただくことになり、心から感謝しております。」
すっきりと乾ききった胸奥に、心地よい風が吹き始めた。そよそよと明日へ向かって吹く、九月の風だ。
信心も、心と財布に余裕のある人間がやることだ。
「俺さぁ、商売って夢がなくちゃいけないと思うわけよ。世の中男と女しかいないんだからさ、みんなやりたいこと同じだと思うのよ。夢のある場所を提供できる商売なら、俺もなにか夢がみられそうなんだ」
過去には、ラブホテルと岐阜県の人とのこんな話題もありました。
東京のラブホテル誕生 奥飛騨からのダム移転者の功績大きい
『 ホテルローヤル/桜木紫乃/集英社 』















