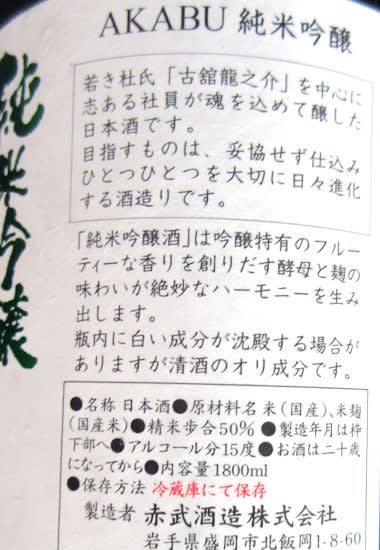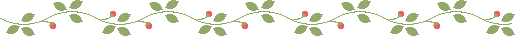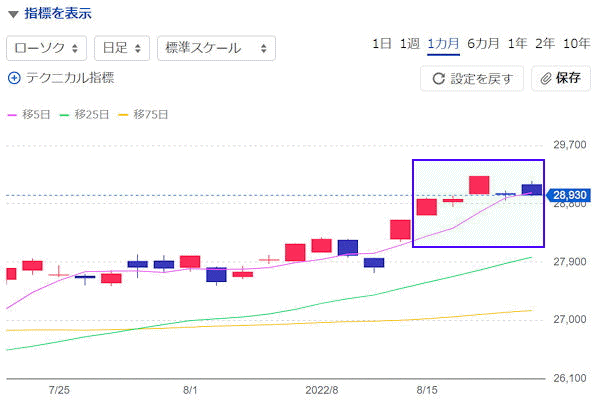■広重ぶるう 2022.8.29
梶よう子 『 広重ぶるう 』 を読みました。
ミステリ以外の小説は久しぶりです。
江戸の浮世絵師の世界がおもしろおかしく描かれています。
版元、浮世絵師、摺師、それぞれとの会話や情景がすぐ目の前で手に取るように展開します。
飽きずに最後まで楽しめました。
人は、生きていれば、いろいろ悲しいことも起こります。
涙を流し、涙が乾けば、また、明日を生きていかなければなりません。

物を手本として写真(しょううつし)をなし、これに筆意を加えて初めて画となる。
「還暦過ぎると、吉原よりも西方浄土が近くなるけどねぇ」と、件の隠居がぽろりとこぼす。
「なにを気弱な。男は死ぬまで男でなけりゃいけませや」
「おれは、喜三郎さんのおかげで朝から酒も飲めるし、豪勢な朝餉も食える」
「馬鹿をおいいじゃないよ」
「女房の粗末な形(なり)にも気づかず、亭主は朝湯に行って、いまは酒をたらふく呑んでいる。ああ、情けないにもほどがある。甲斐性なしの亭主を持つと、女房が苦労する」
「水をくれ。いややっぱり茶がいい。できたら酒でも」
重右衛門はくずおけるようにへたり込んだ。
「馬鹿いっちゃ困るよ、なにが酒だよ。おふざけも大概にしておくれ。あたしはこれから出掛けなきゃいけないんだがね。用事があるなら、さっさとおいい」
喜三郎は、重右衛門をじっと見つめ、舶来物の新しい色だ、といった。
「異国のいろ?」
「そう、ぷるしあんぶるう、という舌を噛みそうな色名だそうだよ。舶来の色だから、まだ値が張るそうだがねぇ。なんでも伯林ってところで作られた物らしい。けど、そんなんじゃ皆、いいづらいってんで、伯林の藍だから、ベロ藍っていっているやうだがね」
腰を伸ばすと背丈があり、肩の張った大男だった。まるで妖(あやかし)の見越(みご)し入道だ。
「おれぁな、てめえみてえな、青臭え奴を相手に画を描いているわけじゃねぇ。おれぁ、おれのために筆を執っているんだ。帰れ、このうすらとんかち」
歯をむき出し、噛みつくような顔をしていい放った。重右衛門は思わずあとじさりする。
「大丈夫ですかい? お顔も真っ黒だ」と、膝をついた頭が心配げに見やる。
「火傷は負ってねえよ。ただ、女房が渋い顔をするだけだ」
「どこでも女房ってのは怖えもんですな。こっちは命張って火に飛び込んでるってのに」
まったくだ、と声を上げて笑うと、頭もつられて笑い声を上げた。
不思議と江戸の町が明るく見えた。妻の加代の顔もこの頃この頃いっそう愛らしく見える。別にこれまでとて暗く沈んでいたわけではない。春夏秋冬、陽射しとてまったく変わらない。ああ、そうか。おれの心持ちが変わったのだ。これが売れるということか。世に出るということか。
「色重たぁ、いっそ潔い。色重ねぇ、はは、こいつはいい」
笑い続ける豊国を、重右衛門は複雑な顔で見つめた。
「そりゃあ、もちろん師匠の画が素晴らしいものだったからですよ。なんといいますかね、情趣がありつつも面白味もある。師匠のお人柄でしょうかね、画がどこか温かいですな。さらにいえば画中の人物がそこらにいる町人そのものだ。滑稽な顔つきも、のんびりした表情も、皆活き活きしている。見る者が画の中に入って旅をしているような気分なるのでしょうな。ええ、それはきっと間違いございません」
と、今度は重右衛門を持ち上げるようにいった。歯の浮くような世辞に尻のあたりがむずむずした。以前ならば、「褒めたって出るのは屁ぐらいのモンだ」と相手に雑言を浴びせたが、人間上り調子だと、おべんちゃらも真に聞こえるから不思議だ。
『 広重ぶるう/梶よう子/新潮社 』
梶よう子 『 広重ぶるう 』 を読みました。
ミステリ以外の小説は久しぶりです。
江戸の浮世絵師の世界がおもしろおかしく描かれています。
版元、浮世絵師、摺師、それぞれとの会話や情景がすぐ目の前で手に取るように展開します。
飽きずに最後まで楽しめました。
人は、生きていれば、いろいろ悲しいことも起こります。
涙を流し、涙が乾けば、また、明日を生きていかなければなりません。

物を手本として写真(しょううつし)をなし、これに筆意を加えて初めて画となる。
「還暦過ぎると、吉原よりも西方浄土が近くなるけどねぇ」と、件の隠居がぽろりとこぼす。
「なにを気弱な。男は死ぬまで男でなけりゃいけませや」
「おれは、喜三郎さんのおかげで朝から酒も飲めるし、豪勢な朝餉も食える」
「馬鹿をおいいじゃないよ」
「女房の粗末な形(なり)にも気づかず、亭主は朝湯に行って、いまは酒をたらふく呑んでいる。ああ、情けないにもほどがある。甲斐性なしの亭主を持つと、女房が苦労する」
「水をくれ。いややっぱり茶がいい。できたら酒でも」
重右衛門はくずおけるようにへたり込んだ。
「馬鹿いっちゃ困るよ、なにが酒だよ。おふざけも大概にしておくれ。あたしはこれから出掛けなきゃいけないんだがね。用事があるなら、さっさとおいい」
喜三郎は、重右衛門をじっと見つめ、舶来物の新しい色だ、といった。
「異国のいろ?」
「そう、ぷるしあんぶるう、という舌を噛みそうな色名だそうだよ。舶来の色だから、まだ値が張るそうだがねぇ。なんでも伯林ってところで作られた物らしい。けど、そんなんじゃ皆、いいづらいってんで、伯林の藍だから、ベロ藍っていっているやうだがね」
腰を伸ばすと背丈があり、肩の張った大男だった。まるで妖(あやかし)の見越(みご)し入道だ。
「おれぁな、てめえみてえな、青臭え奴を相手に画を描いているわけじゃねぇ。おれぁ、おれのために筆を執っているんだ。帰れ、このうすらとんかち」
歯をむき出し、噛みつくような顔をしていい放った。重右衛門は思わずあとじさりする。
「大丈夫ですかい? お顔も真っ黒だ」と、膝をついた頭が心配げに見やる。
「火傷は負ってねえよ。ただ、女房が渋い顔をするだけだ」
「どこでも女房ってのは怖えもんですな。こっちは命張って火に飛び込んでるってのに」
まったくだ、と声を上げて笑うと、頭もつられて笑い声を上げた。
不思議と江戸の町が明るく見えた。妻の加代の顔もこの頃この頃いっそう愛らしく見える。別にこれまでとて暗く沈んでいたわけではない。春夏秋冬、陽射しとてまったく変わらない。ああ、そうか。おれの心持ちが変わったのだ。これが売れるということか。世に出るということか。
「色重たぁ、いっそ潔い。色重ねぇ、はは、こいつはいい」
笑い続ける豊国を、重右衛門は複雑な顔で見つめた。
「そりゃあ、もちろん師匠の画が素晴らしいものだったからですよ。なんといいますかね、情趣がありつつも面白味もある。師匠のお人柄でしょうかね、画がどこか温かいですな。さらにいえば画中の人物がそこらにいる町人そのものだ。滑稽な顔つきも、のんびりした表情も、皆活き活きしている。見る者が画の中に入って旅をしているような気分なるのでしょうな。ええ、それはきっと間違いございません」
と、今度は重右衛門を持ち上げるようにいった。歯の浮くような世辞に尻のあたりがむずむずした。以前ならば、「褒めたって出るのは屁ぐらいのモンだ」と相手に雑言を浴びせたが、人間上り調子だと、おべんちゃらも真に聞こえるから不思議だ。
『 広重ぶるう/梶よう子/新潮社 』