多義詞の次は、同音詞ですが、これについては既に、8月5日に《同音語の形成理由と文章中での効用、及びその分別方法》で説明しているので、そちらを参照してください。今回は、多義詞と同音詞の共通点、及び相違点について、説明します。
同音詞と多義詞の境界
多義詞と同音詞は、何れも同一の語音形式を用いて異なる意味、内容を表す言語現象であり、これらは性質上、一定の共通点があるが、一方、相互間には大きな違いもある。
これはつまり、多義詞が指すのは一つの詞が異なる意味を備えているということに対し、同音詞はいくつかの詞が同じ語音形式を備えているということである。したがって、多義詞のいくつかの意味の間には明確な、必然としてのつながりがある。それらは何れも、一つの基本意義から派生したもので、共同の基礎がある。一方、同音詞はそうではなく、それら相互の間には、語音形式は同じであるが、意味の上のつながりが欠けており、共同の基礎が欠けている。
例えば、“打人”、“打水”、“打井”、“打草鞋”といった言語構造の中の“打”は、そのいくつかは異なる意味を表すが、これらの意味の間にはつながりがあり、これらは皆、“打撃”という基本意義から派生したもので、したがって、多義詞である。
一方、“打今儿起”という構造の中の“打”は、上で挙げた打とは、語音形式上は同じだが、意味の上ではつながりが無く、これらは一つの詞ではなく、二つの同音詞である。
もちろん、これら二つの言語現象は全くつながりがないという訳ではない。これらは皆、同じ音で異なる意味を表しており、言語の歴史発展の過程で、これら相互間で転化が起こった可能性がある。然るに前述のように、いくつかの同音詞は、多義詞の解体の結果生まれたものである。多義詞がより一層発展すると、しばしば同音詞が生み出される。したがって、歴史的な観点から、これら二つの現象を見なければならない。
また、以上で述べた同音詞は、何れも音声形式で類似しているが、内容や意味は全く似ておらず、つながりがなく、これは純粋な同音詞である。
中国語の語彙の中で、もうひとつ、音声形式が類似し、同時に語句の意味の上でも類似し、互いにつながりのある詞があり、このような「音が似て意味も相通じる」詞のことを、言語学では“同源詞”と呼ぶ。なぜなら、それら相互の間には同源関係があると思われるからである。すなわち、同一の語源(関連する意味を代表する語素)から派生したものと考えられる。例えば:
空―孔 框―筺 糠―殻 広―曠
寛―闊 挟―夾 満―漫 朦―盲
溟―濛―茫 合―盍―闔
これらの詞や語素は、現代漢語の中で互いに発音が類似しており、類似したり関連する意味を表すのに用いられることから、これら相互間には同源関係があることが証明できる。こうした現象は、中国語の語彙の発展の歴史において研究を加えなければならないものであり、現在の同音詞の種類を述べる時にも、分析を加えなければならない。
【出典】胡裕樹主編《現代漢語》重訂版・上海教育出版社1995年
民国以降の白話運動に始まる中国語の近代化の動きから、現代漢語が体系として形成される歴史の中で、複雑化する社会での情報伝達の必要から、語彙は益々質量共に豊かになっていきます。正にそういう環境の中で多義詞、同音詞というものが生まれてきた、ということが言えると思います。
にほんブログ村














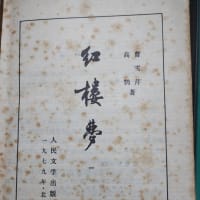











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます