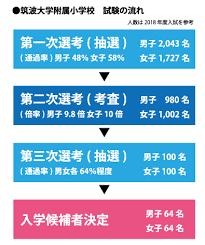泉房穂「東大は『過去問主義』やわ。前例主義」 東大出身の著名人20人が体験した「真の東大」

泉房穂「東大は『過去問主義』やわ。前例主義」 東大出身の著名人20人が体験した「真の東大」
泉房穂「東大は『過去問主義』やわ。前例主義」 東大出身の著名人20人が体験した「真の東大」
東大というと、各高校からの合格者数ばかりが注目されがちだが、どのように受験に挑み、東大で学び、将来につながったのか、実際の話も知りたいところ。そんな期待に応える一冊が出た。AERA 2025年3月17日号より。
* * *
東大卒を隠して生きてきた大宮エリーさんが、東大出身の著名人20人と語り合った新刊『大宮エリーの東大ふたり同窓会』。東大を選んだ動機や合格法、大学時代に過ごした時間が人生をどのように形づくっていったのかをまとめて読むと、真の東大の姿が浮かび上がってくる。
「東大に入って、こんなにもレールに乗ってきた人がいる場所なのかって驚きました」と語ったのは、僧侶の松本紹圭さん(2003年、文学部哲学科卒)。北海道小樽市の漁村の出身。塾にもいかず、独学で現役合格した。高1のときに赤本を買ってきて、「3年後にこれを解けるようになる」ことを目標に“合格までの千日間のプラン”を立て、合格をつかみとった。「道は作ればいいんだって手ごたえを得られたのが東大受験の一番の収穫」と松本さん。自ら道を切り開くように、継ぐ寺もないのに“お坊さん”になり、インドにMBA(経営学修士)留学し、仏教界の構造改革を進めている。
■ギャフンと言わせたい
前兵庫県明石市長の泉房穂さん(1987年、教育学部卒)も漁村の出身。塾も行かず、過去問も買ってもらえず独学で入学した。「入ってみたら(親の年収が)1千万、2千万円選手のお嬢さんとお坊ちゃんたちばかり」「私の分析では東大は『過去問主義』やわ。前例主義。過去問がないと動けなくなってしまう」と語った。
タレントの高田万由子さん(94年、文学部卒)も独学で東大合格をつかんだ一人。学校の先生に、東大は「無理よ」と言われて「ギャフンと言わせたい」と思ったのが高3の10月。そこから夜9時から12時までは電話も出ず、トイレにもいかず勉強だけに打ち込んだ。
試験を作る教員と受験生をつなぐものは「教科書」だからと、ひたすら教科書を読み、「過去問の分析がカギを握る」と解説文を読みこんだ戦略が奏功した。
泉房穂「東大は『過去問主義』やわ。前例主義」 東大出身の著名人20人が体験した「真の東大」
受験で得た「段取り力」
「東大受験で得たのは段取り力だと思うんです。自分が目指すゴールから逆算して今の自分との距離を縮めていく。東大受験を自力で乗り越えたことが、その後の人生に役立っていると思います」(高田さん)

一方、「いつの間にかレールに」と振り返るのは元首相の鳩山由紀夫さん(69年、工学部卒)。鳩山家は5代連続で東大進学。小中は学習院に通ったが、高校は都立小石川高校に。東大合格者数でトップを走る開成高校出身のゲストは、クイズプレーヤーの伊沢拓司さん(2017年、経済学部卒)と角野隼斗さん(20年、大学院情報理工学系研究科を修了)。「開成から東大を目指すのはそんなに珍しいことではなかった」(角野さん)という。伊沢さんは「学校に行くだけでいい塾の先生とか、いい教材とかの情報が入ってきた」と言い、対談では予備校や講師の具体名を挙げて紹介している。
合格者の数が高校のランク付けの指標となり、「東大」がブランド化するなか、経済学者の成田悠輔さん(11年、大学院修了)は、「この国で東大コンプレックスがこれだけ大きいのは、多分、難易度が絶妙だから」と語った。東大の合格者は1学年約3千人。出生数が80万人(対談当時)なので0.3%ほど。届くようで届かないからこそ、コンプレックスを抱く人が多いのだという。(編集部・深澤友紀)
https://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/%E6%B3%89%E6%88%BF%E7%A9%82-%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E3%81%AF-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F%E4%B8%BB%E7%BE%A9-%E3%82%84%E3%82%8F-%E5%89%8D%E4%BE%8B%E4%B8%BB%E7%BE%A9-%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%87%BA%E8%BA%AB%E3%81%AE%E8%91%97%E5%90%8D%E4%BA%BA20%E4%BA%BA%E3%81%8C%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%81%97%E3%81%9F-%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%9D%B1%E5%A4%A7/ar-AA1B2ysf?ocid=msedgntp&pc=NMTS&cvid=8affc894b90e41f89facfdf055b644bc&ei=23