19世紀のあたりまえ「ノアの洪水の証拠がある」「全生物は神の創造物だ」…じつは科学が示した真実に、賛成したのも反対したのもキリスト教徒だった(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース

19世紀のあたりまえ「ノアの洪水の証拠がある」「全生物は神の創造物だ」…じつは科学が示した真実に、賛成したのも反対したのもキリスト教徒だった
3/7(木) 6:43配信
17
コメント17件
現代ビジネス
科学者と聖職者の対立、じつは「正しくない」
illustration by gettyimages
欧米でも日本でも、科学とキリスト教は対立してきた、というイメージが強い。そして、ダーウィンが生きていた19世紀のイギリスは、両者が対立していた典型な時代とされることも多い。ところで、そういうイメージは本当に正しいのだろうか。
【画像】まさか「こいつの子孫がクジラにつながる」とは…驚愕のクジラの始祖の姿
たとえば、「大洪水の地質学的な証拠はノアの洪水を示している」とか、「すべての生物は神の創造物であって進化などしない」とかいった考えは、19世紀のイギリスではありふれたものだった。
しかし、これらの主張を攻撃したのは科学者で、擁護したのがイングランド国教会の聖職者だった、というイメージは正しくない。実際には、これらの主張を攻撃したのも擁護したのも、イングランド国教会の聖職者だったのである。
ペイリーの『自然神学』
左・ウィリアム ペイリー(National Portrait Gallery)、右・『自然神学:自然界に観察される神の存在と特性についての証拠』のタイトルページ(1802年、アメリカ版、Philadelphia)
3/7(木) 6:43配信
17
コメント17件
現代ビジネス
科学者と聖職者の対立、じつは「正しくない」
illustration by gettyimages
欧米でも日本でも、科学とキリスト教は対立してきた、というイメージが強い。そして、ダーウィンが生きていた19世紀のイギリスは、両者が対立していた典型な時代とされることも多い。ところで、そういうイメージは本当に正しいのだろうか。
【画像】まさか「こいつの子孫がクジラにつながる」とは…驚愕のクジラの始祖の姿
たとえば、「大洪水の地質学的な証拠はノアの洪水を示している」とか、「すべての生物は神の創造物であって進化などしない」とかいった考えは、19世紀のイギリスではありふれたものだった。
しかし、これらの主張を攻撃したのは科学者で、擁護したのがイングランド国教会の聖職者だった、というイメージは正しくない。実際には、これらの主張を攻撃したのも擁護したのも、イングランド国教会の聖職者だったのである。
ペイリーの『自然神学』
左・ウィリアム ペイリー(National Portrait Gallery)、右・『自然神学:自然界に観察される神の存在と特性についての証拠』のタイトルページ(1802年、アメリカ版、Philadelphia)

ウィリアム・ペイリー(1743~1805)は、イギリスのノーサンプトンシャーで生まれた。父親が校長をしていたグラマースクールで学んだ後、ケンブリッジ大学のクライスツカレッジに入学し、1763年に優等卒業試験の最優秀合格者として卒業した。そして、1765年以降は、イングランド国教会のいくつかの聖職を歴任することになる。
ペイリーにはいくつかの著作があるが、どれも明瞭でわかりやすいことで知られている。もっとも有名なのは1802年に出版された『自然神学:自然界に観察される神の存在と特性についての証拠』である。
この本のタイトルになっている自然神学と言う言葉は、時代や場所によって少し意味が変わるのでややこしいが、19世紀のイギリスでは「理性や自然の事実に基づく神学」という定義でよいだろう。このペイリーの著作は、自然神学の標準的な教科書となり、ダーウィンをはじめ多くの著名人に大きな影響を与えたのである。
この『自然神学』の冒頭には、有名な「時計の比喩」が書かれている。それはだいたい次のような内容である。
この世界は誰がデザインしたのか…造物主としての神
----------
野原に転がっている石について、どうしてそこに石があるのかと問われたなら、ずっと前から、ただそこにあったのだろうと答えるかもしれない。しかし、野原に時計が落ちているのを見つけたときには、そうは答えないだろう。なぜなら、時計の内部には、精密に作られた歯車やバネがあって、それらが複雑に組み合わされているからだ。時計は、あきらかに時を刻むという目的のためにデザインされている。つまり時計をデザインした者がいたということだ。
(『自然神学:自然界に観察される神の存在と特性についての証拠』William Paley著、筆者要訳)
----------
そして、自然に目を向ければ、生物の眼や体の作りなど、特定の目的のためにデザインされたとしか考えられないものがたくさん存在している。しかも、自然界のデザインは測り知れないほど偉大で豊富である。こんなことを成し遂げたデザイナーは神しか考えられない、とペイリーは言うのである。
もっとも、この「時計の比喩」はペイリーのオリジナルではない。共和制ローマの哲学者、マルクス・トゥッリウス・キケロ(紀元前106~紀元前43)や、イギリスの博物学者、ジョン・レイ(1627~1705)や、気体の体積と圧力は反比例するというボイルの法則で有名な化学者、ロバート・ボイル(1627~1691)なども「時計の比喩」を使っている(ただし、キケロの場合の時計は日時計や水時計である)。それでも、「時計の比喩」といえばペイリーが有名なのは、文章がうまくて印象的だったからだろう。
このような、生物に見られる合目的的なデザインの他に、アイザック・ニュートン(1642~1727)によって示された天体の秩序だった運動なども含めて、造物主としての神の存在を感じる人が、当時のイギリスには多かったのである。
ノアの洪水伝説と地質学
ウィリアム・バックランド。肖像画かT. フィリップスの肖像画をS. カスンズが銅版画にしたものとされる photo by gettyimages
19世紀のイギリスでは、地質学が盛んであった。最初はドイツやフランスの地質学に遅れを取っていたものの、1840年ごろからは世界の地質学をリードするようになった。このようなイギリスの地質学の基礎を築いたのが、ウィリアム・バックランド(1784~1856)だった。
バックランドはイギリスのデヴォンで生まれ、オックスフォード大学のコーパス・クリスティ・カレッジで学んだ。それから、バックランドは同大学で教鞭を取るようになったが、後にはロンドン地質学会の会長も務め、また、ダーウィンの番犬といわれたトマス・ヘンリー・ハクスリー(1825~1895)と論争したことで有名なサミュエル・ウィルバーフォース(1805~1873)の後任としてウエストミンスター寺院の首席司祭にも就任した。
バックランドは地質学によって神の英知が証明されるという自然神学の立場から講義を行った。オックスフォードの宗教教育に、地質学が役に立つと考えたのである。
バックランドが重視したのは大洪水であった。彼は地質学的な証拠から、過去に世界的な大洪水があったという仮説を立て、それをノアが箱舟を作ったときの大洪水と解釈した。
ところが、一つ困ったことがあった。
天地創造の6日間を何百万年の何百万倍も延ばした
イクチオサウルスの化石 photo by gettyimages
それは大洪水の堆積物の中に、人骨が見つからなかったのである。
もしも悪い人々を滅ぼすために神が大洪水を起こしたのであれば、その堆積物からたくさんの人骨が見つかるはずだが、いくら探しても見つからなかったのだ。
そこで、バックランドは仮説を修正せざるを得なかった。彼の発見した世界的な大洪水は、ノアの伝説における大洪水ではなかったと結論し、人間はこの大洪水の後に創造されたと結論したのである。
一方、バックランドは、中生代に栄えた魚竜のイクチオサウルスや恐竜のメガロサウルスを研究したことでも知られる。つまり、現在では存在しない生物がさまざまな生物が、人類の誕生よりはるか昔に生きていたというわけだ。
しかし、聖書の『創世記』では、世界は6日間で作られたという。
これでは、あまりに短いので、バックランドはこの部分の解釈を変えて、長い時間を捻出している。たとえば、「始めに神が天地を創造された」という一つの文が示している時間はとても長く、何百万年の何百万倍もの時間を表している、などと解釈したのだ。
この解釈はバックランドのオリジナルではないけれど、バックランドの著作によって広く知られるようになったのである。
19世紀のイギリスの地質学者の多くは自然神学者でもあったので、地質学の知見に矛盾しないように聖書を解釈した。
しかし、その一方で、聖書を文字通りに解釈する人々もおり、そういう人たちはバックランドの地質学を容認することはできなかった。
ウィリアム・バックランド。肖像画かT. フィリップスの肖像画をS. カスンズが銅版画にしたものとされる photo by gettyimages
19世紀のイギリスでは、地質学が盛んであった。最初はドイツやフランスの地質学に遅れを取っていたものの、1840年ごろからは世界の地質学をリードするようになった。このようなイギリスの地質学の基礎を築いたのが、ウィリアム・バックランド(1784~1856)だった。
バックランドはイギリスのデヴォンで生まれ、オックスフォード大学のコーパス・クリスティ・カレッジで学んだ。それから、バックランドは同大学で教鞭を取るようになったが、後にはロンドン地質学会の会長も務め、また、ダーウィンの番犬といわれたトマス・ヘンリー・ハクスリー(1825~1895)と論争したことで有名なサミュエル・ウィルバーフォース(1805~1873)の後任としてウエストミンスター寺院の首席司祭にも就任した。
バックランドは地質学によって神の英知が証明されるという自然神学の立場から講義を行った。オックスフォードの宗教教育に、地質学が役に立つと考えたのである。
バックランドが重視したのは大洪水であった。彼は地質学的な証拠から、過去に世界的な大洪水があったという仮説を立て、それをノアが箱舟を作ったときの大洪水と解釈した。
ところが、一つ困ったことがあった。
天地創造の6日間を何百万年の何百万倍も延ばした
イクチオサウルスの化石 photo by gettyimages
それは大洪水の堆積物の中に、人骨が見つからなかったのである。
もしも悪い人々を滅ぼすために神が大洪水を起こしたのであれば、その堆積物からたくさんの人骨が見つかるはずだが、いくら探しても見つからなかったのだ。
そこで、バックランドは仮説を修正せざるを得なかった。彼の発見した世界的な大洪水は、ノアの伝説における大洪水ではなかったと結論し、人間はこの大洪水の後に創造されたと結論したのである。
一方、バックランドは、中生代に栄えた魚竜のイクチオサウルスや恐竜のメガロサウルスを研究したことでも知られる。つまり、現在では存在しない生物がさまざまな生物が、人類の誕生よりはるか昔に生きていたというわけだ。
しかし、聖書の『創世記』では、世界は6日間で作られたという。
これでは、あまりに短いので、バックランドはこの部分の解釈を変えて、長い時間を捻出している。たとえば、「始めに神が天地を創造された」という一つの文が示している時間はとても長く、何百万年の何百万倍もの時間を表している、などと解釈したのだ。
この解釈はバックランドのオリジナルではないけれど、バックランドの著作によって広く知られるようになったのである。
19世紀のイギリスの地質学者の多くは自然神学者でもあったので、地質学の知見に矛盾しないように聖書を解釈した。
しかし、その一方で、聖書を文字通りに解釈する人々もおり、そういう人たちはバックランドの地質学を容認することはできなかった。
激しさを増す聖職者の対立と、『種の起源』出版
『種の起源』(初版本、1859年 、ケンブリッジ大学セントジョーンズ校)
もっとも激しくバックランドを攻撃したのは、ヨーク大聖堂の首席司祭ウィリアム・コウバーン(1773~1858)であった。彼はバックランドを名指しで非難するパンフレットを何度も刊行している。
こういう状況の中で、進化論を主張するダーウィンの『種の起源』が1859年に出版された。
『種の起源』(初版本、1859年 、ケンブリッジ大学セントジョーンズ校)
もっとも激しくバックランドを攻撃したのは、ヨーク大聖堂の首席司祭ウィリアム・コウバーン(1773~1858)であった。彼はバックランドを名指しで非難するパンフレットを何度も刊行している。
こういう状況の中で、進化論を主張するダーウィンの『種の起源』が1859年に出版された。
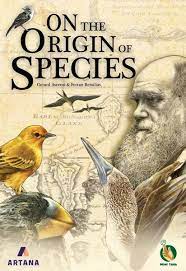
ダーウィンの『種の起源』には、最初の生物は神が創ったと書かれている。したがって、『種の起源』も自然神学書と考えてよいだろう。
しかし、ペイリーの『自然神学』とは結論がまったく異なる。
生物の多様なデザインは、ペイリーは神が創ったと解釈したが、ダーウィンは進化によって作られたと解釈したのだ。
『種の起源』はいかに受け入れられたのか
ハクスリーと進化論争を繰り広げたサミュエル・ウィルバーフォース photo by gettyimages
この『種の起源』は、大きな反響を呼び起こした。さきほど言及したサミュエル・ウィルバーフォースのように、批判した人もたくさんいた一方で、支持する人も結構いたのである。
オックスフォード大学の教授で物理学者であったベイデン・パウエル(1796~1860)はデザイン論を否定して、自然の普遍的秩序に基づく自然神学を主張した。そして、イングランド国教会の牙城であるオックスフォード大学の中で、『種の起源』を支持したのである。
また、イングランド国教会の司祭であり、後にケンブリッジ大学の教授となったチャールズ・キングズリーも『種の起源』を高く評価したことで知られている。
つまり、『種の起源』を攻撃した人も擁護した人も、その大部分はイングランド国教会の聖職者だったのである。
更科 功(分子古生物学者)




























