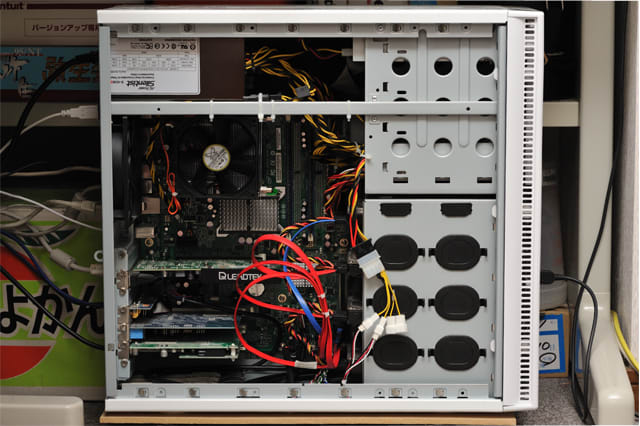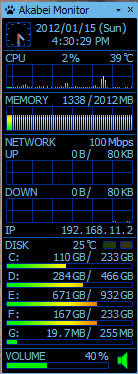大寒を過ぎて、ここ数日の寒波襲来。寒がりの私は外出もままならないですが、仕事上、会議で松江市に出かけることになりまして、ちょっと早めに我が家を出発、出雲の冬を撮影しました。
撮影場所は斐伊川河口です。ここは空がとても広く撮影できます。電線もない。何も無い所です(私の写真撮影を邪魔するものが無いという意味です)。子供の頃、斐伊川河口は地の果て、「虚無の世界」に来た恐怖心がありました。大人の距離感と子供の距離感は違います。車という移動手段を得たからではないでしょうか。野鳥、水鳥はいっぱいいます。
今回の寒波は斐川ではそれほどの積雪はありませんでした。2~3センチくらい。朝方は積もっていましたが、日中少し晴れ間があると直射日光で道路上の雪は溶けてなくなりました。
雪雲が切れて、鍋の底が抜けたような透き通った青空が見えます。太陽が放つ一瞬の光が風景に色彩を復活させます。
今回の撮影も広角ズーム18-35mmを使いました。青空がきれいです。宍道湖端の堤防を車を走らせます。

画面上にグレーの斑点があります。雪が映り込んでいます。はじめはセンサー上の埃かとびっくりしました。
斐伊川河口に到着です。島根半島側、北山山地は綺麗に晴れ渡ります。

上流方向、西側にカメラを向けると北半分の旧平田市側は晴れ。南半分の斐川町側は雪が降っています。山陰の冬はこんな感じ。雪が降ったかと思うと突然に雲が切れて太陽が顔を出します。

南側の斐川町は完全に雪模様。鉛色の空が色彩を奪います。遠くに見えるのは仏経山、すなわち神名火山です。

仕事が終わって、日没直前、雲の切れ間から夕日が少し顔を出しましたが、宍道湖東岸、袖師町の夕日スポットに着いた時には雲に隠れてしまいました。山陰の冬はこんな感じ。一瞬の日差しに春への憧れを募らせます。

Ai AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED
途中、スーパーに立ち寄り宍道湖産のシラウオを購入しました。今年は豊漁だそうですが1パック580円。流水で軽く洗って口にすると、心地よい弾力。歯ごたえ、かすかな苦味。美味でありました。すまし汁で卵とじにして夕食の一品となりました。
もうすぐ節分です。