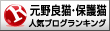ねずみ 何と言う迂闊。うっかり命を落としてしまったなんて話は洒落にもならない。洒落にもならないけれど,死ぬときなんて、そんなものだったのだ。 こんなことになるなら、昨日の台所の皿の上に残っていたチーズは、例えこの身を全て1000ワットの明かりの下に曝しても、食べるべきだった。一生に一度のチャンスだったのに。あの味の美味なることは、年寄達から耳にタコが出来るほど聞かされていた。あれをいま一度食べれるならいつ死んでもいい、本望だと。ならば自分もいつかはと、あこがれ願っていたのに、肝心の時に恐れに負けてしまうとは、負けて暗がりに逃げこんでしまうとは、これでもう、今までに食べに食べ、ただひたすら食べることに邁進してきた、自分の人生は無になってしまった。 求める究極のものを眼の前にして、怯えに負けるなんて何ということだ。その上つまらない芋切 れの誘惑に負けて、こともあろうに、骨肉の争いを演じるとは。食べ物のことになると、どんなに冷静になろうとしても、あらん限りの理性を絞り出しても、それでも気がつくと我を忘れている。おふくろさん、本当に申し訳ない。今日までこの愚かな息子を守り導き、そして慈しみ育ててくれたあなたの手からまで、最後の食べ物を奪ってしまった。あの肉の一切れがあつたなら、あなたは飢死になどしなくて済んだのに。 まだある、まだあるんだ。こうなったらもう隠していても始まらないから言うが、昨年の冬のことだ。あの時ほど自分が何者であるか、分かったことはない。あそこは危険なのは百も承知だったが、毎日雪に降りこめられて、あそこ以外に食べ物を得ることはできなくなっていたのだが、それにしても、まだたよりない子供達まで連れて行くことはなかったのだ。人参でもトウモロコシでも引っぱって、まずあいつがもぐり込めない所まで運んで、そこで皆に食べさせてやれば良かったのに、それくらいの分別もつかないままに、あいつが爪を研いでいる所に、ぞろぞろと引き連れて繰り出してしまった。しかしそれにしても、誰よりも先に、壁の穴に飛び込んだのは自分だっただけではなく、あろうことか、妻や子を突き飛ばして、先頭切って逃げていた。突き飛ばされたあの子が、最初にあの恐ろしい爪に掛けられているのを横目で見ながら、もう一本の手がのびてくる所に、今度は妻を押し倒し乗り越えて逃げた。妻の叫び声を聞いた時は、助かったと思わず叫んで壁の穴に身を躍らせたのだ。何という薄情者だ。そればかりではない、もうあいつが追ってくることは出来ない壁の向こうに逃れた後も一目散に地面の巣穴のトンネルを堀りながら、気がついたら口には人参をくわえていて、そいつをかじって飲み込んだ時のうまかったこと。あの時は確かに、背後で聞こえた妻の叫びも子の悲鳴も忘れていた。 生きていくということは、辛いことなのだよと言いつつ暖かい巣に戻って、しばらくぶりにふくれたお腹をかかえて、たっぷりと眠ってしまった。そんな自分だから、いよいよ今度は自分の番が迫って来たのだ。それだけのことなのだけれど、自分の好みとしては、水を飲み続けてじわじわと死ぬよりはひと思いに、あの妻や子を襲ったやつの爪にかかり、喉元をひとかみで決められた方が嬉しかったのに、いつかはそうなるだろう、そうなるに違いないと確信をしていたのに、それなのによもやと思うこんなドジで間抜けなお陀仏の仕方をするなんて、これはやっぱり、バチが当たったに違いない。食い意地だけの人生を生きた当然の報いというものだろう。 もうそろそろ頭ももうろうとして来たし手も足も動かなくなって来たけれど、どうもこんな時は幻覚を見るというけれど、さっきから、月明かりの中でピンと立って見えるあの耳は、あれはあいつではないだろうかずっと先ほどから水の中てもがいている俺を見ていたような気がするけれど、いや確かにあいつに違いない。ああ今顔を少し上げたので2つの大きな目がまるで鏡のように光った。間違いない、あの妻と子を爪にかけたあいつだ。そうかさっきは水の中でもがいていたから気付かなかったけれど、あいつは身を乗り出して手をのばし、引っかけ上げようとしていたのだ。鼻先を何度も鎌のような爪がかすめていたのを思い出した。そうか、あいつは瓶のふちでよだれを垂らして、俺を釣り上げようとしているのだ。それならそうとさっさっとやってくれ。俺としては、おぼれ死ぬのは、いやなのだ。水死というのは俺達一族の最下等の死にかたであり、恥なのだ。俺達にだって、プライドというものがある。お前たちの爪や牙にかけられて死ぬのが一番の、最高級の死に方であり、飢え死にが次で罠にかかって死ぬのが最低なのだが、罠にかかっておぼれ死ぬのが更にその下の下の下なのだ。浮かばれない死に方なのだ。だから、その手をもうちょっと伸ばしてくれ、さっきから鼻先をかすめているではないか。 ? 先ほどからゴチャゴチャと往生際のわるいやつだな。お前の言い分を聞いていると、馬鹿馬鹿しくなる。それにおかしくなる。面白いと言ってもいい。結構楽しませてくれる。お礼にお前にチャンスをやる。これからワシはこのカメの縁から自慢の尾っぽを垂らしてやるから、お前はそれを伝って上がってくるがいい。ただし、上がって来た所で、ワシはエサにありつくことになるかも知れない。あるいはそのまま逃がしてやるかも知れない。お前にとってはハズレのないくじ引きだ。望み通りワシの牙で喉笛を食い破られて死ねるかも知れないし、もしかしたら、そのまま逃がしてもらえるかも知れない。わるくない話しだろう。それでは、ホラ、ワシのシッポを垂らしたぞ。 これは驚きだ。地獄に仏とはこのことだ。最後の最後にこんな幸運に恵まれるとは、ありがたい助かった。これで死ねる.最上等の位の死に方ができるなんて、あんたが逃がしてくれるなんてことがあるはずはないではないか、あんたは俺達を喰うのが仕事だから、喰えばいいのだ、逃がすなんてあんたらにはできないのは分かっているのだから、それでは登らせてもらうよ。 ありがたい、これは本当にありがたい、これでやっと死ねるというものだ、これでもう何も食べなくてもいい。さっきまでチーズのことを考えていたなんて、食べるための人生を考えていたのに、やれ良かったこれでもう食べなくてもいいんだ、嬉しいよ、その上最高級の死に方を出来るなんて、夢のようだよ。 ホラホラごちやごちゃしゃべるな、また落っこちて水の中だぞ、ホラもっと手に力を入れろ、この際だから歯を使え、噛みついて体を引き上げろ、もうひと息だ、楽に死なせてやるから頑張れ、頑張れ、よし、そこだそこで瓶のふちに足を乗せろ。いいぞあとはまかせろ、この後は、こうやって首ねっこをくわえて、まだまだまだ終わらせはしない、よっこらしょっと、そら、どうだ、地面に足がついた感触はなつかしかろう。何をキョトンとしているかお前はまだ死んではいない。さあ、行け、ワシはまだお前に食い続けさせたくなつた。納屋にでも台所にでも忍びこんで、これからも人間達の食い物を盗み続けるがいい、ワシはそんなお前達を喰うのが楽しみだ、お互いに食いたいものを喰う、それが世の中の仕組みというものだ。 さあ、 行けよ。 「あなた、いつまで庭の瓶のぞきこんでいるの。早くしないと子供達が起きてくるでしょう。今の内にその死んだネズミ始末してちょうだい。だから私水瓶には金網で蓋をしておいてと言ったのよ、始末したら今日中でいいから、瓶の水も棄てて、おいて下さいよ」 ねずみ 本間 昭南
goo blog お知らせ
goo blog おすすめ
カレンダー
最新記事
カテゴリー
- 秘境小幌駅(13)
- 写真で見る一年(2)
- ララ二代目愛ネコのトト…浜の野良(194)
- 詩(9)
- 詩吟(8)
- 山野草(123)
- 渡辺淳一文学と阿寒に果つ(6)
- 東日本大震災(15)
- 昭南の未発表の作品(2)
- 卓球(52)
- 人生(37)
- 合唱(61)
- 白い思い出(3)
- 山田禮ニ先生(4)
- 平和(1)
- 悪夢(13)
- 老いるとは(31)
- 長生大学(290)
- 旧三谷牧場跡(3)
- 有珠善光寺(8)
- 初めてのブログ(1)
- 大滝(23)
- 絵画(43)
- 入院(62)
- 老老介護(5)
- 老後の暮らし(7)
- 市原悦子さん(2)
- 美容(3)
- ユルリ島の馬・馬の話題(6)
- 自家製山ブドウ酒梅酒などなど(1)
- 二代目キキ(61)
- フジコ・ヘミング&クラシック(2)
- パークゴルフ(6)
- 屯田兵(1)
- 社会福祉・母と子(1)
- 愛猫のキキ(16)
- カラオケ(74)
- 歯の延命治療(6)
- 続猫たちの挽歌(5)
- 猫の線維肉腫(31)
- 演芸(カラオケ)クラブ(198)
- 井樫監督(4)
- 中谷宇吉郎(8)
- 珍味な食材・・八角 ゴッコなどなど(44)
- 神田日勝(7)
- 海外協力隊(2)
- 鮭と人生(11)
- 伊達の名所と有名人(64)
- ちょっといい話(150)
- 温泉(42)
- 家族(308)
- ハイキング(2)
- 愛猫のララ(150)
- 桜(48)
- 釣行(148)
- 散歩(24)
- ニュース(187)
- 歌の風景(13)
- 健康(338)
- ジャズ(18)
- 文学・読書(21)
- ネット(97)
- 自家菜園(260)
- 俳句 短歌(59)
- 札幌行(317)
- 伊達・暮らし(569)
- ガーデニング(424)
- 料理(235)
- 写真(25)
- 音楽(34)
- 野鳥(131)
- 月刊誌「旅人」(7)
- 親友・・・気仙沼の富美ちゃん(29)
- 元同僚(52)
- 樺太(31)
- 雪のふる街(10)
- 雪の街のシズ子さん(6)
- 藁葺きアパートの住人たち(5)
- 北の家族(8)
- 思春期(7)
- 青春(35)
- 猫たちの挽歌(17)
- 伊達のカラス(26)
- 昨年のブログ(45)
- 金魚(16)
- お祭り(54)
- 食中毒(6)
- ファッション(21)
- エツセィ(53)
- 映画(24)
- 友人(37)
- 小説(11)
- インポート(683)
- 野良猫・近所の猫(144)
- 教え子・学校(33)
- ジャコシカ・・・小説(219)
- 旅行(147)
- グルメ(188)
最新コメント
- みゆきん/シェパードがいた家
- kシズ子/いずみ70年・・・あの時の坊や、三船遭難事件
- 風花/いずみ70年・・・あの時の坊や、三船遭難事件
- jun19630301/ギクッ
- HAL/人生いろいろ・・・眠れぬままに
- ストレンジャー/人生いろいろ・・・眠れぬままに
- ジューン/ねねカテーテルから解放
- kikilala_nyanko/ねねにまさかの奇跡が・・・猫の悪性リンパ腫
- kikilala_nyanko/ねねにまさかの奇跡が・・・猫の悪性リンパ腫
- ストレンジャー/ねねにまさかの奇跡が・・・猫の悪性リンパ腫
バックナンバー
本間昭南の著書
・「雪の街のシズ子さん」 エッセイ
・「北の家族」 小説
・「雪のふる町」 小説
・「猫たちの挽歌」 エッセイ
在庫あり