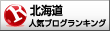ロックガーデン風庭を我家の庭の一画に伊達に来てすぐに造りました。三年目のガーデンです。2008年度の春。

 同じ年の花壇のクロッカスや水仙、福寿草達です。
同じ年の花壇のクロッカスや水仙、福寿草達です。

 ?家の前の鉢さん達です。
?家の前の鉢さん達です。
 多肉さん達
多肉さん達 ? 鹿児島知覧の武家屋敷の庭
? 鹿児島知覧の武家屋敷の庭 ?家の向かいの空き地にあつた木々が眺めが良く、ヒヨドリも春に巣を作り、楽しませてくれたが、今は整地されて何もなく寂しい。
?家の向かいの空き地にあつた木々が眺めが良く、ヒヨドリも春に巣を作り、楽しませてくれたが、今は整地されて何もなく寂しい。



 同じ年の花壇のクロッカスや水仙、福寿草達です。
同じ年の花壇のクロッカスや水仙、福寿草達です。

 ?家の前の鉢さん達です。
?家の前の鉢さん達です。
 多肉さん達
多肉さん達 ? 鹿児島知覧の武家屋敷の庭
? 鹿児島知覧の武家屋敷の庭 ?家の向かいの空き地にあつた木々が眺めが良く、ヒヨドリも春に巣を作り、楽しませてくれたが、今は整地されて何もなく寂しい。
?家の向かいの空き地にあつた木々が眺めが良く、ヒヨドリも春に巣を作り、楽しませてくれたが、今は整地されて何もなく寂しい。