それで私は、この人はきっと何か悪いことをして逃げているのに違いないと思った。
実際はそんな怖い印象は何もなくて、いつも穏やかで優しい人だったのに。子供の勝手な想像だ
ったのだけれど、それにそんな秘密じみた想像を楽しんでいたのかも知れないけれど、それが両親
を失った時、突然現実と結びついてしまった。
とにかくあの時は悲しくて苦しくて、やり場のない怒りで息が詰まりそうになっていて、それを
全部鉄さんのせいにして、ぶつけていたのよ。
馬鹿で攻撃的でひねくれた子だったの私って、それなのに鉄さんはずっとここにいるんだと思っ
ていた。
鉄さんはあの入江の家にいなくてはならないんだ、どこへも出て行くなんてことは赦されないん
だ、そんな風に思っていたのか知ら・・・。
一人で東京に出て、遮二無二前に進もうと思っていたけれど、そんな自分を支えてくれたのはこ
この海と入江の家だった。
高さんはどうか知らないけれど、私にはどうしても故郷というものが必要だった」
あやは少こし眼を細め、言葉を切った。
どこを見るというでもない視線が、オーク材の堅く光沢はあるが、そこ此処に傷跡の目立つテー
ブルの上をさ迷っている。
ようやく残り少なくなったカップに手を伸ばしてあやが口を開いた。
「どうしたのかしら私。こんなこと話して、多分あの手紙の話しのせいね。
野木和美さんという人は、私が自分の周りの大切な人のことを何も知らないでいることに平気な
人間だって知らせてくれたのよ。
考えてみれば識ろうとさえしていなかった。










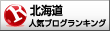


 が退院してくるまでは一人では動かせないし
が退院してくるまでは一人では動かせないし




