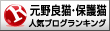本間昭南
一、 矜持
つい先頃まで猫という動物をきちんと飼ったことがない。きちんと飼っていないとはどういうことかと尋ねられると、ちょっとこまるが、この際出来るだけ正確に答えるならば、自分が飼っているという意識が希薄で、いわば猫と同居している状態と言えば良いだろうか。そんな気持になるのは、そもそも一緒に暮らすことになった始まりが、気がついたら、そいつがいつの間にか家の中に居たという、ことによるのだと思う。 普通猫を飼い始める時はペットショップで買ってくるとか、道端にダンボールか何かに入れられて棄てられている処に行き合わせて、切なく泣きつかれ、訴えられてつい拾ってくるとか、あるいは知人に頼まれて貰ってしまうなどの場合が一般的だろう。いずれにしても「それなら飼うか」と決心して、初めてそいつは自分の寝起きする場所と食を得ることになる。今流で言えばそいつは目出度く三食昼寝付の、ペットの地位を得たことになる。
最初の猫との出会いは、つまり同じ屋根の下で住むことになった猫は三毛猫で、ネズミ狩りの名手だった。彼女は私達家族よりも先にその家の住人であって、その地位も家の中で私達よりも確固としたものだった。
少し話しが混み入ってくるが、彼女は、その家に夫婦と一人娘の3人の家族の中の一員だった。その家に私達母と5人の子供が押しかけころがり込んで同居することになったのだ。5人の子供達は一番上が長女で12才、その下に9才、7才、5才と続き末はまだ6ヵ月だつた。
私はこの5人兄弟の真中で7才だった。所は北海道の片田舎、ころがり込んだ家は借家住まいで貧しかった。その貧しい家にさらに貧しい、行き場のない母と子供がころがり込んでしまったのだが、その家の夫婦と娘にとっては、まったくもって迷惑千万な話だった。三毛猫にとっても迷惑なことに変わりはなかったと思うのだが、時間が経つと彼女と我々との関係は少しずつ変化してきた。
最初彼女は私達一家には近づこうとしなかった。猫というのは昔から、おおむね子供が嫌いと相場が決まっている。理由は猫はマイペースで行動するのが基本というか好きな動物で、人間の都合でいじくられるのが厭なのだ。子供はその点自分中心だから猫の都合などおかまいなしだ。彼等は人間といっしょに暮らしていても人間の行動に合わせて生きているのではない。最近は大分変わったが今から50年前は、そうだつた。特に田舎の猫は、ネズミを獲るという、レッキとした正業があったから、彼等は飼われているという意識は極めて薄い。彼等は納屋や米倉のネズミを退治することで、その家で住む地位と権利を得ているのである。だから、彼等の頭には飼育されているという意識はあまりないのではないかと思う。自分の役割を有する彼等は誇り高い生き物である。彼等は自由に歩きたい所を歩き、寝たい時に寝たい所で眠る。彼等はペットなどと呼ばれたら大いに屈辱を感じることだろう。
ころがり込んだ家の三毛猫も間違いなくそんな猫だった。もっともその家は農家ではなく建具師だったので守るのは倉庫の材木と台所の食料である。それまでに猫という動物を飼ったことのない私達は、この三毛猫に大いに興味をそそられたが彼女からは当然ながら嫌われかつ完全に無視された。もしかしたら軽蔑されていたのかも知れない。その家の奥の一室に折り重なるようにして暮らすことになった私達に彼女は、近付こうともしなかった。
彼女は自由に家の内と外を往き来しネズミをしとめると良く茶の間にくわえて来ては披露し、「わかったわかった」とこの家の主婦が半ばどなりつけるように言うと、満足気に獲物をくわえ直して部屋を出て行くのだった。
彼女に与えられるエサは冷や飯に味噌汁をかけたいわゆるネコ飯と、だしを取った後の煮干であるが、その他には煮魚や焼き魚の人間が食べた後の骨や頭である。このように書くと結構な食事のように聞こえるが、問題は、その量である。人間だって3度の飯に米の飯は食べれない代用食の時代である。ジャガイモや南瓜の時は彼女は手は出せないし、水団や雑炊の時は彼女の分は無い。従って一日に1回の食事に必ずありつくというわけにはいかない。だからせっせとネズミを捕る。子供の眼からみても主食はネズミといって良い状態だった。彼女はそんな食事事情に特に不満な様子も見せない。そもそも彼女はこの家の人間にエサをねだるということがなかった。朝どこからともなく現れて、この家の主婦が動き始めると、一応は台所の自分のエサ入れの茶碗を覗きはするが、碗が空であっても何も言わず黙ってまたどこかに出て行く。人間達が食事をしている時で、未だ自分には何も与えられていなくとも、静かにストーブの後ろのいつもの場所で座っている。私達家族は彼女の鳴く声を聴くことが殆どなかった。どんなに腹をすかせていても、彼女は声を上げて、エサをせがむことはなかつた。
私はそれまでに人が猫を飼っているのを、身近で見たことがなかった。猫を飼っているのは大概農家の家で、彼等は屋敷廻りの庭や納屋の前や縁側などで見かけるだけだった。今度同じ家の中に猫と住むことになって、初めて猫について、いろいろと知ることができたのだ。
三毛猫はミケと呼ばれていた。と言うことはミケは確かにこの家に飼い猫として住んでいたのだが、夫婦も娘もミケには余り関心がないように見受けられた。
三人の内で誰も彼女に優しく声をかけることはなかったし、ましてや膝の上にのせてその柔らかな毛に指をすべらせるようなこともなかった。そればかりではない。この家の主は酒が切れても、入り過ぎても暴れる性癖があり、しばしば妻に暴力をふるった。自分の妻に対してさえ、そうなのだから、猫になど容赦もなく、ミケも度々その被害に合っていた。良くある夫婦のいざこざの場面で、夫がやにわに卓袱台をひっくり返すとか、手にしていたドンブリや湯のみを壁に投げつけるなどの行為があるが、この家の主はそうしたメニューの中にストーブの脇に常に置かれている薪を、ミケに投げつけると言う行為を入れている。この点については、ミケもただ自分に薪が飛んで来るのを座して待っているわけではなく、いち早くその雰囲気を察すると身をかくすのだが、そんな彼女の鋭い勘でも間に合わないほど、いきなり何の前触れもなく、くだんの薪に襲われることも良くあった。主は朝起きると、激しく水しぶきを上げて顔を洗ってドタリとストーブの所定の場所にあぐらをかくやいなや、物も言わずに薪を振り上げることがあるのだ。彼はミケの動きのすばやいのを良く心得ているので、その動きは電光石火である。このためさすがのミケも3度に一度は手痛い一撃を受けることになった。時にはその一打の当たり所が悪くて、何日も足を引きずって歩くことがあったが、それでもミケがこの家から姿を消すことは無かった。
今思うに、北海道の冬をノラ猫が乗り切るのは、並たいていのことではなかったのだ。その年に生まれたノラの子は、最初の冬を越せずに姿を消すことが多かった。多分そのせいではなかったかと思うのだが、ミケは度重なる主人の理不尽な暴力にもかかわらず、この家を出て行くことはなかった。
主人の扱いがひどかった分、他の二人がその埋め合わせをして可愛がっているかというと、そうでもない。娘は完全無視であったし、妻も猫好きには見えなかった。この家の猫と人間の関係は、互いに情とは無縁のギブアンドテイクの関係に見えた。
゛ミケはネズミから物置の材木と台所の食料を守り、人間は住いと不充分ながらもエサを与えていた。私が初めて見た猫と人間の関係はそんな風だった。ついでながら、この古い木造の借家にはやたらにネズミが多かった。夜家人が寝静まると、天井裏はネズミの運動場になる。度重なるミケの襲撃を受けているにも拘らず、彼等は怖れを知らないかのようにふるまっていた。借家は幾軒も軒を連ねていたので、彼等の活動範囲は思いの他広かったのかも知れない。
私達兄弟はたちまちミケと家人の関係と付き合い方に気付き、そしてのみこんだ。ミケにとって我々はたまたまゴタゴタと奥の部屋に押し込まれた家財道具みたいなもので、見慣れてしまえば存在しないも同じだったし、我々にとってもミケは時折家の中を動く影のようなものだった。
私達一家にとっては暗く苦しい時が過ぎていた。転がり込んだこの家は私の母の伯母の家で、私達は父親が隣街から出ている支線で五つばかり入った山の鉱山で働くことになり、そこの社宅が決まるまでの1週間の約束でやって来たのだ。季節は秋の終り、冬はもう目の前に迫っていた。
強引に押しかけた約束の一週間はアッと言う間に過ぎたが、社宅はあてがわれず、その上3ヵ月後に父親は新しい勤務先の鉱山から蒸発してしまった。何の蓄えもなく、収入の手段もないままに、冬の北海道の片田舎に放り出されて、母と子は途方にくれていた。伯母に泣き付いて窓のない灯りをつけなければ昼間でも足元も良く見えない部屋で私達は暮らすことになった。
飢えと寒さでさながら冬のノラ猫のごとき生活の中で、私達はミケと出合ったのだ。出合ったと言うよりは、見たと、言った方が良いだろう。
ようやくの思いで一冬を生き延びた私達一家は、春になると、3軒隣の潰れかけた借家に移ることが出来た。以来6年間、私達はこの村に住むことになるのだが、その時から、ミケとの思いがけない関係が始まった。新しい借家はミケのテリトリーの中にあった。彼女は毎日のように家の廻りを巡回していたが、その内家の中にも上がりこむようになった。一冬を同じ屋根の下で暮らしたのだから、当然顔見知りの私達に、彼女の警戒心は解かれていた。家の戸はひしゃげた戸板を蝶番で止めたもので、すそは破れて穴が開いていた。中の引戸のガラスも割れて口を開けたままなので、ミケの出入りに不自由はなかった。
ミケはここでもメガネストーブの後ろに位置を決め、何時ということもなく、そこで丸くなっているのを見かけるようになった。子供達も見慣れた彼女に対する態度は学習済みなので、気にもかけなかった。相変わらずの食うや食わずの生活である。従って、ミケに廻れるエサなどない。たとえ、たまにカレイやホッケなどの干物が食卓に姿を見せても、子供達は骨一本といえども皆胃袋に納めてしまう。かたい骨はストーブの上にのせてこんがりと焼くとせんべいのように美味しく食べられる。
ここでもミケがエサをねだることはなかった。この家で何か腹の足しになるものなど最初から、彼女は当てにしていなかったろう。そうこうしている内に、ここでもミケは捕った獲物を運んできて見せるようになった。彼女がいつもとは違う弾んだ足音をたてて、ネズミをくわえて現れると、最初に気付いた誰かが大きな声で叫んだ。「わかったわかった」その声を聞くとミケは一端くわえた獲物を置いて皆を見回し一同の眼が自分に注がれているのを確認してから満足気に退散するのだった。
猫ほど自由気ままに人間と暮らす動物は居ない。そのことを私達に教えてくれたのはミケだった。彼女は家の周りのあらゆる処で眼にすることが出来た。草ムラを匍匐前進している眼の先を窺うとトンボが留まっていたり、いきなり樹の上にかけ上がってスズメを脅かしたり、かと思うとそのまま、樹上に器用に体を横たえて眼を閉じて気分よさそうにうたた寝を始めたりする。彼女の特に気に入りの場所はひしゃげて今にも陥没しそうな我家の流し場の屋根の上で、彼女は良くそこで昼寝を楽しんでいた。子供の眼から見ても彼女は飼われている動物というふうには見えなかった。
勝手に我家に気の向くままに上がり込んでは、自分の場所を確保した彼女は、最初は伯母の家と同じ姿を見せていた。夏が過ぎて秋も深まり、やがて涼風が立ち始めると周りの山々は一気に紅葉を深め、その鮮やかさに眼を奪われているひまもない内に木枯らしが霜を運んで来た。気が付けば辺りはもう冬の気配に包まれ空は重く暗い雲に覆われている。そんな日が続き始めたある朝眼を覚ますと、戸の外は白一色に包まれている。私達一家にとってもミケにとっても厭な季節が始まったのだ。彼女は縄張りの点検を手早く済ませ、人が居るときはストーブのそばの定位置で丸くなり、誰も居ない時は部屋の中で、移動する窓からの陽の光の当たる場所を追っていた。
12月、吹雪が続き行商の足止めを食わされた母が、ストーブの前で繕い物をする日が多くなった。ある時雪の中を学校から帰った私は、信じられないような光景を見た。繕い物をする母の膝の上に、ミケが丸くなって載っていたのだ。笑顔を向けた後母は、何ごともない様子でまた針を動かし始めた。
その日から、ミケはほぼ毎日のように我家にやって来て、母の膝に乗った。それを見た私達も彼女を膝の上に乗せたくなり、次々と彼女を抱き上げては膝の上に乗せるのだが、彼女はすぐに下りてしまい、決して母の膝の上に居る時のようにじっとしてはいなかった。
子供達はしつこく何度も試みたが、結局彼女を膝に乗せておくことは出来なかった。しかしこの時から私達兄弟のミケを見る眼は明らかに変わった。ミケは急に、自分達にとって身近な生き物、というよりなんだか仲間のような気がし始めたのだ。それまで彼女は毎日我家に顔を見せるが、あまり長居をせずにいつの間にか姿を消していた。彼女は近所の知り合いの処に顔を出し、ほどほどにくつろいでから、また自分の家に帰って行くといった様子だった。だから彼女が我家で朝まで居ることはなかった。ところが、母の膝の上に乗り出してから一週間ほど経った頃、折り重なるように寝ている私達の布団の中に、いつの間にか彼女は入り込んでいたのだ。その頃の私達の寝ていた布団は、実におそまつなものだった。つぎはぎだらけの皮の中身は綿ではなく掛けも敷きも藁だけだったのだ。もちろん最初からそうだったのではないが、前年、冬の食料を買うために、綿はみな抜かれて売られ、代わりに藁が詰められたのだ。藁布団は敷きはまだ我慢ができるが、掛け布団用としては、誠にもって具合の悪いものである。第一に保温力があまりに小さい。次に寝ているうちに高い所から低い所に移動してしまい、結果体の上は皮だけということになる。
物置同然のすき間だらけ、吹雪の日など玄関の履物の上は吹き込んだ雪で真白となり家で眠りを得るには、余りにも心細い代物である。
その藁布団の上に、家中にある衣類を乗せ、着物は着たままで、子供達は重なるようになってもぐり込んで寝る。その足のすき間にミケは頭からもぐり込んで寝ていたのだ。子供達は母の膝の上の彼女を見た時以上に驚いた。驚くと同時に彼女が湯たんぽ代わりになることを知った。その時から部屋の明りが消される時そこにミケがいたら、彼女の争奪戦がくり広げられた。そんな時彼女は一端は布団の中に押し込められるがすぐに出て行ってしまった。私達は彼女に一緒に寝てもらいたい時は、ただおとなしくじっと待っているしかないと言う事を知った。
ミケはどんどん私達に近づい来ているように思えた。私達もまたミケに対する親しみを深めていった。夏の間など、私は川や沼、用水路で捕えたフナやドンコ、小エビやドジョウなどを焼いたり煮たりして食したが、ミケにもおすそ分けをすることを忘れなかった。いつの間にか我家にもミケ用の大き目の鉢が置かれるようになった。この村に来て彼女は私達に近付いて来た唯一の友人だった。
3度目の冬がやって来た時、近くに姿を現したノラ猫のことが話題になった。この猫はオス猫で附近の農家のニワトリを襲って、幾羽も被害が出た。一度茶トラで顔が大きく尾のないこの猫が雪の野原を横切って行くのを見たことがあった。半ば雪に埋まりながら歩いて行く彼の姿は大きく猛々しく、野生の動物そのままの気迫に満ちていたる私は目の前を横切って行く彼を見た時、何か畏れのようなものを感じた。
その夜布団の中で閉じた瞳の中に彼の姿が何度も現れては消えた。私はその時、心の中で叫んでいた。「襲え、トリでもウサギでも襲え。襲って奪い取れ!そして冬を行きぬけ」
それから数日後、彼は猟銃で撃たれて死んだ。直ぐ近くの大きな農家の主が、自家のトリ小屋から獲物をくわえて出て行くところを撃ったのだ。
その話しが母と子の間で交わされた時、兄が母に尋ねた。「猫は自分の死んだ姿を人に見せないと言う。死ぬ時は一人で何処かに姿を隠して、静かに死んで行くと聞いたけれど、本当だろうか」母は即座に答えた。「お母さんもそのように聞いている。多分それは本当のことだと思う」子供達は皆大きくうなずき、そしていつものストーブの後ろに丸くなって寝ているミケを見た。
冬が厳しさを増し、一家は飢えと寒さで、さながら遭難のさ中のような生活をしていた。そんな時ミケの様子がおかしくなった。終日、彼女の定位置から動かなくなり、夜も私達の布団の中にもぐりこんで、朝まで出て行くことがなくなった。狩をしに出かける様子もなく、かといって彼女の本来の家に戻っているようでもなかった。彼女は何も食べていないと皆が気付いて三日目、いつも家にいる姉が末の妹を背負って駅前の製作所から薪拾いをして橇を引いて帰った時、彼女の姿が定位置に居ないのに気付いた。
家に帰ったのだと思っていたのだが、夜になつても彼女は現れなかった。翌日も彼女は姿を見せなかった。夕方私は伯母の家に様子を聞きに行って、こちらにもミケが戻っていないことを知った。それから毎日伯母の家に聞きに行った。一週間後、私達はミケが完全に私達の前から姿を消したことを知った。
その日は朝から激しい吹雪だった。
私達は彼女がその吹きすさぶ雪の中に深く埋もれて、眠りについたことを疑わなかった。
ミケのことは私の中に、猫という生き物の絶対的姿として強く焼き込まれた。そして人と彼等との関り方の変えてはならない約束ごととして、今も心の奥に残っている。
H20,10,1 チロルにて
二、 母と子
9月の穏やかな青い空に、高い煙突から昇る白い煙は軽やかにたなびく間もなく吸い込まれて消えて行った。昨日からの慌しい出来事は、どこか見知らぬ人達のざわめきにしか感じられない。
入れ替わり立ち変わる人の姿は絶え間もなく、皆言葉少なでよそよそしく、忙し気だった。男も女も一様に身につけた黒い喪服が、今何が起っているかを私に伝えていた。葬儀はいつだって何故か現実感のない麻痺した感覚の中で見る白日夢のようだ。母の時もそうだった。悲しみすらどこかわざとらしい。本当の悲しみや喪失感はずっと遅れてやって来る。日が経つにつれ現実感が骨身に浸みて来る。取り返しのつかない時間が流れて行く。
20歳になって東京に出た私は出来るだけ、別れて来た母や兄弟達のことは考えないようにしていた。考えたところで自分には何もできないと知っていたからだけではなく、故郷や家族のことを思えば、心が弱くなると思っていたからである。金もなく伝もなく、生活の宛などまるで無いままに、まるで家出同然に北海道を後にした20歳の若者は、いつも追い詰められたような気持で、生きていた。しかし、そんな時でも母と姉のことは、頭の片隅にこびり付いてしこり、離れなかった。母の人生は貧との闘いの連続であったが、姉のそれもまた母に劣らぬものだった。
生活を顧みない父の放浪癖のため一家は常にその日暮らしを強いられていた。その上、姉が12の時、とうとう家族を見知らぬ田舎に置き去りにして姿をくらましてしまった。一番上の姉の下には、9歳、7歳、5歳の弟そして末はまだ乳呑児の6ヵ月の妹がいた。それまでは姉は常に弟妹達にとってもう一人の母親であったが、父が蒸発してからは、一層その荷は重くなった。生活のため母は冬は行商、春から秋までは出面とりとして働き、12歳の姉は6ヵ月の妹を背に弟の世話をやき、家事をこなした。
腹をすかせて泣く妹を背にくくりつけられて、冬の雪の中に立ちつくし、自身も頬を濡らしていた姉の姿は忘れることが出来ない。殆ど学校にも行けず私達兄弟のいわば犠牲になった姉は、17歳になると洞爺の食堂に住み込み店員として、家を出て行った。私の記憶の中の姉は笑顔を知らない、大人の女だった。しかし、あの頃の姉はまだ中学生から高校半ばの少女だったのだ。少女時代は、姉にはなかったのだ。私が16歳の時中3になった弟と2人で20Kの道を自転車で会いに行ったことがある。出て来た21歳の姉は粗末なトックリのセーターに白い三角巾を頭にかぶり、モンペのようなズボンを履いていた。三角巾の下からは無造作にたばねた髪がのぞいていた。化粧気のまったくない顔で、それでも微かに微笑んだ姉は、主の許しを取り付けてから窓のない自室に招いて、カレーライスをふるまってくれた。帰る時彼女は私達の手に百円札を一枚ずつ握らせてくれた。私は逃げるようにしてそこを後にした。姉に対して、ひどく悪いことをしたという意識があとあとまで残った。
姉はその後、同じ主が経営する札幌の店に移り、その後数ヵ所勤め先を変えやがて結婚したことを東京で知らされた。東京で自分の周りで見かける華やかな若い女性を見る時、時折姉のことを思い出すことがあった。少女時代を奪われた彼女に、その後の青春時代も無かったのではなかったかと。
姉とは東京に出る時、別れてから、45歳になるこの時まで2度しか会っていない。一度は私が仕事のついでに母の所に寄って3日ほど、泊った時、そして最後は4年前の母の葬儀の時だった。別れた時26歳で独身だった姉は、最初に会った時は4人の子の母となっていた。
姉の子は10歳の長女を頭に9歳の次女、5歳の長男、3歳の末娘で、4人はまるでギャングのように部屋の中で暴れ回っていた。借家住まいで間取り3室の仕切戸は全て取り払われて、一間のようにして使われていた。障子や襖は紙も畳みもボロボロにされて、部屋の奥に片付けられていた。ストーブの置かれた部屋は 、頑丈なビニールレザーが敷かれ、食事に使うテーブルの脚の一本はなくなっていて、代わりに、ブリキの缶が置かれていた。部屋の中はいつでもレスリングのリングに早代わりし、試合は5人の乱取乱闘スタイルだった。
子供達は底抜けに明るく、活発だった。すぐ前の海に出ても砂浜から突き出た危険なテトラの上を猿のように渡り歩いて、棒切れにつけた仕掛けで、アナゴを釣り上げ、釣りにあきるとテトラから海に跳び込んで水浴を楽しんだ。夜になっても彼等のエネルギーは静まらず、庭に出て花火に興じ、喚声は夜遅くまで収まらなかった。
私は自分の子供だったころを思い出していた。私達は5人兄弟だった。しかも3人が男の子だったので、部屋の中に型あるもので原型を留めているものは何もないといった有様だった。冬の長い北海道では、雪に閉じ込められた子供達は、どうしても部屋の中で体を動かすことになる。その上当時は兄弟が多かった。私は昔の自分を見せられているような気になった。ただしあの頃私達兄弟のレスリングは、遊びというよりは、いがみ合いだった。すきっ腹をかかえて、笑いを忘れていた私達のつかみ合いは、直ぐに誰かの泣き声で、みじめな気分で幕を閉じた。姉の4人の子供たちにはそんな暗さは微塵もなかったる彼等の乱闘は笑いで始まり、笑いで終わっていた。まるで野生の生物のような自由で奔放な彼等を見ていると、私は姉はとうとう自分の幸せを手にしたのだと思った。相変わらず化粧気もなく衣服も粗末なままであったが、子供達を見る彼女の顔には、始終笑いが溢れていた。彼女の人生は今、充分に満たされているのだと思った。
あれから7年が経ち突然姉はガンに倒れ、あっという間もなく、この世を去ってしまった。残された子供達は上から17歳、16歳、12才、10歳になっていたが、まだ1人立ちには間があった。彼等は突然母を失い、私と同様に、火葬場で立ち昇る白い煙を見ていた。子供達はここ数日、自分達の周りで起こっている出来事を唯全身で受け止めているだけで、一応に青白く疲れ切った顔をしていた。火葬場は林と畑にとりかこまれていた。畑には幾棟かのビニールハウスが今年1年の役目を終えて、次のシーズンを待っているのか、周りのビニールをはずされて手持ちぶさたに控えていた。私は足元から跳び立ったバッタを見るため腰を落としてしゃがみこんだ。その時草むらから現れた茶色のトラ猫と目が合った。
トラ猫は体が小ぶりで、私にはすぐメス猫だと分かった。彼女は暫く私を見ていたが、やがて三間ほどまで近付いて来て、それから声を上げて鳴いた。二声三声鳴き声をあげてから、彼女は私に背を向けて歩き始めた。二、三歩進んでから体はそのままに首だけを振り向けて立ち止った。彼女は、私を見てまた鳴き声を上げた。彼女はすぐにまた数歩歩みを進めそれから再び足を止め、振り向いて私を見て鳴いた。私ははっとなって、立ち上がった。
私の脳裏に鮮やかな記憶が甦った。おそらくはもう17、8年も経っているはずなのにその時、記憶はつい昨日のことのように、鮮明に瞳の奥に現れた。その頃、東京で住んでいたアパートは総2階建で、上下共に4軒ずつ入っていた。2階には外階段を上がり、ドアの前に屋根付の通路がある、いわゆる下駄履アパートである。そのアパートの2階に住んでいた。
夕方帰って来ると階段の中頃に茶トラのノラ猫が良く置物のようにきちんと前足を揃えて座っていた。近づくと茶トラは最初の内は、素早く階段を駆け下りて姿を隠したのだが、幾度も顔を合わせる内に、何故か、階段を逆に駆け上がり、まるで先導するかのように通路の先を進んだ。ドアを開けて中に入ると、脇が台所になっていて、窓が付いているので、そこを開けて様子を見ていると、茶トラは行き止りの通路をすぐに折り返し戻って行った。戻る時茶トラはチラリと上目使いに窓を見上げて去って行った。
次の日も同じ行動をとったので、戻る通路に煮干わ一つ投げ置いて見た。茶トラは迷わず煮干をくわえ、それから私の方を見てから、駆け足で去って行った。それから茶トラは殆ど毎日のように、帰ると階段の中頃に陣取って居て先導役を果した。私も用意しておいた煮干を投げた。時折階段に茶トラの姿が無い時があったが、そんな時でも煮干を置いておくと、朝には必ずなくなっていた。
茶トラはどう見てもノラだった。猫好きの私は街で猫の姿を見かけると、つい足を止めたくなる。直ぐ近くにいるとつい足を止めるし、逃げなければ何かしら話しかける。そんな時ノラ猫か飼い猫かはすぐに分かる。ノラは眼を合わせただけで逃げるが、飼い猫はそれがない。のみならず飼い猫のうちの何割かは声をかけると親しげに鳴いて寄ってくる。頭や体をすり寄せてくるのも珍しくはない。
ノラは人間に対して強い警戒心を持っているが、飼い猫は逆に親しみの感情を持っている。当然のことであろう。二者の違いはそれだけではなく、外見的にもはっきりとした違いがある。別に特別に猫に関心がなくてもこの違いは用意に判別できる。すなわち飼い猫は毛艶が良く奇麗であるのに対してノラは毛艶が悪く、汚れている。冬になるとこの違いはさらに顕著である。ノラの殆どは冬期間は目やにを出している。専門的に見ると、寒さにやられて、カゼなど何かの病気になっているのだろう。寒さの苦手な猫にとって冬は常に生きるか死ぬかの、大関門なのだ。年老いたものや、まだ幼いものは、冬を越すことは難しい。
昔保健所が充分に機能を発揮出来なかった頃は北海道でもやてらと野犬が眼についた。彼等はエサの確保ができさえすれば、冬を乗り切る。しかし猫はそうはいかないようだ。犬のような取り締まりがなくて飼い猫もノラ猫も自由に街を歩き廻っていても、猫が野犬のように増え過ぎて困るということは無い。時折どこかの島や漁港の街でノラ猫だらけというニュースが流れるが、あれはどちらかというと珍しいことである。少なくとも寒い地方でノラは冬の間に数を減らしてしまうのだ。その他に車時代に適応出来ずにいるという面もあろう。猫は何故か車によく轢かれる。
そんなこんなでノラ猫は放って置いてもどんどん増えるということはない。野生の動物はある特定の種類だけが増え続けることはない。必ずどこかで自然のコントロールを受けて、それで生物のバランスは取られている。人間だけがその枠からはずれ出している。犬は他の動物とは違って最も人間に密着して生きて来た。だから、犬の運命は人間と共にある。
しかし猫は少し違う。飼われている猫よりもノラ猫を見ていると特にそんな気がする。ノラ猫は街に生きる野生動物である。彼等には人間のあずかり知らぬ彼等の行き方があり、ルールがあるような気がする。
ところで茶トラは日本猫の雌猫であることもすぐに分かった。猫の雌雄の違いは、まずその大きさに現れる。次に顔の大きさが違う。どちらも雄の方が大きい。それに何よりも分かりやすいのは、後ろから見ると、雄はそれなりに立派な物をニケ付けているのが認められる。彼は人間のようにパンツを履かないから、これは隠しようがないのだ。もっとも隠す必要もないのだが。ただし最近の飼い猫はこの大事なものを取られたものが多いので、その点は注意を要する。やはりパンツを履かなかったのが災いしたのかも知れない。今にして私もパンツを履いていて良かったと思っている。人間だって、いつ何が起るか分からないのだから。
茶トラが雌猫で、毎日のように私の帰りを待って出迎えてくれるのでいつまでも茶トラでは他人行儀なので、トラのトを採ってトトと呼ぶことにした。幾日か経つとトトは私を先導した後通路の行き止まりまで行ってuターンして来るのをやめ、ドアの少し先で待つようになった。その次には煮干をくわえて運んで行かないで、その場で食べるようになり、食べ終わると次を催促して、窓を見上げてねばるようになった。こうなるとついつい一匹が二匹になり、その内何か食べ残しの竹輪やら、ソーセージやら、を与えるようになってしまった。
トトはノラだから何でも食べるし、いつでも腹を空かせている。余り物とはいっても人間からもらう食べ物は、飛び切りのご馳走である。味を憶えると離れられなくなる。私もだんだん彼女が可愛くなってくる。踏み留まる一線を忘れてしまう。深入りというやつである。気がついたら窓の敷居の上に煮干を置くようになり、次にはドアの内側の上りがまちに彼女専用の皿を置くようになってしまった。私は完全に越えてはならない一線を越えた関係になってしまったのだが、愚かにもその自覚がなかった。男とは本当に無責任な生き物なのだ。この時点でも、私は彼女を我家の同居者として受け入れる考えはまったくなかったのだ。第一アパートでは犬猫は飼ってはいけない契約になってた。
それなのに私は彼女を家の中に入れ、食べ物を与えてしまったのだ。しかしさすがにトトは誇り高いノラである。生れた時からのノラは、人間に依存して生きるのを潔しとしない。エサを貰ったからといって、身をうったりはしない、彼女達は誇り高い生き物なのだ。
トトが窓の上の煮干を食べるまでには、10日以上を要した。窓の上から家の中の床に下りて皿に近付くまでにはさらに10日以上を費やした。どの段階でも彼女は全身の毛を立てたように神経を張りつめ、鋭い警戒の姿勢を部屋の奥に座っている私からそらさなかった。くわえていけるエサなら、必ずくわえて素早く外に退避した。私はだんだん狡猾になった。家の中の皿に慣れた頃を見計らって、ネコ飯を出した。これはご飯にかつ節をまぜたものにみそ汁をかけたものである。これではくわえて退散することは出来ない。
彼女は戸惑い一度は食べずに退散した。しかし二度目には一口食べては暫くはじっとこちらを見た。また一口を食べてはこちらを伺い見た。そうして三分の一ほどを食べた処で身を翻して出て行った。私はネコ飯は続けなかったが、3回に1度くらいにして繰り返した。
この頃になると、トトはやって来ると通路で一声か二声、自分が来たことを告げて鳴くようになっていた。
やがてトトはネコ飯を完全に平らげてから帰って行くようになった。この頃になると、私の願望は抑えがきかなくなっていた。次に私が願ったのは、彼女が台所の奥のたった一つしかない部屋にまで入って来て、私が食事をしている脇で彼女の皿で物を食べることであり、さらに、さらにその先は遂に彼女を私の膝の上に抱くことであった。
彼女が生れ落ちた時からノラ猫人生を歩んで来たことは、それまでにもう充分理解できた。のみならず彼女は正統派ノラであって、未だかって食であろうと住であろうと、人間に依存したことは一度もないことは明確だった。もちろん彼女はかつて一度も人の手が近付くことを許したことはなく、ましてやその手によって持ち上げられ膝の上に抱かれることなど、あり得ないことに思えた。あり得ないと思い至った時から、私の頭にそのことが取り付いて離れなくなった。
人間の欲というのには切りが無い。私は彼女から充分に与えられていた。誇り高い彼女が、どれほど多くを譲り、私に心を許してくれたか、もう充分すぎるというものである。それなのに、この上さらに多くを私は求めていた。私は彼女を膝に抱くという願望を諦め切れなくなって行った。私には彼女を自分の飼い猫として迎えることは出来なかったし、今までの行動から、彼女にもそんな気がないことは明瞭だった。それなのに、私は彼女を膝に抱くという願いを諦め切れなかった。
彼女が上がった窓から、ドアの内側の床に下りるということが、どれほど重大な決断を要することなのかは、今までの様子を見て私は良く理解していた。たった一度の間違いで、全てが失われてしまうことは、容易に推察できた。
私は急がなかった。少しずつ、少しずつ、気を長く構えて、皿は回数を重ねる度にじわじわと奥の部屋に移動して行った。その度に彼女の緊張は高まって行くのが分かった。それでもトトは食べ終わるまで逃げ出さず、私との距離を縮めていった。
私の脇に置かれた皿に身を沈めた時、さすがに暫くは彼女は食べようとしなかった。じっと身を固くしている彼女をよそに、私は静かに茶を飲んでいた。
トトの眼が私の動きをじっと追っていた。私はトトに話しかけた。「茶トラくん、君をトトと呼ばせてくれ。トトは僕の友達だ。今日は何をしてたのかな」私はたわいも無い言葉を切れ間もなく、ポロポロ、ポロポロとまるで手にしたリンゴをころがしてやるように、彼女にかけ続けていた。彼女は伏せていた耳を少しずつ立て、やがてネコ飯を食べ終わると、そのまま顔を上げずにそろりと向きを変え、それから大急ぎで出て行った。
次の日もトトは私の脇で食事をした。私は言葉をかけ続け、話し続けた。その後、時々彼女が現れない日があった。たぶん私の帰宅の時間と何かの都合でトトの方がいつもの時間に来れなくなっていたのだろう。私は一定時間しか台所の窓を開けておかなかったので遅くに来て窓が閉じていると、トトはそのまま黙って帰ったのだろう。テーブルの脇まで来るようになって5、6度目かに、食べ終わった時、私はついに彼女に手をのばし、そっとその背に触れた。
私の手が伸びた瞬間、一瞬彼女は身を固くし、わずかに体を低くした。私の指が彼女の背に静かに、そっと、ほんのそっと触れた。彼女は動かなかった。私は話しかけ続けていた。「トト、お前の背にほんのちょっとだけ触らせておくれ。ほんのちよっとでいいんだ。お前はとても可愛いから、どうしても触れてみたいんだ。ほんのちよっとでいいんだ。どうか驚かないでおくれ。どうか怖がらないでおくれ」私はトトがじっとしているのを見とどけてから、その背を静かになでた。
その瞬間、私はノラ猫という生き物が分かった。そのひとなでで、私の手にノラ猫の全てが電流のように身体中に流れた。
トトの毛はまるで秋の田に積み上げた稲藁のようにその1本1本が固く乾いていた。私の知っているしなやかで、ビロードのように柔らかな猫の毛の手触りは微塵も感じることはできなかった。荒く固く、まるですさんだように乾いたその手触りは、彼女の人生を、そのままに伝えていた。私はそっと手を引いた。その時を待っていたかのように、トトは少し顔を上げて私を見た。そしていつもの通りそろりと背を向けて去っていった。
その時私の中で、「もう充分だろう」と言う声が聴こえた。確かにその声を耳の奥に聴いたにもかかわらず、私は尋ねてくるトトに触れることをやめることが出来なかった。そしてとうとう、私はトトを両手に抱き上げて、膝の上に乗せたのだ。トトは両目を一杯に見開いて、全身を硬直させ、それでもじっとなすがままに身を預けた。丸めた体を横たえた彼女は私を見続けていた。ほんの一呼吸の間であったと思う。私は両手を離した。トトはそろそろと体を起こして膝から下りるやいなや、後ろを見ずにいつもより早足で去って行った。私の膝の上には彼女の荒い毛の感触と、小さく軽い体のぬくもりが残った。
本当にトトは哀しいほどに、小さく軽かった。私はきっぱりと、もうこれ以上彼女に触れることはやめようと思った。何にでも聖域というものがあることに、その時になつて私はやっと気が付いたのだ。
次の日から私はトトの皿をまた台所の窓の下に戻した。トトは毎日必ず来るというのではなかったが、来ると例え煮干でも、くわえては行かず、そこで食べ終わってから帰って行った。
夏も真っ盛りの連日の猛暑が始まるとトトは姿を見せなくなった。いつまでも続く暑い日にそろそろ夏バテが全身にまわり始めた頃、珍しく階段で夕日を背に受けたトトが待っていた。いつもの通り通路を先導するかと思ったら、私を認めた彼女は素早く階段をかけ下りて足元を横切った。アパートの隣はブロックの塀を巡らせた庭の広い戸建ての家だった。正面側には塀はなく、植え込みで道路と仕切りを作り、ブロックの塀はアパートの通路と平行して作られていた。正面と反対側が、あまり手の入らない植え木がこみ合った庭になっているのがアパートの2階の通路から見ることが出来た。トトはこの隣家の玄関前にまで戻ってから振り返り私を見た。
私が立って見ていると一声鳴いて、それから少し進んでまた立ち止って私を見て鳴いた。その様子はどう見ても私を呼んでいるように見えた。私は戻って彼女に近付いた。するとトトは隣家の塀の内側の通路に姿を隠した。私はためらいながらも玄関前に入って通路を覗いた。トトは幅一間ほどの家と塀の間の通路を半分ほど進んだ所で私を待っていた。彼女はまた一声鳴いてから背を向けて歩いて行った。
私は躊躇した。これ以上は家人の許可なしに入ることは、どう見ても誤解を招く怪しい行為であり、歴とした家宅侵入である。トトはおかまいなしにどんどん進んで行く。とうとう植え込みの中に姿を消してしまった。彼女の先ほどとは調子の変わった抑えた声が何度か聞こえた。私は思い切ってさらに幾歩か進んだ。
すでに通路の三分の一は入ってしまった。自然に腰が下がり、忍び足になっていた。見つかったら、説明がつかなくなるという不安が頭をかすめた。また植え込みの奥の方でトトの微かな声が聞こえた。もうこれ以上は無理だと思った。少し待って様子を覗ってから腰をかがめたまま体を返しかけた。その時チラリと植え込みの下にトトの姿が見えた。私はそのままの姿勢で視線だけを庭に向けていた。
トトはゆっくりと歩いて来た。完全に姿を現した彼女は植え込みに向かってまた低く二、三度鳴いた。今まで聞いた事の無い、優しい、なんだか甘えているような声だった。私は動けなくなり、いつの間に完全にしゃがみ込んで体もトトに向けて見ていた。トトが1間ほど植え込みから離れた時、何か小さな鞠のようなものが、幾つもころころと伸びた芝の中をころがって出て来た。鞠はたちまちトトの周りをとりかこんだ。トトはその動く鞠をつれて私の方に近づいて来た。3間ほど先まで近づいたトトは用心深く辺りを見廻しながら、すでにしつかりとした足取りでまとわりつく子供達を順番になだめるようになめている。
全部で5匹、子供達は明らかに私を気にして用心深く窺い見ながらも、トトの傍を離れようとしない。トトは子供達をあやしながらも私から眼を離さなかった。私はしやがみ込んだまま、彼女を見ていた。言葉が喉の奥まで出かかった。何か言ってやりたかった。しかし、勝手に入り込んだ人の家の窓の下で声を出すのは、さすがに出来なかった。それに明らかにトトはそっと隠れ場所から子供達を連れ出して、危険を犯している。私は唯黙って見ていた。
子猫たちは声を出さなかった。すでに生まれてから一ヶ月近く経っているのだろう、歩くたびに大きく体は揺れたが、それでも動きは素早かった。やがてトトは喉の奥からくぐもった声を出しながら再び植え込みの中に入って行った。子猫たちはやっと恐ろしい場所から離れられるといった様子で我先にと植え込みの中に飛び込んで行った。
トトの子供達は既にノラ猫として生きる術をしつかりと体の中に刻み込んでいるようだった。私も腰をかがめたまま、急ぎその場を離れた。
トトが私に子供達を見せに来てから幾日も経たない内に、私は家賃を払いに行った場で、大家に言われた。家主は同じアパートの一階の半分を使って住んでいたのだが、ノラ猫が自分の庭に来るスズメを獲るので、エサをやらないでくれと言った。店子としては従うしかなかった。別に家主に言われたからではないが、仕事の都合から私は住いを移ることになった。
トトが子供達を見せに来てから一ヵ月ほど後のことだった。まるで逃げるようにして去ったあのアパートのことは忘れることが出来ない。誰も私に罪を問うことはない。しかし、私はあそこで許しがたい犯罪を犯していた。彼女は決してそのことを忘れなかっただろうし、許しもしなかっただろう。
トトだと思った。眼の前の草叢からじっと私を見て、何度も振り返って鳴く茶トラは、トトだと思った。一瞬の内に私は16年前に引き戻されていた。あの時、彼女は幾度も振り返って、私を呼んだ。そして自分の子供達を見せたのだ。今またトトは私を呼んでいた。
私は呼ばれるままに従って行った。彼女はビニールハウスの中に入って行った。収穫を終えたハウスの中は踏み固められた通路の他は、低い雑草が生え、あちこちに、プラスチックの箱や、長い板や、鉄のパイプなどが、整理されて積んであった。屋根を残して周囲のビニールははずされていたが、それでもハウスの中はまだ暑かった。茶トラは通路をどんどん進んで行き、時折振り返っては、私がついて来るのを確認していた。間違いなかった。彼女は疑いようもなく、私を呼んでいるのだった。
4人の姉の子たちも私の後に従いて来ていた。ついに茶トラはダンボールが幾つか並べて置いてある所で立ち止り、その先には進まなかった。彼女は一度ダンボールの中に首を入れ、それからその周りを廻りながら鳴いた。私達がダンボールの傍に立っても、彼女は一、二メートルしか離れようとはせず、鳴き続けた。ダンボールの中にはタオルやら、何か古いTシャツのようなものが、敷かれ、猫の毛が万遍なく付いていた。私が予想していた子猫の姿はなかった。
茶トラは私達を見て鳴き続けていた。その悲しげな声と訴えるような眼を見て、私ははっきりと理解した。このダンボールの中には、つい数日前かあるいは昨日までか、いやつい先刻までかも知れないが、確かにこの中には彼女の子供達が居たのだと。
「私の子供を返して」彼女はそう言って訴えているのだ。「私の子供を探して」と言っているのかも知れなかった。いずれにしても彼女は子供を奪われ、私に訴えていた。私はその場にしやがみ込んでダンボールの底に手の平を押し当てた。そこにはもう、生き物の温かみは残っていなかった。やがて私は途方にくれて立ち上がった。その場を後にする私達を見ても茶トラはその場を動かず、ただ一層悲しげに鳴いた。
追われるようにしてハウスの外に出た私は思わず空を見上げて大きく息を吸い込んだ。
澄み切った9月の空の下で煙突から立ち昇る白く微かな煙は、まだ小さく棚引いていた。
末の姪がポツリと言った。
「お母さんも私達を探しているのだろうか」
私は言葉に詰まり何も言うことが出来なかった。
時折吹き抜けていく風がザワザワと周りの、早くも紅葉の始まった樹々を鳴らした。
その音が私には、強い絆で結ばれた、母と子の呼び会う声に聴こえた。 H20、10、7