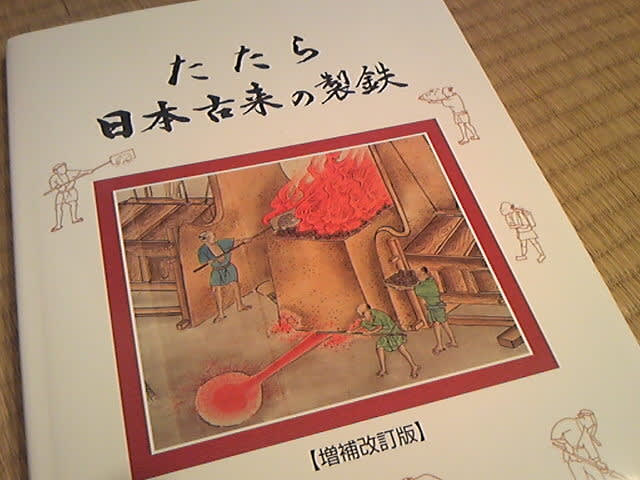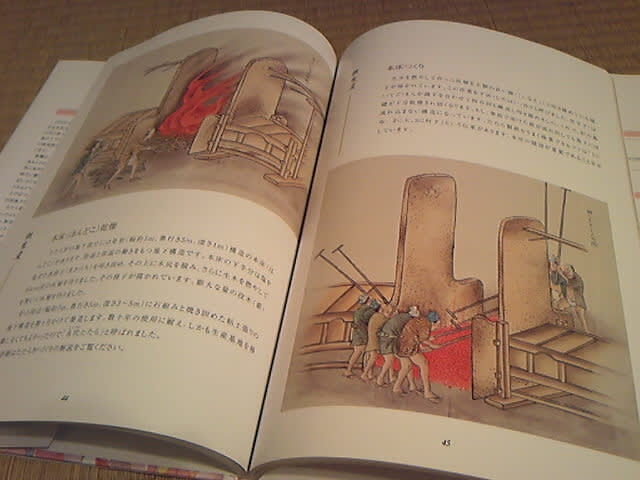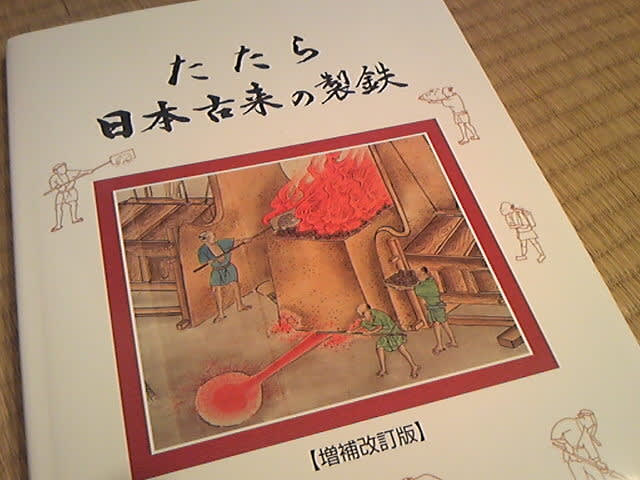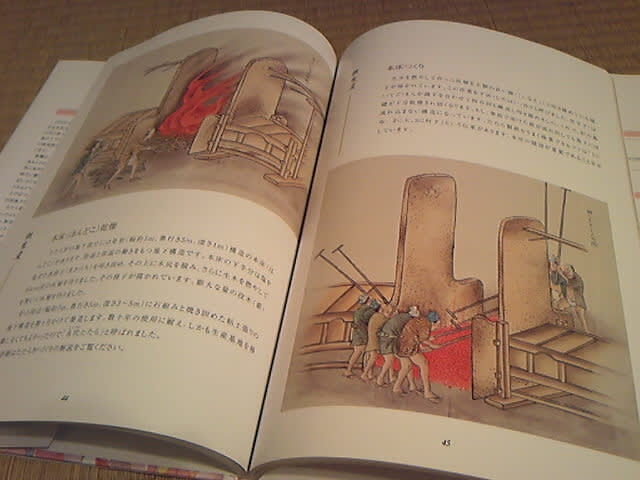不定期にて連載投稿しています、「洋鉄と和鉄」の続きです。
以前の投稿は以下のリンクより、ご覧いただけます。
・
「洋鉄と和鉄(その2)」(2012年04月28日):S-C材について
・
「洋鉄と和鉄」(2012年03月18日):現代の鉄とは何か?
今回は、工具類に用いられる洋鉄(現代の鉄)についてご紹介します。
工具類に用いられている鋼は、3種類に分類できます。「炭素工具鋼」、「合金工具鋼」、そして「高速度工具鋼」です。
○「炭素工具鋼(SK材)」について
この鋼材と前回の構造用鋼との違いは、含有される炭素の量です。
何度もいいますが、構造用炭素鋼は炭素含有量が0.6%以下、それ以上が炭素工具鋼とされています。
工具用の鋼材に必要な性能は、「硬いこと」、「摩耗しないこと」、「粘りがあること」といったところでしょうか。これらの性能は、実は炭素の含有量と密接な関係があります。
鋼の硬さだけを考えると、炭素の含有量が0.6%であろうが1.0%であろうが、ほとんど大差ありません。
しかし、炭素工具鋼では、炭素含有量が0.6%以上です。
では、なぜ0.6%以上に炭素含有量を調整するのでしょうか?
実は、鋼の性質として、炭素含有量を増やせば、耐摩擦性に優れた鋼が出来るからなのです。
では、なぜ炭素が多いと耐摩擦性に優れるのでしょうか?
それは「カーバイド(セメンタイト)」と呼ばれる構造と、密接な関係があります。
鋼材を熱処理すると、鉄の中に多くの炭素を溶け込ませている状態から急に冷やされることで、炭素が過飽和の状態になります。
鉄の中の過飽和状態の炭素は、マルテンサイトという組織に変わります。これは鋼の中でも最も硬い構造です。
そして、その中にさらに硬い球状のカーバイドを均一に分布させることによって、例えば硬いコンクリートの中に、さらに硬い鉄球をたくさん混ぜ込んだような状態となり、耐摩擦性に優れた鋼を作リ出す事ができるのです。
このカーバイドは、炭素の含有量が多ければ多いほどたくさん構成され、耐摩擦性に優れた性能を示すのですが、同時に脆くもなります。
従って、耐摩擦性が必要な用途では炭素を多く含有させ、粘り強さが必要な用途では、炭素の量を制限することで、今日の鋼の種類が生まれました。
SK材では、炭素の量は「1種」から「7種」までに分類されています。
・1種 : 1.30% ~ 1.50% → カミソリ、ヤスリ など
・2種 : 1.10% ~ 1.30% → ドリル、バイト など
・3種 : 1.00% ~ 1.10% → タガネ、ゼンマイ など
・4種 : 0.90% ~ 1.00% → キリ、斧、タガネ など
・5種 : 0.80% ~ 0.90% → ペン先、ノコギリ など
・6種 : 0.70% ~ 0.80% → スナップ、刻印 など
・7種 : 0.60% ~ 0.70% → プレス、ナイフ など
用途別に見るとSK材はかなり硬く、切削にも十分使用できそうな気もするのですが、切削となるとノコギリ程度が精一杯です。その理由は、鋼が熱に弱いからです。
炭素工具鋼は、200℃程度で焼き戻し処理をしているため、使用中にこの温度を超えると、急激に焼き戻ってしまいます。
さらに、炭素工具鋼は、球状に分布するカーバイドが結晶の中でひも状に生成してしまい、脆くなったり変形したりしてしまい、商業的には商品化できないという問題点がありました。
そのため、カーバイドをひも状から球状にする技術が開発されました。
これにはひも状になったカーバイドを細かく砕くために、素材を叩いたりしごいたりすることなのですが、刀匠は作刀過程で球状カーバイド加工を行っていることになります。
そして、その後に熱処理を行うことで、カーバイドは球状化されます。これを「球状化焼き鈍し」といいます。
球状化焼き鈍し処理の後、工具鋼の焼き入れを行うわけですが、これも前回の構造用炭素鋼のそれとは違い、カーバイドを母材に溶け込ませる必要があります。
鋼の焼き入れは、加熱する事により組織がオーステナイトに変わります。
これを急冷することで焼きが入りますが、炭素工具鋼では、このオーステナイトの中にカーバイドを溶け込ませなければなりません。
このためには、オーステナイト組織を保つために、熱的な保持時間が必要になります。これにより、母材がより硬くなるわけです。
焼き入れが終わると、150℃~200℃くらいで焼き戻しを行います。
このような複雑な工程は、すべてがカーバイドの球状化処理のために行われているのです。
鋼にとって重要なカーバイドですが、その大きさや量などは、JIS規格で厳密な規定があるわけではありません。そのため、同じ工具でも、製造国やメーカーが違えば製法も違うため、物の良し悪しがでてしまいます。
良く斬れて長切れする刀を作る刀匠。鑑賞的価値を優先する刀匠。これらの違いがはっきりと出てしまう要因の一つに、カーバイドの存在があるのかもしれません。