
■〔粋〕とは何か?
〔いき〕は、〔粋〕あるいは〔意気〕と表記し、〔粋〕はまた〔すい〕とも読む。
いずれも、江戸庶民文化の確立を背景とした、近世日本文化のキーワードのひとつです。
〔わび、さび〕が仏教的な概念をもつ抽象度の高いことばであるのに対し、〔いき〕は誰にもわかりやすく、現代でも日常的に使われていることばではないでしょうか。
「あの人いきだね」
「いきなはからい」
「こいきなつくりの建物」
…などなど。
〔いき〕は江戸、〔すい〕は上方由来のことばとされ、それぞれ微妙に定義が異なっていますが、辞書の定義よりも明快に説明しているブログがありましたので、以下をご参照ください。
※HP「粋だね~の意味」について考える(団塊オヤジの短編小説)
http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/02/post_670b.html
■世界共通〔粋〕の文化
さて、言の葉庵では〔美的概念〕〔男女の綾〕というよりも、〔いき〕には場を読み、円滑なコミュニケーションをはかりつつ、決して表に立たない「かっこいい行為」「胸のすくようなはからい」という定義が成り立つのではないかと考えています。
陰徳といえば、何かじめじめした印象をもってしまいますが、「いきなはからい」にはすかっと突き抜けたなんともいえない爽快感がただようもの。
このような〔いき〕は近世日本だけではなく、世界中で庶民共通のモラル、美意識として実践され、また様々な創作作品に描かれています。
スタインベックの古典的名作『怒りの葡萄』。天災と資本主義により故郷を追われた貧農の一家が夢の新天地を求めて、カリフォルニアを目指す苦難の旅の長編小説です。
本作には、主要プロットとは別に様々なサブストーリー、エピソードが挿入されています。主人公一家とどこか似通った庶民たちの悲喜こもごもの物語が暖かなまなざしでつづられる。
無一文で互いに身を寄せ合うしか生き抜くすべのない、弱い人々。ほとほと困窮した人には、それより少しましな人から救いの手がのべられます。しかし貧乏であればあるほど、切迫していればいるほど、他人の施しはありがたく、同時に辛いもの。
恩着せがましくなく、相手に恥を与えず、さらりと自然に助けてやることが、この小説に登場する貧しい人たちの誇りであり、その行為こそ〔いき〕の原点なのではないでしょうか。
『怒りの葡萄』があざやかに描く〔いき〕を、貧しい旅人たちのエピソードから要約してお届けしてみましょう。
■スタインベック『怒りの葡萄』要約
66号線沿いにある、ハンバーガー・スタンド。
中年のウエイトレス、メエと、その夫無口なアルがキッチンをとりしきっている。どこにでもある小さなドライバーの店だ。
かれらにとって上客は、長距離トラックの運転手たち。うまいコーヒーをいれ、愛想よく送り出せばまた来てくる良い客である。その他、西へと向かうオンボロ車に家財一式を山と積み上げた移民の集団は、金をもたず、すきさえあれば水や備品をくすねる連中。メエに「クソッタレ」と呼ばれている招かれざる客たちであった。
一台の輸送トラックが店の前に止まった。カーキ色の乗馬ズボンと短い上着、ぴかぴかのひさしのついた軍隊帽の男。そしてもうひとり、運転助手がトラックから降りてくる。
「ハイ!メエ」
「あらまあ。ねずみのビッグ・ビルじゃない。いつ戻ったのよ」
「一週間前さ」
二人の男は店に入り、ジュークボックスに五セント玉を放り込んだ。
<―ありがとう。おぼえていてくれて、浜辺の日焼けした肌を―君は悩みの種(ヘッドエイク)だったにしても、退屈(ボア)では決してなかった>
ビング・クロスビーの黄金の声が店内にしみわたる。
助手はスロットマシンに五セントを入れ、四個せしめたがたちまち全部スッてしまう。
熱いコーヒーと焼きたてのバナナクリームパイをほおばるビルは、ハイウエイをそれ、こちらにやってくる1926年型のナッシュのセダンに目をとめた。後部席に袋や寝具、鍋釜をぎっしりと積み上げ、その上に男の子ふたりが乗っている。
「メエ、テーブルの上のものは隠しといた方がいいぜ」。
メエはカウンターをまわり、店の入り口に立った。
車から降りてきた男は、グレーのウールのズボンに青いシャツ。髪は黒く、あごはとがり、シャツの背中と脇には濃く汗がにじんでいた。子どもたちは裸で、つぎはぎだらけのオーバーオールを身に着けたきり。髪は短くハリネズミのように一面に突っ立ち、顔には埃の縞模様ができていた。
男は聞く。
「水を少しもらえませんか。おくさん」
「いいわよ。使いなさい」
メエはしかし、肩ごしに小声で、
「大丈夫。ホースから目を離さないから」
と奥に伝える。
男はラジエーターにホースを突っ込み給水すると、子どもにホースを渡した。子供たちはホースを上に向け渇いた馬のように水をむさぼり飲んだ。
「わしらにパンを一山わけていただけませんか?おくさん」
「うちは食料品店じゃないから。パンはサンドイッチにするんだよ」
「わかっていますよ。でもわしらはパンがいるんです。腹ペコなんです。この先長い間なんにもないっていうもんで」
「サンドイッチを買ったら?おいしいハンバーガーだってあるのよ」
「そうしたいのは山々なんだが、ムリなんです。十セント玉一個で家族みんな食べなきゃならないんで」
「十セントじゃ買えないわね。うちには十五セントのしかないから」
メエの背後から亭主の太い声が響いた。
「しょうがねえや。メエ、パンをやりな」
亭主は作りかけのポテトサラダに目を落としている。メエは肩をすくめ、夫とトラック運転手たちをちらっ見た。
メエが入り口のドアを押さえていてやると、その男は汗臭い身体で店に入ってきた。
男の後をおずおずと追ってきたふたりの子ども。店に入るとキャンディー・ケースの前で釘付けとなる。ふつうの子どものようにそれをせびろうとするわけでもなく、この世にこんなものがあるのか、とただただ驚きじっと見つめているのである。
メエは、蝋紙で包んだパンをカウンターに置く。
「一本、十五セントよ」
男は帽子をかぶり直し、
「あの。十セント分だけ切ってもらうわけにはいきませんか」
という。亭主のアルがどなる。
「メエ、一本丸ごとやっちまいな」
男ははじめて亭主の方を見た。
「いや。十セント分だけ売ってもらえばいいんで。わしらはカリフォルニアに着くまで細かく計算しているんですよ。だんな」
メエはあきらめ顔で十セントでいいというが、男はそれではパンを盗むことになる、と反論した。
「かまわないわ。アルがもってけっていうんだもの」
パンがカウンターの上で男の方に押しやられる。男は尻ポケットから財布を出すと、ひもをゆるめ口をあけた。中にはコインとしわくちゃの札がぎっしり。
「こんなにつつましくするのも変だと思うかもしれませんが」
男は弁解した。
「わしらはこの先千マイルも行かなきゃならん。はたしてたどり着けるかどうかもあやしいもんですから」
財布の中から十セント玉をつまみ出そうとすると、はずみで一セント銅貨がくっついてきてカウンターに落ちる。一セント銅貨を追った男の目が、キャンディー・ケースの前の子どもの姿をとらえた。
男はのろのろとそっちの方へ歩いていき、だんだら模様がついた長いペパーミントキャンディーを指していった。
「こいつは一セントの飴ですか。おくさん」
「どの飴?」
「ほら、あの縞模様のやつですよ」
子どもたちはメエの顔を見つめ、緊張で身体を固くした。
「ああ―あれ。ええっと、あれは違う。―あれは二本で一セントよ」
「そうですかい。じゃあ二本ください」
男は一セント銅貨をいとおしむようにそっとカウンターへ置きなおした。
子どもたちは止めていた息をふっとついた。二人はメエからおずおずと飴を受け取ると、そのまま手にぶら下げて、互いにぎこちない笑いをうかべ顔を見合わせる。
「ありがとうよ。おくさん」
男はパンを取り上げると、店から出ていき車に戻った。子ども二人はシマリスのようにすばしっこく荷物の上に飛び乗り、中にもぐりこんで見えなくなった。
おんぼろのナッシュはエンジンをかけ、けたたましい音と青く油臭い煙を残し、ハイウエイへとよじのぼっていく。
店の夫婦とトラック運転手は、ものもいわずじっと見送っている。
ビッグ・ビルがくるりと振り向くと、
「ありゃあ二本一セントのキャンディーじゃなかったぜ」
「それが、あんたと何の関係があるのよ」
メエがかみつく。ビルはぼそりという。
「あれは一本五セントだ」
助手は、
「ぼちぼち行こうとするかね」
と椅子から腰をうかす。
二人はポケットに手を突っ込み、ビルが銀貨をカウンターに置く。それを見た助手はもう一方のポケットから同じ銀貨を一枚出し、わきにならべた。
「あばよ」
メエがあわてて叫ぶ。
「ちょっと!待って、お釣り、お釣り」
「何いってやがる」
ビルはドアをバタンと閉めた。
巨体をゆるがしながら、走り去るトラックを見送っていたメエは小声で亭主によびかけた。
「ねえ」
アルはハンバーグをこねる手を止め顔をあげる。
「何だ」
「あれ見てよ」
メエはカウンターを指さし、アルは近くまで歩いていってしばしながめた。
半ドル銀貨が二枚。
亭主は仕事に戻り、メエはつぶやく。
「やっぱりトラックの運ちゃんだわ」
「…あとはみんなクソッタレだ」
(スタインベック『怒りの葡萄』 要約 水野聡2014年9月)
〔いき〕は、〔粋〕あるいは〔意気〕と表記し、〔粋〕はまた〔すい〕とも読む。
いずれも、江戸庶民文化の確立を背景とした、近世日本文化のキーワードのひとつです。
〔わび、さび〕が仏教的な概念をもつ抽象度の高いことばであるのに対し、〔いき〕は誰にもわかりやすく、現代でも日常的に使われていることばではないでしょうか。
「あの人いきだね」
「いきなはからい」
「こいきなつくりの建物」
…などなど。
〔いき〕は江戸、〔すい〕は上方由来のことばとされ、それぞれ微妙に定義が異なっていますが、辞書の定義よりも明快に説明しているブログがありましたので、以下をご参照ください。
※HP「粋だね~の意味」について考える(団塊オヤジの短編小説)
http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/02/post_670b.html
■世界共通〔粋〕の文化
さて、言の葉庵では〔美的概念〕〔男女の綾〕というよりも、〔いき〕には場を読み、円滑なコミュニケーションをはかりつつ、決して表に立たない「かっこいい行為」「胸のすくようなはからい」という定義が成り立つのではないかと考えています。
陰徳といえば、何かじめじめした印象をもってしまいますが、「いきなはからい」にはすかっと突き抜けたなんともいえない爽快感がただようもの。
このような〔いき〕は近世日本だけではなく、世界中で庶民共通のモラル、美意識として実践され、また様々な創作作品に描かれています。
スタインベックの古典的名作『怒りの葡萄』。天災と資本主義により故郷を追われた貧農の一家が夢の新天地を求めて、カリフォルニアを目指す苦難の旅の長編小説です。
本作には、主要プロットとは別に様々なサブストーリー、エピソードが挿入されています。主人公一家とどこか似通った庶民たちの悲喜こもごもの物語が暖かなまなざしでつづられる。
無一文で互いに身を寄せ合うしか生き抜くすべのない、弱い人々。ほとほと困窮した人には、それより少しましな人から救いの手がのべられます。しかし貧乏であればあるほど、切迫していればいるほど、他人の施しはありがたく、同時に辛いもの。
恩着せがましくなく、相手に恥を与えず、さらりと自然に助けてやることが、この小説に登場する貧しい人たちの誇りであり、その行為こそ〔いき〕の原点なのではないでしょうか。
『怒りの葡萄』があざやかに描く〔いき〕を、貧しい旅人たちのエピソードから要約してお届けしてみましょう。
■スタインベック『怒りの葡萄』要約
66号線沿いにある、ハンバーガー・スタンド。
中年のウエイトレス、メエと、その夫無口なアルがキッチンをとりしきっている。どこにでもある小さなドライバーの店だ。
かれらにとって上客は、長距離トラックの運転手たち。うまいコーヒーをいれ、愛想よく送り出せばまた来てくる良い客である。その他、西へと向かうオンボロ車に家財一式を山と積み上げた移民の集団は、金をもたず、すきさえあれば水や備品をくすねる連中。メエに「クソッタレ」と呼ばれている招かれざる客たちであった。
一台の輸送トラックが店の前に止まった。カーキ色の乗馬ズボンと短い上着、ぴかぴかのひさしのついた軍隊帽の男。そしてもうひとり、運転助手がトラックから降りてくる。
「ハイ!メエ」
「あらまあ。ねずみのビッグ・ビルじゃない。いつ戻ったのよ」
「一週間前さ」
二人の男は店に入り、ジュークボックスに五セント玉を放り込んだ。
<―ありがとう。おぼえていてくれて、浜辺の日焼けした肌を―君は悩みの種(ヘッドエイク)だったにしても、退屈(ボア)では決してなかった>
ビング・クロスビーの黄金の声が店内にしみわたる。
助手はスロットマシンに五セントを入れ、四個せしめたがたちまち全部スッてしまう。
熱いコーヒーと焼きたてのバナナクリームパイをほおばるビルは、ハイウエイをそれ、こちらにやってくる1926年型のナッシュのセダンに目をとめた。後部席に袋や寝具、鍋釜をぎっしりと積み上げ、その上に男の子ふたりが乗っている。
「メエ、テーブルの上のものは隠しといた方がいいぜ」。
メエはカウンターをまわり、店の入り口に立った。
車から降りてきた男は、グレーのウールのズボンに青いシャツ。髪は黒く、あごはとがり、シャツの背中と脇には濃く汗がにじんでいた。子どもたちは裸で、つぎはぎだらけのオーバーオールを身に着けたきり。髪は短くハリネズミのように一面に突っ立ち、顔には埃の縞模様ができていた。
男は聞く。
「水を少しもらえませんか。おくさん」
「いいわよ。使いなさい」
メエはしかし、肩ごしに小声で、
「大丈夫。ホースから目を離さないから」
と奥に伝える。
男はラジエーターにホースを突っ込み給水すると、子どもにホースを渡した。子供たちはホースを上に向け渇いた馬のように水をむさぼり飲んだ。
「わしらにパンを一山わけていただけませんか?おくさん」
「うちは食料品店じゃないから。パンはサンドイッチにするんだよ」
「わかっていますよ。でもわしらはパンがいるんです。腹ペコなんです。この先長い間なんにもないっていうもんで」
「サンドイッチを買ったら?おいしいハンバーガーだってあるのよ」
「そうしたいのは山々なんだが、ムリなんです。十セント玉一個で家族みんな食べなきゃならないんで」
「十セントじゃ買えないわね。うちには十五セントのしかないから」
メエの背後から亭主の太い声が響いた。
「しょうがねえや。メエ、パンをやりな」
亭主は作りかけのポテトサラダに目を落としている。メエは肩をすくめ、夫とトラック運転手たちをちらっ見た。
メエが入り口のドアを押さえていてやると、その男は汗臭い身体で店に入ってきた。
男の後をおずおずと追ってきたふたりの子ども。店に入るとキャンディー・ケースの前で釘付けとなる。ふつうの子どものようにそれをせびろうとするわけでもなく、この世にこんなものがあるのか、とただただ驚きじっと見つめているのである。
メエは、蝋紙で包んだパンをカウンターに置く。
「一本、十五セントよ」
男は帽子をかぶり直し、
「あの。十セント分だけ切ってもらうわけにはいきませんか」
という。亭主のアルがどなる。
「メエ、一本丸ごとやっちまいな」
男ははじめて亭主の方を見た。
「いや。十セント分だけ売ってもらえばいいんで。わしらはカリフォルニアに着くまで細かく計算しているんですよ。だんな」
メエはあきらめ顔で十セントでいいというが、男はそれではパンを盗むことになる、と反論した。
「かまわないわ。アルがもってけっていうんだもの」
パンがカウンターの上で男の方に押しやられる。男は尻ポケットから財布を出すと、ひもをゆるめ口をあけた。中にはコインとしわくちゃの札がぎっしり。
「こんなにつつましくするのも変だと思うかもしれませんが」
男は弁解した。
「わしらはこの先千マイルも行かなきゃならん。はたしてたどり着けるかどうかもあやしいもんですから」
財布の中から十セント玉をつまみ出そうとすると、はずみで一セント銅貨がくっついてきてカウンターに落ちる。一セント銅貨を追った男の目が、キャンディー・ケースの前の子どもの姿をとらえた。
男はのろのろとそっちの方へ歩いていき、だんだら模様がついた長いペパーミントキャンディーを指していった。
「こいつは一セントの飴ですか。おくさん」
「どの飴?」
「ほら、あの縞模様のやつですよ」
子どもたちはメエの顔を見つめ、緊張で身体を固くした。
「ああ―あれ。ええっと、あれは違う。―あれは二本で一セントよ」
「そうですかい。じゃあ二本ください」
男は一セント銅貨をいとおしむようにそっとカウンターへ置きなおした。
子どもたちは止めていた息をふっとついた。二人はメエからおずおずと飴を受け取ると、そのまま手にぶら下げて、互いにぎこちない笑いをうかべ顔を見合わせる。
「ありがとうよ。おくさん」
男はパンを取り上げると、店から出ていき車に戻った。子ども二人はシマリスのようにすばしっこく荷物の上に飛び乗り、中にもぐりこんで見えなくなった。
おんぼろのナッシュはエンジンをかけ、けたたましい音と青く油臭い煙を残し、ハイウエイへとよじのぼっていく。
店の夫婦とトラック運転手は、ものもいわずじっと見送っている。
ビッグ・ビルがくるりと振り向くと、
「ありゃあ二本一セントのキャンディーじゃなかったぜ」
「それが、あんたと何の関係があるのよ」
メエがかみつく。ビルはぼそりという。
「あれは一本五セントだ」
助手は、
「ぼちぼち行こうとするかね」
と椅子から腰をうかす。
二人はポケットに手を突っ込み、ビルが銀貨をカウンターに置く。それを見た助手はもう一方のポケットから同じ銀貨を一枚出し、わきにならべた。
「あばよ」
メエがあわてて叫ぶ。
「ちょっと!待って、お釣り、お釣り」
「何いってやがる」
ビルはドアをバタンと閉めた。
巨体をゆるがしながら、走り去るトラックを見送っていたメエは小声で亭主によびかけた。
「ねえ」
アルはハンバーグをこねる手を止め顔をあげる。
「何だ」
「あれ見てよ」
メエはカウンターを指さし、アルは近くまで歩いていってしばしながめた。
半ドル銀貨が二枚。
亭主は仕事に戻り、メエはつぶやく。
「やっぱりトラックの運ちゃんだわ」
「…あとはみんなクソッタレだ」
(スタインベック『怒りの葡萄』 要約 水野聡2014年9月)















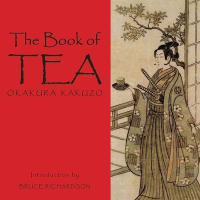










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます