
今回は、現代茶道大成期以前の茶の姿、中世の「闘茶」と「茶寄合」の風俗をご紹介しましょう。
■闘茶とは
闘茶(とうちゃ)とは、中世に流行した茶の味を飲み分けて勝敗を競う遊び。日本では回茶・飲茶勝負・茶寄合・茶湯勝負・貢茶、中国では茗茶・銘闘などの異名がある。
中国の唐代に始まって宋代に発展したと考えられているが、日本に伝来後は中国・日本ともにそれぞれ独自の形式を確立させた。
日本において本格的に喫茶が行われるようになったのは、鎌倉時代に入ってからである。後期に入ると各地で茶樹の栽培が行われるようになったが、産地間で品質に差があった。最高級とされたのは京都郊外の栂尾で産出された栂尾茶で、特に本茶と呼ばれ、それ以外の地で産出された非茶と区別された。最初の闘茶も本茶と非茶を飲み分ける遊びとして始められた。『光厳天皇宸記』正慶元年6月5日(1332年6月28日)条に廷臣達と「飲茶勝負」を行ったことが記されている。また、『太平記』には、佐々木道誉が莫大な景品を賭けて「百服茶」を開いたことが記されている。こうした流行に対して「群飲逸遊」という倫理面での批判や闘茶に金品などの賭け事が絡んだこともあり、二条河原落首では闘茶の流行が批判され、『建武式目』にも茶寄合(闘茶)禁止令が出されている程である。
室町期の書「喫茶往来」には、唐物による座敷飾が施された”喫茶の亭”で、禅院風の茶事が催された後、四種十服の茶勝負が繰り広げられ、都鄙善悪が判じられたという。
闘茶の方法には複数あるが、闘茶の全盛期であった南北朝時代から室町時代初期にかけて最も盛んに行われたのが、四種十服茶(ししゅじつぷくちゃ)であった。さらに前述佐々木道誉の「百服茶」をはじめ「二種四服茶」・「四季茶」・「釣茶」・「六色茶」・「系図茶」・「源氏茶」などがあった。
東山文化へと移行していく15世紀中頃からこうした闘茶は衰退の様相を見せ、更に村田珠光・武野紹鴎・千利休によって侘び茶が形成されていくと、闘茶は享楽的な娯楽・賭博として茶道から排除されるようになっていった。それでも、闘茶は歌舞伎者らによって歌舞伎茶(茶歌舞伎)として愛好され続け、また侘び茶側でも茶の違いを知るための鍛錬の一環として闘茶を見直す動きが現れた。闘茶は十七世紀、如心斎宗左により千家七事式に「茶カフキ」として付け加えられ、今日に至っている。
■茶寄合とは
中国宋代の文人茶会が源流。日本では宋の”茶競べ”を模して闘茶会として茶寄合が開かれるようになった。ここでは多数の武士が集まり、闘茶のみならず、囲碁、双六、連歌などが盛んに催される。基本的には自由な酒食を伴う、娯楽的な集まりである。のちには茶会と呼ばれるようになり、受容層も貴人から庶民へと移行していき、やがて茶の湯、今日の茶会となっていく。
その具体的な風俗が、画像の「祭礼絵草子」にみることができる。右の室では、唐絵・唐物を掛け並べた座敷で、人々が茶を喫す。その手前には、州浜風の盆栽も見える。
左の室では、書院・棚飾りのある部屋に続いて、簀子の部屋があり、手前では男が茶を点てている。簀子の部屋の真ん中には水がたたえられており、その中に水がめも見えるのは、当時「淋汗」とよばれた夏風呂とみられるが、異説もある。
この茶寄合の中でも、唐物を中心とした数奇の茶の傾向がうかがえる。しかし、その主目的は「賭け茶」であった。
■闘茶とは
闘茶(とうちゃ)とは、中世に流行した茶の味を飲み分けて勝敗を競う遊び。日本では回茶・飲茶勝負・茶寄合・茶湯勝負・貢茶、中国では茗茶・銘闘などの異名がある。
中国の唐代に始まって宋代に発展したと考えられているが、日本に伝来後は中国・日本ともにそれぞれ独自の形式を確立させた。
日本において本格的に喫茶が行われるようになったのは、鎌倉時代に入ってからである。後期に入ると各地で茶樹の栽培が行われるようになったが、産地間で品質に差があった。最高級とされたのは京都郊外の栂尾で産出された栂尾茶で、特に本茶と呼ばれ、それ以外の地で産出された非茶と区別された。最初の闘茶も本茶と非茶を飲み分ける遊びとして始められた。『光厳天皇宸記』正慶元年6月5日(1332年6月28日)条に廷臣達と「飲茶勝負」を行ったことが記されている。また、『太平記』には、佐々木道誉が莫大な景品を賭けて「百服茶」を開いたことが記されている。こうした流行に対して「群飲逸遊」という倫理面での批判や闘茶に金品などの賭け事が絡んだこともあり、二条河原落首では闘茶の流行が批判され、『建武式目』にも茶寄合(闘茶)禁止令が出されている程である。
室町期の書「喫茶往来」には、唐物による座敷飾が施された”喫茶の亭”で、禅院風の茶事が催された後、四種十服の茶勝負が繰り広げられ、都鄙善悪が判じられたという。
闘茶の方法には複数あるが、闘茶の全盛期であった南北朝時代から室町時代初期にかけて最も盛んに行われたのが、四種十服茶(ししゅじつぷくちゃ)であった。さらに前述佐々木道誉の「百服茶」をはじめ「二種四服茶」・「四季茶」・「釣茶」・「六色茶」・「系図茶」・「源氏茶」などがあった。
東山文化へと移行していく15世紀中頃からこうした闘茶は衰退の様相を見せ、更に村田珠光・武野紹鴎・千利休によって侘び茶が形成されていくと、闘茶は享楽的な娯楽・賭博として茶道から排除されるようになっていった。それでも、闘茶は歌舞伎者らによって歌舞伎茶(茶歌舞伎)として愛好され続け、また侘び茶側でも茶の違いを知るための鍛錬の一環として闘茶を見直す動きが現れた。闘茶は十七世紀、如心斎宗左により千家七事式に「茶カフキ」として付け加えられ、今日に至っている。
■茶寄合とは
中国宋代の文人茶会が源流。日本では宋の”茶競べ”を模して闘茶会として茶寄合が開かれるようになった。ここでは多数の武士が集まり、闘茶のみならず、囲碁、双六、連歌などが盛んに催される。基本的には自由な酒食を伴う、娯楽的な集まりである。のちには茶会と呼ばれるようになり、受容層も貴人から庶民へと移行していき、やがて茶の湯、今日の茶会となっていく。
その具体的な風俗が、画像の「祭礼絵草子」にみることができる。右の室では、唐絵・唐物を掛け並べた座敷で、人々が茶を喫す。その手前には、州浜風の盆栽も見える。
左の室では、書院・棚飾りのある部屋に続いて、簀子の部屋があり、手前では男が茶を点てている。簀子の部屋の真ん中には水がたたえられており、その中に水がめも見えるのは、当時「淋汗」とよばれた夏風呂とみられるが、異説もある。
この茶寄合の中でも、唐物を中心とした数奇の茶の傾向がうかがえる。しかし、その主目的は「賭け茶」であった。















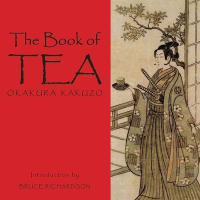




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます