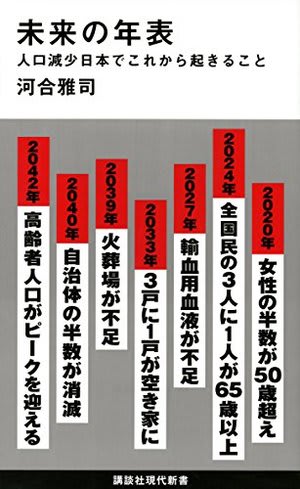3月20日 (火曜日) 寒い日になった。
寒い日になった。
コラムに名刺のことが・・・
うまいなあ。
南魚沼市の人たちが新米と名刺をくっつけた。
1合分を真空パックした袋を名刺に仕立てた。
先日の記事によれば縦が23センチもある。
差し出せば、心だって胃だってつかむ。
出会いの滑り出しは上々だろう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼フレッシュなんて呼ばれたころ、ある業界の懇親会場で失敗した。
話を聞かせてくれる人を探し、手当たり次第に名刺を配っていたら、
相手が「えっ?」。
愚かなことに、さっきもらったばかりの某社長さんの一枚を差し出していた。
大笑いされ、真っ赤っかになった。
▼交換の儀式は悲喜劇を生む。
姓名には目もくれず、ヨロシクの瞬間に肩書比べの火花を散らす人もいる。
昔は違ったのだという。
18世紀のヨーロッパでは、不在の人に用件を伝えるために使ったようだ。
▼作家の半藤一利さんが「歴史のくずかご」(文春文庫)に書いていた。
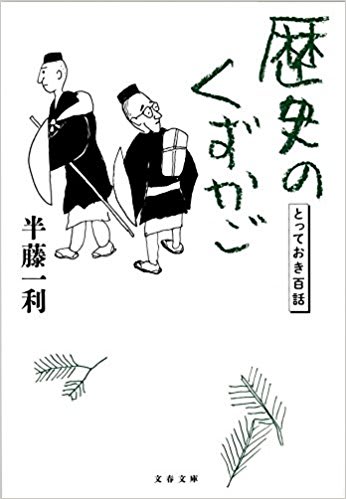
ある紳士が淑女の家を訪ねたものの、あいにく外出中。
そこで枚数不足で使いものにならなくなったトランプの余白に名前と用件を書いて、
留守宅に残してきたのが、名刺の始まりであると・・。
▼一説には、それがハートのエースであった。
となれば、恋文だ。
これがしゃれているということで、がぜんはやりだした。
それで名刺は原則的にトランプと同じ大きさなんだそうな-
▼いい出会いを望む季節になった。
新米さんと呼ばれることになる人たちは、
どきどきしだすころでしょう。
どんな巡り合いから、どんな仕事をつかむのか。
しのばせた胸ポケットの名刺より度胸がものをいう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
蛇足)
名刺の起源で検索してみた。

■名刺は"あの国"から始まった
名刺の起源については、さまざまな説があるようです。
中でも一般的なものは、中国を発祥とする説。
248年に没したとされる三国時代の武将・朱然の墓から、名刺が発見されました。
その頃は、まだ紙のない時代。
そのため、名刺は竹を割って作られ、そこに自分の名前を書いて使っていました。
この竹のことを『刺』と呼んでおり、
名前の書かれた『刺』ということで『名刺』と呼ばれるようになった...というのが、
名刺のはじまりのようです。
竹の名刺は、イメージするとすごく嵩張りそう。
しかし、約2000年も前から名刺が存在していたというのは、驚きではないでしょうか 。
。
その後、名刺は16世紀にヨーロッパへ。
ドイツでの使用を皮切りに、ヨーロッパ全土へと広がっていきます。
さらにアメリカでも使われ始めた名刺は、日本でも使われるようになります...
■日本で初めて名刺が使われたのは「○○時代」!
日本で名刺が使われ始めたのは、江戸時代(19世紀初期)からと言われています。
中国で名刺が使われ始めてから、ずいぶんと間が空いています。
ここには、当時の文化の違いなどがあったのかもしれません。
日本では、墨で名前を書いた和紙を、
訪問先が不在だった際に置いてくるという使い方をしていました。
今でいう、郵便物の不在票のようなものですね。
手描きから印刷になったのは、幕末開国頃。
印刷技術が西洋から日本へと伝わったことがキッカケです。
ちなみに当時、名刺には家紋が描かれ、その下に名前が書かれていたとのこと。
名刺にロゴや顔写真を載せる人がいますが、家紋はそれと同じような位置づけなのかもしれません。
時代と共に、名刺はどんどん頻繁に利用されるようになります。
明治時代以降のいわゆる「鹿鳴館時代」には、社交の場において
既に必須アイテムとなっていたようです。
今や日本は、発祥の地である中国以上に名刺をよく使っています。
世界的に見てもその数は多いというイメージがあり、
例えばキレイにファイリングした名刺の束を見せると、外国人は驚くようです。
確かに日本では『名刺』という存在を非常に重んじる文化があり、
よく会社でも名刺の扱いについて「その人の分身だと思え」など注意されます。
ですから、中には名刺が日本発祥だと思っていた方も少なくないのではないでしょうか。
名刺の起源。何気なく使っているものにも、意外な歴史や真実があるのですね~。
=================
 寒い日になった。
寒い日になった。
コラムに名刺のことが・・・

うまいなあ。

南魚沼市の人たちが新米と名刺をくっつけた。

1合分を真空パックした袋を名刺に仕立てた。

先日の記事によれば縦が23センチもある。

差し出せば、心だって胃だってつかむ。
出会いの滑り出しは上々だろう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼フレッシュなんて呼ばれたころ、ある業界の懇親会場で失敗した。
話を聞かせてくれる人を探し、手当たり次第に名刺を配っていたら、
相手が「えっ?」。
愚かなことに、さっきもらったばかりの某社長さんの一枚を差し出していた。
大笑いされ、真っ赤っかになった。
▼交換の儀式は悲喜劇を生む。

姓名には目もくれず、ヨロシクの瞬間に肩書比べの火花を散らす人もいる。
昔は違ったのだという。
18世紀のヨーロッパでは、不在の人に用件を伝えるために使ったようだ。
▼作家の半藤一利さんが「歴史のくずかご」(文春文庫)に書いていた。
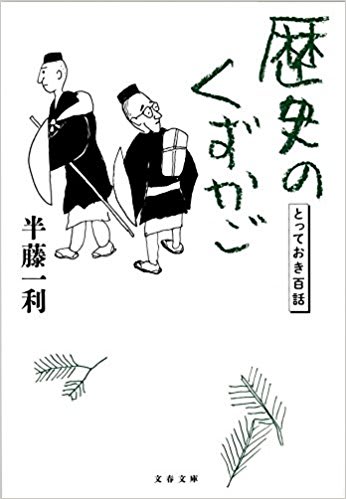
ある紳士が淑女の家を訪ねたものの、あいにく外出中。
そこで枚数不足で使いものにならなくなったトランプの余白に名前と用件を書いて、
留守宅に残してきたのが、名刺の始まりであると・・。
▼一説には、それがハートのエースであった。

となれば、恋文だ。

これがしゃれているということで、がぜんはやりだした。
それで名刺は原則的にトランプと同じ大きさなんだそうな-
▼いい出会いを望む季節になった。
新米さんと呼ばれることになる人たちは、
どきどきしだすころでしょう。
どんな巡り合いから、どんな仕事をつかむのか。
しのばせた胸ポケットの名刺より度胸がものをいう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
蛇足)
名刺の起源で検索してみた。


■名刺は"あの国"から始まった
名刺の起源については、さまざまな説があるようです。
中でも一般的なものは、中国を発祥とする説。
248年に没したとされる三国時代の武将・朱然の墓から、名刺が発見されました。
その頃は、まだ紙のない時代。
そのため、名刺は竹を割って作られ、そこに自分の名前を書いて使っていました。
この竹のことを『刺』と呼んでおり、
名前の書かれた『刺』ということで『名刺』と呼ばれるようになった...というのが、
名刺のはじまりのようです。

竹の名刺は、イメージするとすごく嵩張りそう。
しかし、約2000年も前から名刺が存在していたというのは、驚きではないでしょうか
 。
。その後、名刺は16世紀にヨーロッパへ。
ドイツでの使用を皮切りに、ヨーロッパ全土へと広がっていきます。
さらにアメリカでも使われ始めた名刺は、日本でも使われるようになります...
■日本で初めて名刺が使われたのは「○○時代」!
日本で名刺が使われ始めたのは、江戸時代(19世紀初期)からと言われています。
中国で名刺が使われ始めてから、ずいぶんと間が空いています。
ここには、当時の文化の違いなどがあったのかもしれません。
日本では、墨で名前を書いた和紙を、
訪問先が不在だった際に置いてくるという使い方をしていました。
今でいう、郵便物の不在票のようなものですね。
手描きから印刷になったのは、幕末開国頃。
印刷技術が西洋から日本へと伝わったことがキッカケです。
ちなみに当時、名刺には家紋が描かれ、その下に名前が書かれていたとのこと。
名刺にロゴや顔写真を載せる人がいますが、家紋はそれと同じような位置づけなのかもしれません。
時代と共に、名刺はどんどん頻繁に利用されるようになります。

明治時代以降のいわゆる「鹿鳴館時代」には、社交の場において
既に必須アイテムとなっていたようです。
今や日本は、発祥の地である中国以上に名刺をよく使っています。
世界的に見てもその数は多いというイメージがあり、
例えばキレイにファイリングした名刺の束を見せると、外国人は驚くようです。
確かに日本では『名刺』という存在を非常に重んじる文化があり、
よく会社でも名刺の扱いについて「その人の分身だと思え」など注意されます。
ですから、中には名刺が日本発祥だと思っていた方も少なくないのではないでしょうか。

名刺の起源。何気なく使っているものにも、意外な歴史や真実があるのですね~。

=================