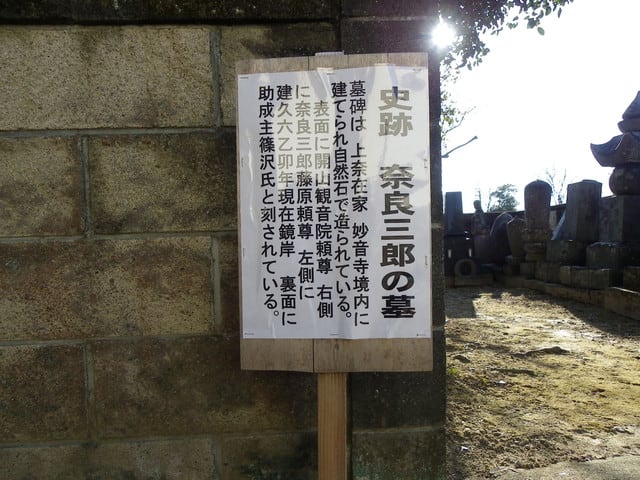ここでは、前々記事で紹介した奈良氏の本家、成田氏館およびその菩提寺である龍淵寺について紹介いたします。
忍に本拠地を構える前から、成田氏がいかに水場好きであったかがよく分っていただけると思います。
成田氏館と龍淵寺は、ともに、国道17号バイパス線沿いにあります。
現在は、17号バイパスによって分断されていますが、両者は目と鼻の先ほどしか離れておりません。
成田氏館は熊谷市北頭部に広がる広大な低湿地の自然堤防上にあります。
この地域は、古くから水の便を活かした稲作が盛んだったようで、弥生時代の池上遺跡、池守遺跡が
発掘されております。
同時に、深い湿田でもあり、17号バイパスの工事の過程で、地盤を安定させるために大量の土砂を
投入しました。その方法は道路予定地に2メートルほどの高さに土砂を1~2年積んで置き、
地面に吸収させるというものでしたが、何度積んでも、地盤が土砂をすべて吸いこんでしまうため、
長い時間を必要としたのでした。
成田氏は、忍に移るまでの長い間、このような低湿地帯に居を構えていたのでした。
成田氏館はバイパスの南側に、龍淵寺は北側にそれぞれあります。
わたしが成田氏館を訪ねたのは、1982年の夏でした。
当時の写真です。この石碑は、現在の石碑の場所と道を挟んで反対側に立っていました。

暑い日で、有名な成田氏の居館が桑畑であることに、驚きとめまいを感じたのを覚えています。
この石碑だけで安心してしまい、水堀というには浅すぎる堀跡は、ろくに撮影せずに帰路につきました。
さて、現況です。



石碑と、木製の案内柱があり、その付近で見ることのできる遺構は畜舎脇の水堀跡です。
畜舎は初訪問当時からこの場所にありました。建物自体は改築されて大きく近代的なものになっているようです。

道の反対側にあった、あの大きな桑畑は、改廃されていました。
しかし、これで終わっては全然しつこくないので、少し歩いて、地形を読み込んでいくことにしました。
少し歩くことになりましたが、裏の道路に回って、畜舎の背後から接近を試みます。

写真は遠景です。道路沿いには民家が多いので、農地を見つけてその畔を通りました。
中央左寄りにある小太刀付近は盛り上がっており、土塁があるようです。
そこを目的にします。

畜舎裏と圃場の間には一段低い水田があり、ここが低湿地を利用した水堀跡だと考えられます。

現在、実際に現存する水路は、水堀跡の強湿田から水を抜くために、水堀跡に、新たに掘り直された排水路だと思われます。

つまり、カッコつきで「水堀跡」なのです。農用地改良に際して、こうした技術はしばしば用いられます。
畜舎裏(水堀内側)の平地を撮影しました。こう見ると、成田氏館跡はかなり広いです。
なにより、障害物なしで可視化されているのがいいですね。わかり易くて。

水堀関係も追いかけてみます。

農業用のくみ上げ井戸もあります。これは、近代のものでしょうね。

この水路が館跡の脇を流れる水堀跡のようです。
付近には、館跡に関係するのか不明ですが、水堀に用いられた可能性があるような低い水田があり、
方形に区切られています。




これ等を見ている限り、成田氏館跡は牧場裏だけでも、かなりの規模を持っていたと考えることができると
推測いたしました。
明日は、もと桑畑である、泰蔵院うらとその周辺について調査の結果を報告いたします。
(つづく)
忍に本拠地を構える前から、成田氏がいかに水場好きであったかがよく分っていただけると思います。
成田氏館と龍淵寺は、ともに、国道17号バイパス線沿いにあります。
現在は、17号バイパスによって分断されていますが、両者は目と鼻の先ほどしか離れておりません。
成田氏館は熊谷市北頭部に広がる広大な低湿地の自然堤防上にあります。
この地域は、古くから水の便を活かした稲作が盛んだったようで、弥生時代の池上遺跡、池守遺跡が
発掘されております。
同時に、深い湿田でもあり、17号バイパスの工事の過程で、地盤を安定させるために大量の土砂を
投入しました。その方法は道路予定地に2メートルほどの高さに土砂を1~2年積んで置き、
地面に吸収させるというものでしたが、何度積んでも、地盤が土砂をすべて吸いこんでしまうため、
長い時間を必要としたのでした。
成田氏は、忍に移るまでの長い間、このような低湿地帯に居を構えていたのでした。
成田氏館はバイパスの南側に、龍淵寺は北側にそれぞれあります。
わたしが成田氏館を訪ねたのは、1982年の夏でした。
当時の写真です。この石碑は、現在の石碑の場所と道を挟んで反対側に立っていました。

暑い日で、有名な成田氏の居館が桑畑であることに、驚きとめまいを感じたのを覚えています。
この石碑だけで安心してしまい、水堀というには浅すぎる堀跡は、ろくに撮影せずに帰路につきました。
さて、現況です。



石碑と、木製の案内柱があり、その付近で見ることのできる遺構は畜舎脇の水堀跡です。
畜舎は初訪問当時からこの場所にありました。建物自体は改築されて大きく近代的なものになっているようです。

道の反対側にあった、あの大きな桑畑は、改廃されていました。
しかし、これで終わっては全然しつこくないので、少し歩いて、地形を読み込んでいくことにしました。
少し歩くことになりましたが、裏の道路に回って、畜舎の背後から接近を試みます。

写真は遠景です。道路沿いには民家が多いので、農地を見つけてその畔を通りました。
中央左寄りにある小太刀付近は盛り上がっており、土塁があるようです。
そこを目的にします。

畜舎裏と圃場の間には一段低い水田があり、ここが低湿地を利用した水堀跡だと考えられます。

現在、実際に現存する水路は、水堀跡の強湿田から水を抜くために、水堀跡に、新たに掘り直された排水路だと思われます。

つまり、カッコつきで「水堀跡」なのです。農用地改良に際して、こうした技術はしばしば用いられます。
畜舎裏(水堀内側)の平地を撮影しました。こう見ると、成田氏館跡はかなり広いです。
なにより、障害物なしで可視化されているのがいいですね。わかり易くて。

水堀関係も追いかけてみます。

農業用のくみ上げ井戸もあります。これは、近代のものでしょうね。

この水路が館跡の脇を流れる水堀跡のようです。
付近には、館跡に関係するのか不明ですが、水堀に用いられた可能性があるような低い水田があり、
方形に区切られています。




これ等を見ている限り、成田氏館跡は牧場裏だけでも、かなりの規模を持っていたと考えることができると
推測いたしました。
明日は、もと桑畑である、泰蔵院うらとその周辺について調査の結果を報告いたします。
(つづく)