現代医学にヒポクラテスの医学医療を復権させよう
ヒポクラテスの復権
1) ヒポクラテス
ヒポクラテスは、ギリシャ医学の中のコス派に属していた。
コス派は「助力せよ、せめて損なうな」という立場であった。残されているヒポクラテス全集は、ヒポクラテスだけでなく、複数のコス派医師の手による物と言われる(川喜田)
ヒポクラテスは、(病名より)予後の判定を重んじた。
二元論を斥け、すべて統一的な自然の中で考えようとする。
(病名の判定ではなく)「病人の現症を正確に把握する」ことが診断であった。
病気を既往から現状を経て、明日へと進む生物学的プロセス(過程)と解する。
個別(患者)の重視
臨床医の仕事は、技術あるいは手仕事であった。
対象が、人である。生物としてのヒト、であると同時に、「悩み」の中にある人である。
「病人」であること。(人の悩みは、悩んでいる限りは、皆同じである―誰かの言葉であったが思い出せない。)
ヒポクラテスの「神聖病」つまり精神病は「他のいろいろな病気と同じ性質をもち、おのおのそのよっておこる牽引を持っている」として、身体病と精神病を分けなかった。
「ヒポクラテスの誓い」は典礼的な意味をもち、コス派のものではなく、前4世紀以後の後期ピュタゴラス派によるものとの説が有力(川喜田)という。
コス派は、病人を全身的に眺め、諸機能のつりあいを重んじ、環境(気候、気象、風土、季節、食物などの自然環境)に注意を怠らない。
この考えは、600年を経て、ガレノス(四体液説と治療の方法を除く)へと受け継がれる。ギリシャ医学はアレキサンドリアからローマに浸透し、ガレノスに到り、その後の中世の暗黒時代になる。ガレノスの後千年にわたる。ヒポクラテス主義は、ローマの滅亡と共にビザンチウム(コンスタンチノポリス)を経て、アラビア医学から西方ラテン世界へとつながる。一部南イタリアに残り、サレルノ医学校(11世紀)で研究される。
17世紀の開業医シデナムは、ヒポクラテスの病者の記録を継ぎ、諸病の経過の正確な記録と病気を除く方法の工夫を経験に求めた。病気の自然誌を考えた。病気を診ずに病人を診た。病気を正常からの「ずれ」とし、害われた人体のはたらきないし状態とみる。病気を他者でなく人体にあるとするギリシャ以来の見方であった。
しかし、ヒポクラテスのもつもうひとつの環境を重視する見方は、抜けていった。
人間的な医学医療を求める考えや養生法や暮らし方、患者に害を与えない治療法は受け継がれていったが、環境説は消えていった。
ローマ時代には、健康には、個人の衛生と公共の健康の二つに区別され、上下水道、公共浴場が発達したが、ローマ帝国の崩壊と共に退潮した。
その後、ペストの防疫、職業病(パラケルスス、ラマッツィニ)の発見から衛生学へと発展し、環境、外因の病理に目が向けられていった。
ラマッツィニ「労働者たちの健康を守り、社会の福祉をはかることが医学者の義務であると考える」1700
18世紀後半のフランク「病気の成因としての大衆の貧困」(1790)の講演と「人民の健康の保全が国の責任である」との見解をとった。ほそぼそと、環境論は再興されていったが、本格的には、ヴィルヒョウの時代まで待たねばならない。
2) ヒポクラテスの復権
ヒポクラテス著作集は、デュボス、ジルボーグ、川喜田らによると、ヒポクラテスが主ではあるが、ヒポクラテス以後の時代のいろいろな時期にヒポクラテスの所属したコス派を中心に、いろいろな学派の医師の手で作られたものの集大成であるという。しかし、現代医学の基本的礎をなしているという。
ヒポクラテスは「人間というものをバラバラの単位の集合物としてではなく、一つの全体として考え、・・・ともかく多少とも一元的な人間の体系を築き上げようとする一つの努力であった。」(ジルボーグ「医学的心理学史」)
しかしプラトンは精神と物質の二元論をとり、ヒポクラテスから一歩後退し、後世の二元論に道を開いたのである。
そしてその後の医学は二元論が支配的であり、心身医学が登場し、心療内科という言葉が一般化した現在でも、今なおそうである。身体医学はこころを診ず、精神医学や心理学は身体を診ないのが大勢である。
セリエが1936年「全身適応症候群」を発表し、1943年シゲリストが「医学は社会科学である」と唱え、1965年デュボスが「人間と適応」を出版し、ヒポクラテスの復権を唱えた。そしてその後、基礎医学者や精神科医にデュボスの提唱に賛同し、病原環境論または適応説をとる医師が出て、精神科では精神神経免疫学や、心身医学(心療内科)が登場し、さらに精神神経免疫内分泌学に到るまでになった。だが私は、まだまだ不十分であると思う。1948年の世界保健機構(WHO)の憲章の前文に「健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に満足できる状態で、単に、病気や虚弱が存在しないということではない」としている。
ヒポクラテスは『病気を外から人に臨む「実体」としてでなく、「病んだ人」として眺める』、『病気を人の状態として把握する。』、『それ(病気)を招くものは、主に気候の変化、不適正な食事、その他外界の激変であるとされる。従って、まずその原因を除くことこそ治病の要諦でなければならない。・・・病気はそこに回復に向かうだろう。医者の任務は人体に備わったその自然治癒の働きを助長することでなければならない。』という。(ヒポクラテス「古い医術について」岩波文庫)
ヒポクラテスは人間をこころと身体に分離せず、更には身体を細かく諸臓器に分解せず、「病める人」としてとらえた。それと同時に「空気、水、場所、気候、その他外界の激変」を病気を招くものとして捉えている。ヒポクラテスの時代と現代とでは環境も病気の種類も大きく変化してきているが、人間そのものが変化していないのであれば、基本的には現代でもあてはまると思う。人間の肉体的身体は、ここ二千五百年以上ほとんど変化していないと考えられている。(ルネ・デュボス)変わっているのは人間の住む環境である。環境には、自然環境と社会環境、そしてそれによって生ずる情緒的環境(精神的、心理的環境とでも言えましょうか)がある。環境の変化によって、生じる病気も変化しているのである。人間は環境に適応して進化して登場したが、環境に適応できない時に病気になるのである。
デュボスの要約によれば、
「病気は悪霊や移り気の神が原因となって起こるのではなく、むしろ自然の法則にしたがう自然の力で起こるものである。したがって、治療の技術を合理的な基礎の上に発達させることができる。こうした手段には、自然の力の害をなしている効果を正すようにと目指された食事、薬剤、手術の利用がふくまれる。
人間の福祉は、特定の空気、水、土地およびいろいろの食糧をふくめて、環境の影響のもとにある。環境が人間におよぼす影響を理解することが、医師の技量の根本的な基礎である。
健康とは、人間の本性のいろいろな成分(すべての人間の活動を制御している四つの体液)、環境、および生活様式との間の調和のとれた平衡のあらわれである。
こころに起こったことはどんなことでも身体に影響が及び、またその逆も起こる。事実、こころと身体との一方を他から分けて別々に考察することはできない。
健康とは健康な身体に存在している健康なこころを意味するもので、生体のいろいろの力と環境の力との間のつり合いを保証している自然の法則と合致するように、毎日の生活を統御することによってのみ達成できるものである。
医療は倫理的職業であり、人間の条件への尊敬の態度を意味するものである。」
さらに「医学的心理学史」のジルボーグは言う。
「ヒポクラテスは、身体病と精神病を分けなかった。」「彼(ヒポクラテス)においては、解剖学、生理学、心理学の三つが同盟を結んでいるように推論されるが、・・・」
「プラトンは、一歩後退して『精神と物質の二つの原理があるが、・・・・』という心身二元論をとり、アリストテレスも二元論をとっている。」「ヒポクラテス主義はすでに、精神医学において実を結んでいた。」
川喜田はヒポクラテスについて、「二元論を彼は斥け、すべてを統一的な自然の中で考えようとする。」彼は病気を外から人に臨む「実体」としてではなく、「病んだ人」として眺める。言いかえればそれ(病気)を人の状態として把握する。「助力せよ、せめて損なうな」
と言っているという。
ここから導き出されるのが、心身一元論であり、病原環境説なのである。
病気は自分の中に生ずるものなのである。外から入って来たものではない。入って来たものはウィルスや細菌や異物であるが、その結果起きる病気はウィルスや細菌に対して闘っている自分の身体の変化なのである。死体にうじがむらがっても、死体はなすがままになり、反応しない。生体であるから、防御反応をし、それが病気なのである。細菌は死体でも生きているが、死体が細菌の栄養にならなくなると死んでしまう。ウイルスは、細胞の中でしか繁殖しないから、細胞の死と共にそこで繁殖できず、細胞内で死んでしまう。細菌やウイルスは、人間が生きているから、それに対する反応として病気になる。つまり、病気は自分の体の変化なのである。
精神的・心理的病気も、自分のこころの持ち方から生じる自分の身体の変化である。
成人病も膠原病もがんも、すべてこれ(病原環境論または適応説)で説明できる。悩んでいた説明がつかなかった先天性、遺伝性の病気も、ゲノムの解析と遺伝子学の進歩によって、説明できるようになった。そのことは、別の項で話すことにする。
2)人間とは
私は、「人間はこころと身体を持つ社会的存在である」としてとらえ、その人間がかかる病気として病気をとらえる。
「人間とは考える芦である」という古典的時代ではもうないが、でもまだこころというものが見えない為に多くの人々や医者に誤解がある。
人間にはこころがあり、物事を考え、記憶していく能力があるが、こころは大脳の活動から生じるのであり、しかも人間の社会で育てられなければ人間のこころをもつことができないのである。他の動物たち(有袋類を除く)のように、生まれたらすぐ、自力で立ち上がったり、母親にしがみついたりすることはできない。有袋類ですら、自力で母親の袋の中に入る。人は、一年早く生まれたという説(ボルトマンの「子宮外早生の一年」という概念――三浦雅士「身体の零度」より)も、「なぜか、どのように進化してそうなったのかと」いう疑問と共に、彼の言う「人間の最も重要な特徴――立つこと、話すこと、考えることという三主徴――が社会的環境との接触によってはじめて形成されていく・・・」ことも検討に値するだろう。
人間はロビンソン・クルーソーのようにたった一人では生きていけない。つまり、人間はその生命活動を社会的に営む社会的生物である。人間が社会を造り出したが、社会が出来てしまうと社会が一人一人の人間を拘束し、影響を及ぼす。病気はその社会によって大きく左右され、社会は自然環境によって左右され、また人は自然環境や社会環境を変えていく。社会は文明を持ち、社会としての活動がある。
疎外、管理社会、戦争と平和、不況と好況 。
今までによく現代医療に対して病気しか見ず、病人を見ないとの批判があった。既にアメリカではがんなどの病気で入院すると多くの各科専門医たちのほかに、精神科医師や心理療法士、病院付きの牧師まで来て、病人が病気を治す為のこころの面での援助をしてくれる。スポーツをすることで気持ちをまぎらわせようと思えば、スポーツの指導員も来てくれる。乳がんで死んだ池田敦子さんの言うように日本に比べたら格段の差がある。
現代アメリカの医療の中身は日本よりはずっとましなのだが、私の考えている「新たなる医療」と比べると、こころの持ち方の方向が違うし、社会的視野が欠けている。それに医療を受けられる人が限られているのが問題である。(問題なのは、アメリカ医療は金のある人だけの為にあることだが、それは医療の問題ではなく、医療制度の問題であるのでここでは省略する。しかし、現在の状況では、日本もアメリカ化しつつある。)
さて人間と動物の違いは大脳皮質、特に新皮質系にある。「動物のなかで新皮質系がもっとも発達しているのは、人間であるし、人間の進化の過程をみても、脳の容積の増大とともに、新皮質系、とくに前頭葉の発達が著しい。人間を社会的動物であらしめ、・・るのはまさにこの新皮質系の作用である。」(田中正敏「ストレスの科学と健康」より)つまり人間の特徴は社会性にある。このように大脳の発達から見ても人間は社会的動物であることが分かる。
「野生児の記録」(R.M.ジング)によれば、狼や熊に育てられた野生児の世界の結論として「人間は生まれてから幼児期または6~7才頃迄に人間社会から断絶されると、人間としての生活が営めなくなる。特に幼少期に隔絶されると四つ足で走る方が速くなる。(二本足で歩けない)言葉も習得できなくなる。人間は、人間社会の中でしか、人間らしく生きられないのだ。人間世界をいろいろな理由で離れた野生児たちは戻されてももう普通の人々と同じような生活には決して戻れないのである。生まれてから人間世界(社会)の中で育てられることが、人間らしさを得るただ一つの手段なのである。」という。人間は常に「社会的に」人間なのである。
狼に育てられた人間はその後言葉を覚えても、記憶に残り話すことが出来ることは言葉を覚えてからのことだけである。言葉を覚える以前のことは決して言葉として語ることはできないのである。人間は生まれながらにして人間ではなく、「人間として」生まれ、かつ「人間として」育てられることが人間になるために必要なのである。
さらに言えば、民族や人種の違いは生まれつきではなく、生まれ育った自然や社会の環境や文化によって違って来ている。よく雪国の子はすぐあきらめてしまい、南国の子はあきらめずに頑張ると、高校野球で言われるが、雪という自然がそこに住む人々のこころを大きく左右するのは不思議ではないと思う。最近は、南国の指導者が来て北国の高校野球も変わりましたが。
このように私は以前から人種や民族による差は少なく、むしろ生まれ育った環境によって変わるのではないか考えていたが、それを証明してくれた人がいた。
「DNAは生物の体の中で、不変なものではなく、つねに変化し動きまわるダイナミックな存在である。DNAが変化する形で、遺伝子が細胞の中で変化する。」ということを証明した利根川進博士の業績は、「環境によって人間の身体やこころが変わり、それが遺伝子によって伝えられる。」という環境を重視する私の考えを裏付けてくれたのである。
そしてアメリカ人は多民族国家ですが、どの民族でも二代三代と経つ内に考え方も、かかる病気もアメリカ化されてしまう。日本人も、一世、二世、三世と次第にアメリカ人共通の病気になるようになっていく。日本では民族差を強調する人が少なくないが、アメリカに住んでいる人々を見ると皆アメリカ人であって出身の民族の差は少なく、むしろ宗教とか国とかその人の住む社会の違いの方が大きい。アメリカに住むユタ州中心のモルモン教やニューヨーク州に住むクウェーカー教徒、アーミッシュの人々、それに日本にも多いセブンズデイ・アドべンチストたちは、アメリカ人の中で極めてかけ離れて、成人病が少ないと言う。
人間はこうしてこころと身体を持つ社会的存在であり、そのどれも切り離すことができない。人間はその身体があるからこころを持ち、そして社会的に存在するから人間でいられる。そして人間社会の中で育てられて人間になる。
そうした意味で人間を「こころと身体と社会的存在」の総体としてとらえ、その人間がなる病気について見ていきたいと思う。
WHO憲章の健康の定義にも「肉体的、精神的、社会的に良好な状態であって、単に疾病や虚弱のないことではない。」とあるように、これは私だけの考えではないようだ。
こころと身体の医学とかこころと身体の健康とかよく言われるが、それだけでは不十分であるし、人間が社会的存在であることを見ないことが問題である。つまりそういう考え方は社会が病気を生んでいることから人々の目をそらす役割を果たしている。病気は個人がかかるもので、社会や企業は関係がないとする方が、現代の支配体制側(資本主義、社会主義などを問わず)にとっては都合がよいのだから、そういう考え方(心療内科など)は支配階級的でさえある。
なぜなら、現代社会に適応できないで病気になった人を、薬やカウンセリングなどというまやかし(社会を変えずに、人を社会に合わせさせる)だと思う。本当は、社会を変えた方が、早く治るし、病気にならないで済むことが多い。残念ながら、私も社会を変えることができないから、薬を処方し、カウンセリングをしている。
3)社会的生物としての人間
前述もしたが、三浦雅士「身体の零度」によると、スイスの生物学者アドルフ・ボルトも重要な特徴――立つこと、話すこと、考えることという三主徴――が社会的環境との接触によってはじめて形成されていくということと、関連して考えられなければならない。・・・人間にとって社会的接触は必須のものである。新生児に対する集団の助力、すなわち愛情をもった世話が確かになされないと、姿勢、会話、精神生活、思考が、完全な人間性に導く軌道から外れていってしまう。」 またマンフォードは、「生物学的な幼児期が長くなったおかげで、人間は、利用できるあらゆる身体器官の実験が促進される可塑的、成形可能的な状態におかれ、もはや人間の器官は、ただ機能的な役割だけを尊重して扱われるのではなく、希望をもった精神の道具として新しい目的のために形づくられるようになった」という。三浦はそれを「いい換えれば、人間の身体は人為的に作られるもの、すなわち文化にほかならない、身体こそ人間にとって最初の文化であったのである。」と解釈している。まだまだ三浦の論文は続くが、私は、まさに私と同じ考えと考えている。
そして、三浦のいう近代の成立が、近代の病気を生み出してきたのである。姿勢、歩行、体育、会話、精神生活、思考、食事、衣服、住居、仕事、職場などの近代化が、現代の病気を生み出してきている。だから、今後も、社会の変化によって、新しい病気が次々とでてくることは、必定である。
ヒポクラテスの復権
1) ヒポクラテス
ヒポクラテスは、ギリシャ医学の中のコス派に属していた。
コス派は「助力せよ、せめて損なうな」という立場であった。残されているヒポクラテス全集は、ヒポクラテスだけでなく、複数のコス派医師の手による物と言われる(川喜田)
ヒポクラテスは、(病名より)予後の判定を重んじた。
二元論を斥け、すべて統一的な自然の中で考えようとする。
(病名の判定ではなく)「病人の現症を正確に把握する」ことが診断であった。
病気を既往から現状を経て、明日へと進む生物学的プロセス(過程)と解する。
個別(患者)の重視
臨床医の仕事は、技術あるいは手仕事であった。
対象が、人である。生物としてのヒト、であると同時に、「悩み」の中にある人である。
「病人」であること。(人の悩みは、悩んでいる限りは、皆同じである―誰かの言葉であったが思い出せない。)
ヒポクラテスの「神聖病」つまり精神病は「他のいろいろな病気と同じ性質をもち、おのおのそのよっておこる牽引を持っている」として、身体病と精神病を分けなかった。
「ヒポクラテスの誓い」は典礼的な意味をもち、コス派のものではなく、前4世紀以後の後期ピュタゴラス派によるものとの説が有力(川喜田)という。
コス派は、病人を全身的に眺め、諸機能のつりあいを重んじ、環境(気候、気象、風土、季節、食物などの自然環境)に注意を怠らない。
この考えは、600年を経て、ガレノス(四体液説と治療の方法を除く)へと受け継がれる。ギリシャ医学はアレキサンドリアからローマに浸透し、ガレノスに到り、その後の中世の暗黒時代になる。ガレノスの後千年にわたる。ヒポクラテス主義は、ローマの滅亡と共にビザンチウム(コンスタンチノポリス)を経て、アラビア医学から西方ラテン世界へとつながる。一部南イタリアに残り、サレルノ医学校(11世紀)で研究される。
17世紀の開業医シデナムは、ヒポクラテスの病者の記録を継ぎ、諸病の経過の正確な記録と病気を除く方法の工夫を経験に求めた。病気の自然誌を考えた。病気を診ずに病人を診た。病気を正常からの「ずれ」とし、害われた人体のはたらきないし状態とみる。病気を他者でなく人体にあるとするギリシャ以来の見方であった。
しかし、ヒポクラテスのもつもうひとつの環境を重視する見方は、抜けていった。
人間的な医学医療を求める考えや養生法や暮らし方、患者に害を与えない治療法は受け継がれていったが、環境説は消えていった。
ローマ時代には、健康には、個人の衛生と公共の健康の二つに区別され、上下水道、公共浴場が発達したが、ローマ帝国の崩壊と共に退潮した。
その後、ペストの防疫、職業病(パラケルスス、ラマッツィニ)の発見から衛生学へと発展し、環境、外因の病理に目が向けられていった。
ラマッツィニ「労働者たちの健康を守り、社会の福祉をはかることが医学者の義務であると考える」1700
18世紀後半のフランク「病気の成因としての大衆の貧困」(1790)の講演と「人民の健康の保全が国の責任である」との見解をとった。ほそぼそと、環境論は再興されていったが、本格的には、ヴィルヒョウの時代まで待たねばならない。
2) ヒポクラテスの復権
ヒポクラテス著作集は、デュボス、ジルボーグ、川喜田らによると、ヒポクラテスが主ではあるが、ヒポクラテス以後の時代のいろいろな時期にヒポクラテスの所属したコス派を中心に、いろいろな学派の医師の手で作られたものの集大成であるという。しかし、現代医学の基本的礎をなしているという。
ヒポクラテスは「人間というものをバラバラの単位の集合物としてではなく、一つの全体として考え、・・・ともかく多少とも一元的な人間の体系を築き上げようとする一つの努力であった。」(ジルボーグ「医学的心理学史」)
しかしプラトンは精神と物質の二元論をとり、ヒポクラテスから一歩後退し、後世の二元論に道を開いたのである。
そしてその後の医学は二元論が支配的であり、心身医学が登場し、心療内科という言葉が一般化した現在でも、今なおそうである。身体医学はこころを診ず、精神医学や心理学は身体を診ないのが大勢である。
セリエが1936年「全身適応症候群」を発表し、1943年シゲリストが「医学は社会科学である」と唱え、1965年デュボスが「人間と適応」を出版し、ヒポクラテスの復権を唱えた。そしてその後、基礎医学者や精神科医にデュボスの提唱に賛同し、病原環境論または適応説をとる医師が出て、精神科では精神神経免疫学や、心身医学(心療内科)が登場し、さらに精神神経免疫内分泌学に到るまでになった。だが私は、まだまだ不十分であると思う。1948年の世界保健機構(WHO)の憲章の前文に「健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に満足できる状態で、単に、病気や虚弱が存在しないということではない」としている。
ヒポクラテスは『病気を外から人に臨む「実体」としてでなく、「病んだ人」として眺める』、『病気を人の状態として把握する。』、『それ(病気)を招くものは、主に気候の変化、不適正な食事、その他外界の激変であるとされる。従って、まずその原因を除くことこそ治病の要諦でなければならない。・・・病気はそこに回復に向かうだろう。医者の任務は人体に備わったその自然治癒の働きを助長することでなければならない。』という。(ヒポクラテス「古い医術について」岩波文庫)
ヒポクラテスは人間をこころと身体に分離せず、更には身体を細かく諸臓器に分解せず、「病める人」としてとらえた。それと同時に「空気、水、場所、気候、その他外界の激変」を病気を招くものとして捉えている。ヒポクラテスの時代と現代とでは環境も病気の種類も大きく変化してきているが、人間そのものが変化していないのであれば、基本的には現代でもあてはまると思う。人間の肉体的身体は、ここ二千五百年以上ほとんど変化していないと考えられている。(ルネ・デュボス)変わっているのは人間の住む環境である。環境には、自然環境と社会環境、そしてそれによって生ずる情緒的環境(精神的、心理的環境とでも言えましょうか)がある。環境の変化によって、生じる病気も変化しているのである。人間は環境に適応して進化して登場したが、環境に適応できない時に病気になるのである。
デュボスの要約によれば、
「病気は悪霊や移り気の神が原因となって起こるのではなく、むしろ自然の法則にしたがう自然の力で起こるものである。したがって、治療の技術を合理的な基礎の上に発達させることができる。こうした手段には、自然の力の害をなしている効果を正すようにと目指された食事、薬剤、手術の利用がふくまれる。
人間の福祉は、特定の空気、水、土地およびいろいろの食糧をふくめて、環境の影響のもとにある。環境が人間におよぼす影響を理解することが、医師の技量の根本的な基礎である。
健康とは、人間の本性のいろいろな成分(すべての人間の活動を制御している四つの体液)、環境、および生活様式との間の調和のとれた平衡のあらわれである。
こころに起こったことはどんなことでも身体に影響が及び、またその逆も起こる。事実、こころと身体との一方を他から分けて別々に考察することはできない。
健康とは健康な身体に存在している健康なこころを意味するもので、生体のいろいろの力と環境の力との間のつり合いを保証している自然の法則と合致するように、毎日の生活を統御することによってのみ達成できるものである。
医療は倫理的職業であり、人間の条件への尊敬の態度を意味するものである。」
さらに「医学的心理学史」のジルボーグは言う。
「ヒポクラテスは、身体病と精神病を分けなかった。」「彼(ヒポクラテス)においては、解剖学、生理学、心理学の三つが同盟を結んでいるように推論されるが、・・・」
「プラトンは、一歩後退して『精神と物質の二つの原理があるが、・・・・』という心身二元論をとり、アリストテレスも二元論をとっている。」「ヒポクラテス主義はすでに、精神医学において実を結んでいた。」
川喜田はヒポクラテスについて、「二元論を彼は斥け、すべてを統一的な自然の中で考えようとする。」彼は病気を外から人に臨む「実体」としてではなく、「病んだ人」として眺める。言いかえればそれ(病気)を人の状態として把握する。「助力せよ、せめて損なうな」
と言っているという。
ここから導き出されるのが、心身一元論であり、病原環境説なのである。
病気は自分の中に生ずるものなのである。外から入って来たものではない。入って来たものはウィルスや細菌や異物であるが、その結果起きる病気はウィルスや細菌に対して闘っている自分の身体の変化なのである。死体にうじがむらがっても、死体はなすがままになり、反応しない。生体であるから、防御反応をし、それが病気なのである。細菌は死体でも生きているが、死体が細菌の栄養にならなくなると死んでしまう。ウイルスは、細胞の中でしか繁殖しないから、細胞の死と共にそこで繁殖できず、細胞内で死んでしまう。細菌やウイルスは、人間が生きているから、それに対する反応として病気になる。つまり、病気は自分の体の変化なのである。
精神的・心理的病気も、自分のこころの持ち方から生じる自分の身体の変化である。
成人病も膠原病もがんも、すべてこれ(病原環境論または適応説)で説明できる。悩んでいた説明がつかなかった先天性、遺伝性の病気も、ゲノムの解析と遺伝子学の進歩によって、説明できるようになった。そのことは、別の項で話すことにする。
2)人間とは
私は、「人間はこころと身体を持つ社会的存在である」としてとらえ、その人間がかかる病気として病気をとらえる。
「人間とは考える芦である」という古典的時代ではもうないが、でもまだこころというものが見えない為に多くの人々や医者に誤解がある。
人間にはこころがあり、物事を考え、記憶していく能力があるが、こころは大脳の活動から生じるのであり、しかも人間の社会で育てられなければ人間のこころをもつことができないのである。他の動物たち(有袋類を除く)のように、生まれたらすぐ、自力で立ち上がったり、母親にしがみついたりすることはできない。有袋類ですら、自力で母親の袋の中に入る。人は、一年早く生まれたという説(ボルトマンの「子宮外早生の一年」という概念――三浦雅士「身体の零度」より)も、「なぜか、どのように進化してそうなったのかと」いう疑問と共に、彼の言う「人間の最も重要な特徴――立つこと、話すこと、考えることという三主徴――が社会的環境との接触によってはじめて形成されていく・・・」ことも検討に値するだろう。
人間はロビンソン・クルーソーのようにたった一人では生きていけない。つまり、人間はその生命活動を社会的に営む社会的生物である。人間が社会を造り出したが、社会が出来てしまうと社会が一人一人の人間を拘束し、影響を及ぼす。病気はその社会によって大きく左右され、社会は自然環境によって左右され、また人は自然環境や社会環境を変えていく。社会は文明を持ち、社会としての活動がある。
疎外、管理社会、戦争と平和、不況と好況 。
今までによく現代医療に対して病気しか見ず、病人を見ないとの批判があった。既にアメリカではがんなどの病気で入院すると多くの各科専門医たちのほかに、精神科医師や心理療法士、病院付きの牧師まで来て、病人が病気を治す為のこころの面での援助をしてくれる。スポーツをすることで気持ちをまぎらわせようと思えば、スポーツの指導員も来てくれる。乳がんで死んだ池田敦子さんの言うように日本に比べたら格段の差がある。
現代アメリカの医療の中身は日本よりはずっとましなのだが、私の考えている「新たなる医療」と比べると、こころの持ち方の方向が違うし、社会的視野が欠けている。それに医療を受けられる人が限られているのが問題である。(問題なのは、アメリカ医療は金のある人だけの為にあることだが、それは医療の問題ではなく、医療制度の問題であるのでここでは省略する。しかし、現在の状況では、日本もアメリカ化しつつある。)
さて人間と動物の違いは大脳皮質、特に新皮質系にある。「動物のなかで新皮質系がもっとも発達しているのは、人間であるし、人間の進化の過程をみても、脳の容積の増大とともに、新皮質系、とくに前頭葉の発達が著しい。人間を社会的動物であらしめ、・・るのはまさにこの新皮質系の作用である。」(田中正敏「ストレスの科学と健康」より)つまり人間の特徴は社会性にある。このように大脳の発達から見ても人間は社会的動物であることが分かる。
「野生児の記録」(R.M.ジング)によれば、狼や熊に育てられた野生児の世界の結論として「人間は生まれてから幼児期または6~7才頃迄に人間社会から断絶されると、人間としての生活が営めなくなる。特に幼少期に隔絶されると四つ足で走る方が速くなる。(二本足で歩けない)言葉も習得できなくなる。人間は、人間社会の中でしか、人間らしく生きられないのだ。人間世界をいろいろな理由で離れた野生児たちは戻されてももう普通の人々と同じような生活には決して戻れないのである。生まれてから人間世界(社会)の中で育てられることが、人間らしさを得るただ一つの手段なのである。」という。人間は常に「社会的に」人間なのである。
狼に育てられた人間はその後言葉を覚えても、記憶に残り話すことが出来ることは言葉を覚えてからのことだけである。言葉を覚える以前のことは決して言葉として語ることはできないのである。人間は生まれながらにして人間ではなく、「人間として」生まれ、かつ「人間として」育てられることが人間になるために必要なのである。
さらに言えば、民族や人種の違いは生まれつきではなく、生まれ育った自然や社会の環境や文化によって違って来ている。よく雪国の子はすぐあきらめてしまい、南国の子はあきらめずに頑張ると、高校野球で言われるが、雪という自然がそこに住む人々のこころを大きく左右するのは不思議ではないと思う。最近は、南国の指導者が来て北国の高校野球も変わりましたが。
このように私は以前から人種や民族による差は少なく、むしろ生まれ育った環境によって変わるのではないか考えていたが、それを証明してくれた人がいた。
「DNAは生物の体の中で、不変なものではなく、つねに変化し動きまわるダイナミックな存在である。DNAが変化する形で、遺伝子が細胞の中で変化する。」ということを証明した利根川進博士の業績は、「環境によって人間の身体やこころが変わり、それが遺伝子によって伝えられる。」という環境を重視する私の考えを裏付けてくれたのである。
そしてアメリカ人は多民族国家ですが、どの民族でも二代三代と経つ内に考え方も、かかる病気もアメリカ化されてしまう。日本人も、一世、二世、三世と次第にアメリカ人共通の病気になるようになっていく。日本では民族差を強調する人が少なくないが、アメリカに住んでいる人々を見ると皆アメリカ人であって出身の民族の差は少なく、むしろ宗教とか国とかその人の住む社会の違いの方が大きい。アメリカに住むユタ州中心のモルモン教やニューヨーク州に住むクウェーカー教徒、アーミッシュの人々、それに日本にも多いセブンズデイ・アドべンチストたちは、アメリカ人の中で極めてかけ離れて、成人病が少ないと言う。
人間はこうしてこころと身体を持つ社会的存在であり、そのどれも切り離すことができない。人間はその身体があるからこころを持ち、そして社会的に存在するから人間でいられる。そして人間社会の中で育てられて人間になる。
そうした意味で人間を「こころと身体と社会的存在」の総体としてとらえ、その人間がなる病気について見ていきたいと思う。
WHO憲章の健康の定義にも「肉体的、精神的、社会的に良好な状態であって、単に疾病や虚弱のないことではない。」とあるように、これは私だけの考えではないようだ。
こころと身体の医学とかこころと身体の健康とかよく言われるが、それだけでは不十分であるし、人間が社会的存在であることを見ないことが問題である。つまりそういう考え方は社会が病気を生んでいることから人々の目をそらす役割を果たしている。病気は個人がかかるもので、社会や企業は関係がないとする方が、現代の支配体制側(資本主義、社会主義などを問わず)にとっては都合がよいのだから、そういう考え方(心療内科など)は支配階級的でさえある。
なぜなら、現代社会に適応できないで病気になった人を、薬やカウンセリングなどというまやかし(社会を変えずに、人を社会に合わせさせる)だと思う。本当は、社会を変えた方が、早く治るし、病気にならないで済むことが多い。残念ながら、私も社会を変えることができないから、薬を処方し、カウンセリングをしている。
3)社会的生物としての人間
前述もしたが、三浦雅士「身体の零度」によると、スイスの生物学者アドルフ・ボルトも重要な特徴――立つこと、話すこと、考えることという三主徴――が社会的環境との接触によってはじめて形成されていくということと、関連して考えられなければならない。・・・人間にとって社会的接触は必須のものである。新生児に対する集団の助力、すなわち愛情をもった世話が確かになされないと、姿勢、会話、精神生活、思考が、完全な人間性に導く軌道から外れていってしまう。」 またマンフォードは、「生物学的な幼児期が長くなったおかげで、人間は、利用できるあらゆる身体器官の実験が促進される可塑的、成形可能的な状態におかれ、もはや人間の器官は、ただ機能的な役割だけを尊重して扱われるのではなく、希望をもった精神の道具として新しい目的のために形づくられるようになった」という。三浦はそれを「いい換えれば、人間の身体は人為的に作られるもの、すなわち文化にほかならない、身体こそ人間にとって最初の文化であったのである。」と解釈している。まだまだ三浦の論文は続くが、私は、まさに私と同じ考えと考えている。
そして、三浦のいう近代の成立が、近代の病気を生み出してきたのである。姿勢、歩行、体育、会話、精神生活、思考、食事、衣服、住居、仕事、職場などの近代化が、現代の病気を生み出してきている。だから、今後も、社会の変化によって、新しい病気が次々とでてくることは、必定である。
















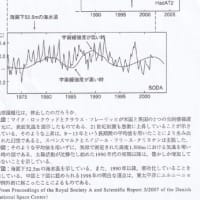
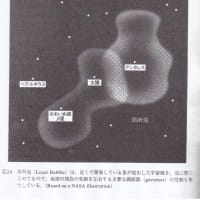
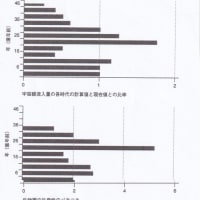
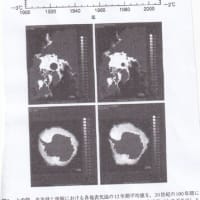
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます