色んな資料を基にまとめてみましたが、
万が一間違いなどありましたら、関係者の皆様、
お知らせ下さいませ。。。
英彦山の記録によると、平安時代の819年(弘仁10年)に
彦山が嵯峨天皇より寺領七里四方を与えられ、彦山の荘園となったとされています。
中世南北朝時代の1333年(正慶2年)12月、後伏見天皇第6皇子長助法親王が
南北朝の戦乱を逃れ、彦山の座主(ざす)として入御され、
その館を上座郡黒川村(現在の朝倉市黒川)につくり「黒川院」と称したとされています。
この長助法親王から舜有法主まで14代の座主が黒川に館を構えました。
1578年(天正6年)、当時の座主・舜有法主は、北部九州を押さえていた
豊後の大友家に対抗していましたが、筑前夜須郡の秋月種実が彦山に背き、
同年12月には黒川院も秋月軍により焼き討ちされ灰燼に帰しました。
その後、15代彦山世襲座主深有尼の時代の1587年(天正15年)の
豊臣秀吉による九州平定の後、彦山は領地を没収されてしまいます。
筑前に小早川隆景が入った後一時期同家により当地を寄進されますが、
再び取り上げられてしまい、座主は黒川を去ります。
この記録から、黒川院は約250年もの間続いており、
また、天皇家からの皇子が来られたことから、
位の高いお方が使っていたであろう様々な品物が発掘・出土しています。
また、彦山修験道の即身即仏を念ずる参龍修行場として、
「彦山流記」では49か所の霊窟をあげており、
黒川の岩屋権言もその1つといわれています。
なんで、こんなところにこんな岩が?!というような、
この地の山の大きさからすると大きすぎるくらいの
岩が祀られていますよ!
なお、彦山神領・彦庄内の各村に置かれていた彦山麓七大行事社の一つである
黒川高木神社は、平安時代822年(弘仁13年)の創建と伝えられています。
10月29日を中心に前後数日間行われるオクンチは、筑前朝倉の宮座行事として、
福岡県の無形民俗文化財にも指定されています。
万が一間違いなどありましたら、関係者の皆様、
お知らせ下さいませ。。。
英彦山の記録によると、平安時代の819年(弘仁10年)に
彦山が嵯峨天皇より寺領七里四方を与えられ、彦山の荘園となったとされています。
中世南北朝時代の1333年(正慶2年)12月、後伏見天皇第6皇子長助法親王が
南北朝の戦乱を逃れ、彦山の座主(ざす)として入御され、
その館を上座郡黒川村(現在の朝倉市黒川)につくり「黒川院」と称したとされています。
この長助法親王から舜有法主まで14代の座主が黒川に館を構えました。
1578年(天正6年)、当時の座主・舜有法主は、北部九州を押さえていた
豊後の大友家に対抗していましたが、筑前夜須郡の秋月種実が彦山に背き、
同年12月には黒川院も秋月軍により焼き討ちされ灰燼に帰しました。
その後、15代彦山世襲座主深有尼の時代の1587年(天正15年)の
豊臣秀吉による九州平定の後、彦山は領地を没収されてしまいます。
筑前に小早川隆景が入った後一時期同家により当地を寄進されますが、
再び取り上げられてしまい、座主は黒川を去ります。
この記録から、黒川院は約250年もの間続いており、
また、天皇家からの皇子が来られたことから、
位の高いお方が使っていたであろう様々な品物が発掘・出土しています。
また、彦山修験道の即身即仏を念ずる参龍修行場として、
「彦山流記」では49か所の霊窟をあげており、
黒川の岩屋権言もその1つといわれています。
なんで、こんなところにこんな岩が?!というような、
この地の山の大きさからすると大きすぎるくらいの
岩が祀られていますよ!
なお、彦山神領・彦庄内の各村に置かれていた彦山麓七大行事社の一つである
黒川高木神社は、平安時代822年(弘仁13年)の創建と伝えられています。
10月29日を中心に前後数日間行われるオクンチは、筑前朝倉の宮座行事として、
福岡県の無形民俗文化財にも指定されています。















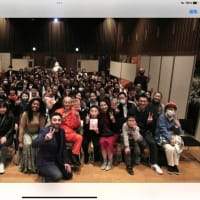


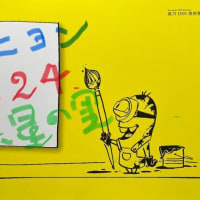
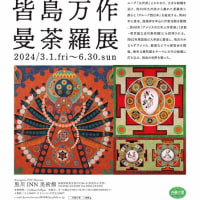
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます