本日、北上川源流とされる「弓弭(ゆはず)の泉」にいって来ました。
出るときは小雨模様で心配しましたが、あちらは曇天ではあるものの雨は降らず、まあなんとかがんばってきました。
北上川の源流はいろいろな説があるようですが「ここが源流!」と一番最初に手を上げたこの「弓弭(ゆはず)の泉」が源流とされたようです。
ここは坂上田村麿が建立したという「御堂観音」(天台宗北上山新通法寺正覚院)があり、その社の脇の杉の木の根元から水が湧いています。
源義家が前九年の役のとき、水を求めて弓弭(弓の先端で弦をかけるところ)で岩を穿ち探し当てたとされている泉です。
しかし、弓の先端で探すより矢のほうが穿つのにはいいと思うのです。
したがって、弓をいって矢が到達したところから水が湧き出た、というお話のほうが説得力があるとは思うのですが・・・
また、杉の木の根元から水が湧くというのは、よく知られている話であって、源義家がわざわざ探さなくても・・・とまあ、あまり深く追求しないほうがいいわけで、ともかく伝説を持っているところで他の誰もが出をあげる前に「源流」と名乗り出たことが勝因といえるでしょう。
今は「川の駅」なるものが整備され、私が始めて訪れた20年前とは比べ物にならないくらいになりました。
岩手町ではここを何とかして観光にと思っているのでしょうが、HPで「安部瀬時征伐」と「頼時」を「瀬時」としたり「征伐」といかにも安部一族が悪いように書いているのは「なんだかなあ」と思ったりするのです。
源流の帰りによった、道の駅「石神の丘」に隣接する石神の丘美術館の屋外彫刻場のラベンダーはちょうど見ごろでした。
出るときは小雨模様で心配しましたが、あちらは曇天ではあるものの雨は降らず、まあなんとかがんばってきました。
北上川の源流はいろいろな説があるようですが「ここが源流!」と一番最初に手を上げたこの「弓弭(ゆはず)の泉」が源流とされたようです。
ここは坂上田村麿が建立したという「御堂観音」(天台宗北上山新通法寺正覚院)があり、その社の脇の杉の木の根元から水が湧いています。
源義家が前九年の役のとき、水を求めて弓弭(弓の先端で弦をかけるところ)で岩を穿ち探し当てたとされている泉です。
しかし、弓の先端で探すより矢のほうが穿つのにはいいと思うのです。
したがって、弓をいって矢が到達したところから水が湧き出た、というお話のほうが説得力があるとは思うのですが・・・
また、杉の木の根元から水が湧くというのは、よく知られている話であって、源義家がわざわざ探さなくても・・・とまあ、あまり深く追求しないほうがいいわけで、ともかく伝説を持っているところで他の誰もが出をあげる前に「源流」と名乗り出たことが勝因といえるでしょう。
今は「川の駅」なるものが整備され、私が始めて訪れた20年前とは比べ物にならないくらいになりました。
岩手町ではここを何とかして観光にと思っているのでしょうが、HPで「安部瀬時征伐」と「頼時」を「瀬時」としたり「征伐」といかにも安部一族が悪いように書いているのは「なんだかなあ」と思ったりするのです。
源流の帰りによった、道の駅「石神の丘」に隣接する石神の丘美術館の屋外彫刻場のラベンダーはちょうど見ごろでした。











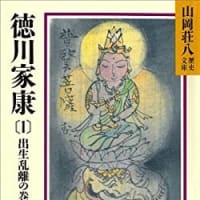
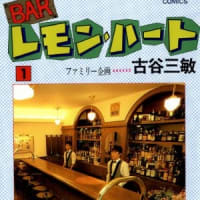
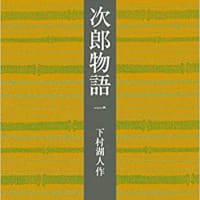
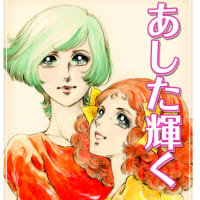
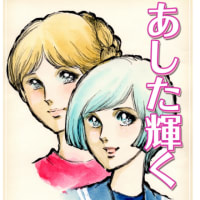
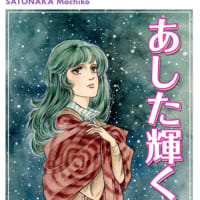
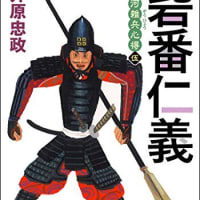
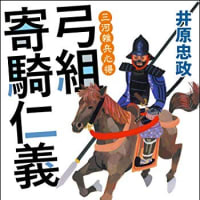
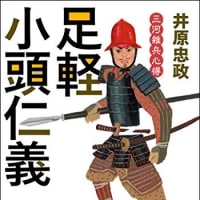
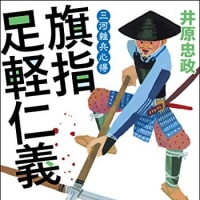






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます