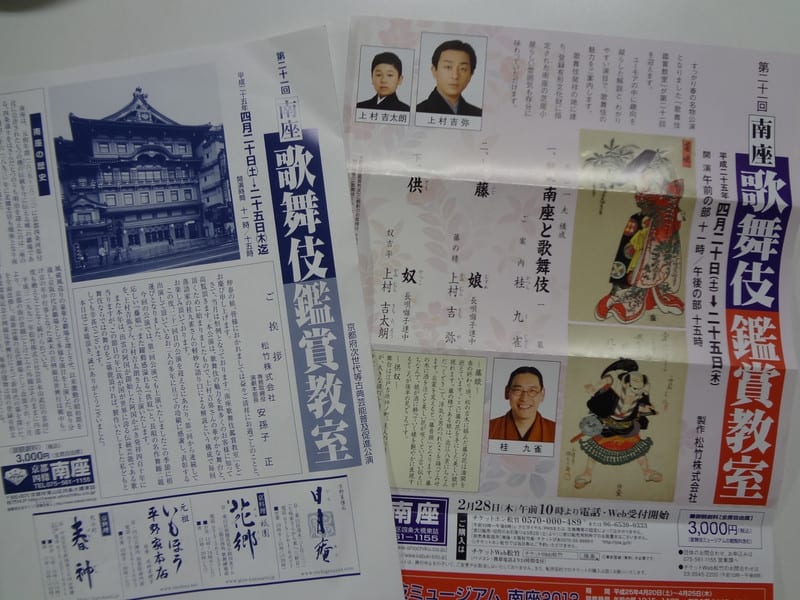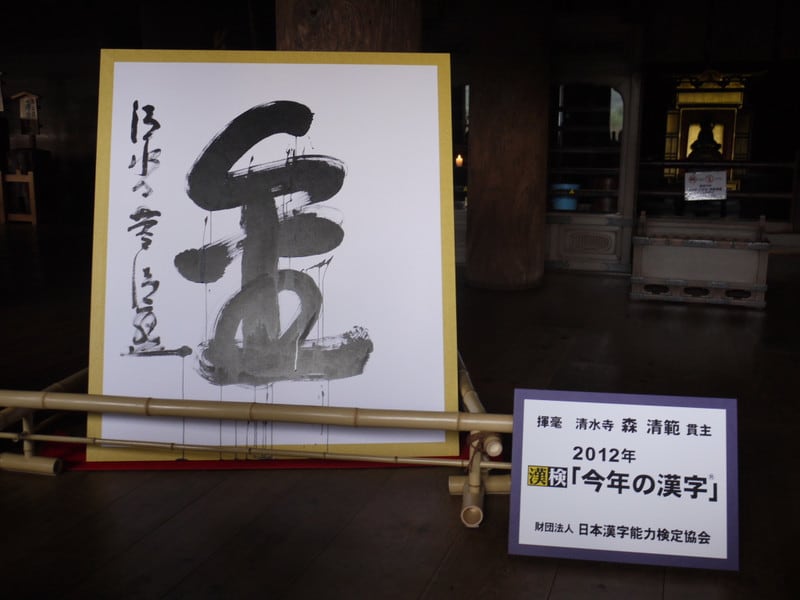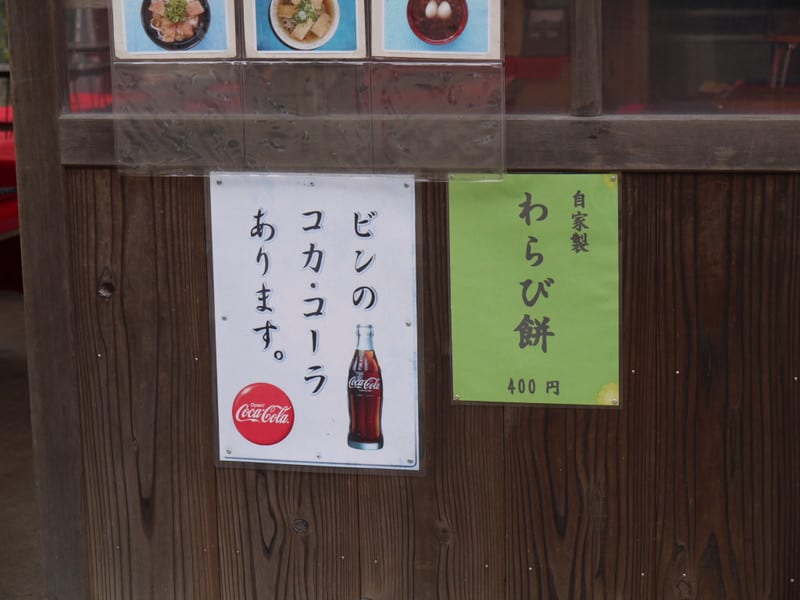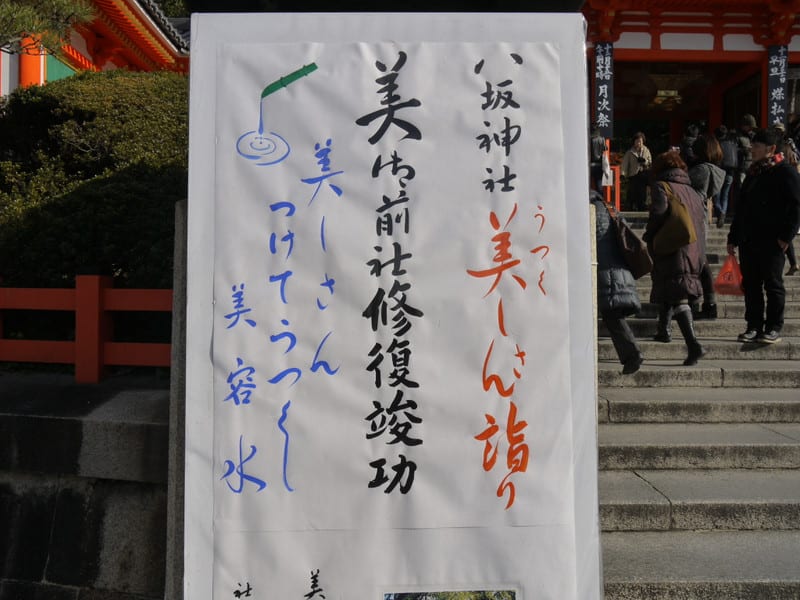今日は出かけた帰りに、東大路七条にある「智積院(ちしゃくいん)」へ行ってきました。智積院は、真言宗智山派の総本山です。全国に末寺が3千余ヶ寺、檀信徒は30万人を擁し、その中には、成田山新勝寺、川崎大師平間寺など有名なお寺もあります。江戸時代、豊臣秀吉の子、鶴松の供養のためのお寺「祥雲禅寺」の跡地を、玄宥僧正に家康が寄進し、紀州根来寺(ねごろじ)の塔頭の智積院を再興したことにはじまります。なお、紀州の根来寺は秀吉によって焼払われています。
東大路に面し、七条通りの東の突き当りのため、お寺の前を通った事をある人は多いかもしれませんが、観光というより総本山としての存在感からか、ゴールデンウィーク期間中でも、観光客は少ないです。境内に入ると、街の騒がしさを忘れてしまうほど静かです。あちこちに紅葉の木が植えられ、特に、本堂(右上写真)の前の紅葉の木は、驚くほど幹が太いです。(左下写真)
寺紋は「桔梗紋」、境内のあちこちに桔梗のモチーフが使われています。智積院の前身の「祥雲寺」を秀吉に命じられて建てた加藤清正の家紋が桔梗紋だったため、その功績を讃えてとの事だそうです。写真は、ルーツの根来寺から持ってきたという不動明王像を祀る「明王殿」と、その屋根です。
本堂の、屋根の上や屋根の内部の飾りも桔梗です。
たたみのへりも桔梗、そして当然、境内のあちこちに桔梗が植えられています。桔梗は冬には根のみで地上は枯れてしまいますが、今の季節は再び芽を出し葉を広げています。今年も初夏には花がいっぱい見られそうです。
以上、参拝は自由にできますが、以下、収蔵庫と名勝庭園は有料です。
左下写真:収蔵庫には、国宝の楓、桜、松に秋草など大きな壁画が展示されています。作者は、長谷川等伯(はせがわとうはく)一派で、等伯は石川県の七尾で生まれ、墨絵を中心に仏画や肖像画を描いていました。その後上京して狩野派の門をたたきましたが作風が合わず、狩野派と対立する立場となった人です。
障壁画のうち、等伯の長子、久蔵の25歳の作である桜図と、その久蔵が26歳で急逝した翌年に父である等伯が描いた楓図は、日本の壁画を代表するものとして知られています。収蔵庫には、対立していた狩野派の障壁画も展示されています。狩野派の壁画は大きな松の木が1本描かれていますが、どーんと重圧感があり、豪華で装飾的、立派な植木鉢の松って感じです。一方、長谷川派の壁画は、写実的でやさしく、自然の広がりを感じます。(あくまでも私見) 右下写真:名勝庭園のある大書院の入り口です。
名勝庭園を眺める大書院で、その国宝の長谷川等伯一派の障壁画の模写(レプリカ)を見ることができます。収蔵庫内は撮影NGですが、大書院は撮影OKです。
左下写真:等伯の息子(26歳で急逝)が描いた桜図の模写一部。右下写真:息子が亡くなった翌年に等伯が描いた楓図の模写一部。大書院の障壁画はとても鮮やかですが、収蔵庫の実物は顔料で描かれ、時代を経て深みを増し迫力があります。本来の障壁画は火災等で焼失し、現存し模写されているのは実物の4分の1程なのだそうです。本来は見上げるほどの大きな木が描かれていたのですね~。見てみたかった・・・。
大書院からの眺める名勝庭園です。 利休好みの庭と伝えられ、中国の蘆山を形どって造られています。池にかかる石橋から奥は、智積院の前身の祥雲禅寺(秀吉の愛児鶴松の菩提寺)のものです。桃山時代の庭の特色である自然石のみを用い、庭の外にある大木を借景とし、深山の中にあるような奥行きのある庭です。派手好きだった秀吉の好みなのか、植え込みが「バチ」の形になっています。わかります?写真の右から柱1本目と2本目の間です。
ツツジの咲く頃が一番華やかとのことですが・・・開花はもう少し進むのかな?つぼみはそれほど確認できませんので、このくらいなのでしょうか。以前訪ねた3月の様子【前ぶろぐ】バチがよくわかります。ちなみにこのお庭、その昔、メナードのCMで岩下志摩さんが佇んでたところです。BGM♪は徳永英明さん。
じーっと見てると・・・カメさん発見。そして、羅漢石の上にカワセミ???ちゃんと写真を撮ろうと思ったとたん、瑠璃色の羽を広げて飛んで行ってしまいました。(TmT)
この庭は小堀遠州の作とも伝えられているそうです。この庭が造られたときはすでに利休は亡くなっており、利休ならこんな庭を好むのでは?と作られたそうですが・・・庭の水を常に濁らせ、緑を映りこむように工夫したり、バチ形の植込み、作庭当初は書院自体が池に浮いてた説?など、どちらかというと秀吉好みのような(・・?)まぁ、どちらの方にもお目にかかったことないので、よくわかりませんけどねぇ。
大書院内もぐるりと拝観することができます。智積院にはたくさんの襖絵があります。今日は、平成20年に奉納された「日本の春夏秋冬」を題材にした墨絵の襖絵などが各部屋に展示されていました。以前、非公開文化財特別公開の際には、堂本印象の襖絵を見ています。【前ぶろぐ】
今日から5月。クール・ビズ、鴨川の川床も始まりましたが・・・時折吹く風も冷たく寒い日でした。ゴールデンウィークの中日という事もあり、拝観客は少なかったです。全くいないわけじゃないです。なるべくいない時を狙って写真を撮っています。σ(^^;)
総本山 智積院 http://www.chisan.or.jp/
参拝自由 参拝者用駐車場有 庭園・収蔵庫拝観料(大人500円、中高300円、小200円) 拝観所要時間:50分~