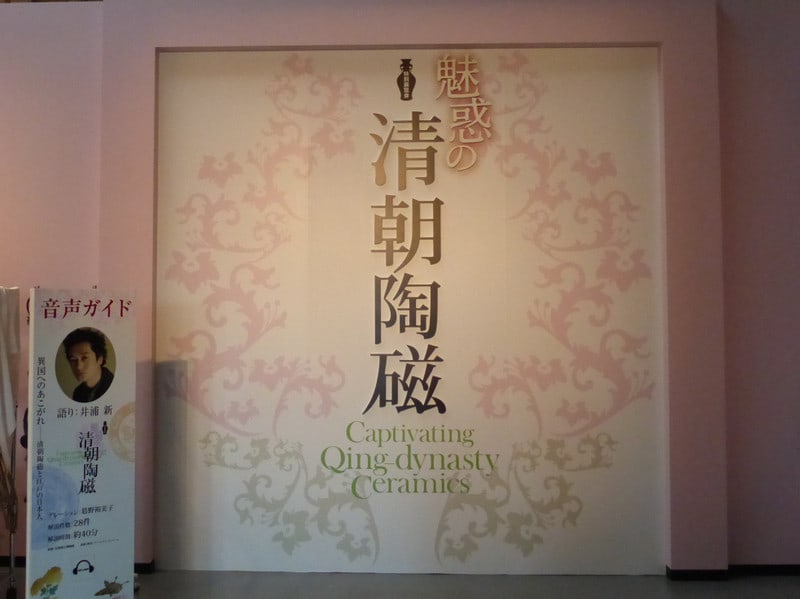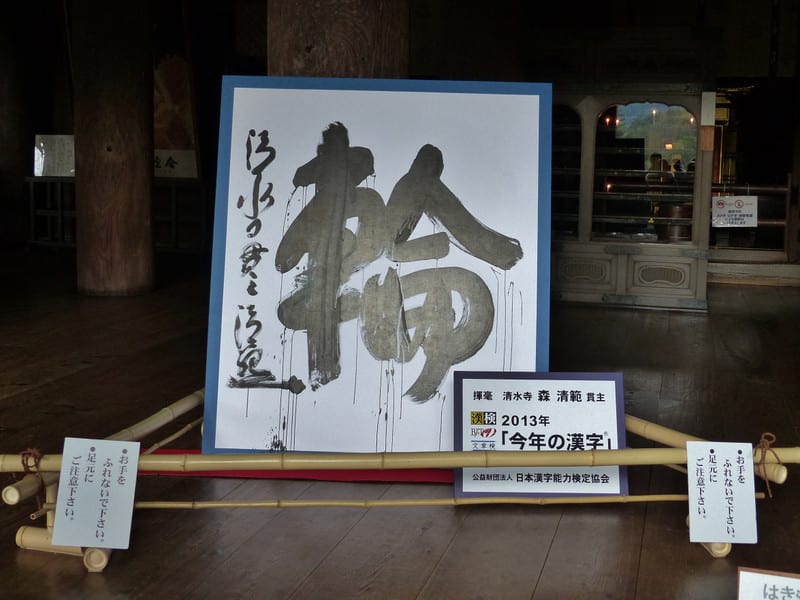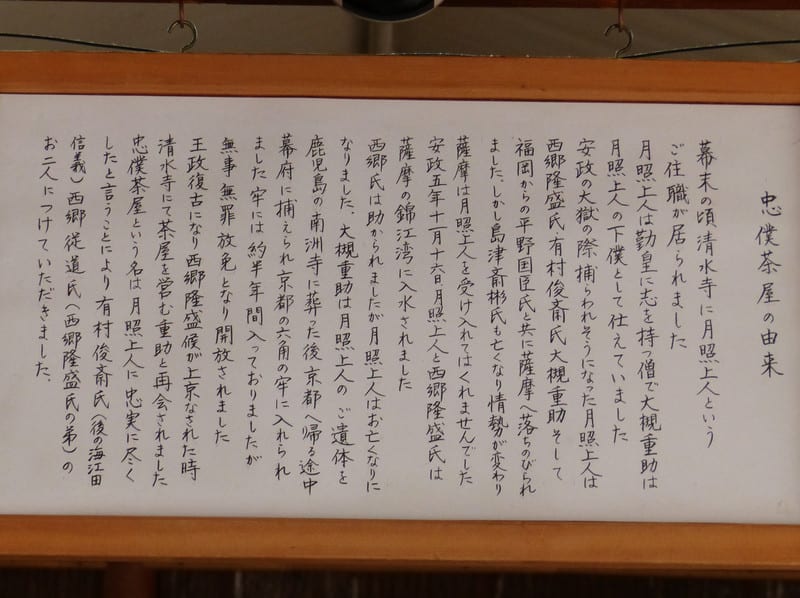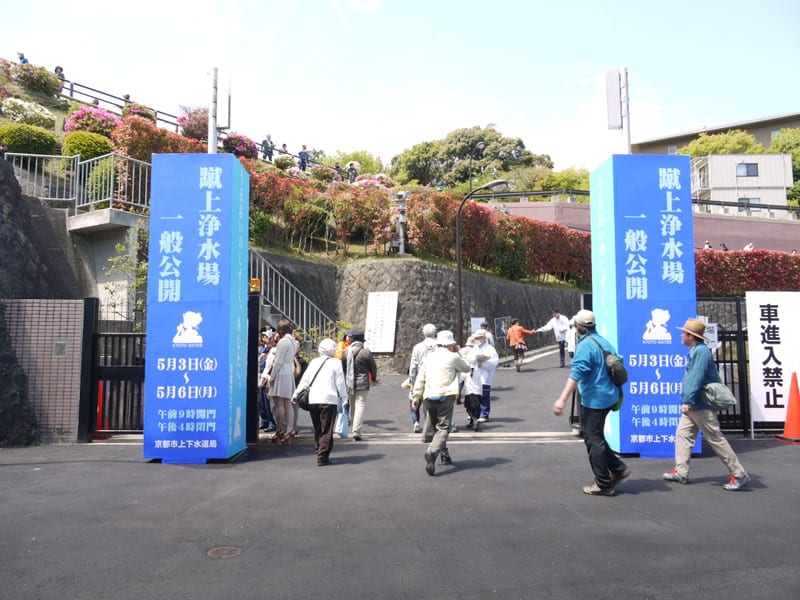先日「第48回京の冬の旅 非公開文化財特別公開」で塔頭を公開中の建仁寺へ行ってきました。建仁寺は、臨済宗建仁寺はの大本山で、鎌倉時代の建仁2年(1202)の開創です。寺号は当時の年号から名づけられています。
先に、開山師であり、日本に臨済宗を伝えた栄西禅師の御廟所の開山堂をご紹介しました。【前ぶろぐ】 続いて「正伝永源院(しょうでんえいげんいん)」です。右下地図の赤マルの場所が、花見小路からまっすぐ行ったときにくぐる門(左下写真)です。門をくぐらずに手前の道を右折(西)です。写真クリックで拡大
「正伝永源院」は、織田信長の弟(織田信秀の十一男)である織田有楽斎(長益)と、熊本藩主細川家の菩提所として知られる建仁寺の塔頭寺院です。明治6年に、もともと祇園にあった「正伝院」と、この地にあった「永源庵」が合併しました。
「正伝院」は鎌倉時代に創建、室町時代に起こった応仁の乱の後に荒廃しますが、元和4年(1618)、織田有楽斎(おだうらくさい)によって再興し、隠居所と茶室を建てます。有楽斎は、千利休に師事した大名茶人として知られ、茶道有楽流の始祖として名を残した人です。
「永源庵」は、南北朝時代に創建、細川頼有が禅に帰依したことが縁で、和泉上守護家細川氏8代の菩提寺となり、さらに、この系統から出た細川幽斎・細川三斎父子を祖とする熊本藩主家細川氏の菩提寺の一つともなったお寺です。
受付を済ませ、境内に入ると、すぐ細川家の大きな墓があります。
その後、方丈へ・・・。中央の仏間に残るのは「蓮鷺図(れんろず)」で、蓮の花と鷺や燕などの鳥を描いた金碧(こんへき)の襖絵です。狩野山楽の作と伝えられており、咲き始めから満開、そして、盛りを過ぎるまで、蓮池の時間的経過を追うような画面構成になっていて、人生とも重なります。
 少しだけ開いた襖の奥には、織田有楽斎のおもかげを伝える木像が安置されています。写真撮影NG。左写真は看板のものです。
少しだけ開いた襖の奥には、織田有楽斎のおもかげを伝える木像が安置されています。写真撮影NG。左写真は看板のものです。
仏間の両側の部屋には、第79代内閣総理大臣の細川護煕(もりひろ)氏が平成25年に自ら描かれた襖絵を奉納されています。東山の夜桜を描いた「知音(ちいん)」 と西山の暁の紅葉を表した「秋聲(しゅうせい)」です。ふわっとしてやさしいお人柄がでてるな・・・と思います。お目にかかった事ないけど。(^^;)
以前、苔寺の近くにある「竹の寺(地蔵院)」でも、細川護煕氏が描かれた水墨画を見ています。【前ぶろぐ】地蔵院も細川家の菩提寺です。(細川家ゆかりのお寺は全国に200近くあるそうです)
庭園には、有楽斎が建てた茶室「如庵(じょあん)」が復元されています。内部を覗くと、腰貼り(壁下部)の部分に古い暦が使われているのがよく見えます。ちなみに如庵という名は、有楽斎のクリスチャンネームのジョアンからきてるとか?内部撮影はNGです。
なお、オリジナルの茶室は国宝に指定されています。祇園の正伝院境内から、東京の三井本邸、大磯の別荘に移築され、現在は、愛知県犬山市にある有楽苑に移築されています。
第48回京の冬の旅 非公開文化財特別公開【こちら】
京都市観光協会 http://www.kyokanko.or.jp/
公開場所によっては、拝観休止日や期間が大きく違いますのでご注意ください。 拝観料:1ヶ所600円(場所によって違う場合もあります)所要時間は公開場所によって違いますが各所約30分~。専門ガイドによる説明があります。「寺町 阿弥陀寺」【前ぶろぐ】「報恩寺」【前ぶろぐ】妙顕寺【前ぶろぐ】スタンプラリー【前ぶろぐ】妙心寺聖澤院【前ぶろぐ】龍泉菴【前ぶろぐ】建仁寺開山堂【前ぶろぐ】
建仁寺 http://www.kenninji.jp/index.php
第48回京の冬の旅で公開予定の塔頭の両足院の公開は3月1日からです。昨夏、半夏生の庭をご紹介しています。【前ぶろぐ】通常は本坊・方丈・法堂の拝観ができます。詳細は【前ぶろぐ①】【前ぶろぐ②】にて。