うーん、どうやって答えたらいいんだろう?
他にもこんな質問をいただいていました。
Q.普段はどんなことをしているんですか?
Q.どのような研究をしているのですか?
Q.倫理学者になるとなにか研究したりするのですか?
また、するとしたらどのようなことですか?
そこまで謎ですか、倫理学者の生活は?
「なにか研究したりするのですか?」 には参りました。
そこを疑われてしまうと、あとはいったい日々なにをやっていると思われているのだろう?
もちろん研究したりしています。
ただしここ (「哲学・倫理学の先生になろうと思ったきっかけは?」) にも書いたように、
研究だけで収入を得られるということはまずありません。
自分で研究書を書いて出版したり、欧米の研究書を翻訳して出版したりすることはありますが、
それで儲かることはまずありません。
むしろ出版すると自腹を切らなければいけないことのほうが多いです。
ごく稀に論文や教科書を書いて印税がもらえるということもありますが、
その場合も、その論文を書くためにたくさんの研究書を買って読んだりしなければいけませんので、
トータルは赤字になります。
したがって倫理学者は、ただの研究者として倫理学の研究をしているだけでは、
「職業」 としてそれで食ってはいけないのです。
ここで倫理学者の中にも格差が生じてきます。
たまたまラッキーなことに大学教員になれた人と、まだ大学教員になれていない人です。
私は前者ですが、未だに後者だったとしてもなんの不思議もなかったのです。
後者の場合は、研究とは別になにかしら手に職をもっておかなくてはなりません。
多くの人は塾の講師や高校の非常勤講師など教育関係の仕事に就いています。
その場合、教育といっても倫理学に関係することを教えられるとは限りません。
私の場合は小中学生相手に数学と英語を教えていました。
家業がある人は家業を手伝ったりしていることもありますが、
そうなると教育の仕事とも限らなくなるわけですね。
こうなってくると倫理学者というのは職業でもなんでもなく、
むしろバイトや家業のほうが職業であって、倫理学は趣味みたいな位置づけになるのかもしれません。
では大学教員になれた人の場合はどうでしょうか?
その場合は幸いなことに、「倫理学者=職業」 に限りなく近づいてきます。
とはいえその場合も、倫理学の 「研究」 で直接お金をもらうというよりは、
教員として 「教育」 の仕事に携わることによってお金を稼いでいるといったほうがいいでしょう。
一昔前は、学者は研究するのが仕事だみたいな国民的コンセンサスがあったのですが、
最近ではそういう見識がどんどん失われてきていて、
大学教員は教えてナンボだみたいな圧力がどんどん高まってきています。
これは長い目で見て国家の根幹を揺るがしかねない由々しき事態だと私は思いますが、
日本のように国家の大計をもたないまま禁治産国家になってしまった国では、
しかたのないことなのかもしれません。
それでも大学教員になれた倫理学者は、倫理学を教えることを職業にできるのですから、
それ以上贅沢を言ってはいけないのでしょう。
それでは、大学教員になれた倫理学者は、
研究と教育という2つの仕事をやっているのでしょうか?
残念ながらそれだけではありません。
そのほかに大学教員には、大学運営という仕事が課されています。
入試をやったり、カリキュラムを組み換えたり、学生生活を支援したり、
就職の手助けをしたり、留学生の面倒をみたり、受験生を増やすために大学の広報をしたり、
そしてそれらのためにありとあらゆる事務書類を作成・提出したり、などなどなどなど、
それはもうたくさんの仕事がどっさりあります。
そうしたことを処理するためにいろいろな委員会が設けられ、たくさんの会議が開かれます。
パソコンとインターネットが導入されて以来、こうした仕事がますます増えており、
今や研究や教育よりも大学運営のための仕事の比重のほうが大きくなっているかもしれません。
これに加えて近年では、大学教員は地域貢献をしなければいけない、
という圧力も高まってきました。
例えば看護学校で 「哲学」 や 「倫理学」 を教えているのも地域貢献の一環です。
もちろん教えているわけですから、教育の仕事とも言えますが、
これはmustの仕事ではありません。
また普通よりはかなり高い時給もいただいていますが、
確定申告をしたらごっそり持っていかれますので、
時間と労力を使うよりも、お断りしてその分、
自分の研究や福島大学での教育に時間を割きたいというのが本音です。
しかしながら、特に地方の場合、哲学者・倫理学者が県内にそれほどいるわけではありませんので、
これをお断りしてしまうと、県内のさまざまな教育が立ち行かなくなってしまうのです。
倫理学者の場合、ほかに公開講座や高校での出前授業など、教育っぽい仕事が中心になりますが、
場合によると倫理規定の策定などの地方自治体やら企業の仕事が舞い込んでくることもありえます。
こういったことにも積極的に取り組んでいくよう求められているわけです。
というわけで、大学教員になることのできた倫理学者には、
以上のようなさまざまな仕事があって、日々それらに追われているわけです。
ですので、最初の質問に対する答えは次のようにまとめておきましょう。
A.倫理学者 (大学教員になることのできた者) は、
倫理学の研究と教育、大学運営の雑務、地域貢献のための事業などを行う職業です。
大学教員にまだなっていない場合は、倫理学者として倫理学の研究に携わる以外に、
生きていくためのなんらかの職業をもっていることが多いです。
こんな感じでしょうか。
では、倫理学者はどんな研究をしているのでしょうか?
これについては十人十色ですのでひと言で言いにくいですが、
ざっくり言うと、倫理について批判的・懐疑的に研究しています。
しかも、すでに歴史のある学問ですので、
まったく0から研究し始めるというのは時間のムダですから、
とりあえずは、誰かの倫理思想についてその人の本や論文を読むところからスタートします。
それらを批判的・懐疑的に検討していく中で、しだいに独自の倫理思想が育まれていくわけです。
具体的に私の場合はということでいうなら、
私のホームページを見てみてください。
それを見るとだいたい私が何を研究しているかわかってもらえるのではないでしょうか。
いや、読んでもわからないかなあ?
このブログで書いているのとはだいぶレベルが違うというか、
学問的な積み重ねの上で研究を進めなくてはなりませんので、
難しい専門用語なども使わざるをえません。
自分が最先端で研究している内容を、
このブログを読んでくださっている方々にもすっきり理解してもらえるぐらい、
明快に説明できるようになるといいのですが、なかなかその域に達するのは困難です。
いずれこのブログにも、まずはカント倫理学に関するカテゴリーを起ち上げて、
皆さんにわかりやすくカント倫理学を語れるようになりたいと思っています。
ちょっとまだその準備は整っていませんので、もうしばらくお待ちください。
他にもこんな質問をいただいていました。
Q.普段はどんなことをしているんですか?
Q.どのような研究をしているのですか?
Q.倫理学者になるとなにか研究したりするのですか?
また、するとしたらどのようなことですか?
そこまで謎ですか、倫理学者の生活は?
「なにか研究したりするのですか?」 には参りました。
そこを疑われてしまうと、あとはいったい日々なにをやっていると思われているのだろう?
もちろん研究したりしています。
ただしここ (「哲学・倫理学の先生になろうと思ったきっかけは?」) にも書いたように、
研究だけで収入を得られるということはまずありません。
自分で研究書を書いて出版したり、欧米の研究書を翻訳して出版したりすることはありますが、
それで儲かることはまずありません。
むしろ出版すると自腹を切らなければいけないことのほうが多いです。
ごく稀に論文や教科書を書いて印税がもらえるということもありますが、
その場合も、その論文を書くためにたくさんの研究書を買って読んだりしなければいけませんので、
トータルは赤字になります。
したがって倫理学者は、ただの研究者として倫理学の研究をしているだけでは、
「職業」 としてそれで食ってはいけないのです。
ここで倫理学者の中にも格差が生じてきます。
たまたまラッキーなことに大学教員になれた人と、まだ大学教員になれていない人です。
私は前者ですが、未だに後者だったとしてもなんの不思議もなかったのです。
後者の場合は、研究とは別になにかしら手に職をもっておかなくてはなりません。
多くの人は塾の講師や高校の非常勤講師など教育関係の仕事に就いています。
その場合、教育といっても倫理学に関係することを教えられるとは限りません。
私の場合は小中学生相手に数学と英語を教えていました。
家業がある人は家業を手伝ったりしていることもありますが、
そうなると教育の仕事とも限らなくなるわけですね。
こうなってくると倫理学者というのは職業でもなんでもなく、
むしろバイトや家業のほうが職業であって、倫理学は趣味みたいな位置づけになるのかもしれません。
では大学教員になれた人の場合はどうでしょうか?
その場合は幸いなことに、「倫理学者=職業」 に限りなく近づいてきます。
とはいえその場合も、倫理学の 「研究」 で直接お金をもらうというよりは、
教員として 「教育」 の仕事に携わることによってお金を稼いでいるといったほうがいいでしょう。
一昔前は、学者は研究するのが仕事だみたいな国民的コンセンサスがあったのですが、
最近ではそういう見識がどんどん失われてきていて、
大学教員は教えてナンボだみたいな圧力がどんどん高まってきています。
これは長い目で見て国家の根幹を揺るがしかねない由々しき事態だと私は思いますが、
日本のように国家の大計をもたないまま禁治産国家になってしまった国では、
しかたのないことなのかもしれません。
それでも大学教員になれた倫理学者は、倫理学を教えることを職業にできるのですから、
それ以上贅沢を言ってはいけないのでしょう。
それでは、大学教員になれた倫理学者は、
研究と教育という2つの仕事をやっているのでしょうか?
残念ながらそれだけではありません。
そのほかに大学教員には、大学運営という仕事が課されています。
入試をやったり、カリキュラムを組み換えたり、学生生活を支援したり、
就職の手助けをしたり、留学生の面倒をみたり、受験生を増やすために大学の広報をしたり、
そしてそれらのためにありとあらゆる事務書類を作成・提出したり、などなどなどなど、
それはもうたくさんの仕事がどっさりあります。
そうしたことを処理するためにいろいろな委員会が設けられ、たくさんの会議が開かれます。
パソコンとインターネットが導入されて以来、こうした仕事がますます増えており、
今や研究や教育よりも大学運営のための仕事の比重のほうが大きくなっているかもしれません。
これに加えて近年では、大学教員は地域貢献をしなければいけない、
という圧力も高まってきました。
例えば看護学校で 「哲学」 や 「倫理学」 を教えているのも地域貢献の一環です。
もちろん教えているわけですから、教育の仕事とも言えますが、
これはmustの仕事ではありません。
また普通よりはかなり高い時給もいただいていますが、
確定申告をしたらごっそり持っていかれますので、
時間と労力を使うよりも、お断りしてその分、
自分の研究や福島大学での教育に時間を割きたいというのが本音です。
しかしながら、特に地方の場合、哲学者・倫理学者が県内にそれほどいるわけではありませんので、
これをお断りしてしまうと、県内のさまざまな教育が立ち行かなくなってしまうのです。
倫理学者の場合、ほかに公開講座や高校での出前授業など、教育っぽい仕事が中心になりますが、
場合によると倫理規定の策定などの地方自治体やら企業の仕事が舞い込んでくることもありえます。
こういったことにも積極的に取り組んでいくよう求められているわけです。
というわけで、大学教員になることのできた倫理学者には、
以上のようなさまざまな仕事があって、日々それらに追われているわけです。
ですので、最初の質問に対する答えは次のようにまとめておきましょう。
A.倫理学者 (大学教員になることのできた者) は、
倫理学の研究と教育、大学運営の雑務、地域貢献のための事業などを行う職業です。
大学教員にまだなっていない場合は、倫理学者として倫理学の研究に携わる以外に、
生きていくためのなんらかの職業をもっていることが多いです。
こんな感じでしょうか。
では、倫理学者はどんな研究をしているのでしょうか?
これについては十人十色ですのでひと言で言いにくいですが、
ざっくり言うと、倫理について批判的・懐疑的に研究しています。
しかも、すでに歴史のある学問ですので、
まったく0から研究し始めるというのは時間のムダですから、
とりあえずは、誰かの倫理思想についてその人の本や論文を読むところからスタートします。
それらを批判的・懐疑的に検討していく中で、しだいに独自の倫理思想が育まれていくわけです。
具体的に私の場合はということでいうなら、
私のホームページを見てみてください。
それを見るとだいたい私が何を研究しているかわかってもらえるのではないでしょうか。
いや、読んでもわからないかなあ?
このブログで書いているのとはだいぶレベルが違うというか、
学問的な積み重ねの上で研究を進めなくてはなりませんので、
難しい専門用語なども使わざるをえません。
自分が最先端で研究している内容を、
このブログを読んでくださっている方々にもすっきり理解してもらえるぐらい、
明快に説明できるようになるといいのですが、なかなかその域に達するのは困難です。
いずれこのブログにも、まずはカント倫理学に関するカテゴリーを起ち上げて、
皆さんにわかりやすくカント倫理学を語れるようになりたいと思っています。
ちょっとまだその準備は整っていませんので、もうしばらくお待ちください。










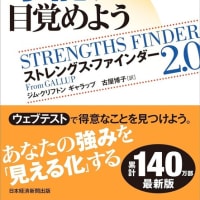









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます