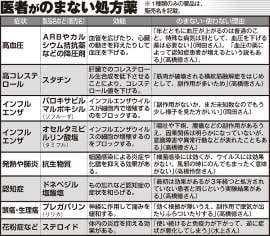ピエール瀧逮捕報道で炎上した深澤真紀は間違ってない! 違法薬物問題に「厳罰より治療を」は世界の潮流だ
リテラ 2019.03.15
ピエール瀧の逮捕報道が過熱の一途をたどっている。
ワイドショーはいまだにピエール瀧のニュース一色となっているが、そんななか、なんとも「ヘル日本」「中世ジャップランド」を象徴するような出来事が起きた。番組のなかで、「厳罰よりも治療を」といった趣旨の発言をしたコラムニスト・編集者の深澤真紀氏が炎上しているのだ。
3月13日放送の『とくダネ!』(フジテレビ)にコメンテーターとして出演した深澤氏は、まず、とかくスキャンダラスに扱われがちで、なおかつ「厳罰主義」な過剰バッシングに傾く傾向のある、芸能人の薬物報道のあり方に対して疑問を投げかけた。
「今回の逮捕も本人の治療につながると思うので、ただただ『仕事全部NG』とか、そういうのは変えていってもいいのかなと思うんですね。特にこういう報道があると、いままで止めていた人も絶望してまた再開してしまったり、あるいは、『どうしよう……』と思っている人がこんなに厳罰になってしまうのなら隠そうと思ってますます隠してしまったり(する)。むしろ明らかにしたほうが治療につながるんだよってことを、今日の報道では是非その流れで話せればいいなと思うんですけどね」
その後、深澤氏は、清原和博がそうであるように、ピエール瀧にも復帰のロールモデルとなってほしいと期待を寄せるコメントをしつつ、もうひとつ大事な点を指摘した。
世界的には薬物問題は厳罰を脱する方向を向いており、加罰よりもむしろ「治療」の問題を論じられるようになっているのにも関わらず、日本の法整備は明らかに遅れているのではないかと語ったのだ。
「本人が売っていたら問題ですけれども、薬物の場合難しいのは、本人が患者でもあるということなので。日本はどうしても薬物依存の方が少ないので、法律が変わっていないんですけれども、法律も50年以上変わっていないので、治療の現場がまったく変わっているなかで、この法律でいいのかというのは、世界的には論議されているところなんですね」
現在、電気グルーヴの作品の出荷停止と回収が決まったり、ピエール瀧が出演した映画・ドラマの出演部分差し替えなどが頻発する事態にもなっている。
これも厳罰主義ゆえに起きていることだが、そういった状況に対しても深澤氏は「ここで彼の仕事をすべて私たちが奪っていくと、ますます病気から立ち直ることはできませんから。他の国で、ここまで薬物をやった人の仕事をすべて消すという流れは減っていますからね」としつつ、このように語った。
「薬物はバレたら人生は終わりだというイメージをつけてしまうことが本当に良くないと思うんですね」
深澤氏がここで語っていることは非常に真っ当なことだと思うが、しかし、そういった深澤氏の提言に対し、ツイッターでは炎上が起こったのだ。

〈薬物使用者がむしろ被害者。ってどういうこと? この深澤真紀って人は頭おかしいのか?〉
〈深澤真紀っていうの? この人。薬物使用した人は被害者、被害者連呼でめちゃくちゃ違和感〉
〈フジの「とくダネ!」コメンテーター、深澤真紀さんは違法薬物犯罪を病気みたいに言ってた。びっくりだよ。被害者? へぇー。それなら、私も一回くらいやってみてもいいかな、なんて思ったわ。ああいう博愛主義みたいなのが国を、人を滅ぼすんだと思う〉
〈#深澤真紀 さんが「薬物バレたら人生終わりというイメージつけるの良くない」と発言してたが其れは違う! 人生終わりなのだ! 賭博行為や若気の至りの種類とは訳が違う〉
〈何言ってんだ? 違法薬物使用者は終身刑、売人は死刑、製造や密輸関係した者は殺処分ぐらい言えよ、何が被害者だ〉
こういった「違法薬物をやったらその時点で人生は終わり」という偏見を補強するような眼差しは『とくダネ!』のスタジオ内にもあった。
荻上チキらが提起した「薬物報道ガイドライン」
先に引いた、「日本の法整備は遅れている」との深澤氏の言葉を受けたコーナー進行担当の伊藤利尋アナウンサーは凍り付いた表情で、このように切り捨てたのだ。
「とても大切な視点だとは思いますが、しかしまあ、現状法律で定められた社会のルールを犯してしまった、本人はその容疑を認めている」
伊藤アナにせよ、深澤氏に噛み付いたネットユーザーにせよ、彼らの主張は「我が村のルールを破った者は厳罰に処されなくてはならない。海外でどんな法律の運用がなされているかなど知ったことではないし、治療の現場にも興味はない。とにかく、ピエール瀧は恐ろしい犯罪者である。彼の行いの何が“罪”なのかはわからないし、考える気もない。とにかく、罰せられるべき犯罪者だ。理由はひとつ。“我が村のルールを破った”からだ!」ということに他ならない。
一度、コミュニティの掟を破ったものは、彼らの言う道義的な「正義」の名のもとにどこまでも断罪され、その後、再び仲間に引き入れられることはない。
彼らの言葉からは、現在日本にまん延する潔癖で閉塞した空気感が集約されている。
おかしいのは、深澤氏ではなく、彼らのほうだ。
2017年に、荻上チキ氏(評論家)、松本俊彦氏(国立精神・神経医療研究センター)、上岡陽江氏(ダルク女性ハウス代表)、田中紀子氏(ギャンブル依存症問題を考える会代表)といった専門家によって、「薬物報道ガイドライン」というものが発表されている。
このガイドラインでは、薬物に関する報道を行ううえでメディアが「避けるべきこと」と「望ましいこと」が具体的に言及されている。
そこでは、「避けるべきこと」のなかに〈「人間やめますか」のように、依存症患者の人格を否定するような表現は用いないこと〉〈薬物依存症であることが発覚したからと言って、その者の雇用を奪うような行為をメディアが率先して行わないこと〉〈「がっかりした」「反省してほしい」といった街録・関係者談話などを使わないこと〉といったものがあり、逆に、「望ましいこと」のなかに〈依存症については、逮捕される犯罪という印象だけでなく、医療機関や相談機関を利用することで回復可能な病気であるという事実を伝えること〉〈「犯罪からの更生」という文脈だけでなく、「病気からの回復」という文脈で取り扱うこと〉〈依存症の背景には、貧困や虐待など、社会的な問題が根深く関わっていることを伝えること〉といった指摘がある。
伊藤アナやネットユーザーが強化した「ルールを破った者は永遠に村八分」は「避けるべきこと」であり、深澤氏の意見の切り口は「望ましいこと」であった。
欧米諸国において違法薬物の問題が「厳罰主義から治療へ」といった方向に変わっているのは、医療の進歩や様々なデータの研究の結果、厳罰主義が薬物事犯の抑制に効果がないということが明らかになったからだ。
違法薬物問題に「厳罰主義から治療へ」は世界の潮流
そういった知見を受けて、単なる所持や使用の場合はむしろ、「治療」に舵を切るようになった。薬物を使用した者を過度に断罪することを避けるようにしているのも、依存からの回復と速やかな社会復帰を促すためである。
薬物を使用したことで社会から追放されれば、精神的にも経済的にも以前の生活を取り戻すことは難しくなるし、今回ピエール瀧が見せしめとされているように、薬物使用ですべての仕事を奪われ人生が崩壊するさまを見れば、依存を脱するために医療機関のサポートを求めたいと思っている人も二の足を踏んで、さらに状況を悪化させてしまうだろう。
深澤氏の指摘はそういった状況を説明するコメントであったわけだが、今回のピエール瀧の報道において、大半のワイドショーでこんな真っ当な意見は聞かれなかった。
むしろ、「違法薬物をやったらその時点で人生は終わり」といったイメージを補強する役割を進んで受け入れたといえる。
「そんな人だとは思わなかった」という街の人の声をVTRで届け、スタジオではコカインに手を出せばどんな人生の末路が待っているかをおどろおどろしく解説し、注射器や白い粉が入った小分けのパケの画像を映し出すのはもちろんインターネットでの購入方法を説明する番組まであり、さらには今回の逮捕で飛んだ仕事の違約金がどれほどの高額に及ぶのかを面白おかしく煽り立てた。
その一方で、薬物を使用した人の回復に関する取り組みや、違法薬物がまん延する社会状況そのものに対する批判的な眼差しはほとんど見られることはなかった。そんななか、深澤氏のコメントは貴重なものであったといえるのだが、それが逆に非難を浴びるという暗澹たる事態となってしまったわけだ。
先に引いた通り、ネットユーザーのなかには〈違法薬物使用者は終身刑〉とまで強く怒りを表明する人がいた。
しかし、もしもそこまで強く違法薬物の問題に怒りを示すのだとしたら、その憤りの矛先は違法薬物を使用した者に対してではなく、違法な薬物に逃げなくてはならないほど過酷な貧困や虐待などの社会状況がまん延していることに対してであり、そういった状況をつくりだしている政府のほうであるはずだ。
ただ、伊藤アナや深澤氏を攻撃したようなネットユーザーがそういった方向に怒りを向けることはないだろう。
彼らは「一度お上が決めたことは絶対に守らなければならない」「“なぜ守らなければならないのか”なんて考える必要はない。ただ命令されたから守らねばならないのだ」という考えが固着した奴隷だからだ。
今回のピエール瀧報道は、メディアに違法薬物に関する建設的な議論が進むための基本的な知識すらないということを改めて示したと同時に、閉塞した現在の社会状況ではそもそも他国のケースと引き比べて現行の法整備に疑問をもつということすらないという絶望的な結果を浮き彫りにした。
言うまでもなく、こういった状況は違法薬物に関する議論だけではなく、他の社会事象を議論する際にも共通する由々しき問題である。
(編集部)
「 厳罰主義」の一方で甘い「性犯罪」
今月12日、絶句するしかない判決が言い渡された。酒に酔って抵抗できない状態にあった女性を性的暴行した会社役員の男性に、福岡地裁久留米支部はなんと無罪判決を出したのだ。
事件が起こったのは2017年2月。判決で西崎健児裁判長は「女性はテキーラなどを数回一気飲みさせられ、嘔吐して眠り込んでおり、抵抗できない状態だった」と認定しながらも、〈女性が目を開けたり、何度か声を出したりしたことなどから、「女性が許容していると被告が誤信してしまうような状況にあった」と判断〉(毎日新聞3月12日付)。西崎裁判長はこう述べたというのだ。
「女性が拒否できない状態にあったことは認められるが、被告がそのことを認識していたと認められない」
え、どういうこと?と突っ込むしかない。テキーラを一気飲みさせられて嘔吐し眠り込んでいるというのは完全に抗拒不能状態で、それで性行為をおこなえば準強制性交等罪が成立する。そして、裁判長も「抵抗できない状態」だったことは認めている。にもかかわらず、目を開けたり声を出したことを理由に「女性が許容していると被告が誤信してしまうような状況」と認定するとは……。
リテラ
酩酊状態にさせ暴行して無罪! 甘い性犯罪判決の背景に司法界の男目線、刑法注釈書に「たやすく屈する貞操は保護に値しない」
2019.03.15冒頭部分より
****
退職の意向が明らかになったNHKの青山祐子アナウンサー(46)がネット上で猛批判にさらされているのだ。彼女は12年3月の第1子を皮切りに、17年2月までに4人の子(2男2女)を出産。およそ6年間にわたり産前産後休暇と育児休業を取得し、現在も育休中。批判の多くは「育休中にもらった給与を返還しろ」「公務員ならまだしも民間ではありえない」といった内容。出産自体には賛同を示しつつ、育休制度を悪用しているという見方だ。
ここで多くの人が誤解しているが、NHKはもちろん、国家公務員や学校の先生に至るまで「育休中に給与は支給されていない」。
〈略)
「育児休業は子が3歳に達するまで取得可能ですが、その間の俸給は支給されません。退職手当(退職金)も休業期間に応じて減算されます。ちなみに、介護休暇期間中も減額されます」(内閣府官房)
〈略〉
日刊ゲンダイ
おかしな国「ニッポン」
NHKは「公共放送」ではありません。
裁判官の「憲法」と「良心」はどこへ投げ捨てたのでしょう!
これでは到底「死刑制度」なんて恐ろしい「殺人機構」に過ぎない。
優しい「寛容」な国民は
「厳罰主義から治療へ」
親による子供への「虐待」についても、「DV」・「いじめ」・「暴力」「ヘイト」加害者への更生教育プログラムが注目され始めれいる。彼らにはには「治療」が必要なのだ。心を病んでしまった病人だ。現代の「社会構造」の犠牲者たち。