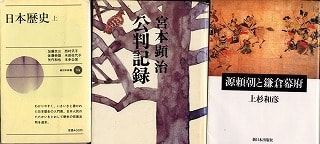
2004年1月に日本共産党は、党綱領の全面的な改定を行いました。
その内容について、不破哲三(当時議長)の「新・日本共産党綱領を読む」の中で、「戦後の「民主化」について「一連の改革が『上からの改革』だったことと結びついた、日本の社会の重大な弱点があると見ています」と分析していました。
私は、国民自からが、社会変革を成し遂げることの確信が持てない国民性なのかと、日本歴史はどうなのか、疑問を持ち続けています。
ことし1月1日の志位和夫委員長の新春トークでは、「ついに労働者が立ち上がりました」とのNHKニュースを取り上げ、2006年の党の24回大会で「社会的連帯で反撃を」との呼びかけどおり、本格的な社会的反撃がはじまった年と述べました。
宮本顕治(元日本共産党議長 故人)の戦前の公判記録では、江戸時代の鎖国政策による、西洋の生産力の発展を輸入できなかったことや自然科学の発展の遅れ、市民階級の不十分な発展などを取り上げ、明治以後、「西洋に於ける様な民主主義的な形態とは根本的に異なった、依然としてすこぶる封建的特徴ある所の支配体制が起こってきたのであります」と陳述しています。
上杉和彦氏の「源頼朝と鎌倉幕府」は、2度読み返しました。平安時代の武士の成り立ちから、平清盛そして、源頼朝と死後の鎌倉幕府の政策そして、この時代をどう見るかについての、様々な見解も紹介しています。
当時の支配体制の移り変わりと支配内部の権力抗争などが、非常によく分かる本です。一方、当時の庶民、生活が分からないのが弱点です。
新日本新書の3分冊「日本の歴史」は、この時代の生産技術の発展による、生産力の発展と奴隷の身分の逃亡などによる反抗の中で、奴隷に土地を与えて食糧を自分でまかなわせながら搾取する、封建制度へつながる、生産関係が生まれていたことを述べています。 先の志位和夫委員長の「このニュースが一番うれしかったですね」は、私の実感です。
その内容について、不破哲三(当時議長)の「新・日本共産党綱領を読む」の中で、「戦後の「民主化」について「一連の改革が『上からの改革』だったことと結びついた、日本の社会の重大な弱点があると見ています」と分析していました。
私は、国民自からが、社会変革を成し遂げることの確信が持てない国民性なのかと、日本歴史はどうなのか、疑問を持ち続けています。
ことし1月1日の志位和夫委員長の新春トークでは、「ついに労働者が立ち上がりました」とのNHKニュースを取り上げ、2006年の党の24回大会で「社会的連帯で反撃を」との呼びかけどおり、本格的な社会的反撃がはじまった年と述べました。
宮本顕治(元日本共産党議長 故人)の戦前の公判記録では、江戸時代の鎖国政策による、西洋の生産力の発展を輸入できなかったことや自然科学の発展の遅れ、市民階級の不十分な発展などを取り上げ、明治以後、「西洋に於ける様な民主主義的な形態とは根本的に異なった、依然としてすこぶる封建的特徴ある所の支配体制が起こってきたのであります」と陳述しています。
上杉和彦氏の「源頼朝と鎌倉幕府」は、2度読み返しました。平安時代の武士の成り立ちから、平清盛そして、源頼朝と死後の鎌倉幕府の政策そして、この時代をどう見るかについての、様々な見解も紹介しています。
当時の支配体制の移り変わりと支配内部の権力抗争などが、非常によく分かる本です。一方、当時の庶民、生活が分からないのが弱点です。
新日本新書の3分冊「日本の歴史」は、この時代の生産技術の発展による、生産力の発展と奴隷の身分の逃亡などによる反抗の中で、奴隷に土地を与えて食糧を自分でまかなわせながら搾取する、封建制度へつながる、生産関係が生まれていたことを述べています。 先の志位和夫委員長の「このニュースが一番うれしかったですね」は、私の実感です。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます