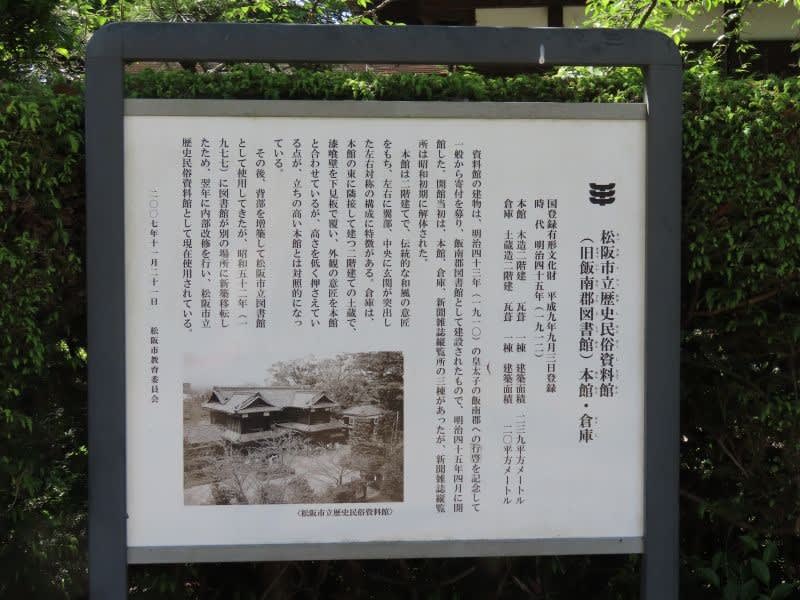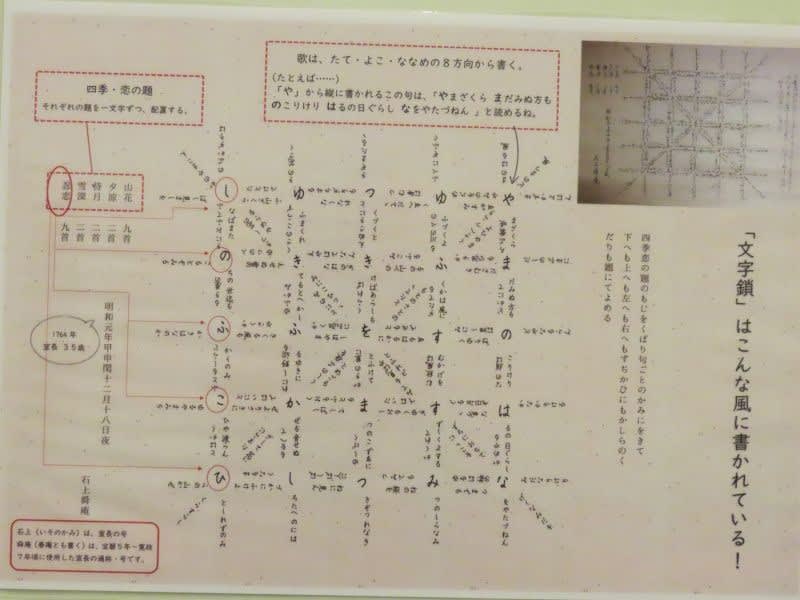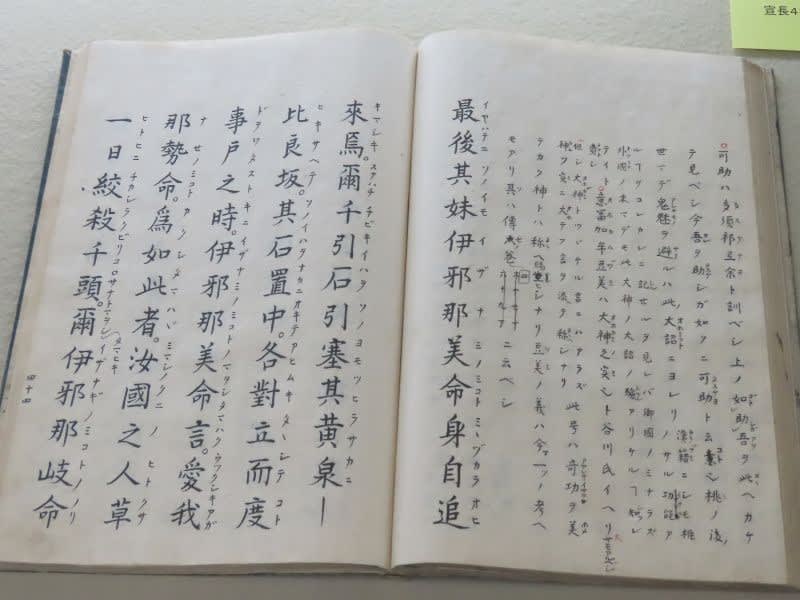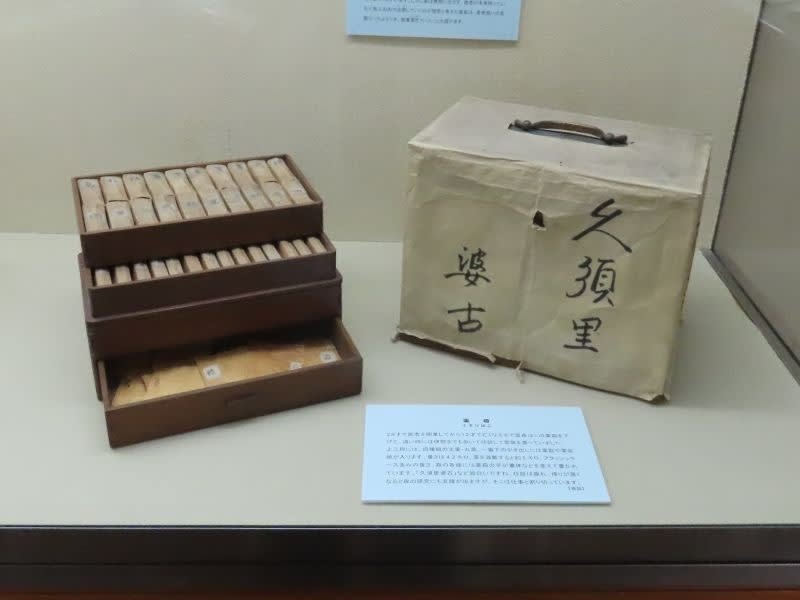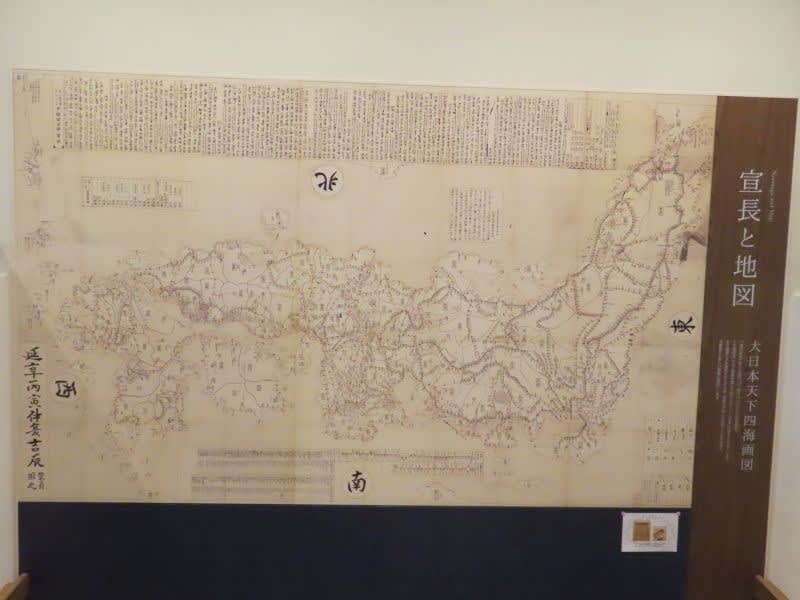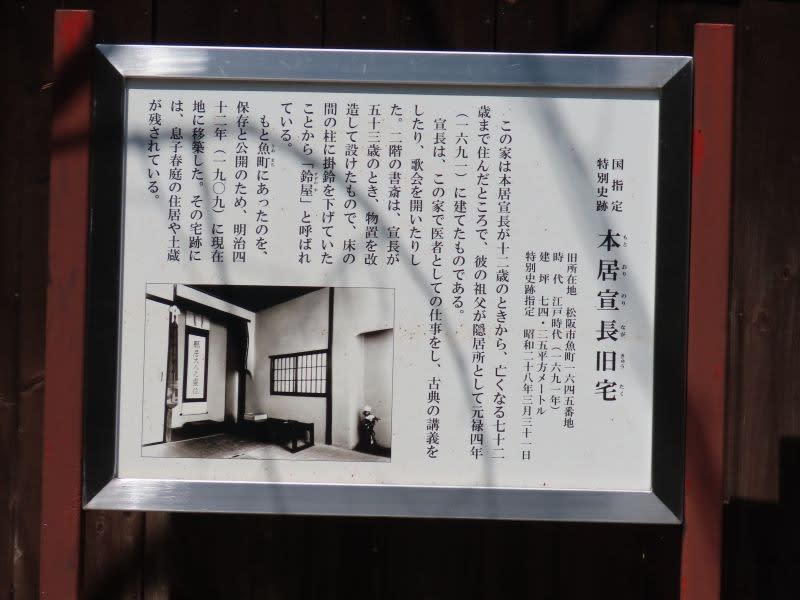5月9日から11日まで松阪・伊勢・鳥羽旅行に行きました。そのときの写真を出し忘れていたので、だいぶ遅くなったのですが、出すことにします。今回は10日に伊勢神宮内宮へ行ったときの話です。


宿泊地は鳥羽でした。ホテルの窓から見た鳥羽湾の風景です。たくさん並んでいるイカダは釣り用のようです。

この日は近鉄で五十鈴川駅まで行き、そこからバスに乗って伊勢神宮内宮に行きました。鳥居が見えているところが五十鈴川にかかる宇治橋です。



ふと見ると、シイの花が真っ盛りでした。

宇治橋の手前です。

これは五十鈴川の上流側を撮ったものです。杭は倒木などを防ぐためのものだそうです。

こちらは下流側です。綺麗な川ですね。

宇治橋を撮りました。

宇治橋を渡ったところが神苑です。


ふと空を見ると、ワシタカが飛んでいました。家に戻ってから調べると、どうやらサシバのようです。

前方に見える橋が火除橋です。


そして、第一鳥居です。

そこから右に行くと御手洗場があり、たくさんの人が来ていました。


五十鈴川は本当に清らかな流れですね。



その近くで咲いていました。Googleレンズで調べると、マルバウツギのようです。


これはオニカナワラビかなと思いました。

これはクロスジシャチホコ。

これはオオカナワラビかな。伊勢神宮は植物が豊富ですね。

これは神楽殿。

その先の参道です。

そして、正宮に着きました。去年も来たのですが、正宮は本当に質素な建物です。ただ、ここは撮影禁止なので、写真はありません。この後、荒祭宮に行ったのですが、続きは次回に回します。


宿泊地は鳥羽でした。ホテルの窓から見た鳥羽湾の風景です。たくさん並んでいるイカダは釣り用のようです。

この日は近鉄で五十鈴川駅まで行き、そこからバスに乗って伊勢神宮内宮に行きました。鳥居が見えているところが五十鈴川にかかる宇治橋です。



ふと見ると、シイの花が真っ盛りでした。

宇治橋の手前です。

これは五十鈴川の上流側を撮ったものです。杭は倒木などを防ぐためのものだそうです。

こちらは下流側です。綺麗な川ですね。

宇治橋を撮りました。

宇治橋を渡ったところが神苑です。


ふと空を見ると、ワシタカが飛んでいました。家に戻ってから調べると、どうやらサシバのようです。

前方に見える橋が火除橋です。


そして、第一鳥居です。

そこから右に行くと御手洗場があり、たくさんの人が来ていました。


五十鈴川は本当に清らかな流れですね。



その近くで咲いていました。Googleレンズで調べると、マルバウツギのようです。


これはオニカナワラビかなと思いました。

これはクロスジシャチホコ。

これはオオカナワラビかな。伊勢神宮は植物が豊富ですね。

これは神楽殿。

その先の参道です。

そして、正宮に着きました。去年も来たのですが、正宮は本当に質素な建物です。ただ、ここは撮影禁止なので、写真はありません。この後、荒祭宮に行ったのですが、続きは次回に回します。