
映画「愛と哀しみの果て」を観る。私が中学三年の時に、公開されたと記憶しているのだが、心に残る映画として何度見返したことだろう。
主演するのは、メリル・ストリープとロバート・レッドフォードという夢のような大スター達。おまけに、原作はデンマークの女流作家、アイザック・デイネーセンの自伝的小説で、彼女がアフリカへ渡り、コーヒー農園主として過ごした歳月を振り返った「アフリカの日々」だというのだから、傑作にならないわけがない!
しかし、この「愛と哀しみの果て」という邦題は、ちょっと疑問。 映画のタイトルもはっきり、「Out Of Africa」とあるのに、このセンチメンタルで安っぽい題名――タイトルを考えた映画配給会社のセンスを疑ってしまうし、作品の持つ格調高さを貶めてしまうように思ってしまうのは、私だけだろうか?
でも、考えてみれば、当時の洋画は、こんな風なタイトルをつけられてしまうことがよくあったのだ。 もう一作、私の好きなクロード・ルルーシュ監督の「愛と哀しみのボレロ」もそうだし、古くは、リチャード・ギアとデブラ・ウィンガーの「愛と青春の旅立ち」というのもあった。 「愛と」というのが、時代の合言葉ででもあったのだろうか。
それでも、現代のハリウッド映画の英語のタイトルをそのまま、カタカナ表記にするよりは、ずっとましだと思う。いくら、トム・クルーズとかレオナルド・ディカプリオといった大スターが出ていたとしても、作品が観客の記憶に残りにくくなってしまうはず。
話を「愛と哀しみの果て」に戻すと、これは上映時間二時間半を超える、超大作。デンマークの富裕な家庭に生まれたカレンは、貴族の称号につられたこともあって、元恋人の弟であるスウエーデン貴族のブロルと結婚する。ところが、ブロルが言いだしたのは、とんでもないこと。 アフリカのケニアに渡り、コーヒー園を始めようというのだ。
そして、物語は雪の降る北欧から、広大なアフリカのサバンナへ――明るい光の降りそそぐ大地の上を、汽車が通ってゆき、そこに洒落た陶器や、家財道具を積みこんだカレンが乗っている。このシーンの切り替えがとても鮮やかで、私たち観客も、1910年代のアフリカに連れ込まれてしまいそうなほど。
この汽車を突然とめた男がいて、それがカレンが、後に心から愛することになるデニス・ハットンだった。レッドフォード演じるデニスが、とても素晴らしい! どんな結びつきやしきたりに縛られることも嫌い、自由自在にアフリカの地を駆け、その大空をセスナ機で飛んで行く。 冒険というものが存在した20世紀の初めには、こんな人が、何人もいたのかもしれない。

ブロルも、当てにはならないものの、魅力的で憎めない人物。はるばるアフリカに来たばかりのカレンを放っておいて、長い狩りに出たり、プレイボーイぶりを発揮したりする。仕方なく、カレンはコーヒー園経営に一人で乗り出すしかないのだが、当然ながら、なかなかうまくはいかない。 その一方、ケニアの原住民たちとのふれあいは、カレンを人間としても大きく成長させたのだと思う。
原住民たちは、とても素朴で、カレンが持ってきた鳩時計から、定刻きっかりに鳩が「ポッポー」と飛び出すのを、かたずを飲んで待ち構え、ビックリ仰天して逃げたりする。 夫を追いかけて、危険なサバンナを旅し、襲いかかるライオンを銃で撃ち殺したりするカレン――その一方、デニスとテラスでモーツアルトの音楽を蓄音機で聞くなど、この映画には、ダイナミックな冒険と優雅な植民地文化が混じりあっていて、「いい時代だったのだなあ」と憧憬の気持ちでいっぱいになってしまう。

カレンは、後にこの頃のことを振り返り、「私はアフリカで幸せだった」と言い、「アフリカの日々」を書いたわけだけれど、決して、成功したわけではなかった。温かな友情が後に残ったとは言え、ブロルとは離婚したし、心血を注いだコーヒー園は火事で焼失し、破産してしまう。そして、心から愛したデニスを手に入れることは、とうとうできなかった。
「私と結婚して欲しい」というカレンに、デニスは「結婚という形で縛られたくはない」ときっぱり断り、破産したカレンがアフリカを去ることになっても、自分はアフリカを離れる意志はなかった。そして、最後に飛行機で送ろうと言い残し去っていくのだが、家具のなくなってしまったガランとした屋敷で、カレンに知らされたのは、デニスが墜落死したという悲しい知らせだった。
それでも、後に残してゆくキクユ族の居住地を確保してやるために、新しい領事夫妻にかけあうカレン。その彼女に、最後、女性禁止の紳士倶楽部は、入室を許し、カクテルを振舞うことで、彼女がこの地で成し遂げたことや、その勇気を称えるのだ。
「サバンナにあるデニスの墓の上には、いつの頃からか、二頭のライオンがやって来て、しばらく休んでいくようになりました」
――アフリカに残した召使いから、カレンに届けられた手紙。けれど、カレンは二度とケニアの地に赴くことはなかったという。



















 。体を動かすことが億劫。
。体を動かすことが億劫。


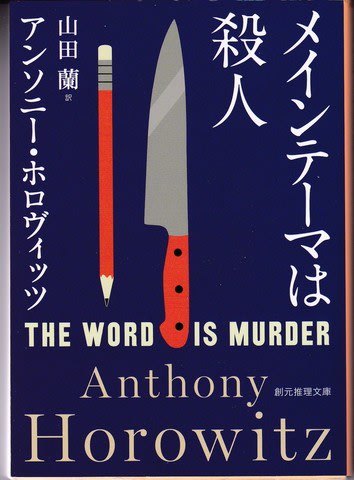



 。
。




