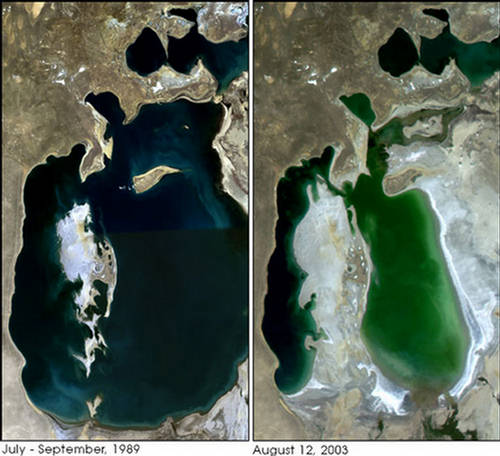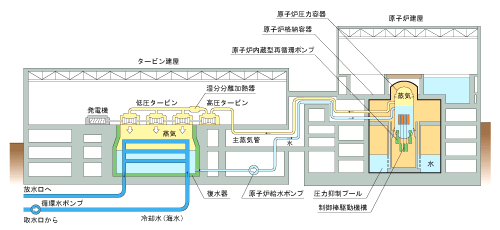■


【敦賀原発のリスク概要】
敦賀発電所は、福井県敦賀市明神町にある日本原子力
発電(原電)の原子力発電所。通称は「げんでん敦賀」。
1号機は日本最古の軽水炉として知られる(最古の商用
炉は東海発電所1号機)。

過去の主なトラブル
1981年4月
福井県の定期モニタリング調査で、海藻から異常に高
い放射能が検出された。調査の結果、敦賀発電所一号
機の一般排水溝から放射性物質が漏洩したことが分か
った。漏れた放射性物質はコバルト60であり、平常時
の約10倍の量が検出された。更に調査を進めたところ、
一般排水路の出口に積もった土砂からも高濃度のコバ
ルト60とマンガン54が検出された。しかし一般排水路
は放射能とは関係のない配水系統であり、ここからは
放射性物質が検出されるはずがない場所であった。結
局、放射性物質が検出された原因は、原子力安全委員
会の調査によると放射性廃棄物処理旧建屋の設計・施
工管理上の問題に、運転上のミスが重なったからとさ
れた。
しかし、コバルト60とマンガン54が検出された原因は、
この漏出が判明する前月に大量の放射性廃液がタンク
からあふれるという事故が起きていたからであった。
そして、敦賀発電所はその事実を隠蔽していたことも
同時に明らかとなった。つまりいわゆる「事故隠し」
が行われていたのであった。この「事故隠し」によっ
て、これ以降の日本での原子力発電に対する不信感が
大きく芽生えるきっかけになったと考えられている。
敦賀一号機で、再循環ポンプなどの溶接部分について
点検が一度も行われていなかったことが明らかになっ
たと発表した。その溶接部分は、冷却水を炉心に送り
込む原子炉再循環ポンプや原子炉圧力の排水用配管の
弁などである。第33回定期検査(2011年に実施する予
定)で再循環ポンプ系の配管を取り替える工事の準備
段階で判明。
2011年1月24日
経済産業省の原子力安全・保安院は、敦賀原発1号機
で複数ある緊急炉心冷却システムの1つが機能しない
状態で約1ヶ月間運転していたとして、日本原子力発
電を厳重注意した
日本最古の商用炉となる1号機は、本来、2009年12月に
役割を終え廃炉になる予定であったが、3、4号機の設
置が遅れたことから運転期間の延長が模索されてきた。
日本原子力発電は、老朽化を踏まえた保守管理方針を
策定した上で、運転の継続を経済産業省原子力安全・
保安院に申請。2009年8月3日に申請が認められたこと
から、2016年までの延長運転に備えた準備が進められ
ている。
2004年8月9日午後3時22分、
営業運転中の関電美浜原発3号機の2次系配管(直径
56センチ) の一部がいきなり幅最大57センチもめく
れる大きな破裂を起こした。破裂箇所はタービンを回
すのに使った2次冷却水を蒸気発生器に戻す復水管で、
付近の2次冷却水は約 140度、10気圧。破裂により高
温の蒸気と熱水が噴出し、5日後に迫った定期検査の
準備作業をしていた「関電興業」の下請け企業「木内
計測」の作業員11人が事故に巻き込まれ、5人が全身
やけどで死亡、6人が重傷を負った。
2008年5月10日(中日新聞記事)
敦賀原発、立地見直しを活断層末端強い揺れの恐れ
活断層が国内の原子力発電所で初めて敷地内に見つか
った福井県敦賀市の日本原子力発電(原電)敦賀原発
について、名古屋大教授など専門家3人のグループは、
この活断層が阪神・淡路大震災でも大きな揺れを生ん
だ横ずれ型の末端部だと確認し「立地を見直すべきだ」
との研究成果をまとめた。うち2人は国への勧告権を
持つ原子力安全委員会の専門委員で、稼働する同原発
の立地自体の是非が問われる可能性も出てきた。
東洋大の渡辺満久教授と広島工業大の中田高教授、名
古屋大の鈴木康弘教授で、いずれも地形の起伏から活
断層を分析する変動地形学が専門。問題の活断層は敦
賀原発1、2号機の原子炉から約300㍍離れた敷地内を
通る「浦底断層」。渡辺教授らは、航空写真による地
形分析でこの活断層が地震で大きな揺れをもたらす末
端部だと確認した。
活断層の末端部では細かな活断層が枝分かれしている
ケースが多い。幹に当たる活断層のずれと連動し、そ
れぞれの活断層がずれて被害が大きくなる可能性が高
まる。阪神大震災では末端部で揺れが大きくなり、枝
分かれした活断層のずれも確認された。グループは同
原発の建設以前の航空写真を分析し、建物近くに活断
層とみられる地形的特徴が表れていた。地震時にこれ
らの分岐断層がずれて建物を破壊する恐れを指摘して
いる。
2008年6月10日
原子力資料情報室第65回公開研究会

2010年7月21日
4月1日午前8時
菅直人首相は31日、東京電力福島第1原発事故を踏ま
え2030年までに原発を現状より14基以上増やすとした
政府のエネルギー基本計画を白紙にして見直す方針を
表明した。福島第1原発の1~6号機すべてについて
「廃炉にしないといけない」とも指摘。政府は原発に
代わるエネルギー源の確保と、地球温暖化対策推進の
両立という難題に取り組むが、難航は必至。エネルギ
ー基本計画が位置付ける14基以上の増設には、日本原
電敦賀原発3、4号も含まれる。

【エピソード】
【脚注及びリンク】
-----------------------------------------
(1)「日本原子力研究開発機構」
(2)「日本の原子力発電所」
(3)「放射性物質による環境汚染予防に向けて」
(4)「地域防災計画データベース:消防庁防災課」
(5)「大飯発電所のトラブル情報」
(6)「国際原子力事象評価尺度(INES)」
(7)「地震大国に原発はごめんだ」
------------------------------------------