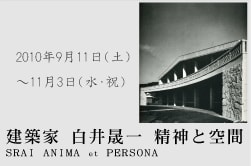読書人階級という言葉を敬愛する副島隆彦先生の学問道場で知ったのですが僕もその一員になりたくて日々意識的に本を読むように努めています。大学時代、友達の影響で意識的に本を読むようになり自分の無知無学ぶりに反省の日々です。十数年前に『後世への最大遺物』という内村鑑三さんの本を読み大変感銘しました。自分の人生の指針になる本として心のバイブルと読んでもいい一冊です。明治二十七年七月にキリスト教徒第六夏期学校において内村鑑三氏が講演した記録ですが、美しい考えが述べられいて瞠目に値することが多々あります。「この美しい地球、この美しい国、この楽しい社会、このわれわれを育ててくれた山、河、これらに私が何も遺さずには死んでしまいたくない、との希望が起ってくる」と内村鑑三は述べます。地球を愛した証拠をこの世に残してあの世に行きたい。そこでまず、一番大切なものは何であるか?お金です。最初にお金の大切さを指摘します。天文学者のハーシェルが彼の友人に「わが愛する友よ、われわれが死ぬときには、われわれが生まれたときより、世の中を少しなりともよくして往こうではないか」というエピソードを紹介しながらお金を残すことができなくても、事業を起こすことはできるだろう、と主張します。お金も事業ももし駄目であったとしても思想を残すことができる。つまり「私はこれを実行する精神を筆と墨とをもって紙の上に遺すことができる」
金も貯めれず、事業家にもなれず、思想を残したり、本を書くこともできず人にモノを教えることもできなくても人は誰でも『勇ましい高尚なる生涯を送る』ことはできるのです。「失望の世の中にあらずして、希望の世の中であることを信ずることである。この世の中は悲嘆の世の中でなくして、歓喜の世の中であるという考えをわれわれの生涯に実行して、その生涯を世の中への贈物としてこの世を去る」
自分で自分を鼓舞することによって艱難(かんなん)に耐えながら勇ましい生涯を送ることの素晴らしさを内村鑑三は強く訴えます。三十代後半に僕はこの本をはじめて読んだ時に人生観が根底から大きく変わったように思います。内村鑑三という人の思想と生き方に全て同意できるわけではないですがこの本は本当に日本人の心のバイブルとよんでもいいと思います。
「われわれが何か遺しておって、今年は後世のためにこれだけの金を溜めたというのも結構、今年は後世のためにこれだけの事業をなしたというのも結構、また私の思想を雑誌の一論文に書いて遺したというのも結構、しかしそれよりもいっそう良いのは後世のために私は弱いものを助けてやった、後世のために私はこれだけの艱難に打ち勝ってみた、後世のために私はこれだけの品性を修練してみた、後世のために私はこれだけの義侠心を実行してみた、後世のために私はこれだけの情実に勝ってみた、という話を持ってふたたびここに集まりたい」
「われわれに後世に遺すものは何もなくとも、われわれに後世の人にこれぞというて覚えられるべきものはなにもなくとも、アノ人はこの世の中に活きているあいだは真面目なる生涯を送った人であるといわれるだけのことを後世の人に遺したいと思います」(内村鑑三)
最後にweb版でもここをクリックすると全文読めます。すぐに読めますので強くオススメします。
自分の半生でこの本に出会ったことは貴重な経験であり、心の財産です。

金も貯めれず、事業家にもなれず、思想を残したり、本を書くこともできず人にモノを教えることもできなくても人は誰でも『勇ましい高尚なる生涯を送る』ことはできるのです。「失望の世の中にあらずして、希望の世の中であることを信ずることである。この世の中は悲嘆の世の中でなくして、歓喜の世の中であるという考えをわれわれの生涯に実行して、その生涯を世の中への贈物としてこの世を去る」
自分で自分を鼓舞することによって艱難(かんなん)に耐えながら勇ましい生涯を送ることの素晴らしさを内村鑑三は強く訴えます。三十代後半に僕はこの本をはじめて読んだ時に人生観が根底から大きく変わったように思います。内村鑑三という人の思想と生き方に全て同意できるわけではないですがこの本は本当に日本人の心のバイブルとよんでもいいと思います。
「われわれが何か遺しておって、今年は後世のためにこれだけの金を溜めたというのも結構、今年は後世のためにこれだけの事業をなしたというのも結構、また私の思想を雑誌の一論文に書いて遺したというのも結構、しかしそれよりもいっそう良いのは後世のために私は弱いものを助けてやった、後世のために私はこれだけの艱難に打ち勝ってみた、後世のために私はこれだけの品性を修練してみた、後世のために私はこれだけの義侠心を実行してみた、後世のために私はこれだけの情実に勝ってみた、という話を持ってふたたびここに集まりたい」
「われわれに後世に遺すものは何もなくとも、われわれに後世の人にこれぞというて覚えられるべきものはなにもなくとも、アノ人はこの世の中に活きているあいだは真面目なる生涯を送った人であるといわれるだけのことを後世の人に遺したいと思います」(内村鑑三)
最後にweb版でもここをクリックすると全文読めます。すぐに読めますので強くオススメします。
自分の半生でこの本に出会ったことは貴重な経験であり、心の財産です。