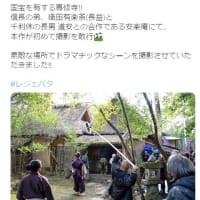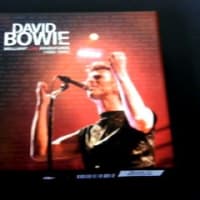表千家北山会館

わびと数寄 ―受け継がれる利休の心―
期間:9月13日(金) ~ 12月15日(日)

三条西実隆筆書状
中務殿宛。三条西実隆が「つかへきてうれしき世にも あへる代や戸さしもきかね 関の藤河」の和歌を添えた書状。
「関の藤河」は岐阜県関ケ原に流れる藤古川の事で、壬申の乱の舞台にもなった旧跡で歌枕になっている。
三条西実隆は茶人・武野紹鷗と交流があった事が『実隆公記』に記されている。
珠光寄竹手桶水指 利休在判
竹を寄せて作られた手桶。珠光ゆかりの水指で利休のケラ判が朱書きされている。
利休はこの手水指と同じ形の手桶水指を塗師の記三に作らせている。
瀬戸米市手茶入
狂言の「米市」より銘が付けられた瀬戸茶入。狂言の「米市」に出てくる米俵に形が似ている事に因む。
片桐石州より江岑宗左拝領した茶入で、石州が江岑に宛てた書状が添い、そこには宗旦や江岑の弟・仙叟宗室の様子を尋ねた内容が記されている。
共筒茶杓 金森宗和作
杓幅広く、露は一文字の茶杓。筒には「宗和(花押)」と簡素に記されている。
金森宗和は高山藩主・金森可重の嫡男であったが廃嫡され茶人となった人物。「姫宗和」と称される茶風で公家達に支持された。しかし武家との交流は続けており息子・七之助も加賀藩に仕官させているところを見ると武士の矜持は忘れていなかったのであろうか。

組立茶室

呈茶